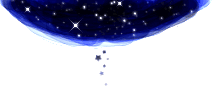
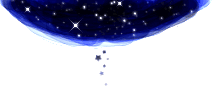
愛しく苦しいこの夜に 「お前が会いたいヤツって、アポロのことだろ?」 団員の彼の予想していた人はやっぱり私の会いたい人と同一人物だった。 アポロという名前は組織内での彼のコードネームで、本当の名前は誰も知らないらしい。 「行くか」 アポロさんが私と会うことを望んだのかは分からないが、どうやら彼のいる展望台へと行けることになったみたいだ。拒まれてしまったらそこまでだと思っていたけれど、よかった。はやくあの声が聞きたい。 部屋を出てアジト内、奥の狭い通路を進むとラジオ塔内の倉庫に出た。そこにはやはりたくさんのロケット団員がいて、私の前にいる彼に挨拶をする。だけど何だか彼らの様子が変だ。さっき彼を出迎えたアジトの人たちと違う。不安と悲しみが滲み出ている、この表情。彼は辺りを一通り見渡すと息を一つ吐いて小さく呟いた。 「タイムリミットが迫ってるってことだな」 17:00 階段を登り、フロアをひとつひとつ抜けていく。途中、団員の姿は見えても人質の姿が一向に見えない。3階まで登ったところで私はその理由を目の当たりにした。 「…やっぱり来たのか、お前」 彼の言葉に反応し、無言で私たちを睨みつけたのは1人の男の子。団員の彼はこの子のことを知っているらしい。 「人質は?お前が逃がしたの?」 「うん」 「まじかよ…で、これからお前どうする気?」 「展望台にいる人を倒して、今していることを止めさせる」 すべて聞き間違いだと思った。 だって信じられない。でもこれが真実だとしたら今まで見た塔内の状況にも説明がつく。不安そうな団員たちの顔、人質のいない塔内、こんな危険な場所で1人佇んでいた男の子。 …いや、1人じゃない。男の子の後ろには頼もしいパートナーたちがいる。たくさんの大人たちを相手にして、ここが危険な場所だということもじゅうぶん分かっているに違いない。 彼はきっとこの組織の計画を阻止するという明確な目的を持ってここまで来たんだ… 「お前みたいなヤツ嫌いじゃないぜ。わかった。俺とバトルして勝てたらこのシャッターを開けてやってもいい」 「わかった」 二人は同時にモンスターボールを取り出す。私が状況を理解するのにもたついていると、団員の彼は私にキーを差し出した。 「というわけだからお前は先に行ってろ。そこから登っていけば展望台に行ける」 「え…」 「今の聞いてたろ?てっぺんのヤツを倒すんだって、コイツは」 はやく行け、キーと受け取る時に真面目な顔でそう言う彼を見て何だか胸が熱くなってしまった。 街で会えたのが彼で良かった。彼があの人に近い存在でなければ、あの人に会うことも、ここに来ることさえも出来なかったはず。彼が私の知らないところで何をしてきたか分からないけれど、今こうやって親切にしてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいだ。 「ありがとうございます…!」 何も言わずひらひらと手を振ってくれた彼の隣で、男の子の私を見る目がすごく恐かった。どんな理由があろうと、周りから見れば私は組織の人間と変わらないのかもしれない。あの人に会いたいという自分の目的だけ果たそうとして他の人のことを考えようともしなかった。最低な人間だって、自分でも分かっている。あの子に軽蔑されても仕方ない。でももう振り返れない。進むしか出来ない。 これが私の出した答えだから。 . . . 階段を登って1つ上のフロアに進むとそこには緑色の髪をしたロケット団の人が立っていた。彼は私に気付いているみたいだが何も言ってくる気配がない。 なんか恐い… 足早に彼の前を通り過ぎようとしたとき、急に声がした。 「その階段を登ってエレベーターに乗れば展望台へ行けます」 「あ…ありがとうございます…」 「止めようたって無駄ですよ。貴方があの人にとってどんな存在であったとしても彼は必ず組織を選ぶ」 たしかさっきの人も同じこと言ってた。何を言ってもムダだと。信用されているんだなあ。そうでなければこうして組織をまとめることは出来ないだろうけど。 「わかっています」 大丈夫。 私も彼らと同じようにあの人を信じている。 微笑みながらそう答えた私を彼は驚いた表情で見ていた。 「イチコさん」 たとえ私が彼のことを一部にも満たないぐらいしか知らないかったとしても。 彼があの店で一緒に笑っていたのも、最後に会った日に寂しそうに笑っていたのも、すべて偽りなんかじゃないと信じている。 「あら、貴方が?」 さらにひとつ上のフロアに上がってエレベーターが見えた時だっただろうか、赤い髪をした女の人が私の前に立ち塞がった。この人もロケット団員だ。 「話は聞いているわ。言いたいことは大体、検討がつくけれど」 「止めてもムダ、なんですよね」 「…さあね。それはあたしにも分からない」 「え?」 二人とは違う返事に私が思わず戸惑っていると、彼女はくすっと笑って「あのね、」と口を開いた。 「あたし、コーヒーって苦手だったの」 「?」 「でも、アポロからするコーヒーの香りは嫌いじゃなかった」 「…」 「貴方からも同じ香りがする」 彼女と目が合う。その赤い瞳はまっすぐと私を見つめていたけれど、どこか悲しげな彼女の表情を見て私は思った。 塔内にいた人たちと同じ… 「下にいた二人も私もアポロも、本当は分かっているのよ」 「…」 「こんなことしても、あのお方が帰ってくることなんてないって。でも、貴方がアポロを止めようとしているのと同じ。少しの希望も持たなきゃ、この場に留まるだけの人生になってしまうから」 何て答えればいいのか、分からなくなってしまった。 彼らが待ち続けているあのお方とはきっとこの組織のボスのことだ。彼らのボスは今、失踪していると報道されていたけど、もしかして今回のことはボスの帰りを待って起こしたことなのかもしれない。 「下、どうなってた?小さな坊やがいたでしょう?3年前と同じようにあたしたち、子供に邪魔されて終わるのよ。皮肉なもんね…」 親の帰りを待つ可哀想な子供…なんて言ったら怒られそうだけど、今の彼らの姿はそう見える。いつまでもここを占拠し続けることなんて不可能だ、世間を騒がせてボスに自分たちの存在を知らせることが目的なのだとしたら…どうしよう、さっきから何も言葉が出ない。 今この状況の彼らにどんな言葉を掛ければいいのかなんて思い付かない。 「なんかあたしの独り言みたいになっちゃったわね。でも、ありがと。もう時間がないから早く行きなさい」 「あ、あのっ」 突然、背中を押されてバタバタとエレベーターに乗り込む。急いで後ろを振り返ると、女の人はもう私を見ていなかった。さっきまでとは違う鋭い目つき…きっと彼女の前には、あの子がいたのだろう。 エレベーターが静かに動き出し、私はしばらく忘れていた瞬きをする。 なんかよく分からないけれど泣きそうだ。彼らとどうして普通に出会えなかったんだろう、なんて。そんなことを思ってしまうのは悪いことなのだろうか。 「アポロさん…」 アポロさんも同じ気持ちなのかな。ボスが帰ってこないと分かっているなら、3年前と同じようになるかもしれない、そう思っているならどうして… 聞きたいことがたくさんある。 伝えたいこともたくさんある。 それは今朝家を出てから、頭で整理出来ないほど増えていって――― ―――ポーン。 エレベーターのドアが開く。私は静かに深呼吸をするとゆっくり前へ進んだ。 |