目を覚ました場所は
(3/4)
「失礼致します」
さっき部屋を出て行った声が戻ってきた。
困ったことに声の主の気配と共に、もう一つ別の気配が直ぐそこにあり、少女は眉間に皺を寄せる。
一体誰に伝えに言ったかなんて、考えなくても判る事。
「あら、身体を起こされても大丈夫なんですか?」
「え、まぁ・・・」
無理矢理起こされたんですけど。と言う毒は胸の奥にしまっておく。
「お館様をお呼びしますが、宜しいですか?」
「・・・もしも私が駄目、と言えばどうしますか?」
意地の悪い質問だ、と内心呟く。
ところがこの質問、あまり意味を成さないようだった。
「それならば、下がらせていただきます。ですが・・・貴女様がお館様の客人である以上、いつかはお目通りして頂きますよ?」
「ぅ・・・」
ある程度予想はしていたが、いずれは会わないといけないらしい。
ならば事は早く済ませてしまうに限る。
「じゃぁ・・・良いですよ。呼んでください。逃げも、隠れもしませんから」
そう伝えた後、一つの気配が近くなった。
「すまぬ、桜。人払いをしてくれぬか?」
「はい」
「佐助もじゃ、そこにおるのはわかっておる」
「へいへい」
記憶にあるより大分渋くなった声に、少女の背筋がゾクリと震える。
妙なところで時間の経過を感じさせられる、と頭が他人事のように考えた。
そして感じる気配が一つだけになる。どうやら2人きりになったらしい。
「久しぶり、晴信」
先に口を開いたのは少女の方だった。
何となくいるだろうと踏んだ方向に向けて、少し無愛想に。
「久しぶりじゃな。だが、今は信玄。武田信玄じゃ」
無愛想な少女に対し、少しも笑みを崩す事無く信玄は少女の頭を撫でる。
「さて、“今”はなんと呼べばよい?」
「・・・凛」
頭を撫でられたことに少し不服そうな顔をしながら、少女は凛は答えた。
不服とは言え、拒否しない辺り嫌ではないらしい。
「凛」
「・・・何?」
「また護って貰い・・・すまんの」
「どうして謝るの」
「こうして凛に再び会い見えたのは嬉しいことじゃ。しかし、裏を返せば凛が姿を見せざるをえない状況に陥ったと言うことにならんか?」
凛は答えない。
代わりに頭の上に置かれていた手を、自分の膝元まで下ろした。
「間違ってはいない。私は・・・土地神でこの地を護る者。だけど全てを護るほど優秀じゃないから、時には何かを切り捨てないといけない。今回の火事もそう。でも、毎年、毎年、祠に来てくれる人たちを見捨てるなんて出来なかった。その人たちの生活の糧である田畑を見捨てるなんて出来なかった。だからそれらを護って消えてしまうなら、本望だったのよ」
「・・・そうか」
信玄の目に凛が映っているが、凛の目には何も映っていない。
ただぼんやりと、膝元に置いた信玄と自分の手を見つめているだけ。
「生憎ワシは人の子での。凛の世界の事は判らぬ」
「いきなりどうしたの?」
「だがの、頼まれたんじゃ。ワシも凛も良く知る奴に「お嬢をお願いします」とな」
「・・・なっ!あの子・・・!」
「落ち着かぬか。あれも凛を心配しておる。それに・・・」
信玄自身、空いている片手を凛の手の上に乗せる。
触れた手は、判りやすいほどに震えていた。
「消えるのが本望、と言いながら何故震えておる?」
「そ、れは・・・」
「本当は消えたくなかったのではないか?」
「・・・」
「それに・・・ワシとの約束、守ってくれぬのか?」
「っ!」
パーンと乾いた音が部屋に響く。
信玄が片手を弾かれたと気付いたのは一瞬遅れてからだった。
「・・・消えたくない、に決まって・・・るじゃない!私、この土地が、甲斐が・・好きなんだよ!?それに、晴信との・・・信玄との約束、まだ、だし・・・!」
本当は立ち上がりたいのに、立ち上がれないせいか、何度も何度も布団を叩きながら凛は涙を流して訴える。
「本当はっ・・・もっと延焼も抑え、られたらって・・・でも、まだ200年そこらの私じゃ無力すぎてっ・・・!!」
「もう良い、もう良い。今、凛は消えずにここにおる。それで十分じゃろう?」
泣きじゃくる凛を抱き上げ、信玄はその背を撫でてやる。
軍医が驚きながら治療したとは言え、包帯で巻かれた両足は相変わらず痛々しさを醸し出していた。
「無力だと思うなら強くなれ。そう言ったのは凛自身ではなかったか?」
「・・・う、ん」
「ワシは人ゆえ、凛の力とやらがどうすれば強くなるのかは判らぬ。だが凛が回復するまで身体を休める場所を供するぐらいは出来るぞ」
「うん・・・」
「どうじゃ?しばらくここにおらぬか?」
「・・・元からその手はずになってるんでしょ?」
―でも、ありがとう。
小さく呟き、凛は信玄の首にしがみ付いた。
(次頁は後書き)
← →
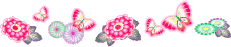
《目次へ》