あの子が仮面をとられたら
◎Tg名物しあわせ脳みそ頭ゆるふわ世界(最原×赤松前提)
◎王馬×非固定夢主
なにか冷たくて鋭利なものが額をすっと縦になぞっていった。
なんじゃこりゃ、と思うより早くその軌跡を追って走ってくる細くちりっとした痛みを指先で追えば、予想していなかったぬるんだ感触。人差し指と中指にべったりと付着した紅色に、ああ成程と合点がいった直後に転子ちゃんの悲痛な絶叫が食堂に木霊した。
「ひ、ひぇええええええええ苗字さああああああああん?! だっだっ大丈夫ですか! はああなんって痛ましいお姿にっ……! 今日こそ看過してはおきませんよそこの男死ッ、苗字さんに代わってこの転子が完膚なきまでに成敗します! 弔い合戦なのです!」
「いや転子ちゃん私死んでないし、弔われるには数十年早いって」
長くて綺麗な転子ちゃんの指がびしっと指し示す先に、今回のクロは未だ佇んでいた。
突然の出来事に処理が追いつかないでいるらしくキュルキュルとテープの巻き戻し音だけを空転させて口を開けたまま静止しているキーボ君――と、恐らくいつもの調子でじゃれていたのだろう愉快犯で確信犯な嘘吐きの王さまの姿がそこにあった。たぶん下手人は王馬君で間違いない。半端な高さに掲げられたままの片手にはバターナイフ。間違いない、あれが凶器だ! ……なんちゃって。
これは厄介なことに巻き込まれたな、と今回の被害者である私は一先ず汚れていない方の手で最後のひとくちだったブリオッシュを口に詰め込んだ。どうせ王馬君のことだ、こうなってしまったからには自分の非などどこ吹く風で兎に角この場をひっちゃかめっちゃかにするに決まっている。どうあっても確実に疲れる。既に薄れつつある額の痛みなんかより俄然頭が痛い事態になることは明白な以上、エネルギー補給は大事だった。斬美さんがみんなのために毎朝焼いてくれるパンはこんな状況下でも絶品だった。向かいで最原君と楓ちゃんがわたわたし始めるけれど、王馬君が爆弾を投下してくるまでそう猶予も無い。構わずもぐもぐさせていただこう。
「主は言いました、流石にこの状況で食事を続けられる名前は大物であると。……そこで血を流しっぱなしにするのは勿体ないなー、アンジーに提供してくれないなら早く止血するといいよー」
「っていうか! ね、苗字さん、手当てしなきゃ! どっどうしよう傷口がちょっとバターで香ばしくなってたらどうしよう!」
「赤松さん落ち着いて、色々おかしいよ……! ――おい、流石にしていいことと悪いことがあるだろ! 女の子なんだぞ、顔に傷が残ったらどうする心算なんだ! 聞いてるのか?!」
おお、ワイルド最原君が出ている。また楓ちゃんがきゅんってなるぞー……なんて未だにどこか他人事な意識で居ながら、ブリオッシュを咀嚼し終えた私も漸く腹をくくって隣に視線を戻した。そして、気付く。――……王馬君の腕は、さっきちらっと窺ったときのその位置から、少しも動いていなかった。いつもなら回り過ぎるほどよく回る舌で私たちが息つく暇もないほど目まぐるしく翻弄しにかかる言葉の嵐も、無邪気なまでに小悪魔な「にししっ」といういつもの笑い声すら、聞こえない。
「あ、……わ、わわ…苗字ちゃ……うそ、……あ、うぁ、」
彼がいつも好んで飲んでいる葡萄味の炭酸飲料のように甘く深い紫色の瞳が、仄かに水分を湛えて揺れる。わざとらしく青ざめているでもない、顔色をなくしたその表情は私が今まで見たことのないそれ。小憎らしい嘘ばかりを吐き出すとばかりついぞ思っていた、形ばかりは愛らしい唇は、本当に動揺しているのだろうかと思ってしまうほどに自然にがくがくと震えていた。
王馬君が、笑ってない。見間違えじゃないなら、――……不意の事態に、慌てているようにすら見える。最原君ですら今の王馬君の真意を測りかねて怪訝な顔をしているほどだ。
「いや、違っ……オレ、わざとじゃ…だってキー坊とふざけるのだって、いつものことで……そんな、今は別に苗字ちゃんのことなんて、なんにも目に入って……ちょっとも考えてなんてなかっ、あ、ゎ――……どうし、どうしたら、」
「落ち着いてください王馬クン! 当の苗字さんがピンピンしてるのにどうしたんですか、らしくない……茶柱さんたち、この場はお願いします。ボクは東条さんを呼んで来ますから!」
手にしていたバターナイフが落ちて、いやに大きな金属音を立てる。それを皮切りに、王馬君が動揺を言葉にまで出し始めた。此方としてはいつ「嘘だよー!」が出て来るか気が気じゃないのに、いっこうに次の感情のステージに移行する感じがない。
これ以上ふざけてると私はともかく転子ちゃんに極められかねないんじゃないか、と被害者の私のほうが心配になってきていたところで、いつだって行動が早いキーボ君が厨房に向かおうと立ち上がったときだった。
「――い、いいって! ……オレが、……オレがちゃんとやるから」
「王馬君……キミに任せるのは幾らなんでも心配なんだけど」
「こんな時に嘘なんか吐くかよッ!!」
……驚きの連続で、正直言って事故で怪我させられただけの私からしてみれば今のこの瞬間のほうがよっぽど大事件だと言っていいような。なんだって、王馬君が私の手当てを自分でするって……?
確かに、にわかに信じがたい話だった。なにせ、王馬君なのだ。日ごろがあれでそれでああな人なのだ。これがたとえば怪我したのが私じゃなく楓ちゃんで、王馬君が今の科白を言ったのであれば私だって「信用できない」と言い放っていたことだろうと思う(楓ちゃんが被害に遭った場合、たぶん最原君は王馬君に構っているどころじゃない気がする。閑話休題)。
でも、最原君が言い終わるのを待たず食い気味に呈された怒鳴り声は、彼が普段あれだけの嘘を弄する人だということを思い知らされている私たちでさえ一瞬息を飲まざるを得ない鋭さがあった。本当にどうしてしまったんだろう、と思うか思わないかのうちに片腕を強く引かれる。
「苗字ちゃん、来て」
「え、いやこれくらいそんな大事じゃないって」
「いいから行くの! ……あ、っごめ、」
ぐっと引かれて痛いほどだった腕は一旦ぱっと拘束を解かれ、次の接触はちいさく袖だけを引っ張るだけのものになった。
食べ終えていたとはいえ食器をそのままにしておくのは躊躇われてそちらに視線を残していると、アンジーちゃんが「お片付けしておくぞー。今は小吉にしたいようにさせたげてねって神さま言ってるよー」と両手を挙げてくれた。……アンジーちゃんに言われると、なんとなくそうしたほうがいいんだろうなという不思議な信憑性が出てくるから不思議だ。
「……えと、手当て、消毒とか…絆創膏って購買部かな」
「倉庫、だよ。王馬くん、……ほんとに名前ちゃんのこと、しっかりやってね?」
「……東条さんがいつでも使えるように救急箱を手前に出してくれてるはずだ」
私にしか聞こえない程度の声量で洩らされた王馬君の躊躇いがちな呟きも、ピアニストの楓ちゃんは拾って答えてくれる。未だに釈然としない表情で帽子の鍔に手を遣っている最原君が、それでも補足をしてくれた。二人ともそれだけ私のことを心配してくれていて、同時に王馬君を警戒している。……オオカミ少年みたいだな、とちらっと思った。私自身、日ごろからこの人には困らされている覚えしかないのに。
さっき怒鳴ってから喉でも痛めたのか、それからずっと口数少なな王馬君が、それを聞いて「じゃ、まず、倉庫……」とまた私の袖を引く。私には大人しくついていく以外の選択肢は最早なかった。
「苗字さんッ! なにかあったらすぐに転子を呼んでくださいね?! ネオ合気道は清く正しい女子の皆さんをお守りするためにあるのですから!」
みんな、優しいなあ。
王馬君への怒りというより私をただただ心配してくれているのであろう気持ちが伝わる転子ちゃんの真っ直ぐな声に見送られながら、いつも以上に早足の王馬君に先導されるまま私は食堂を後にした。
目の前を行く、こちらを振り向こうともしない彼の気持ちだけは、未だよく見えない。
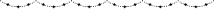
「……苗字ちゃん、……あのさ」
「んー?」
流石にあの流れから寮のどちらかの部屋で、とは運ばれず、私たちは無言の逡巡の結果――正直、いつもの調子じゃない王馬君と過ごすこの数分は今までにないくらい身の振りように困る時間だった!――なんとはなし、体育館に続く廊下にある休憩スペースに落ち着くことになった。
一番手前のテーブルに横並びでつき、向かい合わせに座っている。ちらと横に目を遣れば隠れモノクマと目が合った。トテトテと軽い足取りで歩いて離れていく。……それを眺めて見送っているうちになんだかのどかな気分になってきてしまった。私は本当に単純だと思う。そんな私だから、今日だけじゃなく毎日のように王馬君の恰好のターゲットにされてしまうのだ。――ただ、今日はなんだか、勝手が違う。
「……怒ってるんでしょ、オレのこと」
王馬君の嘘はいつだってみんなを大混乱させるし、ときどき行き過ぎて百田君から追い掛け回されたり斬美さんからお説教を受けたりすることもある。でも、基本的には――そしてどんな嘘でも最終的には、みんなが笑顔で終われるようなものであるはずだ。タチの悪い嘘だって、こちらがぎょっとした次の瞬間にはいつもの彼のチェシャ猫のような笑顔とともに「嘘だよー」とネタバラシをされる。
そうだ、今日はまだ王馬君の「嘘だよー」がないんだ。おどけたように私の前後左右をちょろつきながら「怒った? ねえ苗字ちゃん怒った?」もない。いま私の直ぐ目の前で器用に消毒液をコットンにしみこませている王馬君の表情は――そういえば今日はこの瞬間はじめて、王馬君と正面から向き合っている――未だに、私を謀ろうとする意思も、この状況を楽しんでいる素振りも、一つも感じない。
「怒ってないよ。おでこって血が出やすいし、傷のわりに結構出るから大事に思われやすいだけで」
「……理由になってないじゃん、……苗字ちゃん、嘘吐きだ。痛いんだろ」
「まあ全く痛くないとは言わないけどさあ……でも怒ってないっていうのは嘘じゃない、ほんとですってば。私は王馬君と違って嘘は上手じゃないから――あいてて」
「ほら! ほら痛いんじゃん! 嘘じゃん!」
「痛いのはほんとだって言ってるよね?! 怒ってはないよって言ってるだけで――……あ、」
屁理屈のような、駄々をこねるような問答に無防備に付き合っているうちに、不意打ちでコットンを傷口にぺちゃりと当てられる。思わず声を上げたら我が意を得たとばかりに王馬君がぐっと顔を此方に寄せてくる。普段ならこの距離、次の瞬間には何か仕掛けられて盛大に慌てているところだ。――でも、今の私はここにきてすら未だに無防備でいられた。一つ、肩の力が抜けたからだ。
「……やっと王馬君、ちょっと元気になったっぽい」
「は、……いや、苗字ちゃん何なの……女の子の顔に傷付けた野郎に何気遣ってるのさ、今だーれもオレたちのことなんか見てないのにさ、聖女さま気取ろうったってそうはいかな、」
「もーそんなのどうでもいいから! らしくないどころの騒ぎじゃなくて私ほんとどうしようって思ったんだよ……あーあ、ほっとしたぁ」
「ばっかじゃないの! 苗字ちゃんばっかじゃないのほんとに! もう!」
王馬君が、ちゃんとお腹から声を出して喋っている。楽しいことを求めるエネルギーに満ちた男の子の元気な声。……流石にちょっと憔悴している感じは否めないけど、それでも、ついさっきまで食堂にいたときの彼から考えれば、やっと元気になってくれたのだと安心できた。おまけにいつもの小生意気な軽口まで口を衝き始めた。
もとより大した傷じゃないし、そもそもおでこに傷があるくらいで損なわれるほど私は容姿端麗でもない。最初から怒ってすらいなかった私はとにかく、偶然と不運で意図せず嘘を奪われて立ち往生していた王馬君のことが心配だったのだ。生憎と彼のように感情を隠す手腕なんて持ち合わせない私が目に見えて相好を崩したのがよっぽど面白くなかったのか、王馬君は指先で私の額に当てていたコットンをぐいぐい押しつけてきた。
「心配して損した?」
「……さあね」
「王馬君ならここは『あーあ、苗字ちゃんピンピンしてるじゃん! わざとやってやったのにさ、まあ嘘だけど』くらい言うとこじゃない?」
「んうう、苗字ちゃんはオレを分かってない!」
もう治療してあげないかんね、とぷりぷりしながら絆創膏の包装を開く王馬君は、相変わらず嘘を吐けないままでいるらしい。――私なんかが王馬君を分かっているわけがないのだから、先の言葉には「そりゃそうだよ」と軽く頷きつつ、それでも一つ思い当たったことがある。
王馬君は、たまに行き過ぎた嘘を吐くけれど、ただ誰かを傷つけることだけが目的の嘘を吐くことはなかった。
ましてや、誰かに直接危害を加えるようなことなんて、一度もなかった。
あっ、キーボ君に対してはどうかなあ……と一瞬のインスピレーションが閃いてしまったのは申し訳ないけど一先ず措いて(ごめんねキーボ君……)、ということは、やっぱりこの傷は王馬君の故意で付けられたものではないのだ。つまり、
「……ケガさせといて、莫迦みたいな嘘吐くとか……つまらない通り越してただの下衆野郎じゃん」
「あはは、かもねえ」
「誰が笑ってくれるんだよ、そんなのさあ……あ、やべ」
「なに? どうした? 傷口めっちゃ化膿してるとか? それで3時間以内に解毒薬を見つけないと私が死んじゃうの? それで5分前くらいに嘘だよーって言う?」
「苗字ちゃん! ……ううう、こないだ東条ちゃんがゴン太のケガ手当てしてやってるとき、バンソコ貼るなら消毒液はしないで傷口洗うだけでいいって言ってたの、いま思い出して」
「それも嘘?」
「あのさあ! 苗字ちゃんはどんだけオレを最低野郎にしたいわけ? っつか苗字ちゃん程度でも知ってる知識じゃん、ぼーっと座ってないで教えてくれたらよかったよね?!」
「いや、私も言われて気づいたんだよねー。まあそんな変わらないってば、あっはっは」
……こんな時に嘘なんて吐けない、という王馬君の言葉は、嘘じゃないのかもしれないと思ったのだ。
これこそちょろすぎる考えかもしれないけれど、別にこれが嘘だったところで私に不利益なんて何もない。すすんで騙されたいなんてこれまでも今も考えていないけれど、それでも、不慮の事故で私なんかに望まない傷をつけてしまったことで、王馬君が大好きで大事にしている嘘の世界を閉ざしてしまうことは、やっぱりよろしくないだろうと感じるので。
ぺたんと斜めに張り付けられた絆創膏の下で、消毒液で濡らされた傷口がちくちくと疼くのが分かる。最初にこの傷を認識したときと同じように額へ指先を添えて存在を確認してのち、「ありがと」と告げた。
「……莫迦じゃん。ケガさせられてお礼とか」
「これは手当てのお礼ですが?」
「分かってるよ! でもケガさせたのもオレなんだからおかしいの!」
「わざとじゃないんでしょ? ……嘘だって言う?」
「…………ムカつく! オレから嘘を取り上げるとか……苗字ちゃん明日から覚えてなよね」
あ、それは普通に恐ろしい。ちょっと元気にさせ過ぎてしまったかもしれない。
ひょんなことから勃発した朝の非常事態を乗り越えて、気付けば空気は普段通りになりつつあった。
私が王馬君に対してこんなにも対等に、強気に接することができているのだってきっと今日かぎりの事であって、明日からはまたこの神出鬼没の嘘の王さまに怯えて過ごすことになるのだろう。それでも今は、今日のこの一幕があったからこそ、なんとなく――それもまた良し、かなと思えるようになっていた。
「あ、でも一回ごめんなさいは言ってもらおうかな」
「…………う、ぅ、……ご、……ごめ……うええぇ」
顔を近づけたままだった王馬君が一歩退く。
散々いつもと違う慌てぶりを見せてくれていたのに、それでもなお素直にごめんなさいはできないのか! 出逢った当初はとにかく底知れない、同じ人間とは思えないようなフィルタを勝手におろして見ていたけれど、こうしてみると子どもっぽい部分は案外何の衒いもなくそのまま純粋に子どもっぽいだけなんじゃないかと思えてくる。――でも王馬君は、人を傷付けることを楽しむような人ではないから。
「ほら、私はいいけどみんなが許さないよ?」
「……悪の総統に向かって脅しとか、苗字ちゃん良い性格してるじゃん」
「あー! おでこ痛くなってきたな〜」
「――……分かった、」
わざとらしく頬を膨らませてご立腹を知らせていた王馬君が、一瞬真顔になる。と同時に、決して乱暴ではない強さで制服のリボンタイが引かれた。手当てをしていたときよりずっと縮まった距離に心臓を跳ねさせる暇もなく、鼻先が触れるほど近くにある葡萄色の大きな瞳が、今日はじめて悪戯げに煌めいたのを確かに捉えた。
「女の子の顔に傷付けちゃったんだもんね、オレが責任取るよ――これでいいんでしょ?」
ここだ! ここで言うべきなんだ、さっきまでの「それも嘘だよね」を! 肝心な時に肝心な言葉を口に出すことだけが叶わず、最早ささいな痛みなんてどこかに吹き飛んでしまった私は「ほへ」と文字に起こすもお間抜けな音しか発することができず、今度こそ彼の真意を……というか今なされた発言の意味を反芻しようと試みた。と、その一瞬のうちに至近距離ですっと綺麗な三日月を描く王馬君の唇。
「にしし、……苗字ちゃん、可哀想ないじめられっこのオレの気持ち、分かった?」
――やられた! 明日から、なんて甘い見通しだった。既に王馬君は本調子に戻っている! もう私は安全地帯から足を踏み出していたのだ。身を引くことすらできず、よくよく考えれば異性との適切な距離感とは言い難いような近さで見つめ合う彼の瞳は猫のように細まり、小憎らしいほど楽しそうにしている。自分の本意にできる状況だと見て、ひっくり返しに来たのだ。間違いない。
ここから逆襲されるのか、と思うと背筋に吹きつけるような寒さすら覚え、偶然でもなんでもいいから今すぐ此処に転子ちゃんや楓ちゃんたちが通りがかってくれないかと分かりやすく涙目になった私だったが、王馬君はそこで満足したのか自分から身を離していった。手当てに使った道具を手早く両手に一つずつ取って、いつもの身軽さでひょいと立ち上がる。
強引に連れ出したくせに、一人で去っていくつもりらしい。他愛無い雑談の場から去るようにして足取り軽く一歩踏み出しながら、王馬君は振り返らずに一言だけ残していった。
「――早く、嘘にさせてよね」
……予備の心算なのか、新品の絆創膏を一つだけテーブルの上に残して。
結局私なんかが王馬君に太刀打ちしようというのが土台間違っていたのだ、と未だに何を言われたやら整理しきれていない熱に浮かされる思考のなか、すっかり静まり返った廊下に一人残された私は暫くの間テーブルの上の絆創膏を奪おうとする隠れモノクマを片手でいなす作業に従事することになったのであった。
・あの子が仮面をとられたら
//20170213
「……あっ! 王馬くん、苗字さんはどうしたんだ?」
「最原ちゃん……」
「な、……何だよ」
「ど――――――ん!!」
「っうわあああぁ?! 何するんだよいきなり!」
「煩い煩い煩――いッ! もー! あ゛ー!」
「キミのほうがよっぽどうるさ、」
「あはは、最原くんと王馬くんもう仲直りしたの? 静かにしなきゃ東条さんに怒られちゃうよ」
「えっ赤松さん違っ、騒いでるのは王馬くんだけだってば……!」
「わ゛―――!! くっそ、もぉお――――!!!」
ということで数年来のだいすき大尊敬サイト「メリル」いろはさまへ捧げさせていただきました第2弾、V3王馬くん短篇でございます!(第1弾はゆり特設2にある春川ちゃんゆめです)原作中では誰かに直接的な危害を加えることは(4章のアレ除いて)すすんで行わなかった王馬くんは、不意打ちで望まない傷を誰かに与えてしまったらどうなるんだろう、という話だけは一回かきたいなーと思っていたネタでございまして……これ幸いと相互お礼として捧げさせていただきました運びです。でもやっぱりいろはさま宅の悪戯っ子ショタ感ありつつも嘘のスペシャリストなつかみどころのない素敵な王馬くんには近づくことすらできなかった気がする……。でもベストは尽くした! 愛はこめました! こちらも何卒お納めいただけませば幸いです、ほんとこれからも仲良くしてやってくださいね…一緒にほのぼのやりたいことやっていきましょう!
prev / next
[ back to top ]