※某ゲームパロディふう
※唐突に始まる
 行き倒れは突然に
行き倒れは突然に気が付いたときには、何もかも思い出せないまま見知らぬ土地で一人倒れ伏していた。今まで僕は何をしていたのか、どうしてここにいるのか、そして此処は何処なのか――何より、僕は一体何者なのか。何もかも分からないなかで、ただ空腹と喉の渇きとを感じていることだけがひどく確かだった。
少しずつ鮮明になっていく感覚が、直に接する土の熱さを、ほど近くを流れているらしい川のせせらぎを、遠くから漂ってくる焼きたてのパンの薫りを捉えはじめる。自然豊かな人里であるらしい。あと僅かでも体力が回復したならば、とにかく民家を見つけて食事を乞うことができるのに、と思ったところで未だおぼろげだった僕の視界に何かが飛び込んでくる。凝った装飾のサンダルが印象的な、華奢な足だった。
「――あらあら、まあ! 斯様なところで行き倒れておられる御方がおいでだわ。失礼、貴方、お気は確か? しっかりなさって」
水琴鈴を転がすような、耳に心地好いその声音。努めて少しでも視界を改めようと瞼を持ち上げた僕が初めて目にしたその人は、伝記に語られる妖精か精霊かと見紛うほどに美しく愛らしい容貌を湛えた女性だった。
陽の光の温かさを集めたようにも、月の光の静謐さを集めたようにも思われるような柔らかく波打つ亜麻色の髪。神秘的な深淵と甘やかな幼気さを含んで潤んで見える紫水晶の瞳。ずっと耳を傾けていたくなるような優しげな声は、もしかせずとも僕に向けられているのだろうか。
この美しいひとに、何と返事をすればよいのか。白を基調とした瀟洒な装束の裾が汚れてしまうことも厭わず僕の眼前に屈んでくれているらしい彼女に、おそらく既に目が離せぬまま硬直してしまっているであろう僕は、情けない表情筋をなけなしの力で叱咤しながらなんとか唇を動かした。
「あ、……ッ、あの、」
「! 如何なさったかしら」
「……その、たいへん恐縮なのですが、……水と食料を、恵んでいただけないでしょう、か」
――……とはいえ、口が自由になった途端先ず喉を衝いた言葉は、当座の生命活動の維持を最優先としたものであったが。果たして僕はどれくらいのあいだ飲まず食わずで居たのだろうか、声として発したことによってついぞ忘れかけていた事実をはっきり再認識し、つかの間の活力さえ失った僕はそこで何とか上げていた面をも地に伏してしまう。
「少し待っていらしてね」という有難い返答ののち小走りの足音が何処かへ消え、数刻の沈黙ののち再び帰ってくる。衰弱しきった身の上ながら、男の矜持を振り絞ってなんとか顔を上げた僕は――依然として変わらぬ美しさを湛える彼女が手にしているものにすべての思考を一旦放棄した。
「――……ごめんなさいねお待たせしてしまって、これ、お水よ」
じょうろだった。
紛う方なき園芸用の、何なら幼児向けの愛らしいシールなど貼られているじょうろになみなみ汲まれた水が、とぷんと音を立てて水面を波立たせている。
「…そ、……その」
「?」
「すみません、……あの、できれば、飲み水…を」
「あら! ごめんなさいねえ、お水って飲み水のことだったのね――じゃあ今からお持ちしますから、先に食べ物を」
既に嫌な予感こそしているものの、「お恥ずかしいわあ、あたしったら」と照れ笑いをしている――この状況で行き倒れの人間がなぜ飲み水以外の水を欲していると思えたのかは至極不思議だが――彼女はなんとも愛らしかった。愛らしかったが、その華奢な手指が僕に差し出してきた「食べ物」とやらをふらつく視線で追ってのち、僕の嫌な予感は的中していることが分かった。
「……其方、は」
「うふふ、種ですわ! 小麦の種っ」
「…ぁ、あー……たびたび、恐縮なのですが、……できれば、僅かでいいので、その、……今食べられるもの、は」
「まあいやだあたしったらとんだおちゃっぴいを! 旅の御方、いま行き倒れておられるのだものねえ」
見て分かってほしかった。しかし、残念なことに僕の意識が持ったのは其処まで。
絶望的な状況から誰かに見つけてもらえた安心感と、なぜか味わうことになった徒労感と疲労感。こともあろうにこの目覚めから何ら進展のない境遇にありながら、僕はその場で再び瞼を下ろして泥のような睡眠に落ちてしまったのであった。
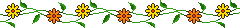
「……なんとお礼を申していいか」
「とんでもない! 寧ろごめんなさいね、直ぐにお望みのものを揃えて差し上げられなくて」
「! それこそとんでもない、何から何まで世話になってしまって、その……」
手作りなのだろう素朴なパンは、噛めば噛むほど素材の甘みを感じることができる。バターとチーズの濃厚で芳醇なこと、きっと新鮮なミルクを使っているのだと分かる。どこで採れたのだろう、葉が瑞々しくしゃきしゃきとした水気と濃い味がその鮮度を伝えてくるような色とりどりの野菜たちが器を彩るサラダ。それから、僕の意識をはっきり目覚めさせてくれるほどに確かな苦みがあるのに味わいには深みと柔らかさをおぼえる熱いコーヒー。どれをとっても印象深い、それこそ現在に至っては先の飢餓状態を脱している僕にとってもなお、質朴でありながら贅沢にも思えるような食卓だった。
今一度、深い辞儀と共に礼を述べる。何度感謝を伝えたとてきっと足りない。
大袈裟だわ、と肩を竦めて微笑む彼女――有栖川白雪さんは、今やすっかり鮮明になっている僕の視界においても尚、眩しい存在であった。
あのあと、再び目を覚ました僕を待っていたのは全身を覆う柔らかい温かさと陽の匂い――有り体に言えばきちんとした家屋の寝台、それから折よく部屋へ入ってきた彼女の「お風呂の準備ができてよ」という慈愛の響きに似た声だった。大の男を如何様にしてこの家屋(彼女の自宅であろう)まで運んできたのだろう、その苦労を想像するだに申し訳なさは極まるばかりだ。寝台の傍に準備していただいていたらしい一杯の氷水は、これまで口にした中で間違いなく一番美味しいと思える潤いであった。……と、思う。生憎と、そうそう都合よく記憶までは回帰してくれないらしかった。
そののち「殿方のお着替えなんて流石に用意がなかったものだから、あたし慌てて町の皆さまに相談しに伺ったのよ」と悪戯げに笑う彼女から、町の住人に借りたのだという着替え一式を受け取り有難く風呂を拝借してのち、待望の食事を与えられて今に至る。
「よくよく考えたら可笑しいわよねえ、どう見ても行き倒れの旅人さんにいきなりじょうろと種をお渡しするだなんて」
「……ええ」
「どうしてもお渡ししたい気になってしまったのよねえ、あたし。あなた――ええと、石丸さん…石丸清多夏さん。あなたにすごくお似合いになる気がしたのよね、じょうろと種が」
「はあ……」
白雪さんに呼ばれた己の名は、自分でも意外なほどにしっくりと自分のものとして受け入れることができた。というのも、ここにきた経緯も己の出自も現在の身の上すらも思い出せない僕であったが、名前だけは覚えていたのである。相も変わらずそれ以外にはてんで引っ掛かりすらしない、もちろん名前から想起されることも何もないというありさまは依然として絶望的であることに変わりは無かったのだが。
農耕が似合う、と言われても喜んでいいやら遺憾の意を覚えていいやら分からない。僕がそれまで如何様な生業に就いていたのかすら判然としていないのだから仕方がない。そして、仕事の話題が出たことによって、それまでついぞ喫緊の危機的状況に居たことですっかり考えることができないでいた重要な問題――即ち、これから僕はどうすればよいのかという極めて具体的且つ卑近な問題に漸く僕は直面することになった。己が何者であるか証明する手段を持たない、そもそも自分自身にすら分かっていないなどという人間が、この先どう生きていけばよいというのだろう。
彼女の些細な問い掛けを発端に声すら出ないほどの深い絶望感に苛まれることを余儀なくされた僕は、おかげで自分に新たに掛けられている問いにも暫く気付くことができなくなっていた。
「それで、あのぅ、石丸さん」
「……申し訳ないのですが、今暫く、今夜一晩だけでも猶予を戴けないでしょうか」
「あらあら、困ったこと」
「! さ、然様ですか、……否、而して僕はそもそも無理やり押しかけた身、貴女にこれ以上のご迷惑は掛けられませんね」
「いいえ、あたしは構わないのだけれど……先刻あなたのお着替えを工面しに行ったときにいろいろな方にお話してしまったものだから、彼らが待ちきれるかどうかが分からないのよねえ。もしかしたら今直ぐにいらっしゃるかもしれないわ、何方か」
「――……は、? あの、…白雪さん、その、……先刻僕が遮ってしまったお話というのは、その」
「勿論、町の皆さんへのご挨拶よ。新しいお仲間だもの、みんな今からお待ちかねなのだから」
僕は椅子から落ちた。
「きゃあ、石丸さん?! いけないわ、未だ体力も十分に回復なさっていないのだから、急に動いてはだめ」
「い、い、今、何と仰ったんですッ?!」
「んう? ですから、今日から此方で新しく暮らされることになった石丸さんを皆さんにご紹介しなくてはならないと思ったもので、……ご挨拶は人間関係の基本でしてよ?」
「そうでしょうけれども! ぼ、僕が、この町で……?!」
出会ったころと同じように――ほんの数時間前のことであるはずなのに、既に遠いようにも感じられる――膝を折って僕に限りなく目線を近づけてくれながら、「だって」と白雪さんはこともなげに微笑んでくれる。
「先程あなた、仰っていたじゃない。なにも思い出せないでいるって」
「……信じて、くださるのですか」
「うふふ、仮に嘘だったとしても特に問題ないもの。それなら、嘘じゃ無かった場合を心配したほうがずっとお得だわ」
「お得……? その、……ええと、僕にとってはこのうえなく有難いお話、なのですが」
白雪さんが、未だ腰を抜かしたままの僕の手をとって助け起こしてくれる。
華奢で儚げなその手が、今は僕のすべてを救ってくれる優しさに満ちたものであるように思えた。
「ゆっくり思い出していけばいいわ、この町に息づきながら」
//20161027
豊かな自然と、人々の温かな絆に育まれながら。
image BGM:Lil'「RUNE」