※メインページ内「Absolutely blue bird」から、鰐教授と助手
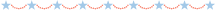
「――あ、船!」
「煩ェ」
「っな、一刀両断とかひどくないですか! ただの船じゃないです、豪華客船ですよ」
「はしゃいでんじゃねェよ幾つのガキだ手前は。……怠ィな」
「折角のご招待券ですよ、楽しまなきゃ損ですってば。サー、ただでさえ日頃お忙しくしておいでですし、こゆときくらいゆっくりしてほしいです」
「はァ、つまり平生から暇そうにしていやがる売れねェ作家のアリスちゃんにゃ休息なんざ要らねェ、と」
「強い遺憾の意を表明します! だいたいあたしだってそんなゆわれるほど暇じゃないですからね、しょっちゅう呼び出すくせにぃ――……あ、わーすごい、汽笛! 煙が輪っかですよ! 晴れててよかったですよね、絵になる〜」
「……下らねぇ」
「船に乗ったら先ずは船内探検でしょ、そのあとデッキのバーで昼からビール! ふふー、平日の昼間から飲み散らかすクールビズ運動ならぬビールクズ運動」
「手前のオトモダチの何たらって編集者が泣くぞ」
「う? なんか仰有いました?」
「……否。仮にもおれの同伴で連れてきてやってるんだ、醜態だけは晒すンじゃねえぞ」
「うそ、ぜったいなんかゆったでしょいま……汽笛のぽっぽーに邪魔されました」
「あーあー、能天気なお嬢さんは始終楽しそうで羨ましいと言ったんだ」
「前々から思ってたんですけどクロコダイル先生は本当にいじわるの国家的権威ですよね」
「知るか。……これを妙だと思わねェ方がどうかしてる」
「今回の招待券です? 怪人からでもないし送り主不明でもない、ちゃんと警察のかたから直で手渡しだったじゃないですか。内々でお礼に〜って」
「はっ、死体見つけて悲鳴挙げる役に指名されたかも知れねェんだぞ。暢気なことで」
「ネガティブよくないですよ?」
「アリス先生の乏しいボキャブラリを愁えて心優しいおれが新しい言葉を教えてやろう、これは深慮と云うんだ」
「いつもよかサーがおしゃべりに付き合ってくださる。やっぱりお船の旅にテンション上がってますよね? ね!」
「噛み合わやしねェな。次の現場にゃ手前ェの代わりにpepperでも連れて行こう」
「あ! 受け付け口にpepperくん居ますよ先生! わーい、pepperくん、このおじさまがお話したいってゆってるんです!」
「……、」
頭痛がした気がして眉間を押さえるが、指先に触れた皺の深みをいつもより浅く捉える。その事実にまた嘆息した。紫煙の雑ざらぬそれは、夏の盛りの温く緩い外気にのんべんだらりと融けていく。
やはり軽口でこの女に張り合うものではない。此方の視界の先、気の済むまでふざけ倒して満足したと見える女は白いサマードレスの裾を翻して俺に振り直りながら、帽子の鍔を傾けて稚気めかして笑った。
「なんかあっても、だーいじょうぶですよ。なんたって名探偵さまが一緒なんですもん」
まあ、成程――暢気なことで。まっこと、無邪気なことで。
図に乗らさぬようまた釘をひとつ、「手前、おれにゆっくりしろとか何とか宣ってたのは出鱈目か」などと刺すにはまったく労することがない。案の定また数メートル先で何やら頬を膨らませているのと同類視されるのは不本意というほかないが、今更――このアリスが常におれの傍をうろつく面白推理芸人であることは界隈においては最早知れたものだろう――であれば、私用のポーチを適当に放りながら歩み寄るのにもやはり労することはなかった。無様なへっぴり腰で受け取った彼奴が、此方が何を指示してやるでもないうちに勝手知ったるとばかりジッパーを引きながら受付の船員へ「大人ふたりです!」と懲りもせずはしゃぐ声を聴きながら、いつになく軽い鞄から葉巻を取り出す。ノートパソコンも、纏めかけの学術資料も、同業者の著作である面白みのない献本も、今この鞄には入っていなかった。
「なにかあったらお手伝いくらいしますってば」
「率先して仕事をしようという意識が感じられねェ」
「なんもないですってば、たぶん。そうそういつも心配ばっかしてられません」
何度かポーチを投げ返して来ようという気配をアリスから感じないではなかったが、生憎とそこでご親切に応じてやる俺ではない。
タラップを踏み、彼奴が軽やかに船内へ滑り込んでいくのを追うこともせず眼上のデッキの様子を窺えば、何とはなし、此方が警戒しているのが阿呆臭く思える程に何の衒いもなく能天気な空気だけが其処にあった。
これは却って一事が万事ウラを疑っていては傍目から見て少々具合が悪かろうか。俺のことなど置いて行ったとばかり思っていたアリスがロビー入口でにやついていやがるのは意図的に無視してやる。
「楽しみましょー、先生」
「ご勝手にどうぞ、先生」
売れないなら売れないなりに精々次作のネタ探しでもすればいい、とまでは言わないでやったというのに、其処は最早ツーカーか、飽きもせず面倒な絡み方をして寄越す。この女のようにお目出度い思考回路を持ち合わせている心算は無いが、こいつが羽目を外し過ぎないように監督してやりながら、たまには平生になくゆるりと瞼を閉じてみる時間を持つのもまあ、悪くは無いだろう。
こいつを呼び立てるのに「人が死んだ」から始めなかった旅など、実に今まで一度もなかったのだから。
・はじめての夏
//20170105
デッキを見遣った折に、夏の陽に目を焼かれでもしたか――忌々しい。
この日のためにわざわざ散財したのだと聞かされた、彼奴のサマードレスの白がいたく眩しく網膜を染めた。
←