Special"ONE"
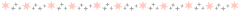 「楽しかったですねー! ……なんて、主賓じゃないわたしがテンション上がっちゃって困ります。ふふ、でも名前ちゃんも同じですよね?」 いつもの寄宿舎、私の部屋。テーブルに紙袋をおろした舞園さんが笑顔でこちらを振り返る。やわらかく上がった口角、形のよいくちびるの端に幼気な白い、宴のあとが残っていた。 「舞園さん、クリームついてる」 「! お恥ずかしい……さっきのケーキですよね」 「みんな、あんなに無理してくれなくたってよかったのに。でも、そうだね、私も楽しかっ……え、なに?」 盾子ちゃんから掛けられた「本日の主役!」のタスキを外して取り敢えずベッドに置いて(今後使う機会があるんだろうか……)、先程までの光景をぼんやり思い返しながら、気付けば自然と「楽しかった」なんて口に出しかけていた。楽しかったし、嬉しかった。それは私にとって、誕生日を祝ってもらったという出来事においてはまさしく初めてではないかと思える感慨で――そうだったはずなのだが、そんな私のしみじみとした感傷は、舞園さんによって一時停止された。 いつの間に私のごく近くにまで寄って来ていた超高校級の忍者、もといアイドルは、そこから更に私へ綺麗な顔を近づけてきて、見惚れるほど鮮やかに微笑みかけてくる。 「名前ちゃんが舐め取ってくれていいんですよ?」 「よくないです」 ただし言動はいつもの舞園さんだった。いや、笑顔が見惚れるほど綺麗なのも行動がスマートなのも私が想像もつかないことを仕掛けてくるのもよくよく考えればいつもの舞園さんだった。つまりいつもの舞園さんだった。 とはいえ、正式に「お付き合い」を初めて私も多少は成長した。動揺してばかりいられない。即座にお誘いを切って捨てつつも、右手を伸ばして舞園さんの口端からそっとクリームを拭ってやる。ほんの少しの接触。それでも目の前の綺麗な蒼穹の瞳は僅かに見開かれて揺れる。――自分から触れてくるぶんには大胆なのに、触られるのは意外なのか。それとも、いつもの私であれば単に断るだけで留まるだろうと思っていたか。こういうときの舞園さんは、いつにも増して女の子らしくてとても愛らしいと思う。ついぞ彼女は忘れているんじゃないかと思うのだが、自分ばかりが好きでいるだなんてとんでもない、私だって彼女を確かに「そういう意味」で好きでいるのだ。でないとキスだってさせないし、しない。 どちらからともなく、照れたような気恥ずかしいような小さな笑いが漏れ、そのまま二人でベッドに座る。 「……うん、楽しかった」 「それはよかったです。主催者冥利に尽きます、なーんて」 テーブルの上に置かれている紙袋からは色とりどりの包装紙が覗いている。そのすべてが言わば私の戦利品――つまり、皆から貰った誕生日プレゼントたちだった。ずいぶんと話題が逸れてしまっていた(私の中で)が、そこにきてようやく私たちは今日の日について思い出す時間を迎えた。 つい数十分前まで、私たち78期生は食堂で小さなパーティーをしていた。主賓は他でもない私、苗字名前。盾子ちゃんと舞園さんが音頭をとって――このクラスでも指折りで多忙なはずの二人が、わざわざ私なんかのために――、皆でそれぞれ準備をしてくれていたらしい。まさかそんなことが計画されていたなんてつゆも思わなかった私は、食堂に足を踏み入れた瞬間に腰を抜かしかけ、舞園さんによる開式の辞が始まるまでしばらく大神さんに支えてもらうお世話になってしまった。 その中で真っ先に出てきたプレゼントが、先程話題に出ていたケーキ。なんと、76期の"お菓子職人"の指導のもと男子のみんなが協力して――まさかの十神くんまで含めて全員参加だとのことだった――作ってきてくれたのだ。 「全員参加、とか。石丸くんの統率力…というか強制力?の賜物、なのかな。十神くんを調理室まで引っ張ってったのは舞園さんだって聞いたけど」 「十神くんがやったの、最後にイチゴいっこ乗っけただけですけどね」 「逆にすごくない?」 「確かに……。それにしても、男性陣が名前ちゃんにそれぞれプレゼント用意せずにみんなでケーキ、ってした理由ほんとに面白かったです。名前ちゃん、聞きました?」 「えっ…そもそもそういう流れがあったってことすら今初めて知ったんだけど」 オーソドックスな苺ショートのホールケーキに、私の才能を考えてくれたのか楽譜型のチョコレートやお誕生日ケーキらしさ満点のろうそくが、とても個性的な、独創的な――率直に言えば、非常に男子高校生らしい不器用なバランス感覚で散らばっているのが手作り感満載で、私としてはそれも嬉しかった。 しかし、まさか男子の間でケーキを作るにあたってそんな共通認識があっただなんて思っていなかった。そういえば、私に個別でものをくれたのは一人の例外を除いてはみんな女子であったことをそこでようやく思い出す。「わたしも苗木くんから聞いたんですけどね」と人差し指を立てて解説モードの舞園さんは、どうしてだろう、心なしか満足げなように見えた。 「本人が意図するか否かに関係なく、異性間の贈り物って何かしらの含みを持つような気がしたんですって。いつもだったらクラスメイトの誕生日なんだしそんなこと気にしないでプレゼントしてますけど――名前ちゃんだって他のみんなの誕生日にはいろいろしてますもんね――、こと、あなたに限っては特別に気が引けたんですって」 「……ど、どういうこと? え、私みんなに嫌われて」 「な訳ないじゃないですか! 答えは、いつも名前ちゃんの隣にいて名前ちゃんに寄り付く者すべてにもれなくセコムを発動する鉄壁ガードのアイドルが妬いちゃうから、だそうです」 杞憂は即座に振り払われたが、理由はそれより斜め上だった。そんなに私と彼女はクラスのみんなにとってセット扱いの存在になっているのだろうか――それって面子というか体裁というか、その、どうなのだろうか。実情をどの程度悟られているのだろうか。 「いやいや、多分だーれも何も分かってはないと思いますけどね」 「?!」 「エスパーですから?」 「早いよ! ……うーん、そんなものなのかな」 「そもそもわたし、名前ちゃんについてはお友達のときから好き好き大好きでしたし、クラスでそれを隠してた覚えもないですしね。そのあたりが印象深くてこうなってるんじゃないのかなーって」 「あっ、納得した」 いつもの舞園さんは思えばずっと前からいつもの舞園さんだったのだ。 おもむろに立ち上がり、つい今しがた自分でおろしたばかりの紙袋をテーブルから回収して戻ってくる舞園さんは、「それに、」と言葉を継ぎながら当然のように元の場所より私にぴったり添うような位置に腰を下ろして一人しみじみ頷いている。 「それこそもし皆さんが"分かってる"のであれば、わたしがやきもち妬いちゃう相手は男の子だけに限らないっていうことも分かってるはずじゃないですか」 「……あっ」 「というか寧ろ女の子に対してのほうが名前ちゃんいろいろ距離近いですから妬くことも多いんですって! なんですかこの江ノ島さんのプレゼントってば! わたし知ってますよこのスマホケース確か江ノ島さんご自分も色違いの持ってるはずです、さりげなくお揃いとか何なんですかもう! 彼女が自らデザインしたものでいま大人気ですから絶対に名前ちゃん喜んで使うだろうってわたしにも分かります! もうもうアイドル泣いちゃうんですから!」 今の私の「……あっ」は盲点に気付かされた驚きであると同時に、舞園さんのやっかいなスイッチが入ってしまったらしいことを察したものでもある。 案の定セコムの警報が鳴り始めた。紙袋におさめられていたクラスメイトの女子のみんなからのプレゼントを取り出しながら、我が国の現代美術の粋であるとすら称される美しく愛らしい顔立ちをとてもテレビで放送できないレベルに歪ませる舞園さん。さっきまで会場で私の隣に立って「すごーい、よかったですね名前ちゃん!」って一緒に喜んでたのは何だったんだ。狼狽が顔に出ていたらしく、「それはそれ、これはこれです!」と美しく凄まれる。美人の凄みはやばい。 「霧切さんのこれ、ハンカチも一見しただけで分かりますよ相当いいブランドのものでしょう……シンプルで上品な白無地にレース刺繍ですけど決して古臭くはない、名前ちゃんがコンサート会場に持って行っても恥ずかしくないような長く使えるものですね」 「う、うん。綺麗だよね」 「そして名前ちゃんは律儀で真面目ないい子ですからきっとこのハンカチは本当に長く使われちゃうんです、うう、霧切さんの贈り物を名前ちゃんが後生大事に持ち歩くんです」 「いやいや逆に使わないほうが失礼でしょ! 舞園さんが…えっと、その、……好、きでいてくれる私、は。友達から貰ったものを粗末にするような子じゃない、はず、……だよ、……ね?」 「好きです結婚しましょう」 ノンタイムで両手を握られる。なお、そうであってもその一拍後には「勿論そうじゃありませんけど恋する乙女心としては複雑になっちゃうんですよ」とアイドル全然納得してません感を醸し出されるもよう。 そのあとも、やれ腐川さんから貰った小説は男性キャラが魅力的に描かれ過ぎていて私の目を晦ましてしまわないか不安で仕方ないだの、セレスさん謹呈の紅茶は上質過ぎて私には淹れられないだろうから彼女自身が手ずから淹れてやるための口実に違いないだのと、明らかに舞園さん以外誰も心配しないような観点から散々に贈り物について心配されてしまった。基本的に悪口は一切なく、一つ一つの品と贈り主の子たちを絶賛するからこその心配ではあったけれど。舞園さんのこういうところも好きだ(口に出そうものならどうなるか分からないのでとても言えない)。 ひとしきり言い終えて長い息を吐いた舞園さん――ちなみにここまでの間、ずっと私の両手はホールドされたままである――が、「でもね名前ちゃん」とそれまでより一層か細い声で私の名を呼ぶ。何だろう。 握られていた手がやわらかく離されると、肌が感じる空気の温度が猶更冷たく感じた。舞園さんは紙袋のいちばん底、つまり一番最初に私が受け取ったプレゼントを引っ張り出してきて、月9ドラマの愁嘆場を演じる主演女優さながらに涙目で大きくかぶりを振った。 「わたし、今回に限っては誰よりも、この人にだけは負けたくないんですよ……!」 簡素なクリアケースは、中身がよく見えるようにと意図されている洒落た計算。ゴールドの茎と葉、ジルコニアを思わせる明るいオレンジ色の水晶でかたどられた大輪の花――上品且つ可愛らしいブローチがそこに収められている。完全な、大人のチョイスだった。 クリアケースの片隅にちょこんと貼られた黒いレースのテープには、「K.Kizakura」と白字のサイン。そう、私が誕生日プレゼントを受け取った唯一の例外である男性こそ、私をこの学園にスカウトしてくれた――ひいては私をこの生活へと救い上げてくれた、スカウトマンの黄桜さんである。 「勝ち負けじゃなくない……?」 「ううう……でも、だって、あーこれはほんとに名前ちゃんに似合うだろうなってわたし一目見た瞬間思ったんですもん」 パーティーが始まる前、食堂に向かう道すがらで不意に呼び止められたと思えば、『毎日楽しそうにしてるみたいで何より。これからもお友達と仲良く過ごしなね』といたって簡潔な言葉とクリアケースだけを私に握らせ、いつものように飄々と手を振って去って行った黄桜さん。私の隣で私と一緒にしばらくきょとんとしていた舞園さんが、私の手元にあるブローチを視界に認めるが早いか「んむうううう……!」となんとも言えない表情で震えて唸っていたのはこのせいだったのか。 「確かに、うん、すごく素敵だと思った。コンサートとか取材とか、人前に出るようなときにも着けていけるよね。有難い」 「んむうぅ……!」 「わ、私、黄桜さんにはほんと、感謝してるからさ……」 そういえば、誕生日について黄桜さんについてはもう一つ大きく感謝していることがあるのだ。 希望ケ峰に来る前の段階で既にピアニストとして世間から評価されている身とあって、私はプロとして一人前になった時分から、ファンの方から決して少なくない数のプレゼントを贈られてはいた。いたのだが、それが直接私個人の手に取られる機会はついぞなかったのだ。私の家庭には「あの」両親がいたこと、そしてピアノをはじめクラシック音楽を趣味とできるようなファン層は基本的に富裕層であり、プレゼントも上等で高価なものが殆どであったこと、これだけで事情は察してもらえるはずだ。 それが、この学園に来てから誕生日を迎えた今日、きちんと私の手でファンの方からのプレゼントを受け取ることができた。勿論、高価なものや上等なものであることが嬉しいのではない。大事なのはそれに付属してくるほう、きっと親からは不要なものとして私の目に触れることもなく処分されてしまっていたであろう、メッセージカードや手紙に目を通すことができるという点だった。これも、私を見つけて根気よく環境づくりをしてくれた黄桜さんが居てくれたからこそ叶ったことだと思う。思う、のだけれども。 「うぅ…冗談じゃなくアイドル泣きが入りそうです」 「でも、舞園さん」 「ふえ」 「私、舞園さんにもいつも感謝してるし。その、えと、……好き、とか、あとファン感情とか、そういうのとはまた別口で、純粋に、舞園さんに感謝してる」 「名前ちゃん……」 あと、それでもまだ勝ち負けがどうとか言うのであれば、舞園さんには何より先ずすべきことがある。 離されてからそのままになっていた両手を、今度は私のほうから握り返してみる。 「だから、最後に舞園さんが私に何をくれても、私の中では舞園さんが一番……なのは、たぶん変わらないと思う」 なにせ私は、当の舞園さん自身からまだプレゼントを受け取っていないのだ。昨日の夜から日付が変わって今日のついさっき、パーティー最中まで、「わたしがプレゼントですよ!」としきりに連呼されてはいたけれど、まさか本当にそれだけということもないだろう。 そこで言葉を切って、舞園さんをまっすぐ見る。困っているような、笑っているような、そのあいのこのようなはにかんだ表情の彼女は、なにかを躊躇っているようすで暫く長いまばたきを繰り返して、「……ですね」と観念したようにひとつ頷く。無言のまま、紙袋と一緒にテーブルから持ってきていたらしい小さな黒いペーパーバッグを、まるで母親にテストの答案を渡す子どものように私へ差し向けてきた。 「ありがと、舞園さん」 「……いっぱい考えたんです、でも、なにを贈るにしても難しくって」 「うん。あ、開けていい?」 「ええどうぞ、――……ぅ、それで、結局わたしが一番名前ちゃんに持っててほしいものを、と思って、それにしたんですけど」 中身は小さな黒い箱。 私の掌に載るサイズのそれを開けると、中には、 「わ、……綺麗。えっと、ブローチ?」 ホワイトゴールドでかたどられたト音記号のアクセサリー。頭の部分にちょこんと座っているのはこっくりとした色合いのコットンパールと、透き通った青い石。今まさに私の目の前で、私の表情の機微を窺おうと固唾をのんでいる彼女の煌めく瞳の色にとてもよく似ているなと思った。 てっきり黄桜さんと同じでブローチだと思ったのだけど、そっと裏返してみて針がついていないことに気付く。囁くようなボリュームで舞園さんが「チャーム、なんです」と補足してくれた。 「袋の中に、チェーンとキーホルダー用の金具も入れてます」 「あ、ほんとだ」 「ペンダントヘッドにもできますし、鞄とかにもつけられるんです。――……その、」 ばつの悪そうな表情になって舞園さんが続ける。 「最初は、指輪にしようって思ったんです。わたしとお揃いでもいいし、サプライズでちょっぴりお高いのにしてもいいな、って」 「う、うん」 「でも、名前ちゃんはピアニストですから。プライベートのときなら付けてくれるかもしれませんけど、いつもだって練習しますもんね」 「……うん、そうだね」 「だから、今度は日常で持ち歩けるようなものを考えたんです。バッグとか、文房具とか。……でも、そしたら今度は名前ちゃんの晴れ舞台には一緒に連れていってもらえないなって思ったんです」 「……う、ん?」 「だから、学園にいるときも、ピアニストとしてステージに立つときも、いつでも身に着けてもらえるようなものにしようって思ってオーダーメイドしたんですよ。……えへへ、その、名前ちゃんにずっと持っててもらいたいなって思ったから」 ――……驚いた。そんな動機があったなんて。 すべてを言い切ったとばかり目じりを美しい紅色に染めた舞園さんは、「ちなみに青い石を選んだのはわたしの私欲です」なんて分かりきったことを教えてくれる。流石に私にも分かる。――分かるからこそ、とても嬉しかった。 「ありがと、舞園さん」 「……いいえ。名前ちゃんのお誕生日をお祝いできて、わたしのほうが嬉しいんです」 「ううん、きっと違う。多分、今日に限っては、私のほうがずっとずっと嬉しいって思ってるよ」 みんなが私のことを考えて、今日のために準備していてくれたことが嬉しかった。 今まで素直に受け取ることができなかった好意を、きちんと受け止めることができるようになったことが嬉しかった。 子どものころに味わえなかった喜びを、取り返せたことが嬉しかった。 そして何より、 「ずっと大事にするから」 この何もかもが美しい奇跡のようなひとに愛され、少しずつでも同じ愛を返すことができる自分としてここにいることができて、本当によかったと思った。 ・Special "ONE" //20161016 「あとね名前ちゃん、もういっこプレゼントがあるんです。おまけです」 「えっ、何?」 「なんと国民的アイドル舞園さやかちゃんを差し上げます! どやです!」 「ぇ、あ、…いや、……もう貰ってるよね?」 「!」 超絶憧れ大好きサイト「レートCXX%」の小宮山さま(ここまで定型文)のお誕生日記念に献上したお祝いSSとなります。同宅ゆりゆめシリーズ「舞園さんと私」のお二人を再びお借りしてのファンフィクション、三次創作となります。捏造いろいろやらかしてますけど本家のおふたりとは一切関係ありませんのでご了承ください。(迫真) こみさまこのたびはほんとにおめでとうございました〜! これからも論破ゆりゆめ界の創造神・絶対的希望として我々を燦然と照らし続けてくださいますよう願っております。 ちなみに拙作のイメージソングはツッチーニときんぐ「Happy Birthday!!〜with a million kisses〜」です。よしんば名前ちゃんが自分自身をお祝いできなかったとしてもそのぶん、いあ軽く倍くらい舞園さんが祝ってくれるから問題ないです! |