招かれざらざる客

徹底された警備を掻い潜るという苦行ではないにしろ、本船に入った伝達だけを頼りに海を飛び、単独航行しゆく客船を追う行程は口で言うよりずっと過酷なものであり、日頃大して優先したい私情のない俺にとっては至極久々なことでもあった。高度を下げ甲板すれすれに着地する。目当ての船に辿り着き羽根を仕舞ったところで漸く一息吐いた。子供じみた低次の達成感が沸き起こる。何処ぞの舞台悲劇よろしく身分違いの懸想であろうと、甘いものは甘いのだ。
数名用の小型客船は何処を取っても己が場違いなように思えるほどに優雅な外内装をしており、それでいてこうして部外者(あいつにとっての俺がそうであるとは言いたくないが)の侵入に警鐘を鳴らすような装置がまったく無い辺りに所有者――我らが白ひげ海賊団の”教育係”にして「世界政府」の創り手たる創造主の一、アリスの言い知れぬ余裕のようなものが窺える。
船内へ続く扉を押し開ければ、幾度歩いても慣れぬ感触を足元に受ける。毛足の長い絨毯はいかにも高価なものであると言わんばかりで、昨晩敵襲を受けて数限りない賊の屍を踏みつけて来た足で汚してしまうことを躊躇いかけた。この廊下を真直ぐ行けばアリスに会えるのだという高揚感が歩を止めこそしなかったものの、こうして彼女の私船を訪ねる折にはいつも柄にもない張り詰め方をしてしまうのだということは否めない。
突き当たりの操舵室まで歩む間に左右に並ぶ船室はどれも〆切られていたが、そのどれもが空だということを俺は知っている。否、中に先客がいないというだけで、実際「客船」を銘打ちつつも殆ど人を招かないこの船では、常に談笑の代わりに黙して語らぬ知識が――つまり、膨大な本が――我が物顔で客室を陣取っているのだという事を知っているだけだ、と言うのが正しいだろうか。兎に角。曲がりなりにもウチで一番アリスと親しいのは俺で間違いないのだから(当然だ)、本人に掛け合えば俺の滞在用に一室、など確保してくれやしないだろうかと時折邪な考えが頭をもたげたりもするが、現状それは勇み足以外の何物でもないことは自明であった。(これは蛇足だが、逆にアリスがモビーに来航する機会もそれなりに頻繁にあることだし、本船に彼女の部屋など設けても良いのではなかろうかと打診することもしばしばある。一番隊隊長室――つまり俺の部屋、の隣に断固として他の船員を入居させないのにはその辺りに理由がある訳だ。アリスと出会って二十年、未だそれは一度として叶った試しは無いが。)
夜を徹して飛んで、本船からそう距離は無かったにしろ如何せん反対方向に舵を取っていたこの船へ降り立った現在、12月24日の早朝である。「世界政府」のお偉方――何せ、それを築いたご本人さまの一人だ――のアリスは、これからこの船を”聖地”マリージョアへと走らせ、海軍将校だの天竜人だのという俺たちからして見れば世辞にもお近づきになりたいとは思えない面子と晩餐会に臨まんとしている訳だ。何処ぞの神が人としての形をとってこの世に生まれた記念の日、だったか(うろ覚えなのは致し方ない、十年そこら前にアリスの手ほどきを受けて読んだ本にそうあった、程度の覚えしか無いのだから)、恐らくあちこちで沸き立ち祝宴を挙げている連中の誰も、そう深く考える訳でもなく杯を掲げているに違いない。と偉そうな口を利きつつ俺とて神の生誕祭などに興味がある訳では毛頭なく、ウチでも宴をやるというのでそれならば、と腰を上げたのに過ぎなかった。何をしにわざわざ他所の船までやって来たのかと問われれば、答えはひとつだった。即ち、この船の針路を180度真逆に――モビーに、向けさせる。「世界政府」から創造主を一日、奪う。なかなかに高揚感のある響きだと思った。
どうせ攫うのなら船は置いてアリスごと是非ウチに、寧ろ俺の処に――などと言いだすとキリがないのでとっとと事を片付けるとしよう。操舵室の扉に取り付けられた窓硝子に俺の影が落ちて光を遮りでもしたのか、扉を開く前にアリスの稚気を残した柔らかい笑顔が此方を振り向く。そういえば、二人きりだと気付いた。
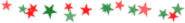
「いらっしゃい、マルコさん。どうされました?」
「否、……ちょっとな」
「あは、『ちょっと』でモビーから飛んでいらしたので? 一番隊の隊長どのともあろうものが伝書バットのような扱いに甘んじていていいんですか」
「おれの好きで来てんだ、使いじゃ無ェよい」
廊下や甲板の装飾の豪奢さから察せられるであろうが、この操舵室も最早どこかの屋敷の応接間と見紛うばかりの素人目にも高級と分かる調度品に囲まれている。「自動操舵に切り替えました。お話致しましょう」とさり気なくとんでもない事を――この船には操舵主はおろか航海士すらいないのだ、何故ならこの海において”聖地”まで帰るのに、アリスは海図を必要としないほどの土地勘を持っているからだ――宣いつつ、一見して実に暢気なご様子の此方のお嬢さんは、ひらりと手を翳して此方手前にあるソファを示してみせる。が、生憎それじゃと優雅にお話しようだなんて安穏とした目的を以て来ている訳ではなかった。否、相手がアリスであるなら幾らでもどのような話でも、したいが。それは今は措く。
「お茶、お淹れしますね。ご存知です? 毎年この時期になるとどこの紅茶屋も挙って限定ブレンドを販売するんですよ。平時のフレーバーティーと違って、ちょっとナッツやベリーなんかの遊び心が加わった心躍るラインナップでして、」
「アリス」
「ん、なんでしょう」
食器棚ひとつとってもモビーの食堂にあるそれとは何と言うか、そう、格調が違う(ウチの場合は何より頑丈さを重視しているので致し方無い事ではあるが)。缶を片手に此方へ向かって小首を傾げる仕草が堪らなく愛らしい。丁度ソファ向こうのテーブルの片隅に乗っかっていた小さな置き物を目で示してやると、合点がいったかのように「ああ、」と一層笑みが甘やかなものになった。
「今日――いあ、到着は明日になりますかねえ、それの、”向こう”での晩餐会の招待状に付いてきてたんです。ミニツリー、可愛らしいでしょう」
「お偉方と飯食うのの何が楽しいんだか、おれにはさっぱりだが」
「あは、隊長ともあろうお方が、……いあ、マルコさんは基本的に何時もそうですよね。『気取った奴は好きじゃ無ェんだ』ですっけ」
肩を竦めるのに、二の句が継げない。ただ、天竜人だの役人だのという人種を好かないのは何も俺ひとりに限ったことではなく、海の無法者である海賊であるなら誰しも同じようなものであろう。アリスがこういう言い方をするのはつまり、それだけ俺がアリスの「世界政府」絡みの用事について何かに付けて文句を言っているからに他ならない。何とも阿呆臭いことに、俺は立場がどうとか偉い奴が嫌いだとかそのような次元を超えたところで、ただアリスの時間を正式ぶって(我ながらひどい言葉の使い方だとは自覚している)拘束することができる連中に対して嫉妬しているのだ。「世界政府」に嫉妬。これほど途方も無い事も他に無かろう。
恐らくはオヤジもそれを分かっていて、且つ俺が一歩も退く気が無い事をも分かっていて、俺に航海記録の補佐をさせる名目でアリスの位置情報を流してくれたのだと思う。……そして恐らくは今頃、他の隊長陣――イゾウとビスタは確実に、ハルタとジョズ辺りも薄々――も、俺が船を空けている事から何処で何をしているのかなど深く考えずとも悟っているのに違いない。ここ数年で「腹を括った」俺は、既にこの不毛な懸想について隠し立てすることを放棄していたから、特にすべきこともないこの時間を好きに使う事に何のためらいも無かった。何と言っても海賊、欲しいものは奪うのが信条なのだ。
「楽しいですよ。あたしにとっては、彼らもまた大切な友人ですから。大将諸氏もとってもよくして下さいますし、我が愛すべき子孫たる天竜人の諸君はとってもお行儀がよくてお話が面白いわ」
「……ふぅん。んで、高い酒呑んで美味いメシ食って、それがアリスの今年のお楽しみかい」
「トゲがあるなあ。しかし、予定ではそうなっています」
いつの間に湯を沸かしていたのか、脇の給湯台へ歩を進めようとしたアリスの腕を取る。それが分かっていたかのように簡単に留められた身体は、殆ど動揺を見せることなく上体だけを此方に仰がせてわざとらしく「今度は何ですか」などと尋ねてくるのだ。
「残念だが、その予定は流れるだろうな」
「あら、どうして?」
「この先の海域、あと数時間もしたら大荒れに荒れるんだとよい」
緩く半開きになっている桜色の唇が、ゆっくり息を吐き出したのち呆れたように閉じられる。淡く苦笑の色が混じる、「仕方ないな」然としたその表情も好きだ。「関係無いですよ、この船なら耐えられます」との返答もそう真剣味を帯びず、何処か楽しげに供された。俺の右手はアリスの左、二の腕の少しばかり下部の殊更柔らかい部分を押さえている。一番大部分が触れている親指をもっと強く押し当ててその感触を思い切り味わいたい、などとこの期に及んで場違い極まりない欲望に駆られながらも、「いいから引き返せ」と続ける。
「時化に乗じてそこらの賊が乗り込んで来やがったらどうすんだ、アリスが幾ら強ェっつったって多勢に無勢じゃ結果は見えてる」
「……多勢に無勢。難しい言葉、よく覚えましたねマルコさん「莫迦にしてんのか」あは、冗談ですってば」
放っておけば「偉いです」とか何とかと褒め出しかねない処を牽制する。なけなしのプライドだった。
不意に合った視線を逸らさず居ると、アリスの目が此方を探るようなそれから何事か考え込んでいるようなそれに、ややあって何らか決断をしたようなそれになったところで俺から外れた。「やれやれ、とんだ駄々っ子に行き合ったものですね」との呟きを俺は聞き洩らさなかった。心外だ。俺は何もアリスに「とにかく一緒に来い」などと脈絡もくそも無い我儘をぶった覚えは無いのに。――まあ、先の時化の件は正直全くの出鱈目ではあったが。
缶を一旦傍らに置いたアリスが次に手に取ったのは、俺たちが平時の連絡に使うよりも過剰に装飾が施されているらしい電伝虫だった。「センゴクさん、あたしです。――申し訳ありません、あたしったら不味いときにこっちに来てしまったみたいで、この辺りの海域、なんだかここ数日ちょっとばかし不穏な空気なんですよね。……あ、無理しなくていい、て、いいんですか……? あ、いあそんな謝らせてくださいよ欠席するのはあたしの都合なんですから! ――はい、……はい。うん、申し訳ありません、シャルリアちゃんには、日を改めてまたお茶ご一緒しましょうと此方から連絡させて貰います。では」などと、何時もながらよく回る口だった。あの半分かそこらでも俺にあれば、もう少しスマートにアリスを誘いだせただろうか。否、最早それは俺ではない気がする。
通話を終えた電伝虫の頭を軽く撫ぜてから(アリスのこういう処をいちいち愛おしく思ってしまう訳だが)再三此方を振り向いたアリスが言う事には、「それで?」。
「針路、真反対に取ってくれ。ここからなら半日で戻れるだろうから」
「了解です、――あは、前代未聞ですよ。”聖地”の晩餐会を土壇場キャンセルしといて、事もあろうに海賊の宴にお呼ばれだなんて」
「前人未到じゃ無ェか。良かったな」
「……前人未到。難しい言葉、よく覚「それはもう良い」……うふ、いあ、ごめんなさい、どうにもマルコさんに馴染まなくて。難しい言葉が。ずっと見ているからかしら」
失礼極まりない物言いにもあまり強く反抗出来ない。言い分がごもっともである事もあるが、それ以上にアリスというのは機嫌を損ねればすぐにでも変更した針路を訂正しかねない女だったからだ(そもそも滅多に機嫌を損ねることが無いが)。
アリスが体重を前方に掛け一歩を踏み出すのを感じたところで初めて、先の拘束を解いていなかったことを思い出した。手を離す前に一度でも、その腕を強く握っておけばよかったと性懲りもなく後悔する。茶器に湯を注ぎ入れながら、「それにしても」とアリスは此方を見ずに今回の成り行きに関して感想を寄越した。
「もう十年も前は、マルコさんもうちょっと素直ないい子でしたよ。――いつからこんなに聞き分けが悪くなってしまったのかしら」
生憎だが、それは生まれつきである。
・招かれざらざる客
//20101225(20161224 Rewrite!)
最初から素直に「お前とこの日を過ごしたいんだ」と言ってしまったほうが楽だったのではないか、という後悔は確かにあった。