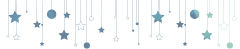「行ってらっしゃいませ名前様。」
「幸村様、くれぐれもお気をつけてくださいまし。」
「楽しんでらっしゃいませ。」
上田の城門を幸村と相乗りした名前に城の皆が見送りながら言葉をかける。名前は喜色を押さえきれない笑顔で『行ってきます!』と応え、幸村もそんな彼女を満足げに見下ろし「行って参る。」と言えば佐助が馬の手綱を引いた。
「良い天気に恵まれましたな。」
『うん!』
見上げた空は青く、春めいた暖かな風がどこからか花の香りを運んできて名前の心を弾ませた。城門からゆるゆると下れば水を湛えた堀に魚が泳いでいるのが見てとれてそれでさえ新鮮なもののように目を輝かせている。
そうして馬の背から望む城下の景色は彼女が思い描いていたものよりずっとずっと広大で美しく鮮やかな風景。名前が暮らした町は大きくなくとも背の高いビルや電柱に電線、大きな看板に視界が遮られて全体を見通すことなど出来なかった。ここはどうだ。
『う、わぁ…、綺麗、』
一面の緑、山の、森の、田畑の。緑にも色とりどりな色があるのだと改めて思い知らされる。正に命の息吹の色。素直な感嘆の声に幸村は同意すると共に、他ならない名前からの言葉を嬉しく思う。父から譲り受けたこの地を治める者としては誇らしい。そして、久方ぶりに見れた彼女らしい笑顔に幸村は万感の思いで胸がいっぱいだ。
「名前殿、今日は楽しみましょうぞ!」
その極まりを押さえることなど出来ず声を出せば感情に比例した大音声。轡を取っていた佐助が耳をふさぎ「旦那うるさいから、」と苦情をいい名前
はにこにこと溢れんばかりの笑みで幸村を見上げ、嬉しそうに頷いた。
ゆるゆると穏やかな陽気に合わせて城下へ下る。田畑で仕事をする領民が笠を外して幸村達に頭を下げて、つい名前もペコリとお辞儀する。その姿が微笑ましくて幸村も佐助も口元を弛ませた。
カポカポと馬の蹄の音はどこまでも長閑で幸村と何気ない会話をたのしみながら野道をゆるゆると進む。名前は館にはないけれど自分に見知った草花を見かけては『レンゲ!学校の帰り道にも咲いてたよ!』『うわ、つくしってこんなにたくさん生えてるの?』などと語れば佐助が「帰りに採って帰って佃煮にしよっか」と。
『土筆って食べたことない、』
「佐助の作る佃煮は美味なれば是非ともご賞味くだされ!」
『うん!』
他愛ない話に花を咲かせ、和やかに馬を進めて行く。初めての外の風景に大人びた風情は失せて、年相応の子供らしさを見せる名前に幸村の心は安堵に包まれた。
『あ、幸兄ちゃん!あそこ?ピンク色になってるお山!』
「ぴんく?」
「ああ、あちらでは桃色を総じてぴんくと表すのだ。」
「へー、旦那がぴんくなんて言うと微妙だけど名前ちゃんが言うとなんか可愛いねぇ。」
『あ、えと、ありがと佐助お兄ちゃん。』
「佐助ぇえええ!破廉恥!」
「なんで!?」
理不尽!と言いながらも佐助の顔は笑っていて、そんなかれらに名前の表情はもうずっと緩んだまま。三人で出掛けれた事が本当に嬉しくて仕方ないのだ。
山裾から丘の上、緩やかな坂道を上りながら見上げれば見事に尽きる桜の花。短い花の時を惜しむことなく精一杯咲かせる姿は命の潔さを体現しているよう。
『う、わぁ…すごい!』
「誠に、美しゅうござる!」
「今年はまた見事に咲いたねー。」
それぞれに感嘆の声をあげる三者。馬の手綱を手頃な木に結わい付け名前達は徒歩で桜の下をゆるゆると歩いていく。ちらちらと小さな薄桃の花弁が時たま風に舞う姿さえとても美しく見える。
その桜を感慨深く眺めていた名前が不意にすん、と鼻を鳴らした。つい桜に魅入っていた男二人が彼女に目線を落とすとふっくらとした頬に涙が一筋滑っていた。
「い、いかがなされた名前殿!?」
「え、ど、どうしちゃったの?どっか痛いの!?もしかして変な虫に刺されたりした!?」
幸村がオロオロする中、佐助は名前の着物の袖や裾をぱたぱた動かして虫を追い出そうとする。そんな二人に『ち、違うよ、なんでもないよ』そう言ったところで二人が納得するわけもない。二人を心配させちゃいけない、涙、止まれ止まれと目を擦っているとその手をやんわりと捕まれた。
「名前殿、そのように目を擦られては赤くなってしまいまする。それに、無理に止める必要はございませぬ。どうかお心のままに、この幸村が受け止めますれば。」
そうしてそうっと腕の中に包み込めば、ひっく、と喉を痙攣つらせて嗚咽を洩らしはじめた名前。小さな手が幸村の着物をぎゅっと掴む。その手を大きな手が包み、空いた手が背中をポンポンと打つ。佐助はただ黙って名前の頭を優しく何度も撫でた。
しばらくそうしていると、落ち着いたのか名前が幸村の腕の中で『あのね、』と語り始める。それは幸村もよく知る二人と娘である名前の家族三人の思い出。
春になったら、いつも三人でお花見に行ってたの。お母さんが朝早くから作ってくれたお弁当をお父さんが持って。それから三人で手を繋いで近くの広い公園へ。桜の下で、三人で遊んで、お弁当を食べて、お父さんがビールを飲んでちょっとお昼寝。その間、お母さんと二人であやとりしたり学校や友達の話をする。ここに幸兄ちゃんがいてくれたら楽しいのにね、なんてことも。しばらくしたらお父さんのいびきとか寝言が大きくなって恥ずかしいなぁ、もう!なんていいながら二人でお父さんの鼻を摘まめば驚いて飛び起きるお父さんを笑った。
「お幸せな様が目に浮かびまする。」
幸村の脳裏にいつも仲良く、明るく互いを思いやり、また他人をも思いやれる暖かな二人が思い出される。それだけに健やかに、幸せに過ごしてきた家族を突然奪われた悲しみは想像に難くない。そしてそれは、今の戦国の世ではどこにでもある悲しみで。
だからこそ、幸村は名前を思う度忘れてはならないと思う。このような悲しみに一人でも遇わぬように、皆がいついつまでも平らかに暮らせる世をと。
「名前殿、拓也殿、春香殿に及びませぬが、春が訪れくればこうやって幸村と過ごしましょうぞ。」
『毎年?』
「毎年でござる!」
『また、ここに連れてきてほしいな、』
「何度でも。お約束いたしまする。」
『うん、』
ぎゅっと抱きついて目の縁に残った涙を拭うと名前は顔を上げた。
『いつも、ありがとう幸兄ちゃん。』
大好き
その笑顔に佐助は口を手で押さえ胸中で可愛い可愛い!と悶絶し、幸村は某も大好きでござる!と力強く抱き返せば、小さな名前は苦しい苦しいと訴えて。けどその表情は春の日差しのように暖かく明るい。
「じゃ、ここら辺りで昼食にしますかね、ほーら俺様特製の弁当ですよーっと。」
蓙を広げた上に置かれた重箱の中は佐助が朝から拵えた品々。その中で目を引いたのはこちらでは中々お目にかかれなかった、でもあちらではお弁当と言えば必ずあったもの。
『あ!卵焼きだ!』
「卵焼きでござる!」
「名前ちゃんから聞いて作ってみたんだよね、ご賞味あれ。」
二人でいただきます!と声を揃えて取り分けられた目にも鮮やかな黄金色に輝く卵焼きを口に頬張る。すると口中に広がる仄かな甘さ。幸村と名前は顔を見合わせて「美味い!」『美味しい!』と大絶賛。そんな二人に佐助も満更でもなさそうで。鉄鍋から作った甲斐あったな、なんて。
「名前殿、佐助の弁当と桜を堪能したあとは町に下りて色々見て回りましょう!」
『そっちも楽しみにしてたの!』
「二人ともそれはちゃーんと食べてからだからね、」
佐助があれも食べてみて、こっちも、名前ちゃん、好き嫌いしないの。旦那!頬張り過ぎ!詰まらせるよ。まるでお母さんだね佐助兄ちゃん。そういう名前に佐助は苦笑う。
そうさせてんのはあんた達の所為なんだけど、けどまぁ、悪かないよこんな役もさ。
陽だまりを集めたかのようなささやかな幸せが、この二人の傍に束の間でも在ればいい。この乱世できっと悲しみや怒り、あらゆる負の感情がいつか二人に圧し掛かる日が来ても、温かで穏やかなこんな日が幸村と名前を支えてくれるだろうから。
『佐助兄ちゃんも早く一緒に食べよう!幸兄ちゃんが全部食べちゃう!』
「要らぬならこの幸村が!」
「いただきますよ!旦那に遠慮なんてしちゃ損だしね。」
腹一杯になった二人が寄り添い桜の木の下でうたた寝をしているそこへ、薄桃の花びらがヒラヒラと落ちてまるで桜の褥のよう。佐助はそんな二人を忍びに有らざる優しさを瞳に滲ませて見守っていた。
うたかたのゆめ
とこしえにねがう
初出2017.1.25吾妻