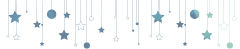暖かい春めいた日差しが室内に降り注ぐ。開け放った向こうに見える庭の花々も柔らかい気温に誘われるように固い蕾を綻ばせていた。
それを眺めていた上田城の主、真田源次郎幸村は目線を手元に戻すと書状の文字を追う。拙いながらも女手で書かれた可愛らしい文。内容の微笑ましさに幸村の表情も柔らいでいた。
「だーんな、そんなしげしげ見てたら文に穴が開くよ?」
「そ、それはいかん!名前殿からの大事な文!大切に取って置かねば!」
言葉の綾だが主なら本当に穴を開けそうだと呆れた佐助が言えば幸村は漆の文箱の中にそっと仕舞う。その中にはもう何通もの彼女からの文が収められていた。
「ずいぶんこっちに慣れてきたね、名前ちゃん。」
「うむ、名前殿の努力も大きいが、何より上田の者が温かく接してくれてる。ありがたいことだ」
それは、まぁ、城主のお人柄じゃないの?と佐助は思う。当の幸村が民を大事に考えるからこそ皆がそれに応えるように敬ってくれている。
そしてそれはそのまま、主が愛でて慈しんでいる女子にも向けられているのだ。
「そうだ佐助。そろそろ上田の桜も見頃、一度名前殿を連れて行きたいのだか、」
「あ、いいんじゃない?ちょうどあの丘の桜が頃合いになるよねぇ。でも名前ちゃんの足で歩くとちょっとあるよ?」
「うむ、なので馬でゆるりと行こうと思っておるのだ。名前殿には城下の町並みなども興味がある様子。一度行ってみたいと言うておられた。」
「そりゃあ喜ぶよ名前ちゃん。」
返事の文をしたためる為に墨を摺りながら幸村は思う。向こうではきっと、もっと「あれがしたい」「これが欲しい」とわがままや甘え放題でいられた筈だ。両親が亡くなり親類に預けられるとはいえ、それなりに自由があったに違いない。
それに比べここでの生活は窮屈で我慢の日々だ。庭に出ることは許しているし城の中なら自由にしていいと言っても彼女は日当たりよい部屋からあまり離れない。
なるべくこちらの手をかけないよう、一人で出来ることはしようとして、迷惑をかけまいとする心がいじらしくて胸がつまる。
あんなに甘い物が好きだったのに甘味一つねだったことがない。この辺りは佐助が気を利かせ色々と取り揃えてくれているがそれでもあの世界に比べてこちらの食生活は厳しい。
幸村と過ごしていた頃から数年経ち、成長してもまだまだ子供。きっと甘えん坊だったのもほっとけえきが好きなのも変わっていないはず。
あの二人の代わりになれなくても彼女を守る存在で在りたい。だから頼ってほしいのだ。家族であるこの俺に。
「色々、連れて行って差し上げたい。」
「そうだよねぇ。あ、そうそう。辻の小間物屋で京から仕入れた手鏡や櫛が並んでるらしいから寄ってみれば?」
「おお、それは良い!名前殿もきっと心惹かれるであろうな!」
名前をどのように案内して回ろうかと考える幸村は至極嬉しそうにして、もう今からそわそわとしている。文の返事に近々に桜を見に出かけようと誘いの文字を書く筆の動きは滑らかだ。
「旦那、お出かけすんのはいいけどその分の仕事は終わらせといてよ?」
「わかっておる!」
一心不乱に文を綴る主にやれやれと佐助は呆れたため息を零すがその表情は柔らかかった。
幸村の返事を佐助から受け取った名前。
何度も何度も読み返し、その度に佐助を見ては『ほんと?』『ほんとにいいの?』と佐助に窺う。佐助は彼女の頭を撫でて「ほんとほんと。」と笑うとやっと信じたのか表情をパァと明るくした。
『あ、あのね、ずっとずっとお城の外って気になってたの!どんなお店かな?どんな人達がいるかな?って』
「うんうん、」
『す、すごく嬉しい!って幸兄ちゃんに伝えて佐助お兄ちゃん!それからありがとうって!楽しみって!』
「かしこまりましたーてね!」
久しぶりに見た子供らしい喜び様を佐助はすぐ幸村に伝えると、なら明日にでも!となるのは当然で。抜かりない忍隊の長は警備も準備も万全。ただ一つだけ予想外だったのは、
「佐助も一緒だ!」
『佐助お兄ちゃんいっしょに行かないの?』
影に徹するつもりでいた佐助は驚いて目を見張るも、あるはずない尻尾をブンブンと千切れんばかりに振るのが見える主と、下から覗き込むつぶらな瞳がキラキラした可愛い名前。
佐助に「否」など言える筈もないのだった。
世界と世界の狭間で見つけた
小さなひだまり
初出2015.8.23 吾妻
お題<たとえば僕が>様