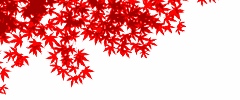 ‖撫子 「見付けたっ!撫子!」 彼女は先ほど案内してくれた自室にいた。小さな机に付属されている椅子に座っている。机の上には彼女の愛機、フリーダムガンダムロゼッタが、未だにコックピットが無い状態で立っていた。 「ニルス君……」 「っ…!!」 こちらを向いた撫子は、笑顔は湛えているが、瞳は濡れている。 儚げな微笑みに、一度言葉が出なくなった。 「怒られてしまいました…」 「え…?」 「リカルド……。私の幼馴染みに。すごく怒られました…」 リカルド。リカルド・フェニーニのことか。確かに彼女は彼を友人だとは言っていたが、幼馴染みと呼べるほど深い仲だとは思ってもいなかった。 「あの。私、先ほど、イタリアに帰ろうとしたんです」 ぽつりと、彼女は言葉を吐き出していく。なぜか……は多分、聞かなくても大丈夫だろう。僕は当事者なのだから。 「でも、それをリカルドに言ったらすごく怒られてしまいまして。私、両親が日本人で……小さい頃に飛行機事故で亡くなってしまったのですけれど…」 僕の知らない彼女のヒストリー。聞いてはいけないことかもしれない。彼女の独り言かもしれない。でも、僕は無言で耳を傾けてしまっていた。 彼女のどんなところも知りたいと思うのは、それこそ「恋」なのだと思う。 「身寄りがいなかった私は、父の友人だった今のお義父さんの養子になりました。その人がイタリアに住んでる人だったので、私は物心つくころからイタリアにいました。リカルドに出会ったのも、ガンプラバトルが好きだったお義父さんの繋がりです」 彼女はロゼッタを手にすると、優しく微笑みかける。その姿は、ひどく脆く映り、僕は咄嗟に視線を逸らした。見てはいけないものかのように感じたのだ。 「そのお陰で、私もガンプラバトルにハマって、いつか世界大会にいこうと決心しました。ガンプラバトルで世界大会にいけるまでは絶対に日本に行かないと。私にとって、日本は両親の愛した国で、すごく憧れた、大切な場所だったんです。簡単に来たくなかった」 でも、今撫子は日本にいる。そのことを指摘しようと口を開く。しかし、撫子はそれより先に言葉を発した。 「それでも今私がここにいるのは」 撫子の顔が持ち上がり、しっかりと僕を見据えてきた。スッと澄んだ瞳は美しすぎる黒色で、思わず唾を飲み込んでしまう。 「ニルス君に会いたかったからなんです」 突然呟かれたその言葉に僕は肩を震わせてしまう。撫子は少しだけ口角を持ち上げると、言葉を続けた。 「私、日本を愛した両親とニルス君を重ねて見てたんですよ。彼に会えば、両親といるのと同じ気持ちになれるかな。もっと日本のことを知れるかなって、そう思っていたんです」 「でも」途端に彼女の声は沈んだ。 「私、ニルス君を好きになっちゃいました。私は日本が好きだからここに来たはずなのに、ニルス君を好きになってしまったんです。日本よりもニルス君に対しての思いが大きくなって、それがとても怖くなった。両親の存在に、ニルス君が勝ってしまうのが」 たどたどしく、彼女は一つ一つを僕に教えてくれる。彼女の全てを。思いを。痛みや、苦しみまで。 その事実に歓喜する僕は、きっと汚い。 「諦めるとか、迷惑だとか、自分も他人も、その言葉で騙して逃げてた。満足だって、そんなことないのに。嘘ばっかり並べて。自分を支えるために躍起になった。じゃないと……漏れ出てしまいそうで…」 自嘲するように笑う彼女の頬が、ゆっくりと濡れていく。それでも彼女は泣いていないかのように続けた。 「でも、もう無理なんです。私、自分が思っていた以上に、ニルス君が好きだった。分かんないんです。日本も大切なのに。ニルス君が勝りそうで怖い…!!今までの私が嘘になりそうで……!!」 彼女が泣いている。震えている。助けを求めている。 ああ、僕が言わないと。 今彼女の、撫子の側にいるのは僕なのだから。 「僕は日本が好きです。でも、撫子も好きです」 告白、だ。一応。 彼女は、表情を歪める。きっと、感情がごちゃ混ぜになっているんだ。 「二つの思いは同じぐらいの大きさと重さで、それは多分、撫子も同じなのでしょう」 自惚れだと思われてもいい。どんな言葉でも、彼女を助けられるのなら。不器用でも不格好でも構わないから、助けたい。 「なら、二つを合わせればいいんですよ」 「え……?」 バカみたいかもしれない。僕にしては珍しい、ただの感情論だ。でも、今彼女が欲しいのは理論的な考えではなく、感情論。 「僕は撫子を思います。撫子は僕を思ってくれるのでしょう。ならば、二人で日本を思えばいい。掛け合わせればいい」 「ニルス君……」 「一人では勝れない思いでも、二人なら勝てるでしょう?撫子は二つの思いを同じだけ持って、今のままでいればいいんです。僕がいますよ。大丈夫」 我ながら恥ずかしいことを言っている。その自覚はある。でも、ほら、彼女が笑える未来を望むのならば、これぐらいは、簡単だ。 「に……ニルス君………っ」 撫子は子供のように涙を流す。それすらも愛しくて堪らない。僕は彼女に腕を伸ばし、抱き締めた。下心が無いわけない。抱き締めたくなったのだ。 彼女の身体は思っていた以上に小さかった。 「愛しています、撫子」 「はいっ…」 「撫子は、僕を好きでいてくれますか?」 「好きですっ……大好きですっ……!!」 「二人で、日本を好きでいましょう」 「はいっ……はい!」 彼女は何度も頷いて、「ああ、不器用なんだな」と理解するには時間はかからなかった。 「これからは、僕と共にいてくれますか?」 彼女はもう喋ることも出来ないのか、また何度も頷く。可愛い と思ってしまうのは末期だからだろうか。いや、きっと、多分そうなのだろう。 「僕は古風な考えを持っているようです。それも日本の」 撫子はこてんと首を傾げた。最初は積極的な子だと思っていたけれど、違うのかもしれない。むしろ、鈍感な方か。 「だから……」 そっと彼女の頬にかかる髪を払い、唇を重ねる。まるで触れるだけの口付け。それでも、撫子は呆然と両の目を見開いていた。 「僕は結婚をする相手としか接吻などしませんからね」 分かりやすいほどに撫子は真っ赤になる。やっと出た言葉は「ずるい」。僕はくすりと笑ってしまった。 「好きですよ、撫子」 僕はきっともう彼女を放せないんだと思う。でも、撫子は嬉しそうに笑うから、少しぐらいわがままに、彼女を独占してみようと思う。 「世界大会が終わったらいっそのこと日本に移住しましょうか。京都辺りに」 「ええっ!?いや、流石に子供だけでそれは……!!」 「ヤジマ商事に手配すれば、管理ぐらいはしていただけると思いますよ」 「あ、いや……あの…」 「それとも、いやでしたか?」 「いやではないですっ!嬉しいですっ」 「なら、構いませんね」 お互いを愛して、お互いで愛して。そうして二人で生きていきたいと思う。 この、日本という素晴らしく美しい国で。 back |