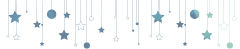
ここから始まる物語〜
「はあーあ、キリスト教でもねえのにクリスマスとか浮かれてて、ばっかじゃねーの?」
椅子をギーコーギーコー揺らして、ハヤテは後ろに伸びをした。
そこから見えた窓の外は、雪。
夕方から降り出したそれは黒いアスファルトを、すっかり白に染めていた。
「おまえ……一緒に過ごす女はいねえのかよ」
カウンターを挟んだ向かい側で、ナギは片手でフライパンを振るう。
その横で、火にかけた鍋からは、白い湯気。
狭い空間にイイにおいを存分に振りまいて
それを片手間で掻き混ぜながら、呆れたようにナギは口に笑みを浮かべた。
チリンチリンとドアが開いて、冷たい風が吹き込んでくる。
「さむっ……つか、オレはオンナとか、別に……」
ちぇ…と振り向いたそこには、5組ほどのカップル達。
今しがた入って来た、男女2人のカップルも
1つだけ開いていた席に慣れたように座った。
今日はクリスマスイブ。
顔を寄せ合い、笑い合うテーブルから囁く愛の言葉が、今にも聞こえてきそうだ。
「てか、ナギ兄の店は相変わらず混んでんな…」
店内にはナギ好みの、落ち着いたジャズが流れている。
狭い店内に並べられたテーブルは、今の客ですべて埋まってしまっていた。
手広くやっている訳ではない。
その日仕入れた旬の食材を使って、日々、お任せ料理を5組限定と云うふれこみで
コアな客に振舞っているのだが。
趣味と実益を兼ねた商売でありながら、凝った料理が幸いしてか
店はいつも盛況だった。
「つか、そう言うナギ兄だって毎年ひとりのクリスマスじゃねーかよ」
トン、と皿が前に置かれて、ようやくハヤテは椅子を引いて座りなおした。
鳥を使ったこの料理はクリスマス限定、ナギの店の名物料理だ。
この日の予約は半年も前に埋まっていた。
「……おれは店があるからな…」
濡れた手を拭きながら、ナギは店内を見渡した。
落ち着いた雰囲気の中、客はゆったり食事を楽しんでいて
会話と料理、その両方を堪能する、この空間が好きだった。
ゆえにこの店を開いてからというもの、女とイブを過ごした事は1度もない。
いや……
イブに限らず普段の日ですら、買い付けやら何やらに追われて
平日1日、定休日があるものの
試作をしたり、翌日の仕込をしたり…
正直オンナとイチャイチャするのが苦手な自分は、このスタイルを変えるつもりはなく
そんな自分に付き合って喜ぶオンナは居ないだろうと
特別女を作ろうとも、思った事は今まで無かった。
「ナギ兄は店が恋人みてーなモンだからな」
ハヤテが笑って、フォークとナイフを両手で握った。
カチャカチャと、皿を叩く音がする。
「うんめーー!」
めいっぱいほっぺたを膨らませたハヤテに、ナギはフッと笑みを漏らして
最後の客に料理を振舞うべく、食材をフライパンに放り込んだ。
ジュウウウウーと、小気味のいい音が、少しだけ店内をにぎわせる。
「ね、ナギ…っ!」
踊る食材を眺めながら、ふと浮かぶのは、1人の顔。
「イブはお店、忙しいでしょ?仕事が終わってからだけど……手伝ってあげよっか」
2週間ほど前。
出した料理を頬張りながら、詰め寄ってきたあっさみぃの顔だ。
「だっていつも、タダでご飯食べさせて貰ってるから……
それくらいしないと、バチが当たるでしょ?」
ニコリと笑う彼女がフラリと店に入って来たのは、いつ頃か。
いつの間にか常連になっていた彼女に試食をしてくれと新しいメニューを振舞ったのが始まりだった。
そのうち客に出す物とは別の、いわゆる、まかない料理を
目の前に居る腐れ縁のハヤテと同様に、いつもタダで出していた。
自分の作った料理を心底ウマそうに食う、彼女の顔が好きだった。
そんな行為に気を遣ってか
あっさみぃは仕事が休みであろう土日になると、時々店にひょっこり現れ
たいした会話もできない自分の
仕込やら店の掃除やらを、ニコニコ笑って手伝っていた。
気を遣わせているのだろうか。
たかがメシくらいでせっかくの休日を、面白味も何も無い自分に、つき合わせている。
それを申し訳なく思いながらも
来なくていい…と、強く突っぱねられないでいるのは
いつしか彼女に特別な感情を、いだくようになったからだ。
店の手伝いなんか、やって楽しいはずが無い。
なのに彼女は、独りでしゃべって、ひとりで笑って
店の物を、時々壊す。
そのたびに、しゅんとうな垂れる彼女の姿が、いつしかたまらなく愛しくなった。
「……は」
とはいえ、くすぶり続けるこの想いを
いまだ彼女に、告げる事が出来ずにいる。
それは単に、怖いから。
想いを告げた途端、「こめんなさい」というひと言で壊れてしまう
この想いと、この関係が。
だから、先日の彼女の申し出も、顔が赤くなるのを悟られないよう
「手伝いはいらねー」と、無愛想なひと言で、片付けた。
「………そっか」
いつもなら「いいよ、行くよー!」とか「押しかけちゃうもんね」とか
笑いながら、喰って掛かってくる筈のあっさみぃは
あの日そう言って肩を落とした。
キツイ言葉だっただろうか
「手伝いはいらねーけど、暇ならメシ、食いに来いよ」
そう付け足せば、彼女は慌てたように笑みを浮かべて
「うん」と小さく頷いた。
「……あっさみぃ、おせえな…」
ボーン、ボーン…
壁に掛けたアンティークの古時計が、午後8時の時刻を告げる。
振り上げたフライパンの上で炒め終わる食材が、宙を舞った。
「あれ、ナギ兄知らねえの?」
ハヤテが手を止め顔を上げた。
「……なにがだ?」
「いや…1ヶ月くらい前だっけ?あっさみぃ、会社の同僚に告白されたとか言って…」
ガシャン…
手にあるフライパンがコンロの端で音を立てた。
「その返事をクリスマスイブに聞かせて欲しいとか言われて、悩んでたんだよ…
てっきりナギ兄に相談してると思ったんだけど…」
「………っ」
そんな話、聞いてねえ…
だってアイツは…
「仕事が終わってからだけど、手伝ってあげよっか」
笑ってそう、言ったじゃねかよ。
「8時か…。確か今ぐらいの時間に待ち合わせ、とか言ってたな」
どくどくと心臓が激しく脈打つ。
窓の外は、未だしんしんと降り続く雪。
この空の下、アイツは手を擦り合わせて、自分の知らねえ男の事を
鼻を赤くして待ってるだろうか。
「アイツ、男が出来たら…もう店に来ねえかもな…」
ハヤテの声が、全く耳に入ってこねえ…
あっさみぃが、どんどん遠くに行っちまう。
さようなら…
そんな言葉も告げないままに
客と店主と云う関係は、そんな簡単に壊れてしまうものだったのか。
「知らねー男に持っていかれるくらいなら……おれ、告白しとけば良かったな…」
けど、身体はまるで機械のように腕を動かし続けていて。
無意識のうち、素早く料理を皿に盛り付け、カップにスープをよそった。
「ハヤテ悪い……これ出しといてくれ」
いつもなら絶対にしない所作で、出来上がった料理をカウンターの上にドンッと置く。
首を傾げるハヤテの顔も視界に入らないほどのスピードで
背中を向けてポケットをさぐった。
そこからはもう、身体が勝手に動いていた。
耳元でコール音が無常なまでにゆっくり響く。
「……もしもし?ナギから電話なんて珍しいね?」
間抜けた声に、けれど、心臓のどくどくがとまらねえ。
「おまえ……今、どこだ?」
「今?……今、○○駅だけど…」
会話の途中で素早くバンダナを掴み取り
腰のエプロンを放り投げた。
「ハヤテ悪い!あとは金、受け取るだけだから!店番頼む!」
「は?……ちょっと、ナギ兄ーー!」
チリンチリン、と鈴が鳴って、バンッとドアが音を立てた。
「……さむっ!」
冷たい風が吹き込んできて、ハヤテは肩を両手でさする。
「やっとナギ兄も、気持ち伝える気になったかよ…」
おせえよ…
閉まったドアを見つめて、ハヤテはフッと笑った。
「ちょっとナギ、話し聞いてる?」
握り締めた携帯電話の通話口から、慌てた声が響いている。
閉じ込めた想い、それを口にしなければ…
この先もずっとこの関係が
続くもんだと思っていたのに…
「おまえ、まだ、ひとりか?」
「え?…あ、うん、…って、何かあったの?ちょっとホントに聞いてる?」
クソッ
ノーがどうした
ごめんなさいがどうしたよ
そんなモンもう、くそったれだ
「ねえ、ナギ…!もしもーーし、もしもし?」
「……俺は……いや。おまえ、そっから1歩も動くなよ!」
無口で不器用なサンタクロースが
今からお前をさらいに行くから
ここから始まる物語〜〜
(告白?あの話は断るってハヤテに言ったじゃん)
(あー…そう、だっけか?)
(……ハヤテてめー!)
おわり