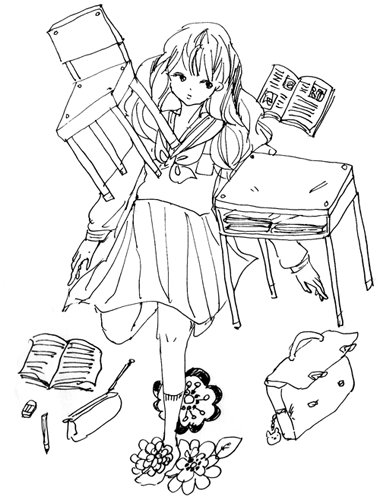蒼茫と縹渺
突然人が来たことに驚いたのか、男は力を弱めた。チャンスだ、そう思ったベルタはすがる思いで「たすけて」と声を紡いだ。ジャージ男と視線が交わる。
「最初からそのつもりだ」
自信に満ちた表情で、響くような低音。男がそう言い切った瞬間、ベルタの黒く沈んだ世界は鮮やかに色付いた気がした。急にどくどくと脈を打ち始めた心臓は酷く冷えた体からじわじわと熱を放った。赤く染まる頬に気づかない振りをして、ジャージ男を見つめたベルタの一瞬だか何分だかわからないような時が進む。すると信じられないほどの速さで振り下ろされた何かが目の前を掠め、ふわりと髪が舞った。
そしてそれはベルタの腕を掴んだ。引っ張られる感覚の中、やっとその何かがジャージ男の腕だと理解した。男はもう片方の腕をベルタの背中に回すと力強く引き寄せた。硬い胸板に頬が当たると、お線香のような煙たい臭いが鼻を刺激する。瞬間、先程ベルタを捕らえていた男は吹き飛んでおり、ドン、と鈍い音が路地に響き渡る。巻き上がった土煙が視界を悪くするのを横目で見ると、今度はモヤの中にいる影がたすけてと地面を這いずっていた。
路地の埃っぽい臭いも相まって、何が起きているのかベルタにはわからず、男の抱擁の中、呆然とその光景を見つめるだけしか出来なかった。
「平気か」
終わったぞと優しく離す丁寧な動きに驚いた。ジャージの上からでもわかる鍛えられた腕、先程の常人離れした動き。この男がやったことは全て現実なのだろうか、ベルタは信じられなかった。ベルタは男の顔を見上げた。こちらを見ずに走り去った男や、目の前のジャージ男に思考を奪われて、おい、という突然の声に全身が震えた。大丈夫ですというベルタの声も上擦った。
「もう夜中に出歩くんじゃねえぞ」
返事をしたことで大丈夫だと判断したのだろう、満足そうな顔をしながら今度はジャージ男が去ろうとした。ベルタは先程感じた高揚感を思い出し、この男を知りたいと思っていた。
このまま帰らせては、全てなかったことになる。ベルタは、来た道を戻る男を追った。ジャージの裾を引っ張り、「まだ怖いので家まで送ってください」と、その場しのぎの、なんとか時間を稼ぐための言葉を吐いた。何度も通っている道だからなのか、奇跡が起きたからなのかはわからない。実はもう怖くなかった。なんなら今さっき起きたことは夢だったのかもしれないと、そう思えるくらいには立ち直っていた。だって、それなりにいい体格をした男があんな軽々しく、あんな清々しく吹っ飛ばされるだなんて、あまりにも現実味がなかった。そんなベルタの心情を知ってか知らでか、大きなため息が頭上から聞こえてきた。
「しょうがねえな、どこだよ」
ため息と一緒に吐かれたイエスの言葉に思わず笑みがこぼれた。ベルタはこの出来事を夢にしたくなかった。これから起こるだろう何かを期待して、ベルタはこっちです、と男の行く方とは反対の、噴水のある公園へと向かった。
一定の距離で置かれた公園の灯りに照らされながら、無言の状態が続いていた。ホタルの出すような光で、ぱちぱちと不規則に音を鳴らす街灯の下に、酒瓶をもってベンチに寝そべるホームレスがいた。ベルタはそのホームレスが消えかけの街灯と同じように見えたが、「あぁ、また居る」と無感情に思いながら横を通り過ぎる。なんだかんだベルタもこの街に染まっているんだと、細い針で心の隅をつつかれているような気になった。
同時に、ベルタはどうやってこの男に礼をするかを考えていた。ベルタにとっては、こっちの方が大事だった。することがなければこのまま感謝の言葉を伝えて、さよならすればいいのに、ベルタにそうするつもりはない。
名前と連絡先を聞いたら家で食事を振る舞うか、それとも今度どこかのレストランでご馳走した方がいいか、悶々と思考に耽っていた。が、結局どっちもやろうという答えを出して考えるのをやめた。
何も考えないでいると、ざ、ざ、と一定のリズムを刻んでコンクリートを蹴る音が耳に入ってきた。普段なら大して気にしないその音だけれど、一人分、それもベルタの、自分の足元からしか聞こえないそれはあまりにも違和感があった。男のほうは無音だなんて、普通ではない。緑のジャージに怖い顔、昨日の盗みに、今日のこと、色々思い出して改めて感じた。
「あの、この辺りに住んでるんですか」
後で聞ければいいと思っていたベルタだが、この不思議な男のことを急に知りたくなった。今を逃したら二度と知ることができないような、謎の予兆にベルタはすぐさま無鉄砲に質問を始めた。男は眉をひそめ、突然どうしたと言いたげな顔で答えた。
「いや、たまたま寄っただけだ」
歩く速さを緩めずに男は答えた。男にとってこの出来事はなんということもない日常なのだろうか。落胆する気持ちを抑えられず、ベルタは「そうですか」と返事をした。
ということはすぐに帰ってしまうだろう。先程の考えは当たったように思えた。残念な気持ちを隠さずに、呟くようにお礼がしたい旨を伝えると、男は眉間にシワを寄せたまま「気にすんじゃねえ」と言うので、ベルタは何も言えなくなる。
そのまま歩き続けると自分の住んでいるマンションが見えてきて、連れてきたのは自分なのに少し恨めしく思った。ここでお別れか。
ベルタはここですと、この背の高い男を見上げた。男は「おう」と一つ言葉を置くと、「じゃあな」と続けた。そしてまた先程のように背中を向けてしまい、ベルタは焦る。このままでは何も知れないまま終わってしまう。そんなの嫌だ。
「あの!」
気づいたら叫んでいた。男は歩みをピタリと止めた。振り向く間も与えず、私は続けた。
「連絡先、教えてください」
真っ白になった頭で言いたかった言葉を絞り出す。尻すぼみになったが、伝わったのだろう。男はゆっくり私の方に戻ってきた。歩いてくるのを見て安心する。
良かった、教えてくれるのかな。
男のことをまっすぐと見つめて、いいよの合図を待った。
「わるいな、いま携帯持ってねーんだよ」
しかし期待とは裏腹に、言われたものはノーという返事で、ベルタは泣きそうになった。
ウソだ。持ってるでしょ。なんで教えてくれないの、ひどい。
ベルタは男のポケットが長方形に主張してるのを見つけていた。手を優しく頭に置かれたが、惨めで、恥ずかしくて、振り払いたいとさえ思った。
私はこれっきりにしたくない。
「じゃあこの辺で困ったら、絶対ここに来てください」
考えて出てきた言葉はベルタの勝手な約束。暖かくなった春の夜風が目の前の男の視線のように冷たく感じた。
「この辺で困ったらな」
そして男は皮肉った笑みを浮かべる。それは男がここには二度と来ないと暗に伝えていた。
「ベルタです。私の名前。あなたの名前も教えてください」
終わりたくない。関係を持ちたい。せめて名前だけでも教えてほしい。
あー、とか、んー、などしばらく考える素振りを見せると、この男はあっけらかんに「ダニエルだ」と答えた。
「ダニエルさん」
ベルタは忘れないように復唱した。それじゃあと言って去っていったダニエルの背中が見えなくなるまで、ベルタはその場を動けないでいた。遠くで、弱々しく光を放っていた街灯がブツリと切れたのが見えた。