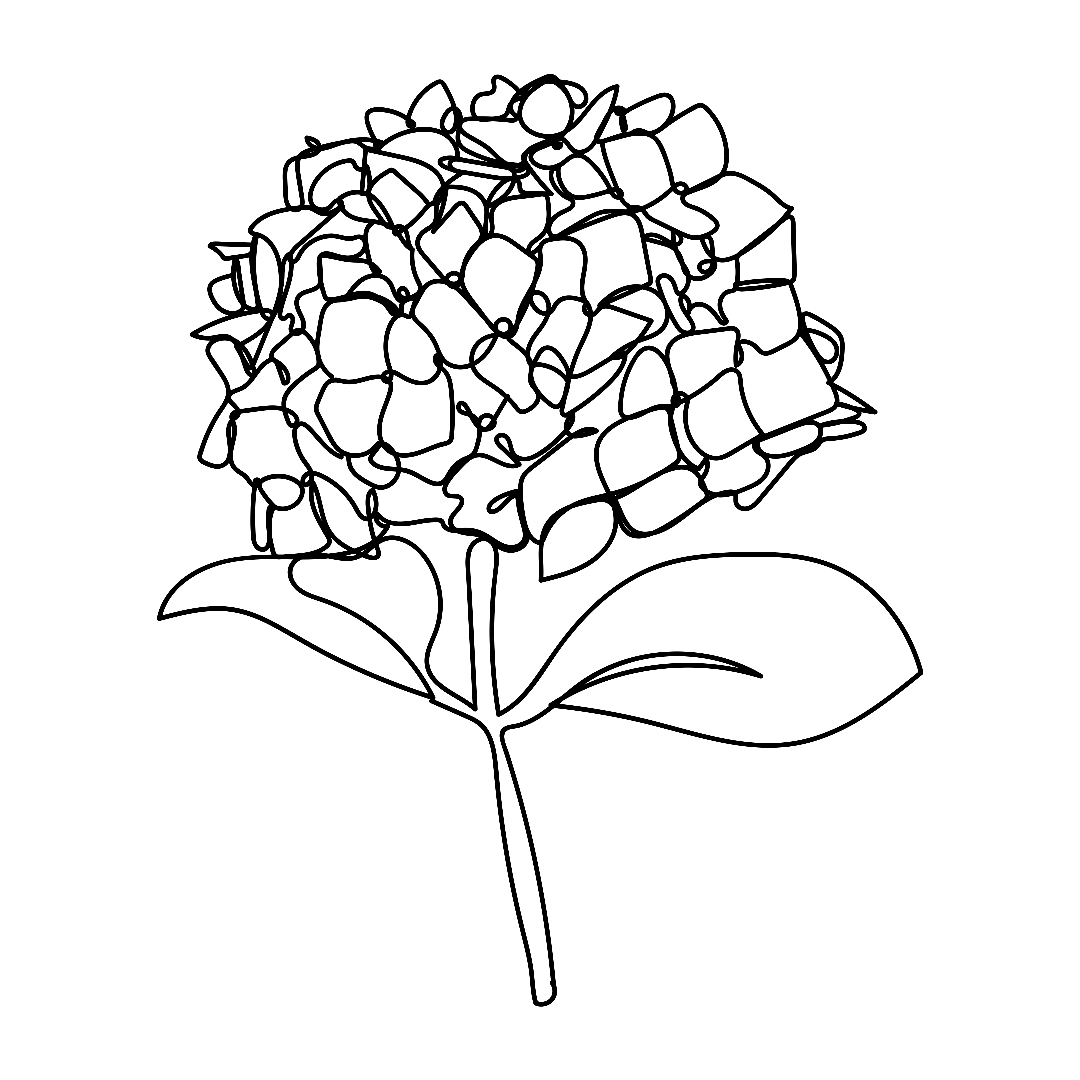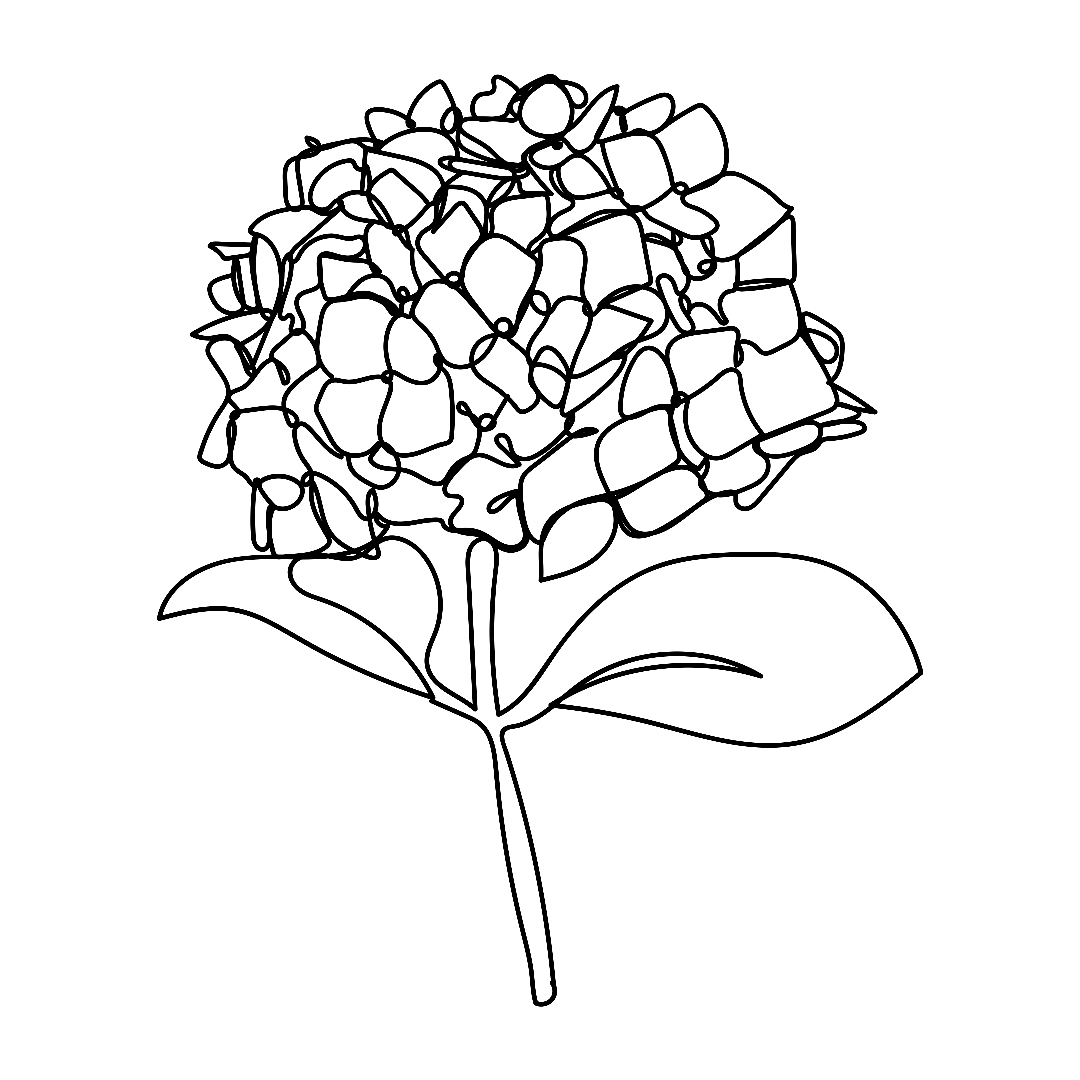透きとおるガラス瓶。差しこむ朝日にかざせば、瓶底にあつめられた小さな天然石がきらきらと瞬いて、心地よい音をたてて転がっていく。淡い期待と初恋のような甘酸っぱさが詰めこまれた、新しい自分のかけら。それをまとえば、たちまち春になった気分になって、ドアノブに手をかける瞬間から浮き立つようだった。
「なまえ! おはよう」
「あ、二人ともおはよう……って、なんだか眠たそうだね」
「昨日灰原が急に部屋に押しかけて来たんだ」
「えぇ……七海だって結構楽しんでたのに」
女子寮を抜けてすぐ、男子寮へ続く道と合流する場所で七海くんと灰原くんと出会った。いつも通り制服をきっちり着こんでいるけれど、どこかその姿はまだ覚醒しきっていない様子で二人とも何度も目を瞬かせている。出会ったころから少しだけ背が伸びた彼らは、あのころ変わらないまま、いやそれよりもうんと打ち解けて互いを支え合っていた。
「なまえはおやすみだよね、どこかに行くの?」
右に灰原くん。左に七海くん。途中まで一緒に行こうと、三人並んで出入口の門へ向かう。すると灰原くんの問いに答えたのはわたしを挟んだ七海くんで、「夏油さんのところだろう」と彼はあっさり見抜いてそう言った。
「ああ! だから可愛い格好しているのかぁ。似合ってるよ」
「おい灰原」
「えっ。あ、ありがとう……」
別に今更かもしれないけれど、改めてそう言われるとなんだか恥ずかしくて二人の顔を見れなかった。彼らと出会ってから五年目の、久しぶり休日。高専の五年目は卒業後のために設けられた期間であるのでほとんど授業はなく、各々のペースで任務に就いたり、将来のための準備や勉強など、わりと自由に時間を使うことが出来る。そして傑先輩は去年高専を卒業しており、もう寮にはいないため、こうして休みの日は彼が住まう家や高専以外の場所で会うことの方が多くなったのだ。
「じゃあ私たちはこの先で補助監督と合流するから」
「うん、気をつけてね」
「なまえも楽しんで来てね。あ、あと夏油さんにもよろしく!」
この地はある意味ひとつの故郷のようなものなのかもしれない。視える者、そして同じ志を持つ者、みなどこかしらに共通点あって、苦難や困難と戦いそれを乗り越え帰ってくる地。もちろんその中には二度と帰って来れなくなった者もいれば、帰りたくないと思う者もいるだろう。けれどもわたしたち三人はこの約五年の間、それぞれを送ったあと、必ずまたここに帰ってきている。それはとても、とても幸せなことだった。
手を振って、灰原くんと七海くんを見送る。ちょうど向こうからも補助監督が来たようで、そのまま二人は車に乗り込み高専を出発していった。すると彼らの手を引くように追い風が吹いて、色づいた木の葉が空高く舞う。どうか二人とも、必ずまたここに帰ってきますように。もう何度目かわからないそれを祈る。高専に入学して約五年。たくさんの仲間と出会い、そしてたくさんの別れも経験したわたしたちは今、新しい秋に迎えられている。
* * *
高専から少し離れた都内。駅から少し離れた待ち合わせ場所に向かえば、既にそこには傑先輩が到着していた。彼もまた出会ったころよりも背が伸びて、少しだけまとう空気や雰囲気も変わった。
「おはよう、なまえ」
「ごめんなさい、遅くなりました」
「ううん。ちょうど私もさっき来たところ」
わずかにつめたさを孕んだ眼差しが、途端に柔らかくあたたかいものへと変わっていく。その変化は誰かにとっては寂しくて悲しいことなのかもしれないけれど、わたしにとっては喜ばしいと思えるものでもあった。以前の彼は、感情を隠すことがとても上手くてたくさんのことを抱えていたから。
傑先輩は高専を卒業後、フリーの呪術師となった。そして非術師との交流も極力控えるようになった。出会ったころから彼の奥底に眠っていた傷や、彼を追いつめる原因となっていたものは少しずつ彼を蝕んでいって、あるとき彼自身を襲ったのだ。数年前の夏。とある任務で二人の少女を保護したときの話だ。
彼はわたしの手を取って、駅から遠ざかるように道を進んでいった。近ごろの任務の話。それと今朝会った灰原くんと七海くんの話。傑先輩の最近あった出来事の話などをしながら、住宅街を抜けていく。
「じゃあ今日の可愛いなまえを最初に見れたの、私じゃないのか」
「……」
「ふふ、赤くなった。この服はじめて見たけど、新しく買ったの?」
「えっと、はい。久しぶりに会えると思ったらつい……」
すると傑先輩はもう一度「可愛いね」と言って、繋いだ側とは反対の手でわたしの頭をそっと撫でた。
「あれ。なまえ、なんだかいい香りがする」
「あ、実は……香水を買ってみたんです」
「香水?」
「はい。あんまり好みではないですか?」
新しい自分、と言うとなんだか大袈裟な気もするけれど、少しでも傑先輩に見合う人になりたくて、家入先輩と相談しながら購入した香水。強すぎず、繊細な印象を持ったそれは春のような心地よい香りで、わたしのお気に入りになったものだ。
彼は一度瞬きをしてから顔を寄せてわたしの髪の上で小さく息を吸った。途端に縮まった距離に少しだけ緊張して、身を固くする。ハーフアップにされた彼の黒い髪の、下ろされた部分がゆらりと揺れた。
「ううん。すきな匂いだ」
「……よかった。傑先輩も……あっ、傑……さんもすきだといいなって……」
「あはは、簡単には抜けないね」
「ずっとそう呼んでいたので……」
「別に無理しなくてもいいんだよ」
「わたしが、呼びたいんです」
「そう?」
「はい」
小さな変化は日々の中にたくさん潜んでいる。それはまるでかけらを集めながら生きていくようだった。浜辺で見つけたシーグラス。空から降り注ぐ白雪。肩に舞い落ちた花弁。そのかけらは決しておそろしいことばかりではなくて、わたしたちが大人になっていく、眩いかけらでもあるのだ。
歩幅を揃えて歩いていく。たくさんのことを抱えて、たくさんのことを背負って前に進んでいってしまう傑さんに、少しでも追いつきたかった過去。でも今は、彼はわたしの隣にいて少しずつ色んなことを分け合うようになった。だから今度こそ、今度こそ彼を守りたい。ずっと隣にいられるように。
* * *
整備された大きな公園は土日になれば家族連れで賑わう場所でもあるが、今は予想通り人も疎らで穏やかな静けさに包まれている。陽射しはあたたかいけれど、涼しい秋風がわずかに吹いて過ごしやすい空間。辺り一面に咲く白や桃色の秋桜が、風に揺られてさわさわと音を立てる風景がとても美しい。
この公園にはもう何度も訪れていて、わたしたちは決まって人通りの少ない散歩道を歩き、花を眺め、鳥を眺め、会えなかった時間を埋めるように言葉を交わす。途中の見晴らしのいい丘のようなところで昼食を食べるのも、もういつものことであった。
「今日は本当に天気がいいね」
「そうですね。昼寝したら気持ちよさそうですね」
「いいね、このまましちゃう?」
レジャーシートを敷いた上にころりと横になって、傑さんは瞼を閉じる。空から注ぐ柔らかな陽射しに照らされた彼は、数年前よりもどこか解放されたようにも見えた。あのころはよく眉間に皺を寄せて、苦しそうな、切なそうな表情をよくしていたから。
「本当に寝ちゃうよ」
「あ、ごめんなさい」
「ううん。そのまま撫でて」
記憶をなぞるように触れていた眉間にもう一度指を這わす。そこから額へ、髪へ。ゆっくりと、傑さんの頭を撫でる。すると彼は心地よさそうに表情を緩め、再び瞼を閉じた。
もどかしい夜を過ごし、不安な朝を迎えた日々。それは呪術師である以上、今も、そしてこれからもわたしたちに付きまとうものではあるけれど、あのころよりも少しだけ強くなれたわたしたちは、乗り越えられる力がある、勇気がある。不安だと、心の声を零せる勇気が。わたしたちはあのころよりも、自分たちに優しくなれているような気がするから。
誘われるようにそっと、彼のくちびるに口づけを落とした。穏やかな時間。安らかな時間。そんなときを、彼がこれからも過ごせますように。もう彼が自分を追いつめたりしませんように。だいすきな彼が、幸せだと感じられる未来が訪れますように。
「さっきよりも優しくて甘い香りがする」
「香水、ですか?」
「うん。なまえらしい香りだ。柔らかくて、落ち着くような」
近づいた距離の先。傑さんはゆっくりと目を開くと、下からわたしを覗き込んでじっと見つめた。あのころよりも大人びて見えるのは、自分の不安や葛藤を受け入れることが出来たからなのだろう。けれどもそんな彼だってただの一人の男の子だということを、わたしはもう知っているから。
「傑さん。やっぱりお昼寝はやめて今日の晩御飯を考えながらゆっくり帰りませんか?」
彼が少しでも健やかな日々を送れるように。彼の隣にいられるように。見合う人になれるように。わたしはそのためならなんだって、どんなことだって出来る。
わたしたちはまだいびつで、未完成だ。けれど、それでいいのだ。変化に溢れる日々。そのなかでときに悩み、迷いながらも、ひとつひとつかけらを集めるように生きてゆくことでわたしたちは大人になっていくのだから。そこに正解か不正解かなんてなく、ましてや誰かが決めることでもない。自分で考え、選択していく。そうしてそのこたえは。
そのこたえは、彼と生きる四季が教えてくれる。