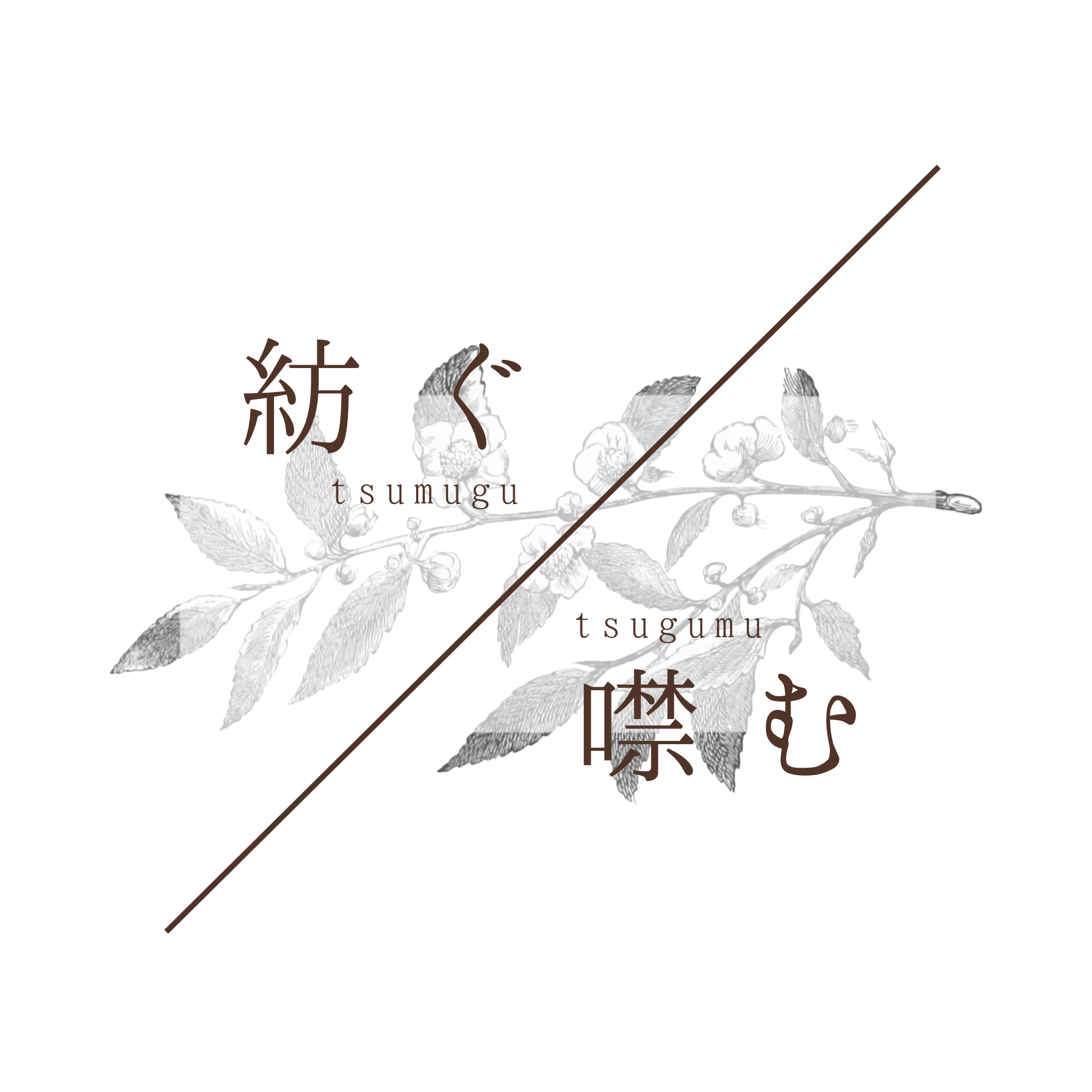
肌寒くなってきたから鍋が食べたいね、という話をしていたのだ。その年は暑さの残る曖昧な期間が特に短かった年で、あっという間に寒くなったのを覚えている。金木犀の香りがまだ記憶と鼻の奥に残ったように名残惜しい日々を過ごしながら、白くて薄い、スーパーの袋をぶら下げて足並みを揃えて家へと帰った日。二人の家ではなかったが、昔から雲雀はよくわたしの家に転がり込んで夕食を食べ、たまにそのまま泊まることもあった。じゃあ次来る時は鍋にしようかだなんて話もして、彼が好きな鶏団子のレシピを頭の中で思い返したりもした。ほんのり柚子の香りがするやつ。好きだとか、そういうことは一度だって言ったことはなかったけど、他の具材よりも手をつける回数が多いことは知っていた。それなのに。それ以降、彼がわたしの家に来ることはなかった。もう、一年前の話だ。
雲雀に対しての印象は、まずはじめに美形から始まった。その次に恐ろしい人。更にその次は不思議な人。そこから先は案外普通の人、だった。もちろん、やっぱり普通じゃないやと感じる時もあったけど。
並中に入学したばかりの春。初めてその姿を見た時わたしは、年は同じくらいのはずなのにもう随分と顔立ちが出来上がっているな、と思った。ツンと澄ました表情で校内を歩く姿はつい数年前まで小学生だったとは思えなくて(この時わたしは彼が同級生なのか先輩なのかよくわかっていなかった)、その完成された姿に驚いた。
どんな声なのだろう。どんな性格なのだろう。そう思うまでは一瞬のことで、わたしも、そして周りも、その飛び抜けた容姿と纏う空気に惹き込まれ、いつの間にか目で追うようになっていた。しかし彼がその見た目通り、いやむしろそれを上回るほどの冷たさと強さを兼ね備えた人だと周知されるのも、また一瞬のことだった。わたしも、そして周りも、しばらく前とは打って変わって視線を合わせないようになった。廊下ですれ違ってから、その背中を盗み見ることはあったけど。
わたしはなにに関しても平均に値するような人間で、特にこれといって褒められたことも、また叱られたこともなかった。しかしその日だけはたまたま寝坊をして、朝から全力疾走して学校へと向かっていた。友人から借りた少女漫画にハマり、結局最終巻まで読んでしまって気がついたら三時過ぎ、なんてことになってしまったからだ。
別にそれほど朝の準備に時間がかかるわけでもないけど、せめて前髪くらいは真っ直ぐに整えたいとドライヤーを当ててから家を飛び出した。時間には間に合わないけど先生が来るまでには間に合いそうな、ギリギリセーフ(アウト)のところまでせめて頑張りたいと、起きたばっかりの体に鞭を打って足をとにかく動かした。追い詰められていたからか、普段の登校時よりも体が軽いような気がした。多分、百メートル走のタイムをこの時測ったら自己最高記録を叩き出していただろう。それくらい、わたしは焦っていたし、無我夢中で走っていた。
「はい、アウト」
「う、っわ?!」
「五分遅刻。遅れてきた場合どうなるか、わかってるよね?」
びっくりして、思わずその場にひっくり返りそうになった。何故なら誰もいないように見えた校門から、並盛最強といつの間にか恐れられるようになっていた雲雀が姿を現したからだ。彼は冷たい目でわたしを見下ろして、どこから取り出したのかもわからない長い鉄の棒を手に持っていた。わたしは、そんな物騒な、と思ったけど逆らう方が怖いので下を向いたまま「ハイ」と素直に答えた。しかしいくら待ってもその鉄の棒が振り下ろされることはなく、不安に思ったわたしは少しだけ顔を上げて彼を盗み見た。パチリ。目が合ったあと、ヤバい、と一瞬焦ったが彼は「……鞄は?」と訝しげに眉をひそめるだけだった。
「鞄?」
「まさか、忘れてきたのかい?」
「鞄……え?! スクバ!!」
サーッと全身から血の気が引いていくのを感じた。体がいつもより軽いとは思っていたけど、まさかスクールバッグを家に忘れてくるだなんて思いもしなかった。というより、それに気付かない自分に驚愕しすぎて固まった。雲雀は眉間の皺を更に深くして、「馬鹿だね」と言ったあと「家の人は誰も気付かなかったのか」とも言った。
「あ、いや、わたしは一人暮らしなので……。すいません……戻ります。咬み殺されるのはあとででもいいですか」
「…………」
「えっ、と……」
「はあ、いいよ。別にこっちにわざわざ寄らなくてもいいから」
「え、でも」
「いいから。もう鬱陶しい」
雲雀は「興ざめした」と言ってその場を立ち去った。結局その日は一旦家に帰ってもう一度登校したが、よく見たらセーターのボタンも一つずつ掛け違えていてあとになってめちゃくちゃ恥ずかしくなった。
◇
そのあとしばらくわたしと雲雀の間にはなにもなかったが、約一年ほど経った頃に突然話しかけられる機会があった。内容的には「近所に沢田綱吉という男が住んでいるか」というようなものだったが、住んでいることは知っていても特に関わりがないのでそのまま彼に伝えた。その時は「ふうん」の一言で彼との会話が終了したが、しばらくしてから謎のハプニングに巻き込まれることが多々あり、その度にわたしは雲雀と遭遇するようになった。それは校内でも、校外でも。
それからだろうか、特に意味もなく彼から話しかけられるようになったのは。初めは驚いたけど、尋ねれば案外答えは返ってくるし、間違ったと謝罪すればあの鉄の棒で殴られることもなかった。本人から聞いたが、あれはトンファーだと言うそうだ。どうしてそんなもの持っているのかと尋ねた時は返事が返ってこなかったけど。
「そういえばあの日から遅刻はしていないみたいだね」
「う"……今思い返しても恥ずかしいのでその話はやめてもらっていいですか……」
「ボタンも掛け違えていたし」
「気付いてたの?!」
「…………」
「あ、いや、気付いてたんですか……」
今度こそヤバい気がする、と思った。出会ってから約一年と半年。あの日と同じようにわたしは思わず俯いた。多分、トンファーで殴られるまではいかないだろうけど、流石に怒られるかなとは思った。
しかし、隣にいた雲雀からは「別にいいよ」といつもと変わらないトーンで返された。残暑の残る放課後、ぬるい風にのって黒髪がさらりと揺れるのを見つめながら、わたしはパチパチと瞬きを繰り返したのを覚えている。彼は「なにその顔」と少しだけ眉をひそめた。
「えっと……怒られるかと」
「前から言おうと思ってた。その喋り方変だよって」
「へ、変って……」
「別に今までも敬語が外れてる時あったし」
「うそ……」
「それに僕のことも違うところでは雲雀って呼び捨てだろ」
「え、なんで知って……?」
「声が大きいから」
確かに雲雀と話すようになってからクラスメイトに色々と聞かれることは多かったが、そんなに大きな声で話していたつもりはなかった。しかし無自覚が一番怖いなと思ったので、わたしはこの時密かに気をつけようと思ったのだ。そして雲雀はその時、一人決意するわたしの姿を見て「アホ面」とほんの少しだけ笑った。夕焼けに照らされたその姿に、わたしは再びパチパチと瞬きを繰り返した。
◇
どうしてこうなったのかもう詳細を思い出すことは出来ないけど、ひょんなことから雲雀がわたしの家でご飯を食べることになった。わたしが一人暮らしをしていたことはあの寝坊をした日に知られていたし、確か有無を言わさずわたしが夕食を作らなければならない状況になったような気がする。そもそも彼は基本的に我儘で横暴だから、突然変なことを言ったりするのだ。だからこの時もそんな感じで決まったんだと思う。
しかし料理のことはしっかりと覚えていて、その日わたしはハンバーグを作った。理由は母が得意だったのと、メニュー的にも王道だったから。どうしてそのことだけは覚えているかと言うと、緊張して何度も練習したのと、後日雲雀の好きな食べ物がハンバーグだと言うことを知ったからだ。その時は、わたしって実はエスパーなのでは? と思ったりもした。「馬鹿なの?」って彼には呆れられたけど。
その日から彼は度々わたしの家にふらっとやってきてはご飯を食べるようになった。まるで野良猫が餌を求めにやってくるようだった。それは中学生活を終え、高校生活でも、そして大学生活に突入したあとも。もちろん進学するのは別々の学校だったので中学を卒業してからは校内で会うことはなかったが、家に来るようになってからは校内で話すこともなくなっていたので(元からそれほどたくさん話していたわけでもなかった)、特にこれといって変化を感じることもなかった。
話す内容は学校の話や、最近誰を咬み殺しただとか、そんなようなこと。たまに沢田綱吉の名前が出てくる時があって、二人の関係がいつの間にか繋がっていたことにも、そして中々切れないことにも驚いたことがある。あといつの間にか雲雀を取り巻く環境が“風紀委員”から“風紀財団”という名前に変わっていたことにも驚いた。
わたしと雲雀の関係性は年を重ねることによくわからなくなっていった。はじめは確かに友人だったはずだ。しかし中学を卒業しても、また高校を卒業しても、彼はずっとわたしの隣にいたし、いつの間にかその距離間も縮まっていた。暖かい春の日には手を繋ぐようになったし、寒い冬の日には体を寄り添うようにもなった。しかし体を許したことはただの一度もなくて、彼もそれを求めたことはないけど、妙な空気感になったことはある。
体を許したことはないと言ったが、キスは、何度かしたことがある。しかしその時わたしは既に雲雀のことが好きになっていて、わたしって雲雀のなんなの? とは聞くに聞けない状況になっていた。存外彼のキスはガラス細工に触れるかのように酷く優しくて、勘違いしそうになった。別に毎日優しいというわけではないけど、そういう、わたしに触れてくる時だとかたまに見せる表情だとかが、次第に優しく甘くなっていくのをむず痒く感じながら、しかしその糖度に侵されつつもあった。過ごす時間が長くなればなるほどわたしは彼のことが好きになっていった。そうして変わらずわたしのところに来て隣にいてくれることに喜びと、そして哀しさを感じるようになっていった。気ままな野良猫は、わたしから手を伸ばしてしまえばどこかへ行ってしまうだろうと思ったから。哀しくはあったけど、でも幸せだった。
◇
雲雀がわたしの元に来なくなってから一年以上の時間が経って、遂に夢にまで見るようになったらしい。数ヶ月来ないなんてことはあったけど、一年は過去一度もなかった。不安になり始めた頃は、なにがいけなかったんだろう、最後の会話はそれほど変なことは言っていないはずだと、何度も何度も考えた。今まで大して交わしたこともないメッセージ画面を開いたりもした。けど、なんて送ればいいのかわからずにその度にその画面を閉じた。原因が、わからなかった。
共に過ごした日々の中で、たくさんのことがあった。楽しいことも、悲しいことも。高校を卒業したあたりだろうか、喧嘩をしたことだってあった。流石に殴り合いはしたことはないが、言い合いみたいなことはした。主にわたしが一方的に怒っていたようなものだったけど。それでも当時の雲雀も思ったことをわたしにぶつけて、しばらく不穏な空気が流れていた時期もあった。しかしそんな時期があっても離れることはなかったのに。
出会いから今まで、雲雀の本質や日常は未だ謎な部分が多い。いつの間にか出来た風紀財団にいるということは聞いているが、具体的になにをしているかまでは把握していなかった。しかし以前と変わらず並盛が好きだということは十分理解していて、最近並盛で行方不明者が出ており以前よりも安全な場所とはいえない状況になっていることも知っていた。だから、雲雀は今並盛にいないのでは、とも思った。
こんなことになるなら、やっぱり好きだって言っておくべきだったんだろうか。今更になってたくさんの後悔がわたしを襲う。そう言うなら、会いたい、と素直に連絡してみたらとも思うけど、やっぱりわたしはどこまでも臆病で、打つことは出来ても送信ボタンが押せないのだ。
彼と話した最後の日の翌日、鍋をやるために奥から引っ張り出した土鍋をわたしは未だにしまえていない。あの鶏団子の材料だって、用意したのに。こんなにも、好きなのに。
すると突然、玄関の鍵が開く音がした。そしてそのあとには鈍い金属音。わたしは机に突っ伏した顔を勢いよく上げて、壁越しにじっと見つめた。耳の奥で大きく響き渡るように脈の音がして、じっとりと汗が滲むような感覚が襲う。この家の鍵を持つ者はわたしと、そしてふらりとやってくる一人の野良猫のみで。
「やっぱり泣いてる」
まるで一年ぶりとは思えない様子で雲雀は姿を表した。目が合うと彼は小さく笑って、いつも使うグラスを食器棚から抜き取って麦茶を入れる。やっぱり泣いてるって、なに。こっちはこんなにも不安になりながら過ごしていたというのに。突然のことにわたしは混乱したが、いても立ってもいられずに彼の元へ駆け出した。
トン、と彼の背中にぶつかって、緩く作った拳をその広い背中に向けて叩く。溢れ出る涙も、ずるずると流れる鼻水も、もう止められなかった。そのせいで彼のスーツが汚れたとしても、絶対に謝ってなんかやるもんかと思った。
「鍋の準備、してたのに」
なにも答えない雲雀に、わたしはその黒いスーツをぎゅっと握りしめる。本当はなにしてたの。わたしのことどう思ってるの。聞きたいことは山ほどあるはずなのに、わたしの唇はそれを紡がなくて。好きだよって、ずっと会いたかったんだって、素直な気持ちも言えなかった。
雲雀はくるりと体を反転させると、わたしの顎を掴んでぐっと上を向かせた。そうしてわたしの顔を見るなり、「酷い顔」と小さい声で呟いたあと、「待ってた?」と続けた。
「待ってた、って。そんなの、待つに決まって……もう、なんなの、」
最初に鍋が食べたいって言ったのは雲雀なのに。一周回って怒りが湧いてきそうだった。けれど雲雀の指先があんまりにも優しくわたしからぼろぼろと零れる涙を拭うから、そのあとに続くはずだった言葉は喉の奥でつっかえたように出てこなかった。表情は相変わらず澄ましているのに、やけにその手つきと眼差しは柔らかくて、キスをする時みたいに甘かった。
「……好き、好きなの」
気づけばそう口にしていた。雲雀がわたしをそんな目で見つめるから、紡いでしまったのだ。一度言ってしまえば、あとはもう塞き止めるものがなくなった川のように溢れていって「今までなにしてたの」だとか「雲雀はわたしのことどう思ってるの」だとか、今まで悩んでいたのが嘘のように零れていく。
「ムカつく奴がいたんだ」
「へ……?」
「僕の並盛を荒らそうとした奴がね……。だから咬み殺そうと思って」
「一年も……?」
「ここからは秘密。知りたい?」
勿体ぶった言い方にわたしは一瞬戸惑ったけど、それでも素直に頷いた。雲雀はわたしの指に細くて長い自身の指を絡めると、ぐっと屈んで顔を近付ける。窓から射し込む夕日が睫毛の影を作り、彼の頬に映った。そうして彼は「いいよ、教えてあげる」と、うんと、優しく囁いた。
「ただその代わり、もう前みたいには戻れないから」
「戻りたく、ない」
「その言葉、後悔しないようにね。ああ、それと、僕もなまえが好きだよ」
え。と、言葉を発する前に、雲雀の唇がわたしの唇を塞いでそれは飲み込まれた。