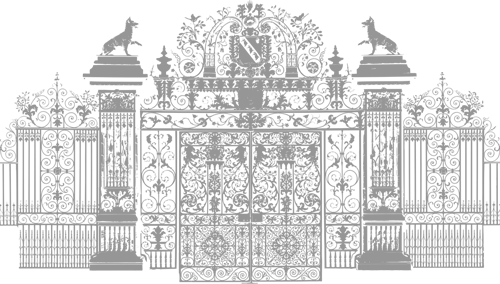夏月の記憶
夏月の記憶俺たちの関係性を一言で表すなら、やっぱり幼馴染だと思う。
幼い頃からずっと一緒で、なにをするにも三人で。誰かが風邪を引いたりしたら、二人でお見舞いに行ったりしたし。三人でいるのが当たり前過ぎて、別々の道を歩む未来を想像できなかった。
小さい頃からの癖で、秋良と俺は「秋ちゃん」「月ちゃん」と呼び合う仲だった。
俺たちの仲の良さを揶揄して『おホモだち』だとか『男レズ』って言ってくる人もいたけれど、それを気にして離れるなんて選択肢は浮かびもしなかった。二人も揶揄する言葉自体への抵抗はあったみたいだけど、離れようとしなかったからたぶん俺と同じ考えだったんじゃないかな。
何でも俺は赤ちゃんのときから『整っていた』らしくて。アルバムを見る度両親や親戚が褒めそやすのを聞いていた。
小学校に上がってからはハーフを珍しがられて、中学生になったら学校中の女子に告白されたんじゃないかってくらい、日ごとに呼び出されたりして。高校にもなると学区外の人も集まるようになるから、本当に気が休まらなかった。人の多い街に出たときなんかは逆ナンだけじゃなく怪しいスカウトまで寄ってきたし。残念ながら俺は普通の芸能界と裏ビデオやホストの勧誘を見抜けるほど場慣れしていなかったから、寄ってくる人は全部怪しい人だと思ってお断りした。
周りの人間は俺のことを王子様だって言う。完璧な見た目に、完璧な中身を勝手に想像して、俺と付き合ったら自動的にお姫様になれると思ってる人ばかりだった。
俺はどちらかというと、自分がお姫様でいたい人間だったんだ。っていっても別に年中ちやほやされなきゃ嫌だとか、そういうんじゃなくて。
性を自覚したときから、俺は後ろでしかイけなかった。AVを見ても、女優さんのほうに感情移入しちゃって「俺もあんなふうにおま○こにおち○ぽがほしい」としか思えなかったり。女の子を抱きたいなんて一瞬だって思わなかった。
絶対誰にも言えなかったし、学校で孤立なんかしたら待っているのは地獄だから、俺は必死に皆の望む王子様で居続けた。
そんな俺が自分でいられるのは、秋ちゃんと冬悟と一緒にいるときだけ。
最初のきっかけは、高校の修学旅行のときだった。
旅館では複数の班で纏めてお風呂に入らなきゃいけなくて、冬悟が大浴場で股間のご立派様をクラスメイトに「AV男優ち○ぽw」「勃起させてみろよ!」「やべえ、人殺せそう」と揶揄われていた。
それを俺たちが助けて、落ち込む彼を二人で慰めたんだ。
冬悟は中学三年になった辺りから体が大きくなっていって、比例しておち○ぽにも成長期がきちゃったらしくて。高校二年生になる頃には大人顔負けどころじゃない、極悪な凶器が完成していた。
そんなだから冬悟は女の子と付き合ったことはないし、人前で裸は勿論下着姿にも絶対なりたがらなかったのに。女の子だったら修学旅行で生理だって言えばお風呂を一番最後に回してもらえたんだけど、俺たち男子はそうもいかない。
畳に敷かれたお布団に座り込んで、大きな体を縮めて俯く姿は、等身大テディベアみたいで凄く可愛くて。俺はいつもなら高すぎて届かない冬悟の頭をくしゃくしゃに撫でたんだ。
「夏月……?」
「そんな顔しないの。俺は冬悟がどんなに大きくなってもずっとずっと大好きだよ。秋ちゃんだってそうだろ?」
「うん。中学で背を抜かされたときはふざけてズルいって言ったけど、あんなの全然本気じゃないし……いや、ちょっとは羨ましかったけどさ……そうじゃなくて、俺は見た目や身長で友達選んだりしないよ」
ゴツいクマさんみたいな大男がくしゃりと顔を歪ませて、タオルに顔を押しつけてぐすぐす啜り泣く姿はあまりにも可愛かったけれど、身長のことでそんなに悩んでたなんて思っていなかった俺たちは、顔を見合わせてから冬悟を左右から抱きしめた。
大きくて頼もしくて力も強くて、オマケにち○こまでデカくて。男として羨ましい要素の詰め合わせみたいな冬悟。
可愛くて愛おしくて。こんな優しい子が、なんで自力じゃどうしようもない身長や体格のことでとやかく言われて悩まなきゃ行けないんだって思ったら、やるせなさで胸がいっぱいになって――――
「んぅっ……!?」
気付いたら、不意に顔を上げた冬悟の唇を、そっと塞いでいた。
「んっ……ふ、んぅ……は……ッ……」
冬悟はびっくりしたけれど、抵抗しないでいてくれた。もしかしたら彼の力で俺を突き飛ばしたら命が危ないってわかって抵抗出来なかっただけかも知れないけれど。
「る、月ちゃん……!?」
「んー? ふふ。秋ちゃんもする? 冬悟のお口、気持ちいいよ?」
「えっ、ええっ!?」
冬悟の唇を舐めて見せながら言うと、秋ちゃんはあからさまに動揺した。だけど、秋ちゃんも冬悟も俺のしたことを「ありえない」「気持ち悪い」とは言わなかった。
混乱しちゃってそれどころじゃなかっただけかな。そうだとしても、いきなり男が男にキスしたら、それを本気で嫌悪してたら、やっぱり顔に出ると思うんだよね。
「え、と……俺も、していいの……?」
「ん……」
冬悟はよくわかっていないなりに頷いて、秋ちゃんのほうを向いて目を閉じた。
俺たちは全員童貞で、それぞれが訳あって女の子が苦手で。かといって、俺以外はたぶん同性愛者の自覚はなかったんじゃないかな。
抑も誰かと付き合うとか、そういう発想がなかったんだ。
だって俺たちは、ずっと一緒だったから。
「んんっ……ふぁ……
 あっ……んっ
あっ……んっ 」
」冬悟は最初、唇同士をくっつけるだけの拙く幼い秋ちゃんのキスをただ受け止めていたけれど、すぐに秋ちゃんの後頭部を抑えて舌を割り込ませた。
分厚い舌が口内を蹂躙する度、秋ちゃんの体がぴくんぴくんと跳ねる。下を見れば秋ちゃんの秋ちゃんが元気になっていた。
「ね、気持ち良かったでしょ」
「う……うん……」
ふわふわする頭で頷く秋ちゃんも、ほんのりとろけた冬悟も可愛い。
いまなら押せるんじゃない? って、心の悪魔が囁いた。
「俺、考えたんだ。俺たちは生まれたときから一緒だったでしょ。だからこれからも一緒がいいなって思ってた。でもこの中の誰かが他の誰かと付き合ったり結婚したら一緒じゃなくなっちゃうじゃない?」
秋ちゃんと冬悟の視線が集まる。二人とも熱っぽい顔で、股間を膨らませていて、凄く可愛い。そんな顔されたらいますぐ二人がほしくなっちゃう。
「そうなるくらいなら、俺たち三人で付き合っちゃえばいいんだよ。ね?」
「俺たち、三人で……?」
「そ」
ピンときていない様子の二人をぎゅっと抱きしめてから、それぞれのち○ぽに手を添えた。二人ともビクッとなっただけで、振り払われたりはしない。
「片方と付き合ってるのに、黙ってもう片方ともえっちしたら浮気だけど、最初から一緒なら浮気じゃないもの。いつも通り、いままで通り、一緒にいるだけ」
「うん……そう、なのかな……?」
服越しにち○ぽをくにくに弄っていたら、快楽に弱いのか、早々に秋ちゃんの顔がとろけてきた。冬悟は難しい顔をしていたけれど、暫くして俺を窺うようにそろりと見上げて。
「月と秋は……俺のこれ、へいき……?」
そう言って、下を脱いでギンギンに勃起したち○ぽを見せた。
俺のとも秋ちゃんのとも全然違う。規格外過ぎるお化けち○ぽ。どうしてだろう。あんなの絶対痛いし、苦しいってわかってるのに、ほしくて仕方ない。俺の体をあの凶器で屈服させて、俺の身も心も雌にしてほしいって思っちゃった。
隣を見たら、秋ちゃんも俺と似たようなことを考えてる顔をしていた。
「へいきっていうか、ほしいって思っちゃった……いきなりは無理だと思う、けど、慣らしてとろとろにしたところに突っ込んだら気持ちいいだろうなって」
「……月ちゃん、凄くえっちで綺麗な顔してる」
「秋ちゃんもね」
くすりと笑って、俺たちは二人揃って冬悟のち○ぽに顔を近付け、二人揃って太い幹に舌を這わせた。
「先生の見回りが来ちゃう前に、おち○ぽいい子いい子しなきゃね」
「お布団、汚さないようにしないとだよね……?」
「そうだねえ。イキそうになったら俺が咥えてあげる」
「いいなあ、月ちゃん。次は俺に譲ってね」
「もちろん」
いま俺が舐めてるのって腕だっけって思うくらい、ガチガチに固く立ち上がって、ぶっとい血管が浮き上がって、張り出したカリ首は紅く充血していて。全方位隙なく立派なおち○ぽ。しゃぶってるだけでも体が勝手に雌だと思い知っていくのに、もしこれをお腹に収めちゃったらどうなっちゃうんだろうって期待が膨らんでいく。
視線を上げてみれば、冬悟は口元を押さえて必死に耐えていた。その表情が本当に色っぽくて、本当に同じ高校生だろうかって過ぎった。
「ッ、月……っ、もう……」
「イキそうなの? いいよ」
ぱくりと冬悟のち○ぽを咥えると、喉奥まで迎え入れて吸い付いた。驚いたことにそれでも真ん中くらいまでしか飲み込めてなくて、これを全部口に収めるには本当に喉を使わないとだめだなあ、って思いながらじゅぽじゅぽ音を立ててしゃぶった。
俺が冬悟のち○ぽを咥えているのを、至近距離で秋ちゃんが見つめている。視線はとろけて、頬は紅く染まって、呼吸は浅く短くなっている。
「ぐ、うっ……!」
「んんっ
 」
」どぷっと勢いよく口の中に射精した瞬間、ただでさえぶっといち○ぽが膨らんだ。顎が外れるかと思ったし、冬悟の精液に溺れるかとも思った。
口の中がどろどろのえっちなミルクでいっぱいになって、濃厚な雄の匂いで、脳の芯まで犯されている気分になる。
こんなの知っちゃったら、冬悟のち○ぽなしじゃ生きていけなくなっちゃう。
「はぁ……
 冬悟の濃厚おち○ぽミルクおいし
冬悟の濃厚おち○ぽミルクおいし 秋ちゃん、ちょっとだけおすそ分けしたげるねえ」
秋ちゃん、ちょっとだけおすそ分けしたげるねえ」「んんーっ
 んふっ
んふっ んぅうっ
んぅうっ
 」
」ねっとりと絡みつくようなキスをして、口の中に少し残しておいた冬悟のミルクを舌で送り込むと、秋ちゃんは腰をビクビク跳ねさせて果てちゃった。
「ふぁ……
 るなちゃ、どうしよ……おれ、ねむい……」
るなちゃ、どうしよ……おれ、ねむい……」「あらら、いっぱい気持ち良くなっちゃったんだね。いいよ、あとはやっとくから、秋ちゃんは先に寝てて」
「ん……ありがと……るなちゃ、とーご、らいしゅきぃ……」
スヤァ。っていう擬音の幻覚が見えた気がするくらい、スッと寝入った秋ちゃんを二人で暫く見つめて、それから外が少し静かになっていることに気付いて。もうすぐ見回りの時間だと思い出した俺たちは、慌てて後始末をした。
その日から俺たちは、誰かの家に集まって遊ぶついでに、冬悟のち○ぽを舐めた。家ではま○こにしてもらう穴をほぐしたし、学校へ行く前にローターを仕込んだりもした。どれもこれも、大好きな秋ちゃんと一緒に、大好きな冬悟のち○ぽに雌にしてもらうため。
きっと俺は、誰よりも大事な二人を間違った方向に導いてしまったんだと思う。
けれど今更、手放す気になんてなれるはずがなかった。