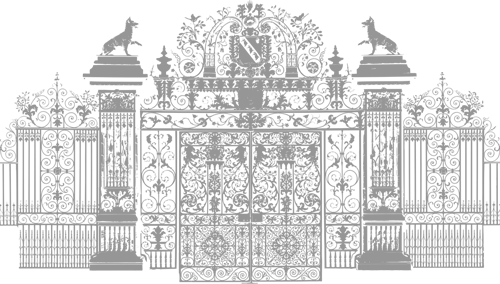テセウスの少女
テセウスの少女朝の身支度をしているときのこと。
ふと視線を感じて振り返ると、鏡を見ながらピアスを装着している
 の姿をじっと見つめる鶚と目が合った。その表情には隠しきれない好奇心が映っており、手招きをすると素直に近寄ってきた。
の姿をじっと見つめる鶚と目が合った。その表情には隠しきれない好奇心が映っており、手招きをすると素直に近寄ってきた。「なんか気になることでもあったか?」
小動物のような仕草に思わず笑みを零しつつ訊ねると、鶚は「それ」と言って
 の耳を指した。
の耳を指した。 の両耳には所狭しとピアスが空いている。メジャーな耳朶だけでなく耳殻などにも銀の装飾が輝いており、それが彼の印象をより近寄り難く見せている。
の両耳には所狭しとピアスが空いている。メジャーな耳朶だけでなく耳殻などにも銀の装飾が輝いており、それが彼の印象をより近寄り難く見せている。変異種は基本的に、どのCODEであっても肉体の修復機能が高い。それはピアス穴を空けたときも同様で、通常の人間が数ヶ月から長くて年単位の時間を要するのに対し、変異種は一日もかからない。
傷の修復が早いため、ファーストピアスをうっかりすぐに外してしまうと穴自体が消えてしまうほどである。
「……凄い数だと思って。痛くはないのか?」
「全然とはいわねえけど、痛いのはあける瞬間くらいのもんだな」
「そういうものなのか」
目を丸くして見入る鶚の表情は、珍しく年頃の少女らしくあどけない。
 は左側の髪をかき上げて良く見えるようにすると、一つ一つ指していった。
は左側の髪をかき上げて良く見えるようにすると、一つ一つ指していった。「これがインダストリアル。こっちがトラガス、これがダイスでこれがヘリックス。ピアスはあける位置にだいたい名前があるんだ」
「へえ。知らなかった。ピアスは全部ピアスって呼んでいたな」
「それでもいいんじゃねえの。あけてなきゃわかんねえことだしな」
依然真っ直ぐ注がれる視線を感じながら、かき上げていた指を髪から離す。
はらりと落ちた髪が耳元を覆い隠して、鮮やかな金色の隙間から鈍い銀色が僅かに覗くばかりとなった。
「ピアスが痛そうっつーけど、お前こそ全身機械化してるだろ」
「施術には麻酔が使われるから、別に。それにもう、痛みを感じる部位は殆ど残っていないしな。なにより、戦略兵器として運用するのに痛覚は邪魔だから、最終的には全てなくす予定だ」
「……そうか」
当然のように自身を戦略兵器と言い切る鶚の有り様に、
 は得も言われぬ寂しさを覚えた。六歳から見守って来た少女は、いつしか人型戦術兵器と化していた。
は得も言われぬ寂しさを覚えた。六歳から見守って来た少女は、いつしか人型戦術兵器と化していた。二人の所属する電脳症変異種管理局NOISE対策本部は、決して非人道組織ではない。なにも知らない少女を騙して人間兵器に改造し、単身前線へ放り投げるようなところではなく、それどころか鶚も
 も最大限の好待遇を受けている。なにより鶚の改造は、彼女自身が望んだことだ。
も最大限の好待遇を受けている。なにより鶚の改造は、彼女自身が望んだことだ。エクスマキナの能力者として、人体パーツは寧ろ障害でしかないからと。
「お前の全部が兵器になったら、お前は何処に行くんだろうな」
「……? 哲学の話か?」
最後のピアスを耳に留め、鶚を腕の中に閉じ込める。単純な力でいえば鶚のほうが遙かに強いのだが、鶚は無抵抗に閉じ込められている。
「いや……あー……まあ、そうだな。哲学の話になるのかもしんねえ」
「私はあまりそういった話は得意ではないが……そうだな。ピアスを空ける前の君といまの君は、別物になったか?」
鶚の問いに、
 は小さく息を飲んだ。
は小さく息を飲んだ。「私は既に全身の八割を機械に変えた。エクスマキナでも此処まで改修された個体は稀だろう」
「……そうだな」
エクスマキナは機械を操るCODEだ。中には鉄分や磁力などを操る者もいるが、それも全て機械へ通じている。そしてエクスマキナは基本的に、自らの体を機械へと改造する。しかし鶚のように全身を対象とする者は滅多になく、精々腕や足に武器を仕込む程度だ。
鶚は既に全身の筋肉や骨や内臓を機械に入れ替えて、皮膚を兵器として運用するに耐える素材に変えており、最も衝撃に弱い脳は間もなくデータチップを内蔵した人工頭脳へと交換される。現在は、脳に埋め込んだ解析チップで思考パターンを集積している最中で、それが終われば改修施術が行われる。
それほど大がかりな変化とピアスの一つや二つでは比較にならないのでは、と
 は思ったが、鶚はそう思わないようだ。
は思ったが、鶚はそう思わないようだ。「なにも大差ない。人は、生物は、情報の塊だ。ゆえに電脳症を発症する。生き物でありながら、コンピューターウィルスによって変異種になる。その情報を、外部からいじった場合、何処まで自分と言えるかなど、定義づけられるものでもないだろう」
「お前は……」
鶚を抱きしめる腕に力がこもる。
普通の、十代の少女であれば、いい加減息苦しさを覚える力だ。しかし鶚は平然としたままで、
 の言葉を待っている。
の言葉を待っている。「お前は、怖くないのかよ」
「ないな」
あっさりと言い切り、鶚は腕の中に収まったまま小さく笑う。
「君は私を見捨てない。そうだろう?」
「っ……」
鶚の肩に埋めていた顔を上げ、大きな紅い瞳を見下ろす。鶚の目は僅かも揺らいでおらず、その目には良く磨かれた鏡面のように、泣きそうな
 の情けない顔が映っていた。
の情けない顔が映っていた。「なにを恐れる。君が約束したんじゃないか。なにがあっても、何処へ出撃しても、必ず私を迎えると。君が私の帰る場所である限り、私は私でいられる」
 は鶚が十三歳で初出撃をした日の夜、いまのように、彼女に縋った。
は鶚が十三歳で初出撃をした日の夜、いまのように、彼女に縋った。重傷を負い、補修箇所が痛々しい姿となっても平静を保っていた少女に。鶚は
 の絞り出すような「おかえり」の言葉に、うれしそうに微笑んだ。
の絞り出すような「おかえり」の言葉に、うれしそうに微笑んだ。そして
 にこう言ったのだ。
にこう言ったのだ。『君がそうして私を迎えてくれると、私は兵器からただの鶚に戻れる気がする』
戦闘力を持たない
 は、前線には立たない。見送ることしか出来ないと嘆いていたことに、鶚も気付いていたのだろう。肩を並べて、或いは背中を合わせて戦うことが出来ない
は、前線には立たない。見送ることしか出来ないと嘆いていたことに、鶚も気付いていたのだろう。肩を並べて、或いは背中を合わせて戦うことが出来ない にも、ちゃんと出来ることがあるのだと、鶚は微笑った。
にも、ちゃんと出来ることがあるのだと、鶚は微笑った。『だったら、俺はお前の帰る場所であり続ける。なにがあっても。何処へ行っても。お前が帰って来るのを待ってるから。だから……』
『ああ。私は必ず帰る。君の元へ、必ず』
煤と硝煙の匂いがする細い体を抱きしめて、
 は誓った。
は誓った。その日から、彼女との約束を果たし続けている。帰る場所であるという、唯一つの約束を。
「――――だから、私に恐怖はない。この身がどれほど変わろうとも、私は君の元に在るのだから」