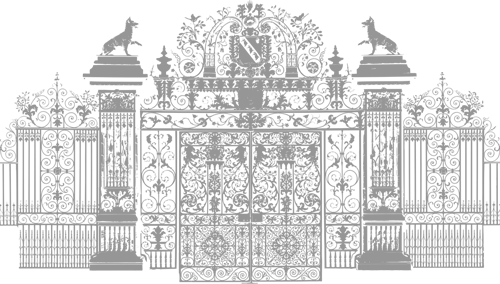有言実行
有言実行ソルジャークラスのソロネの日常は、案外一般人と大差ない。
月曜から金曜にかけては学校へ通い、土日にはSIREN本部で訓練をする。
戦闘訓練で本気を出すことは出来ないので、いま自分がどれだけの破壊力を持っているのかは数値でしか知らない。
私の変異係数と戦闘能力を数値化した、世間でいう健康診断書のようなものを
 に見せたところ、彼は数秒フリーズしてから再起動していた。頭がいいとたった一つの情報から無数に枝分かれした想像を働かせてしまうらしく、毎年変異係数計測日から暫くは彼の過保護が加速する。
に見せたところ、彼は数秒フリーズしてから再起動していた。頭がいいとたった一つの情報から無数に枝分かれした想像を働かせてしまうらしく、毎年変異係数計測日から暫くは彼の過保護が加速する。しかしながら、本部では不働の破壊兵器扱いをされていても、学校でそれを見せることなどあるわけもなく。今日も私は高校で一般人に紛れてありふれた日常を送っている。
「夜明さん、スマホ持ってこないの? 学校でいじってるの見たことないけど」
「うちの高校、授業中のゲームとかは禁止だけどさ、スマホ自体は持ち込みオッケーだよ?」
放課後、ひとり帰宅準備をしていたら、同じクラスの――確か、水鶏口理恵と久我麻友子とかいう名前だった気がする――女子に声をかけられた。彼女らの手には薄い板状の端末が握られていて、画面には短文メッセージツールのホームが映っている。その隣では彼女らの友人である別クラスの女子、上青木愛衣が似たような表情で私を見ている。
「持ってない。特に必要じゃないからな」
「えーっ、持ってきてないんじゃなく?」
「不便じゃない? スマホなくてどうやって生活してんの? 原始時代じゃん」
SIREN職員に支給される端末は持っているが、それを表の世界で使うわけにも行かず。その理由を馬鹿正直に話すなど以ての外だ。
鶚は少し迷って、それらしい言い訳を選択した。
「面倒なのに絡まれたとき、持ってないっていうとしつこく食い下がってこないから便利で。家が厳しいって言うと、嫌そうな顔してすぐいなくなるんだ」
「あー……それはわかるけどさあ」
彼女らも覚えがあるのか、半分は理解したようだった。それでも生まれたときから当たり前に普及していた個人端末のない生活はどうにも考えられないようで、同意は出来なさそうだ。
そんな話をしていたら、教室内外が突然ざわめいた。
「えっ、なになに?」
「みんな外見てるっぽい……何だろ? 犬でも入ってきた?」
言われてみれば、クラスの人も廊下にいた人たちも、なにやらベランダに集まっている。視線は窓の外、随分と下のほうで、其方には学校の正門があるはずだ。
周りに倣って視線を追うと、見覚えのある立ち姿が其処にあった。
「……アイツ……」
私は鞄を引っかけると、クラスメイトの群をかいくぐって階下に駆け下りた。
後ろから、担任が廊下は走るなと叫ぶのが聞こえたが、それどころではない。
靴を履き替え、真っ直ぐに正門へと駆けていく。こういうとき本気で走れないのは面倒だ。
「本当に来る奴があるか!」
「残念だったな! 俺は言ったことは守る人間だ!」
正面に立つや抗議をぶつけた私に、勝ち誇った笑みが返される。
門の周囲に集まった生徒たちの視線が痛い。彼はただでさえ目立つのに、人が多く行き交う時間帯に堂々と現れたものだから、いい注目の的だ。しかも、精華学園は元女子高で、共学となったいまでも女子の割合が九分九厘を占めている半女子高だ。
男というだけでも目立つのに、
 のような派手な男がいたら明日には学校中に知れ渡ってしまうだろう。
のような派手な男がいたら明日には学校中に知れ渡ってしまうだろう。「さ、帰ろうぜ。帰りに寄りたいところはあるか?」
「ない」
一刻も早く帰りたいという想いを込めて言うと
 はうれしそうに肩を組んできた。それを見て周りがまた騒がしくなったが、私は弁解を諦めて早々に学校を去った。
はうれしそうに肩を組んできた。それを見て周りがまた騒がしくなったが、私は弁解を諦めて早々に学校を去った。学校には、家庭の事情として兄と社員寮のような場所で暮らしていることは伝えてあるし、暫くは物珍しさで騒がしいかも知れないが、邪推されることもないだろう。もし誤解されたら都度話していけばいい。面倒だが仕方ない。
「……なあミサ、学校まで行って怒ったか?」
高校から離れたところで、
 が突然そんなことを言った。
が突然そんなことを言った。「別に。高校の外壁の陰に、三人いただろ。あれがいつも絡んでくる連中だ。今日も出てくるのを律儀に待っていたらしい」
ああして待ち伏せして、周りを囲ってネチネチと言いがかりをつけてくるのだ。
ただ、彼らは上級天使ではないから専用の宿舎には入り込めないので、ゲート前で警備職員に睨まれては逃げるように去って行く。
「ほーう。顔は覚えたから、あとでIDと照合してやろう」
「……はぁ……言うんじゃなかった」
ソロネの階級とミーミルの頭脳と上級クラークの権限が合わさってしまったいま、彼らに逃げ場はない。尤も、彼らの言う「ソロネ共はただ飯喰らいの穀潰し」という言い分を取り上げるのであれば、
 や他のソロネにまで飛び火するのだから。
や他のソロネにまで飛び火するのだから。彼らからすれば、クラークとして働いている
 たちと普通に日常生活を送っているだけの私は、明確に別枠なのだろうが。
たちと普通に日常生活を送っているだけの私は、明確に別枠なのだろうが。いい加減に身のない嫌味を聞き流すのもうんざりしてきた頃だったので、私は
 を止めることはしなかった。
を止めることはしなかった。