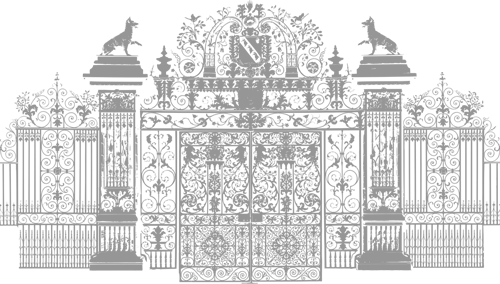甘い蜜の檻
甘い蜜の檻――――微睡みから浮上した私の視界に、二つの緋色が映った。
「……人の寝顔を覗き見とは、随分趣味が良くなったな」
「違えって! 俺の名前を呼んだから、起きてんのかと思ったんだっての」
「君の?」
一瞬怪訝に思うも、そういえば幼少期の夢を見ていたような、と思い出す。
「ああ。出逢ったばかりの頃の夢を見たんだ。十歳でソロネなんかになって、十三で出撃して、十四歳のときにはただ飯喰らいだと揶揄されたな、と」
「おい待て。俺、最後の知らねえんだけど」
「…………おっと」
わざとらしく自分の口を塞ぐと、上からじっとりと睨まれた。
「過去の話だ」
「いーや、嘘だ。お前がそういう顔をするときは、だいたい嘘なんだ」
至近距離で詰められては、これ以上誤魔化しようもなかった。
十年。彼と過ごした日々は確実に彼の中に私の情報を蓄積していた。私の知らない私を、彼は知っている。覚えている。僅かな言動、仕草一つも漏らさずに。
「……これだからミーミルは」
「ミーミルじゃなくたってわかるさ。お前のことだからな」
ニッと笑う得意げな顔が憎たらしい。
ソファに寝そべったまま話すのも何だか居心地が悪かったので、体を起こして座り直した。至近距離で見下ろしていた顔が退いて、隣に並んで座る。
そうは言っても、其処まで大した話でもない。ソロネ階級のソルジャーは『其処に存在すること』が仕事であると実感出来ていない一般職員が、未だあとを絶たないというだけのことだ。私は何処かの国が持つ核のボタンみたいなものだ。ただ在ること自体が抑止力になる。
 はクラークだから通常業務があるが、戦闘員であるソルジャーの私にはない。
はクラークだから通常業務があるが、戦闘員であるソルジャーの私にはない。「……つまりだ。一般人と殆ど同じ生活をしているだけで高給取りなわけだからな、私は。学校帰りに待ち伏せされて因縁つけられたりは日常の範疇なんだ」
「はぁあ!? おま、お前……! そういうことは報告しろよな!」
絶対こうなるから言わなかったんだ、とは言わずにおいた。
 は、ブツブツと呟きながら、何事か考え込んでいる。嫌な予感がした。
は、ブツブツと呟きながら、何事か考え込んでいる。嫌な予感がした。「よし、決めた! 次から俺が送迎する!」
嫌な予感はしていたが、この台詞は予測していなかった。いや、彼の性格を思えば予測して然るべきではあったのだ。ただ私が、考えたくなかっただけで。
「何故そうなる」
「初等科のときはそうしてただろ」
「一桁年齢のときのことなんか持ち出してくるな。それに、君にはクラークとしての業務があるだろ」
「俺は天才なので、自分の仕事をこなした上でお前も守れるんですー」
ぐうの音も出ない。
 が天才なのは事実で、実際やり遂げるのだろう。
が天才なのは事実で、実際やり遂げるのだろう。「嫌だつってもついていくからな」
こうなった
 は止められない。
は止められない。絡まれるのも面倒になってきた頃合いだしと、溜息を吐いて了承した。
 が過保護なのは、いまに始まったことではない。
が過保護なのは、いまに始まったことではない。戦闘力だけなら私のほうが遙かに上だが、だからこそ彼は心配なのだと、わかっている。結局私は彼の甘さに浸ることしか出来ないのだということも。
わかっているから、厄介なのだ。