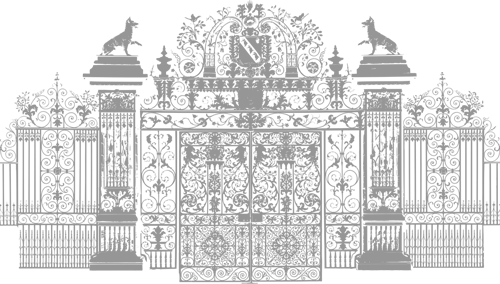ホワイトデー
ホワイトデー目の前に突き出された、可愛らしいラッピングの箱をまじまじと見る。
淡い水色の包装紙に、深い青色のリボンが巻かれたそれは、十五センチ四方程度のサイズに見合った軽さであった。
「これは?」
「今日はホワイトデーだろ」
「……ああ、まあ、そうだな」
鶚は頭の中で日付を確認し、確かにと頷く。
しかしホワイトデーというものは、一般的にバレンタインデーのお返しを贈る日であったはずで。だが鶚はというと、一ヶ月前に贈り物をした記憶がとんとなかった。それどころか、バレンタインには
 が作ったプロ顔負けのチョコレートケーキを共に食べたはずである。
が作ったプロ顔負けのチョコレートケーキを共に食べたはずである。「因みにだが、ホワイトデーがどういう日かわかっているんだよな?」
「其処まで馬鹿じゃねーっての。たまたま駅前の店に寄ったら臨時催事場が出来ててお前の好きなブランドの焼き菓子があったから、ついでに買ってきただけだ」
「そうか」
ついでと言うだけあって、ダイニングテーブルの上には彼が買ってきた食材が山と積まれている。
 は駅前のスーパーが安売りをする土曜日に一週間分の食材を買い込み、常備菜を大量に作って冷凍・冷蔵保存する方法で食品を管理している。
は駅前のスーパーが安売りをする土曜日に一週間分の食材を買い込み、常備菜を大量に作って冷凍・冷蔵保存する方法で食品を管理している。鶚はそんな
 に十歳の頃から食育されてきたこともあり、料理が下手な自分が作るよりはと、すっかり彼に甘えた生活を送っている。
に十歳の頃から食育されてきたこともあり、料理が下手な自分が作るよりはと、すっかり彼に甘えた生活を送っている。手の中に収まった水色の箱をじっと見つめてから、鶚は顔を上げ、
「ありがとう」
そう言って淡く微笑んだ。
「おう。俺は暫くキッチンにこもるから、何かほしくなったら自分で取りに来いな」
「わかった」
これも、毎度のこと。
土曜の
 は、昼過ぎから夕食時にかけて、キッチンを戦場に変える。
は、昼過ぎから夕食時にかけて、キッチンを戦場に変える。鶚はそのあいだ、高校の課題をこなす。それも、毎度のこと。
自室に入り、もらった包みをほどくと、中から想像していたブランドのクッキーが出てきた。
「これは……紅茶を淹れたほうがいいな」
課題のお供にしては上等過ぎる気もするが、折角の厚意だ。ありがたく頂くことにして、鶚はいま入ってきたばかりの扉を開けようとドアノブに手をかけた。が、鶚が開けるより先に向こうからノックがされた。
「なんだ」
「お求めの品はこれだろ?」
料理を始めるのではなかったのかと思いつつ開けると、扉の前にはトレーに紅茶のカップを乗せた
 がいた。ご丁寧にお代わり用のティーポットと、カップウォーマーまでついている。
がいた。ご丁寧にお代わり用のティーポットと、カップウォーマーまでついている。「……よくわかったな」
「何年の付き合いだと思ってんだ。ほれ、零すなよ」
「ん。ありがとう」
トレーを受け取り、机の左側に置く。カップウォーマーのUSBをセットして上にカップを乗せた。
 と二人暮らしを始めるに当たって購入した学習机は、高校卒業を控えた現在までしっかり働いてくれた。買ってすぐに、お菓子のオマケでついてきたシールを貼った鶚を、
と二人暮らしを始めるに当たって購入した学習机は、高校卒業を控えた現在までしっかり働いてくれた。買ってすぐに、お菓子のオマケでついてきたシールを貼った鶚を、 は叱るどころか笑って褒め、追加のシールを寄越してきたりしたことも記憶に新しい。
は叱るどころか笑って褒め、追加のシールを寄越してきたりしたことも記憶に新しい。部屋の至るところに、二人分の軌跡がある。ひとり課題に向き合っている最中でもそれは意図せず脳裏に飛び込んで来て、懐かしさを呼び起こす。
「無事卒業出来たら、なにか返してみてもいいかも知れないな」
楽しい企みは紅茶の湯気に溶かして。
キッチンからの賑やかな音をBGMに、鶚はペンを走らせた。