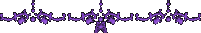
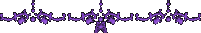
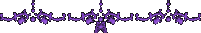
BELLISSIMA
ベリッシマ改めBELLISSIMAは
ときめきメモリアルGirl's SideⅢ~Fantasia~ 連載専用サイトになりました!
Fantasiaのヒロインバンビ、あいりチャンをよろしくお願いします!
 迷いの森
迷いの森
十年ぶりに帰ってきたはばたき市は、あいりの記憶の中にある姿とさほど変わりがなく、懐かしい思いを溢れ
させた。昔住んでいた家もそのままの姿で残っており、たまらず少女は周囲を散策に出かけた。
「海も変わってないなあ」
海沿いのガードレールをカンカンと叩きながらゆっくりと歩く。まだほんの少し風は冷たいが、柔らかな日差
しがぬくもりを与えてくれる。そのまま歩き続け、気が付けばいつの間にか鬱蒼とした木立の中に居た。
「あれ、ここどこだろ?」
街中や先程の海辺からさほど離れていないはずなのに、潮のにおいもしないし恐ろしいほどに静かだ。恐怖で
早足になりつつ、とりあえず眼前に続く道をあいりは歩く。やがてあっけないほどに森は切れ、古い教会がぽっ
かりと現れた。
「こんなところに教会…?」
中に人がいたら道を聞こうと思い、木製のドアの取っ手を引くもびくともしない。
「それ、今はまだ開かないよ」
「っ!」
急に響いた涼やかな声にびくんと振り返ると、蔦塗れのレンガ塀の上に青年が座ってこちらを見つめていた。
「誰…?」
「―迷ってるんだろ、俺と同じだ」
ばっ、とかなり高い塀から飛び降りた彼は見事に着地し軽やかな足取りであいりに近づいてくる。白い肌にプ
ラチナの髪、黒ずんだ銀のよう不思議な目の色に圧倒されてしまう。
「道、教えてあげるよ」
「は、はぁ…」
薄く眩しげに笑いすたすたと歩き始める青年を慌てて追いながら、あいりは僅かなひっかかりを感じていた。
なにか、何かを私は忘れているのではないか。
「…覚えて、ないか」
「なあに?」
ぼそりと青年が何か呟いたが、あいりには聞こえなかった。
あれほど深い静寂が支配していた森をあっさり抜け、気が付けば二人はあいりの自宅前に立っていた。
「あの、ありがとうございます。お名前を…」
「…もし、出来たらでいいんだ。今夜あの教会に来てくんない?」
そしたら自己紹介するよ、といたずらに笑い白い青年は手を振り去っていった。
 今夜、森を抜けて。
今夜、森を抜けて。
「ごめんな、あいり」
「明日には戻るから」
なにやらガス漏れか水漏れがあったらしく、両親はつい昨日まで住んでいた家にあわてて戻っていった。一晩
はあちらに泊まるらしい。
「どうしよう…」
今夜は新しい家にあいり一人、ということになる。昼に出会ったあの青年の約束を果たそうと思えば叶えられ
る状態になってしまった。夜に外出することは憚られるし、素性を知らない男に会いに行くなんて言語道断だ。
しかし、昼から身の内を苛む違和感は膨れ上がるばかりで、破裂してしまいそうだ。
「よし」
夜七時、薄闇の中あいりは出かける覚悟をした。今から歩いていけば、八時。何事もなければ九時には帰宅出
来るから、そこまで危険ではない気がした。
まだ馴れない鍵を使って家を出、帰宅するサラリーマンや学生の間を海のほうへと歩いていく。教会へ行く道
がわからないから、昼と同じように海沿いの道路を歩く。東の空に満月がぷかりと浮かび、春の霞がかった夜空
をぼんやり照らしている。
「…来たの」
又、だ。いつの間にか周囲は木に囲まれている。昼間の真っ白な青年が半ば驚いたように薄暗い森の中に立っ
ていた。
「だって、来いって言ったでしょ」
「うん…」
青年はくるりと背中を向け、道の向こうへと歩いていく。あいりもそれを追いかけると、また古い教会にたど
り着いた。
「わぁ…」
しかし、そこは昼間とは違い非常に幻想的な表情を見せていた。教会周辺の草むらのそこここに、薄桃色の花
がぼんやりと光を放って咲いている。
「これは、特別なサクラソウなんだ」
青年が瞳を閉じると、いっそうサクラソウの輝きが強くなった。そのあまりに不可思議な光景を、あいりは何
故か懐かしく感じた。
「…私、これを見たことが、ある…?」
「そうだ、アイリ。見たことがある、俺と」
「俺とルカとオマエで、見たことがある」
ふと教会の裏から現れた影が、青年の言葉を継いだ。
その声を聞いたとき、さぁっと脳内の霧が晴れたように、あいりの脳内にある光景が広がった。
ずっと、ずっとずっと昔。
ここではないどこかで、幼いアイリと白い青年―ルカとその兄であるコウと、サクラソウの咲く教会で、毎日
遊んでいた。
「ルカくん…?コウくん…?」
「思い出した?」
「…思い出さねェ方が良かったんじゃねェのか」
ざぁ、っと強い風が吹いた後、青年二人の姿が変わっていた。
純白のロングコートに赤い瞳のルカ。
漆黒のジャケットに、白目部分が黒く金の虹彩を持つコウ。
「お帰り、アイリ」
「…まァ、ヨロシク…な」
口を開くと見え隠れする長い犬歯が、彼らの正体を如実に現していた。
純血の吸血鬼。
夜の王、化け物の総領、暴力と破壊の象徴、恐怖の権化。言葉を尽くして恐れられる一族の末裔が、彼らだ。
「どうして…?ここで、何してるの?」
「まァ、いろいろあんだよ」
「人間の生活も楽しいよね?」
しかし、あいり自身の正体はわからない。時の彼方で、途方もない寿命を持つルカとコウの幼少期を知ってい
る自分は何者なのか。
「悩んでる所悪いけど…あのさ、今はばたき市って結構いっぱい変なのがいるんだ」
「変なの…?」
ルカとコウが交互に説明するところによると、異界から続く扉の出口がはばたき市に集中しているため、様々
な種族が人間に擬態して生活しているという事態が起こっているらしい。
「明日から、アイリと俺らが通うはば学にも結構いるみたいだ」
「えぇー」
高校生活に期待はしていたものの、そんなファンタジックなことが起こるとは思うはずもなく、つい不満げな
声が出てしまった。
「ま、アブネー奴は俺がシめる」
「駄目だよ、コウくん」
「俺も俺も!俺もシめる」
「もう、ルカくんまで!」
ぼんやりと光り続けるサクラソウの中で笑う三人を、大きな月が見下ろしていた。
 純白のバンパイア
純白のバンパイア
昼間のルカ―琉夏、はいたって普通の高校生だ。まあ真っ白な金髪で素行不良な美形、という強い特徴は持っ
ていたが。
「そういえば、琉夏くんは日光もにんにくも平気なのね」
さんさんと陽の照る屋上で、あいり特製のお弁当をがっつく琉夏は、頬にご飯粒をつけたまま顔を上げた。
「コウは少し苦手みたいだけど、俺はへーき」
にっ、と笑って再度弁当をかっこみ始める。今日は奮発してステーキがおかずに入っている。そして歯を磨け
ば大丈夫かな、と思いガーリック風味にしてあったのだ。
「十字架も平気なの?」
あいりは首に掛けているクロスモチーフのネックレスを抓んで、琉夏の目前に掲げてみる。
「へーき、俺、突然変異なの」
 ただ一人の隷属
ただ一人の隷属
後に知ったことなのだが、コウとルカは実の兄弟ではない。血縁上いとこにあたり、コウが正統の名を継ぐ吸
血鬼でルカは他の血が混ざった亜種である、とのことだ。
「だからさ、サクライの名前は俺に適用されないの。サクライの眷属はコウのもの、俺にはひとりのしもべもい
ない」
真っ白な薔薇と百合の噎せるような匂いが、天蓋つきベッドの中に篭っていた。花弁まみれの純白のシーツに
アイリは押し倒されている。幾重にも重なる白い紗のカーテンが、二人を完全に外界から切り離していた。
「だから、アイリ。俺と、俺のただ一人のしもべに…なんない?」
あいりは頷いた。赤い瞳に幻惑されたわけではない、自分の意思で、はっきりと頷いた。
すると、真っ赤な瞳だけが輝いていた視界に僅かに開いたルカの口も赤く見えた。次の瞬間、肩に焼けるよう
な痛みが走り、噛み付かれていることを知った。
「――っ!あ!」
深く牙がめり込み、意識が途切れそうなほどの痛みがあいりの全身を痙攣させた。しかし。
「や…ぁ?…ん」
肩からじわりと何かが広がる感覚に、痛みとは違うものが少女を震わせる。
「ん、ふあ…、やっ、なに、これ」
『キモチイーだろ?麻酔みたいなもんだって』
ルカの意識が直接脳内に流れ込んでくる。これが僕になるということか、とぼんやり理解するも熱を帯び始め
るからだが思考を邪魔する。
『じゃあ、ついでに。…イタダキマス』
肩から外されたルカの唇が、血にまみれたままあいりの唇を深く塞いだ。
 漆黒のバンパイア
漆黒のバンパイア
「コウくんって、あんまり吸血鬼ーって感じしないね」
ガソリンスタンドで働く人間姿のコウ―琥一を迎えに来たあいりは、ふとそう口にした。
「あァ、何言ってんだオマエ」
晩飯の買い物も済ます、という彼についてとことこと少女もスーパーに入る。
給料が入ったのだろうか、琥一は肉・魚・野菜・酒…とバランスよくかごに放り込んでいく。
「お酒駄目!」
「ウルセ」
頭をぐしゃりとかき混ぜられて、あいりはいやいやと首を振る。その間にさっさとレジに進んだ琥一は、会計
を済ませてしまう。
「もう!」
「もうじゃねえ、オマエは牛か」
外に出ると既に陽は落ち、夜になっていた。
「…、血を吸ったり蝙蝠呼んだりするのは、能力のごくごく一部だ」
「うん?」
琥一の目が金色に変わり瞳がにごり始める。ざわり、と彼の影が蠢いたかと思うと一瞬で琥一とあいりはその
影に取り込まれ地面に解けてしまった。
「ほれ、目ェあけな」
「え?あれ?」
気が付くとルカとコウのねぐらであるウエストビーチに立っていた。
「影に潜って移動した。ま、序の口だ」
「えええ?実は私が思っているより、かなり凄い…?」
その問いには答えず、青年は買い物袋を持ってキッチンへと消えていった。
 暴虐の王(グロ注意)
暴虐の王(グロ注意)
あいりに襲い掛かってきた二階建ての家より大きな巨人を、コウは片手でいなした。というより巨人の腹を拳
で破り、内臓をちぎり捨てたのだ。つんざくような悲鳴を上げる巨人を突き倒し、腕と足をもいで放り投げる。
醜悪な赤ん坊ほどの大きさの小人の頭蓋骨を片手で握りつぶし、その脳味噌がこびりついた手で大きな牙
と口だけの異形の歯を無造作に毟り取る。
化け物たちの体液にまみれながら、強烈なまでの暴力を振るい続ける姿はまさに恐怖そのものだ。
いつか、琥一だったコウが言っていた言葉が蘇る。『吸血鬼の最大の武器は、強靭な生命力と純粋な力だ』と。
「…」
「―っ」
やっと化け物どもからあいりを救い出せたのに、かける言葉がない。彼女が暴力に怯える事などわかりきって
いたのに、恐怖に見開かれた瞳を見ることが琥一には辛かった。
蝙蝠を操る力より、闇を潜る器用さより、血の契約を結んだ眷属を使う度量より、凄まじいまでの暴力が琥一
が正統な吸血鬼の末裔たる証だった。
と、ぎゅうと腹に縋りつかれる感触がして、驚いてコウは視線を下にやる。
「嫌いにならないよっ」
「―ッ、オメェ…」
「知ってるもん、コウくんがやさしい事、私しってるもん…」
軽くつついただけでもあいりを壊してしまう腕をもてあまし、触れないようにコウは腕で彼女を囲った。
 エリート魔族
エリート魔族
ぶわ、と屋上に生ぬるい風が吹く。すると落ちてきそうな程に大きな満月が雲の隙間から現れ、一気に校舎の
屋上が明るくなった。
「紺野、先輩…?」
生徒会活動の後屋上にあいりを誘った紺野は、先程までと同じようににこやかに立っていた。
「サクライと仲がいいなら、僕の事聞いているよね」
満月を背にして立つ彼はしかし、羊のようなねじれた角を持ち、軍服のような衣装に身を包んだ姿になってい
た。
「聞いてない…、です」
「本当に?」
こつこつとステッキを突いて歩いてくる動作が、実に様になっている。大きな角と折りたたまれた羽が悪魔の
ようだ、と思う。
「サクライが吸血鬼だということは?」
笑顔なのにとても冷たい視線で、紺野はあいりを見下ろす。答えられないでいると、腰につけていたらしい乗
馬鞭をひゅっと取り外し、鞭先であいりの顎を捕らえる。
「しって、ます」
「うん」
よくできました、と頭を撫でられる。表情もいつもの優しい紺野に戻っていて、はぁとあいりは息をつく。
「しょうがないな、自己紹介するよ。僕は魔族だ、…解りやすく言うと悪魔、かな?」
紺野の説明によると、吸血鬼や悪魔に獣人等が跋扈する世界にも一応統治機構としての中央政府というものは
あるらしい。
「そこで、異世界に渡った輩を監視する役割を任せられている。公務員みたいなものだよ」
「は、はぁ…」
確かに、沢山の異界人がはばたきに来ている、とコウは言っていた。しかし、優等生で人望もあって、なによ
りとても優しい紺野が悪魔だなんて信じられない、とあいりはぷるぷる頭を振る。
「まさか、紺野先輩が…。そんな…」
「ショックかい?」
大人しくこくんと頷くと、はは、といつもの調子で笑われてしまった。
 不死貴族の優雅な生活
不死貴族の優雅な生活
「なんだ、ばらしたのか」
「知ってると思ったんだ」
紺野が悪魔だと知らされた翌日、あいりは設楽の屋敷に連れてこられていた。
「あの、まさか、もしかして設楽先輩も…?」
「そうだ」
設楽がりん、と呼び鈴を鳴らすと、一枚膜がはがれるように屋敷の姿が変わっていく。普通の日本的洋館だっ
た内装が、ゴシック調の薄暗いものに変わっていく。
「何時見ても趣味が悪いな」
「煩い紺野、俺の眷属だ」
ゴシックロリータ趣味のクラスメイトが泣いて喜びそうな、不気味なお人形や骨が散乱する光景に、あいりは
圧倒される。
「ほら、お客様だ、皆動け」
そう設楽が声を掛けると、いっせいに骨や人形、ぬいぐるみが動き始める。
『紺野様、お久しぶりでございます』
「ああ」
ぬっとあらわれ紺野に挨拶をした女性は全身に縫い目が走っていてフランケンシュタインのようだし、設楽の
足元にじゃれ付いている猫は腸が飛び出している。
縫い目の女性に促されたあいりはテーブルに座り、出された紅茶で口を湿したあと震える声で質問した。
「あの、これは、一体…?」
『お嬢様、セージ様は我ら不死…アンデットの貴族でいらっしゃいます』
そういいながら骸骨の執事が、恭しく茶菓子を供する。
「ほら食え、別に腐ってないぞ」
「は、はい!」
「急かすなよ、設楽」
「うるさい!」
設楽自体は全く変わっていない様に見えたが、茶菓子を差し出す手に全く体温がなくあいりはぞっとしてしま
った。
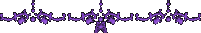
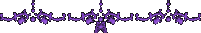
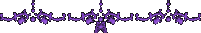
 冗談でした
冗談でした
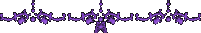
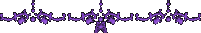
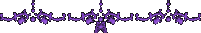
 迷いの森
迷いの森 今夜、森を抜けて。
今夜、森を抜けて。 純白のバンパイア
純白のバンパイア ただ一人の隷属
ただ一人の隷属 漆黒のバンパイア
漆黒のバンパイア 暴虐の王(グロ注意)
暴虐の王(グロ注意) エリート魔族
エリート魔族 不死貴族の優雅な生活
不死貴族の優雅な生活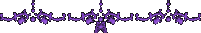
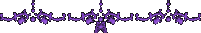
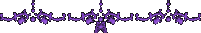
 冗談でした
冗談でした