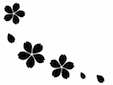後編 -side赤司-
※R18はエロではなくグロの方です。
流血表現などがありますので、何でも許せる方のみお読みください。
「…今日でもう四日目ですね」
「何がだ?」
「黄瀬君が学校に来なくなって四日経ちましたよね」
「…あぁ、そうだね」
テツヤの言葉に一応相づちを打つ。
「やっぱり、何かあったんでしょうか…」
「心配ないさ。風邪をこじらせたりでもしたんだろう」
「…そうですよね」
…案外、あっさり引き下がるんだな。
まったく、涼太はテツヤのどこがいいんだろうか。
容姿も頭の良さも運動神経も、全て僕の方が優っているのに。
涼太への想いも絶対にテツヤには負けてない。
なのに、何でテツヤなんだろう。
「…いっそのこと、消してしまうか…」
「…?何か言いましたか?」
「…いや、ただの独り言だ。気にするな」
…うっかり口に出してしまったな。
気をつけなければ…。
部活が終わり、部室で着替えていると、テツヤが携帯を開いて「あっ」と言葉を漏らした。
「どうした?」
「…黄瀬君からメールが…」
「………涼太から?」
そんなはずはない。
涼太の荷物はあの時隠したはずだ。
……まさか。
「…涼太から何て?」
「…いえ、何でもないです。ちょっと用事を思い出したので、先に失礼します」
少し焦り気味に携帯を閉めて、テツヤは部室を出ていった。
「………」
本当に涼太がテツヤにメールを送ったとしたら…。
僕は鞄を持ち、早足に家へ帰った。
******
「…いない」
玄関の鍵が開けっ放しになっていたから逃げたな、と思ったが、一応確認するために自室に行くと、やはりいなかった。
逃げないようにと涼太の両手にベッドの柵と繋がっている手錠をつけていたが、その手錠は壊れて床に落ちていた。
まだ少し温かい手錠には、血が付着している。
無理矢理壊したのか…。
「…まぁいい」
涼太の逃げた先はもう分かっている。
明日、テツヤにさりげなく聞くとしよう。
「絶対に逃がさない…」
次の日、午後の授業も全て終わり、体育館へ向かった。
「あの、赤司君」
部室の扉を開けようと手を伸ばしたとき、背後から声をかけられる。
「…テツヤ、どうした?」
「すみませんが、今日の部活休んでも大丈夫ですか?」
「何でだ?」
「……いや……あの…」
僕の問いに、テツヤは口籠もりながら視線を彷徨わせる。
「何か心配事でもあるのか?よければ聞くが」
…どうせ、涼太のことだろう。
「………昨日、黄瀬君からメールがきたんです。いつもなら絵文字などをたくさん使った読みづらいメールを送ってくるのですが、『今黒子っちの家の近くにいるっす助けて』とだけ書かれたメールがきて…。こういう冗談は言わない人なので急いで家に帰ったら、玄関の前に黄瀬君がうずくまってたんです」
話すテツヤの顔はどんどんと曇っていく。
「寒い中、シャツ一枚で靴も履いてないで。それに身体中に見るのも痛いほど傷がたくさんあって血も少しですが出てて…。僕に気付くと涙などでぐちゃぐちゃな顔を上げて、震えながら抱きついてきたんです」
「…それで?」
「ただ事ではないと判断して家に上げたのですが、部屋の隅に縮こまって、何があったのか話してくれないんです。今朝も『僕は学校に行きますが、黄瀬君も行きませんか?』と聞いたんですが、首を思い切り横に振って震えていて…。なので、早く帰って黄瀬君をどうにか落ち着かせようと思ったんです」
「…そんな事があったのか」
涼太はまだ何もテツヤに話していないのか…。
逃げたことは後で叱らなくてはいけないが、それは褒めてやらないとな…。
「………多分ですが」
「…ん?」
しばらく考え込むかのように黙っていたテツヤが、おもむろに口を開いた。
「黄瀬君は誰かに監禁されていたのだと思います」
「…どうしてだ?」
「黄瀬君の両手首に、輪形の痣があったんです。手錠か何かをつけられていたんだと思います。血も滲んでいたので無理矢理壊して逃げてきたんじゃないでしょうか」
「……へぇ、テツヤは凄いな。探偵みたいだ」
「いえ、そんなことないです。それより、黄瀬君を監禁していた人が誰なのかを、黄瀬君に聞かないことには…」
「…だな」
口から出そうになる笑みをなんとか隠しながら言う。
目の前にその当人がいるなんて、テツヤは少しも考えてはいないだろう。
心の中でほくそ笑み、提案を出す。
「僕もテツヤの家に行っていいか?」
「…え?」
「涼太が心配なんだ。…駄目か?」
「大丈夫ですが、部活の方は平気なんですか?」
「あぁ、問題ない」
今は部活よりも涼太の方が優先だ。
学校を出て、テツヤの家に行く。
「お邪魔します」
玄関でそう挨拶して中に入ると、テツヤが階段を指差しながら言う。
「黄瀬君は二階にいます」
「なら行こう」
「はい。…少しは落ち着きを取り戻しているといいのですが…」
「…そうだな」
そんなことよりも、僕を見た涼太がどんな反応をするのか楽しみで仕方なかった。
怒りをぶつけてくるのか、驚いて何も言えないのか、恐怖で泣き崩れるのか、それとも…。
「ここです」
一つの部屋の前で言い、扉を開ける。
「黄瀬君、今帰りました。大丈夫ですか?」
「…く…ろこ、ち…?」
テツヤの後に聞こえた声は、とても小さくて力ない涼太の声だ。
僕の前にちょうどテツヤがいるので、涼太の姿が見えない。
だが、それと同じで涼太からも僕が見えていないだろう。
「あ、話せるようになったんですね!」
「…う、ん。…心配か…けて、ごめんね…」
「そんなの気にしないでください。あ、赤司君も心配して来てくださいましたよ」
「……え…」
その瞬間、明らかに涼太の声が震えた。
「…やぁ涼太。体大丈夫か?」
「…あ…か…っ」
テツヤの後ろから顔出して言うと、涼太は目を見開き、その大きな瞳に僕を映した。
「……、…っ」
涼太の体は小刻みに震えだし、言葉にならない言葉を吐き出す。
「……黄瀬君…?」
「…い、やだ……ひゅ…っ」
「っ!可呼吸を起こしてます!」
「小さめの袋を持ってくるんだ」
「あ、はい…っ」
駆け足で階段を降りていくテツヤを横目に、隅で苦しそうに息継ぎをしている涼太の前に片膝を立てて座る。
「…昨日ぶりだね、涼太」
「…ひゅっ…ひゅー…っ」
目に大粒の涙を浮かべ、焦点の合わない目で僕を見つめる。
その姿がどうしようもなく愛しくて、そっと涼太の頬に手を添えると、ビクリと肩を震わせた。
「…馬鹿だね涼太。僕から逃げられると思ったのか?」
自分でも驚くほどの甘い声で言うと、涼太の涙が頬を伝って落ちていく。
「持ってきました…っ」
テツヤの声にぱっと涼太から手を離し立ち上がる。
「その袋を涼太の口に当てて息をさせるんだ」
「はい」
こういう経験は初めてなのか、テツヤの手つきは少し危なっかしかった。
口の周りを袋で覆い、背中を擦ってゆっくりと息をさせる。
「…は……ふー…」
「…もう大丈夫だろう」
「良かった…」
涼太が落ち着きを取り戻した頃合いを見てそう言うと、テツヤが安堵の息を吐いた。
「…あ、黄瀬君、寝てしまいましたね」
壁に体を預けるようにして寝ている涼太に、毛布をかける。
そんな二人を見ていると胸がムカムカしてくる。
…触るな。
「…黄瀬君を病院に連れていった方がいいですよね…」
「…それなら、僕が連れて行くよ」
「え、でも…」
「帰るついでに病院に寄っていく」
「僕も…」
「僕一人で平気だ」
有無を言わさぬ強い口調で言うと、テツヤは口をつぐんだ。
「涼太をおぶっていくから、手伝ってくれないか」
「…は、はい」
テツヤの手を借りて、涼太を自分の背中に乗せた。
身長差があるせいか、少しぐらつく。
「大丈夫ですか?」
「あぁ。じゃ、僕は帰るよ。邪魔したね」
「いえ、気をつけて帰ってください」
テツヤの不安げな視線を背中に受けながら、家を後にした。
「……さて」
どうしてやろうか…。
病院なんかに連れて行く気は微塵もなかった。
まっすぐ自分の家に向かう。
******
家に着き、自室に行って涼太を下ろす。
引き出しから新しい手錠を取り出し、柵に繋げてから涼太の両手首につける。
また逃げないとも限らないので、手錠は二つに増やした。
「……涼太」
「…ん…」
静かに名前を呼んでみたが、目を覚まさない。
涼太の綺麗なさらさらの髪に、指を滑らせる。
…本当に可愛いな。
こんなに可愛い涼太は、目を離すとすぐに誰かに奪われてしまうだろう。
誰の目にも触れさせず、僕の物にしたい。
僕だけの涼太にしたい。
「…黒子っち」
「っ!」
僕の手に顔をすり寄せてテツヤの名前を口にする。
目は閉じていて、規則正しい寝息も聞こえる。
…寝言、か。
何でテツヤを呼ぶんだ?
ムカつく…。
髪をすいていた手をあごに持っていき、口唇を口唇で塞ぐ。
「…ん…っ、ふっ…、!?」
「…ん、あぁ、おはよう涼太」
「あ…赤司…っち…っ」
涼太の喉の奥から小さな悲鳴が上がる。
すぐに視線を彷徨わせ、僕の部屋と気づいて青ざめる。
「…な…で…?黒子っち…は?」
「僕の家なんだから、いるわけがないだろ?」
「…そんな」
「…僕の許しなしで勝手に家から出るなんていけないな。しかも、テツヤのところに行くなんて…」
「…ひっ」
傷だらけの涼太の足を手で撫でる。
テツヤの元に二度と行かせないためには、どうすればいいのだろう。
僕の元にずっと居させるには、どうすればいいのだろう。
「……ああ」
そうだ…。
「僕から逃げる悪い足が無くなればいいのか」
「…っ!?」
近くに落ちていた鋏を取り、刃でペタペタと涼太の太ももを叩く。
「それがいい。涼太の綺麗な長い足が見れなくなるのは寂しいが、仕方ないよな。なぁ?涼太?」
「…や…っ…ひ…!」
「逃げようとした涼太が悪いんだからな」
鞄から部活用に持っていっていたタオルを取り出して、涼太の足の付け根にきつく縛る。
あまり出血が酷いと、涼太が死んでしまうかもしれない。
いや、その前に痛みで終わってしまうかもしれない。
けれどその時は僕もすぐに後を追おう。
「…愛してるよ涼太。…ずっと一緒にいよう」
今の僕の顔は、多分今までで最高の笑顔だろう。
「──っ!!」
そして涼太の顔は、今までで一番綺麗だ。
持っていた鋏を高い位置まで上げて、思いきり振り落とす。
「ーっぁああぁあっ!」
これで涼太は、ずっと僕のもの──。
―END―
エピローグ Side黒子に続く