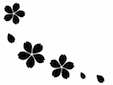悩み
俺はこの頃、悩んでいることがある。
「涼太」
部活のため、まだ人のいない部室で着替えていると、赤司っちが少し微笑みながら入ってきた。
しかし、オッドアイの綺麗な瞳は少しも笑っていない。
「…なんすか?赤司っち」
「今日の昼、教室にいなかったが、どこにいた?」
「…屋上で涼んでたんすよ」
「……誰と?」
赤司っちの低かった声音が、一層低くなる。
逃がさないためか、赤司っちは俺の腕をきつく握る。
「一人っすよ」
嘘をついた。
昼は青峰っちと屋上でお昼を食べていた。
でも、赤司っちに嘘が効かないことは知っている。
「…何で嘘をつく」
「…嘘じゃないっすよ」
「じゃあ、隣にいたあれは幻か?」
「…見てたんすか」
「ずいぶんと楽しそうだったね。何を話していたんだ?」
握られていた腕に、赤司っちの手がギリギリと音をたてながら食い込む。
「…いっ…。…バスケの話っすよ」
また、嘘をついた。
「バスケの話に、わざわざ二人きりになる必要がどこにある?」
「………」
赤司っちに告白されて、付き合い始めて約一ヶ月。
赤司っちの束縛が酷くなってきているのが悩みだ。
青峰っちには、そのことで相談に乗ってもらっていた。
でも、そんなこと本人には言えない。
「……ごめんなさい…」
「謝るようなことをしたのか?」
「…いや…、そうじゃないっすけど…」
それ以外、何を言えばいいんすか…。
何を言っても、どうせ納得も許しもしてくれない。
「そうか…。言う気はないんだね」
「そうゆう訳じゃ…っ!な…っ、赤司っち?」
いきなり強い力で体を押され、後ろにあった椅子に座らせられた。
そして、首筋に顔を埋めてくる。
「…んっ…!」
「悪い犬は、躾け直さないといけないな」
「あか…っ、…いっ…」
さっきまで強く吸われていたそこを、歯をたてて、思い切り噛まれた。
「い…たいっす…っ、赤司っち…っ」
「痛くしないと躾にならないだろう?」
目尻に涙を溜めながら、目の前にいる赤司っちの顔を見上げると、無表情な赤司っちと目が合った。
「…そんなそそる顔をされると、したくなるな…」
そう言いながら、俺の自身をズボンの上から撫でられる。
「ぁ…っ!やっ、待って!ここ部室で…っ、みんなが来ちゃ…っ」
「そんなこと関係ないよ」
俺の制止なんか目にも留めず、そのまま上下に擦られる。
服が擦れて、その気は無いのに感じてしまう。
「や…ぁ…っ」
どうにか逃げようと後退ってみたが、すぐ後ろの壁にぶつかり阻まれた。
「逃げようとするなんて、そんなに酷くされたいのか」
「ちがっ…、ひ、んっ!」
まるで喋るなとでも言うように、ぎゅっとそこを握り、胸の突起も痛いほどきつく掴まれる。
その瞬間、電気でも流れたかのように、身体中を何かが駆け巡った。
それは快感のそれではなく、痛みのだった。
「…ごめ、なさ…っ。許し…赤司っち…」
我慢していた涙が、ポロポロと頬を伝って落ちていく。
「もう降参なのか?涼太。まだこれからだぞ」
「…や…っ!」
笑みを浮かべながら、赤司っちは服の中に手を入れる。
これから始まる行為に覚悟した、その時だった。
「誰かいるんですか?…っ!」
「どうした、テツ。…っ、お前、何やってんだよっ」
ガラッと音をたてて入ってきたのは、黒子っちと青峰っちだ。
「…邪魔が入ったね」
ドアの隣にいる二人を横目に見ると、赤司っちは俺から離れてドアへと歩く。
「じゃあ僕は先に行っているから、お前たちも早く来るように。いいな?」
それだけを言い残して、赤司っちは部室を出ていった。
「…ひっ…く…」
赤司っちが出ていった安心からか、涙が溢れて留まらなかった。
ドアを見つめていた二人が、急いで駆け寄ってくれた。
「大丈夫ですか?黄瀬君」
「何があった?」
黒子っちは慰めるように優しく背中を擦りながら、青峰っちは心配そうに顔を覗き込みながら言ってくれる。
二人には赤司っちと付き合っていることなどを話していたから、こんなに心配してくれるのだろう。
「…だ、大丈夫っすから…」
「それが大丈夫な顔かよ」
「首筋の、痛そうですね…」
「首…?」
何のことかと聞きなおすと、黒子っちが鞄から鏡を取り出して、はい、と俺に見せてくれた。
そこには、くっきりと赤司っちの歯形がついていて、血も滲んでいた。
「………」
「…お前、そんなことされてもまだ別れないのか?どんどん酷くなってきてるんじゃないか?」
青峰っちの言う通り、赤司っちの行動は日を増すごとにどんどんとエスカレートしている。
そのうち、大怪我するだろうとは、俺も分かっている。
……でも。
「…それでも、俺、赤司っちが好きなんすよ…」
どんなに酷いことされても、俺から赤司っちを拒絶するなんてできない。
「…黄瀬」
「…黄瀬君」
それは多分、赤司っちの行動は、俺を愛しているが故のことだと分かっているから。
普段はちゃんと、俺を優しく、壊れ物みたく大切に愛してくれるから。
「…まぁ、お前がそう言うんなら別にいいけどよ」
「何かあったら、相談に乗りますからね」
「…二人共、ありがとう…」
いつの間にかとまっていた涙が、また再び流れだす。
そんな俺を見て、二人は困ったように笑いながら頭を撫でてくれた。
二人に感謝しながら「ありがとう」と心から伝えて笑い返す。
そのあと、俺たちは部活に出て、いつも通り練習をした。
多分、いや、絶対部活終わりに赤司っちに呼び出されることは目に見えているけれど、何故か今日は心がとても軽かった。
−END−