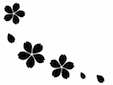第一話
「…せ……、…き、君、…黄瀬君っ」
「……ん…」
聞き覚えのある声に名を呼ばれ目を開けると、心配そうな表情をした黒子っちが俺の顔を覗き込んでいた。
「…あれ…、黒子っち…?おはよー」
へにゃりと笑って言う寝ぼけなまこの俺を、黒子っちが思い切り揺さぶる。
「おはよう、じゃないですよ!ちゃんと起きて下さい!大変なんです!」
「ちょ…っ、黒子っち揺さぶりすぎっ!起きた!起きたから!」
ガクガクと強く揺さぶられた所為で少し気持ち悪い。
けれどそのおかげで一気に目が覚めた。
「何が大変なんスか?…て、あれっ?黒子っちその格好どうしたんスかっ!?」
覚めた目で改めて黒子っちを見ると、何故かシャツ一枚で、下は何も着ていなかった。
それに両手足には鎖の部分が長い、先に錘のついた手錠を着けている。
「えっ、えっ!?何か劇でもやるんスか!?プレイ!?それとも、そういう趣味…痛っ!」
目のやり場に困って顔を赤くしながら言うと、いきなり顔を殴られた。
顔はモデルの命なのに、そのグーパンチは少しも容赦ない。
「バカ言わないでください、殴りますよ」
「も、もう殴ってるっス…」
「自分の姿もよく見てはいかがですか。黄瀬君だって僕と同じ格好ですよ」
「え?…うわぁっ!?何で!?」
促され自分の体に目を向けると、俺も黒子っちと同じシャツ一枚で両手足に手錠が着いていた。
シャツの大きさが黒子っちと一緒なのか、少し小さくて足が露になっている。
なんか下スースーすると思ったら…!
黒子っちの格好に驚きすぎて気づかなかったが、今俺たちが居る場所も見覚えのない場所だった。
映画とかでしか見たことがない、一面コンクリート造りの薄暗い部屋で、出口であろう扉は鉄格子でできている。
まるで牢獄のようだ。
「…く、黒子っち、ここ…どこ?」
思えば俺たちは学校に居たはずだ。
何故こんな格好で知らない場所に黒子っちと二人きりなのだろう。
今更自分の置かれている現状の不可解さに眉を寄せると、隣から深いため息が聞こえてくる。
「やっと事の重大さを理解してくれましたか。僕もここがどこだかは分かりません。黄瀬君より少し前に目を覚ましたんですから」
「そんな…、俺たちさっきまで学校に居たはずだよね…?」
「そのはずですが」
「…えっと…、確かショーゴ君も一緒に居たはず…」
俺は手を顎に当て、今日のことを思い返す。
******
「黒子っちー!お昼一緒に食べよー!」
授業終わりの合図と共に教室から抜け出し、黒子っちの教室の扉を勢いよく開けた。
扉の横で手を振る俺をいつもの静かな目でちらりと見て、ゆっくりな足取りで扉まで来る。
「…大声で呼ばないでくださいっていつも言ってるじゃないですか」
「えー、だって聞こえなくないっスか?教室って人いっぱいいるし」
「聞こえますよ。特にキミの声は聞き分けやすいですから」
「そうなんスか?」
「はい。不思議と黄瀬君の声は遠くから呼ばれても聞こえます」
「…っ」
深い意味じゃないことは分かっているけど、つい顔が熱くなってしまう。
好きな人からそんなこと言われたら、嬉しくならない訳がない。
「今日もいつもの場所ですよね?」
「あ、うん」
「じゃあ行きましょうか」
少し火照る顔を仰ぎながら、歩きだした黒子っちの隣について歩く。
いつもの場所、というのは体育館裏にある芝生が気持ちいい大きな巨木のある場所のことだ。
木のお陰で日陰が出来ていて熱くないし、どこからか流れてくるそよ風も気持ちがいい。
それにほとんど誰も来ないから静かで、俺たちのお気に入りの場所だった。
お昼はいつもそこで食べている。
「…お、やっと来たかお前ら。おっせーよ」
巨木の根を枕替わりにしてふんぞり返りながら寝ているショーゴ君が、俺たちに気づいて起き上がる。
「…また来たんスかショーゴ君。この頃よく来るっスね」
「ここはいい盗み食いスポットだからな。つーわけで飯寄越せ」
「それ盗み食いって言わないっスよ」
近くに座る俺たちに手を伸ばして、寄越せアピールをするショーゴ君。
そんな彼に飴玉を一つ投げ渡す。
「俺今日パンだからそれで我慢して。じゃなければ食堂行くのをオススメするっスよ」
「んだよリョータのくせしやがって生意気な」
「よければこれ食べますか?実はお母さんに弁当二つ作ってもらったんです。今日も灰崎君来るんじゃないかと思って」
そう言いながら持っていた包みの一つをショーゴ君に見せる。
なんで二つ持ってるのかと思ったら、そういう事だったんスね。
「ええーっ!!ショーゴ君のくせに羨ましいっス!そのお弁当、俺が食べたい!ショーゴ君にはこのパンあげるから!!ね!ね!」
黒子っちから弁当を受け取ったショーゴ君の腕を強く掴む。
「はぁ?」
「いいっスよね!?黒子っち!」
「まぁ、食べてくれるなら誰でもいいです」
「やった!じゃあはいこれ!」
半ば奪うようにして弁当を取り、代わりにパンを渡す。
それに若干眉を寄せつつも、「食えればどれも一緒だろ」とパンを噛じるショーゴ君。
「あー、でも勿体なくて食べれないっス!」
「食べないなら灰崎君に渡してください」
「嘘っス!食べるっスよ!」
蓋を開ければ黒子っちのと同じおかずが入っていて、思わず頬が緩む。
「黄瀬君、ケータイ鳴ってますよ」
「え?あ、ホントだ。メール?」
開いて読んでみると、『開幕ですか?』という短い文と、その下にURLが貼ってあった。
登録してある人からしかメール来ないようにしてるのに、差出人は不明だった。
「…なにこれ?」
「どうしたんですか?」
携帯の画面を黒子っちにも見せる。
「…迷惑メール、ですか?」
「でも俺、登録してある人からしかメール来ないようにしてるんだけど…」
「なんか変なURLが貼っつけてあんぞ。ほれ」
いつの間にか隣に来て携帯を覗き込んでいたショーゴ君が、なんの躊躇いもなくURLをタッチしてしまう。
「ああ!ちょ、なにすんスか!ウイルスとか入ってきたらショーゴ君の所為っスよ!!」
「そんなん知らねーよ。お、またメール来たぞ」
「…『開幕します』?何なんスかこのメール。意味分かんないっス」
特にウイルスとかは入ってきていないようだ。
安心しつつ、携帯をポケットにしまおうとする。
しかしそれは黒子っちに手を掴まれて阻まれた。
「黒子っち?」
「…黄瀬君のケータイ、光ってませんか?」
「そんなまさかー…、て、うわっ!マジで光ってる!!え!?」
ありえない事に、俺の携帯のディスプレイから眩しいくらいの光が放たれていて、その光はどんどん眩く明るさを増していく。
「ちょっと!ショーゴ君の所為で俺のケータイがおかしくなったじゃん!どーしてくれんスか!」
「いや、ウイルスで携帯が光るとか聞ーたことねーから!」
あたふたする俺たちを他所に、光は一層強く輝いて周りを白い光で包んだ。
「まぶしっ!」
「…っ!」
「うわっ!?」
余りの眩しさに目を瞑った。
それから―――。
******
「――それから…どうしたんだっけ?」
記憶はそこで途切れていて、いくら考えても思い出せない。
「僕もそこからは思い出せません」
「黒子っちもっスか?…じゃあ、あの後俺たちなんでか知らないけど気失って、気づいたらここにいた、てこと?」
「…現実味ありませんしそんなことありえないと思いますが、そういうことになりますね。でもそれなら灰崎君はどこにいるんでしょうか…」
「だよね…。よし、とにかくここから出ないスか」
考えるよりも行動っス!
俺はおもむろに立ち上がり、鉄格子の扉を目指して歩き出す。
けれど、手足についてる鎖の手錠の所為であと一歩届かない
「…ぐ、と、届かない…っス、!」
「あともう少しですよっ。そのムカつくほど長い手足に長身、ここで使わないでいつ使うんですかっ。このデルモめっ。イケメン爆発しろっ」
「ちょっと黒子っち!?それ応援してんスか!?」
「もちろんです。キセクンガンバッテーっ」
パンッパンッ!
黒子っちが一定のリズムで手を叩いて応援してくれてる(?)も、いくら踏ん張っても扉には届かなかった。
ドサッと元の場所に寝転がると、黒子っちに優しくデコピンされる。
「諦めるのが早いですよ黄瀬君。もう少しなんですから」
「うぇー、無理っスよぉー…」
泣きべそかきながら抱きつくと、ため息をつきながらも頭を数回撫でてくれた。
「…えへへ」
「笑ってる暇じゃないですよ」
「だって黒子っちが撫でてくれるの気持ちいいから好きなんだもん」
「…そうですか」
「もっと撫でてくれないスか?ナデナデしてー」
ふざけ半分に言い、頭を黒子っちに向ける。
「…これぞまさに犬ですね。首輪つけてやりたいです」
「え?何?」
「いえ、何も」
その時、俺たちの会話を断ち切る様にどこからか響きの良い靴底の音が聞こえてきた。
「…誰か来ましたね」
「うん。…ショーゴ君、スかね…?」
コツ、コツ、とゆっくり近づいてくる足音は俺たちの居る部屋の前で止まった。
しかし鉄格子の隙間から顔を覗かせたのは、少し厳つい髭面の男と、見るからに高級そうな服を着ている男の二人だった。
全然見知らぬ男の登場に、どうしたものかと顔を見合わせる。
黒子っちも少し動揺しているようだ。
「今ウチにいる中での上玉はこの二人だけでございます」
「…ほう、これほどの上玉は初めて見たぞ」
「そうでございましょう。それにまだ何方様にも手を付けられていないので、今が目付き時かと」
「それはまたいい時に来れたものだ」
厳つい顔に似合わない敬語で、髭面の男はもう一人の男によく分からない事を言っている。
上玉…?
一体何の事言ってるんだ?
それに手を付けられてないって…、何に?
「では、どちらになさいますか?」
「そうだな…、髪が水色の方にしようか」
「…っ!?」
黒子っちのこと!?
「かしこまりました。では、今晩のみの奉仕でよろしいでしょうか?」
「あぁ」
「ちょっと待てよ!」
嫌な予感がして、俺は咄嗟に声を上げた。
奉仕とか、意味分かんないし!
「何言ってんのアンタら?上玉とか奉仕とか。てかここに俺たち閉じ込めたのってアンタなん?何考えてんの?」
俺の言葉に、男たちは怪訝な眼差しを向けてくる。
「…何を言ってるんだ?コイツは」
「すいません、拾ったばかりの奴隷でして、まだよく理解していないんですよ」
奴隷…!?
拾った…!?
本当に何を言ってるのか意味が分からない。
それは俺の頭が悪い所為とかじゃなく、黒子っちも同じようだった。
「奴隷って一体何のことですか?拾ったって…」
「お前らはウチの店の前に落ちてたんだ。その整った顔は売れるから拾ってやった」
今まで敬語で話していた男が、急に声のトーンを落として言う。
「はぁ!?俺ら学校に居たんだけど!?拾ったとか意味分かんねーし!それにこれ人拐いって言うんだけど!警察捕まるよ!」
「…ガッコウ?ケーサツ?お前らこそ何意味分かんないこと言ってんだ?頭でもおかしくなったか?」
そう言いながら、髭面の男は鉄格子の扉を開けて中に入ってくる。
「とにかく、お前らはもう奴隷の商品登録されたんだ。で、早速水色の髪のお前は今晩売れた。分かったか?」
軽く馬鹿にしたような言い方にムッとするも、今はそんなことどうでもいい。
いつからこの世の中は奴隷なんてものが認められたんだ。
この男の言ってることは俺と噛み合わなくて、まるで別の世界にでも来てしまったような気分だ。
「…奴隷って何すんの?」
「そんなものは買った人それぞれだ。言われた事を文句を言わずにやる。それが奴隷だからな。まぁ大体は夜の奉仕、だな?」
「!」
「おら、行くぞ」
男が鍵を取り出し、黒子っちの手錠を外そうとする。
その間にすぐさま入り込み、守るように両手を広げて背中に黒子っちを隠す。
「黄瀬君…!?」
「俺がやる!だから黒子っちはやめて…、ください!何でもするから!」
「何言ってるんですか黄瀬君!それこそやめてください!」
俺の肩を掴んで抗議する黒子っちは無視して、再度男に言う。
「俺なら何でもするから、だから黒子っちだけはやめてください!」
「そうは言われてもな、注文はこっちの水色髪なんだよ」
「…いや、気が変わった。その金髪の方にしてくれ」
扉の外からこちらの会話を聞いていたもう一人の男が俺を見る。
その視線は俺を値踏みするようにねっとりとした目付きで、少し気持ち悪い。
「よろしいんですか?」
「あぁ、そっちの方が面白そうだ」
「かしこまりました」
俺の手錠を外して部屋から出る様に言われ、大人しくそれに従う。
「黄瀬君!」
「黒子っち一人にさせちゃうけど、ちょっとの間待っててほしいっス。今晩、って言ってたし、朝までには戻ってこれると思うから」
「待ってください!」
「じゃあ、また後でね黒子っち」
「黄瀬君…っ!!」
後ろから黒子っちに叫ぶように名を呼ばれたけど、振り返らずに男について行く。
黒子っちを守れた、それだけでも良かった。
それからはもうどうでもよくて、黙って男について行って、俺たちが今まで居た店らしきところから外に出て、停まっていた馬車に男と乗り込んだ。
外の景色は日本とは思えないほど綺麗で、建物も洋風なものが多かった。
歩いている人々もドレスやスーツを着ている人がいたり、ステッキを持っている人などがいた。
それに傭兵というのだろうか?
そんな格好をしたいかにも警備中な感じの人もちらほら居る。
まるで夢でも見ているかのような気分だった。
むしろ夢であってほしい。
そう思いながら、窓から見える美しい景色をたたじっと見ていた。
「…僕は…、黄瀬君に守ってもらうんじゃなくて、守りたいんです…。何で、分かってくれないんですか…。…黄瀬君…っ」
─END─
二話に続く