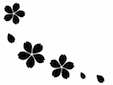恋人
「……またか…」
靴を仕舞うために下駄箱の蓋を開けると、綺麗な可愛らしい封筒が一枚入っていた。黄瀬はそれを手に取り、眉を寄せて深いため息をつく。昨日フラレたばかりで、今こういう物を見ると胸が痛む。
「…どうしよっかな、コレ…」
「おはようございます、黄瀬君」
「うぉわっ!?」
いきなり隣に現れた人物に、モデルらしからぬすっ頓狂な顔でそちらに目をやる。驚きすぎて、開いていた自分の下駄箱の蓋に思い切り頭をぶつけてしまった。
「――っいってー…っ!」
「大丈夫ですか?というより、何やってるんですか」
「黒子っちがいきなり声かけるからビックリして頭ぶつけたんスよ!」
「それはそれは。ご愁傷様です」
「ヒドっ!」
しゃがみこんでいる黄瀬の前で合掌する黒子。涙目で頭を押さえながらなんとか立ち上がる。
「それにしても、黄瀬君が僕に気付かないなんて、すごく久しぶりですね。キミが一軍に入ったばかりの頃以来でしょうか?」
「あー…、そうだっけ?」
「そうですよ。いつもは黄瀬君から挨拶しに来るじゃないですか。…それ、なんですか?」
黒子が黄瀬が持っていた封筒に気付いて首を傾げながら指を指す。それ?と黒子の視線を辿って自身の持っている手紙のことだと分かり、胸元まで持ち上げてヒラヒラと振った。
「あぁ、俺の下駄箱に入ってたんスよ」
「…ラブレター、ですか。相変わらずモテますね」
「モテるって別に嬉しいことじゃないっスよ。手紙とかプレゼントとか、貰っても困るだけだし。返すと泣かれるし、だからと言って捨てられないし」
「…自慢ですかこの野郎」
「自慢じゃないって!本当に困るんだって!」
「その手紙はどうするんですか?」
「うーん…、まだ中身見てないから分かんないけど、呼び出しとかだったら一応行くっスよ。そんで断って手紙を返す、スね。あー…泣かれたらどうしよう…」
「…まぁ、僕は何も手伝ってあげられませんけど、頑張ってくださいね。女の子泣かせさん」
「ちょっ、その呼び方ヤメテ!」
ちょうどいいタイミングで、二人の会話を遮るようにチャイムが鳴り響く。それを合図に黒子はいそいそと上履きに履き替えてさっさと黄瀬の横を通り過ぎていく。
「もうこんな時間ですか。ホームルームに遅れてしまいます。では黄瀬君、また放課後に」
「え…っ、あ、放課後は俺…っ…て、…行っちゃった…」
部活には行かないと伝え終わる前に、黒子は自分の教室へと入ってしまった。
「まあ言わなくてもいっか。約束してる訳でもないんだし。…そういえば」
緑間もそうだったが、黒子もいつも通りに接してくれた。本当は少し軽蔑されたり距離を取られたりするのではないかと心配していた。黒子たちが人を見た目で判断しない人徳者だという事は充分分かっているが、男に告白してるところを見られたのでこれは流石に避けられたりするかも、と。しかし二人共避けるどころか逆に話しかけてくれて、表にこそ出さなかったが本当に、本当に嬉しかった。
「俺なんかより、二人の方がずっと何倍もイケメンだろ」
女の子は見る目ないっスねーなんて苦笑しながら呟き、黄瀬も自身のクラスへと急いだ。
*****
1日目のテストが全て終わり、ガヤガヤと騒がしい教室内ですっかり忘れていた封筒の存在を思い出し、鞄に入れっぱなしのそれを取り出した。丁寧に封を切れば中には1枚の手紙が入っていて、女の子らしい小さい可愛らしい文字で『お話があるので、放課後、屋上に来てくれると嬉しいです』という短い一文と、送り主であろう名前が書いてあった。
「…やっぱラブレターか」
読み終わった手紙を封筒に戻し、再度鞄に入れ直す。
「どうせ放課後暇だし、断って手紙返すために行こうかな」
告白される前から返事を決めるのもどうかと思うが、誰であろうと付き合う気はない。女の子で名前を覚えているのは桃井くらいで、他は名前もそうだが顔すらも覚えていないのだ。赤司を好きになる前は告白された女の子と付き合っていた時期もあったが、モデルの仕事やバスケ、黒子たちとの約束を優先していたら、別れて、と言われた。別に好きでもなんでもなくてただお互い楽しめればいいという軽い気持ちで付き合っていたから二つ返事で分かったと答えたら、思い切り頬を叩かれた。あの時は叩かれた意味が分からなくて、商売道具の顔に傷がついて、相手が女の子なのも気にせずに睨んでしまった。どうせお前だって俺じゃなくて、俺の顔とモデルの肩書きが好きだったんだろ、と。その数日後に風の噂で、元カノは灰崎と付き合い始めたと耳にした。それから黄瀬の中で女は自分勝手でめんどくさいものとされ、告白されても全て断ってきたのだ。
重い腰を持ち上げて鞄を肩に引っ掛ける。チラリと後ろの席を見てみれば、いつの間にか紫原の姿はなかった。手紙を読んでいる間に体育館へ行ってしまったのだろう。それに少し安心して教室を後にする。下駄箱の前を通り過ぎ、屋上へと続く階段を上がっていく。
「紫原っちってば、一言くらい声かけてくれてもいいのになあ」
テストの合間の休憩時間や昼休みの時はいつも通りの様子で話しかけてくれていたから、多分無視された訳ではないのだろう。急ぐ用事があったのか、手紙を読んでいたからほっといてくれたのか。
扉を開けて屋上に入り、他に誰もいない事を確認してからいつもサボる時に使っている青色の長椅子の上に寝転がった。ここは丁度日影が出来ていて日が当たらなく、涼しい風も通り抜けるので結構気に入っている。入口の建物の後ろなので、誰か来たとしてもそうそう見つかることもない。
「……ふぁー…、ねむ…」
早く来すぎてしまったのか手紙の相手は中々姿を表さなかった。ゴロゴロしながら待っているとだんだんと眠くなってきて、降りてくる瞼をそのまま閉じて意識を手放した。
******
「……く…、き…君、黄瀬君」
「…ん…?」
自分の名を呼ぶ聞きなれない誰かの声に、黄瀬は薄らと目を開ける。寝ぼけて定まらない目を擦り、体を起こして声の主に顔を向けた。
「……えっと、キミ、誰?」
肩に掛かるくらいの黒髪に、小柄で華奢な体。大きなつぶらな瞳に黄瀬を映し、頬を染めている桃井とも並ぶ美少女に首を傾げる。
「その、手紙…の…」
「…あぁ、この手紙、キミが?」
鞄から取り出して女の子に見せると、おずおずと小さく頷く。
「ごめんなさい、日直の仕事が長引いて、待たせてしまって…」
「大丈夫だよ、どうせ暇だったし。それで、話って?」
ニコリと笑顔を作って優しく問いかけると、女の子はきゅ、と結んだり開いたりと暫く口をはくはくと開閉させてから、意を決したように黄瀬を真っ直ぐに見つめた。
「……あ、の…、…黄瀬君のことがずっと好きでした、付き合ってください…っ」
「…あー…」
予想通りの告白にため息が出そうになるのをなんとか留める。
「…ごめん。俺、キミのこと知らないし、それに今バスケに力入れてるんだよね。だからもしキミと付き合うとしても、部活があるから放課後は会えないし、休日も先にキミとの約束が入っていたとしても、友達に遊びに誘われたらそっち優先すると思うんだ。本当に、ごめんね」
いつも断るときに使っている言い慣れてしまった台詞を言う。この後はだいたい泣かれて、泣き止むまで謝り続けることになる。今回もそうなるだろう、と辟易しながら頭を上げて女の子を見る。
「!」
しかし、予想していた泣き顔とは違い、女の子の顔は真剣な表情のままだった。先程までのオドオドとした雰囲気とは違う力強い視線。
「…それでもいいです。黄瀬君に時間がある時に少し会ってくれるだけでも私は充分幸せなので、付き合ってくれませんか…!」
「……ぇ…」
真っ直ぐな視線を受け、戸惑いに口を噤む。泣かれるか、怒り出すかのどちらかだと思っていたのに。
何でそんなに真剣な表情なのだろう。
まるで、本気で俺のことが好きみたいな…。
「…一つ、聞いていいかな?」
「は、はい」
「…変なこと聞くけどさ、…俺のどこが好きなの?自分で言うのもなんだけど、顔以外じゃ良いところなんてないと思うんだけど」
「え!?」
黄瀬の問いに、女の子の顔が一気に林檎のように真っ赤になる。
「…それは…、ぜ、全部…です」
「全部…」
「バスケしてる時の楽しそうな表情とか、意外と寂しがりなところとか、モデルの仕事に真剣に取り組んでるところとか…。それと…好きな人といるときの、幸せそうな表情も…」
「…っ。好きな人って…」
「…赤司君、ですよね…?」
驚きすぎて、何も言えなかった。そんなに俺は赤司っちに対してあからさまだったのだろうか。
「…私、よくバスケ部の練習見に行くんですけど、黄瀬君の視線の先には必ず赤司君がいるから、好きなのかなって…」
「…気持ち悪くないの?」
「恋愛は人それぞれだと思うし、気持ち悪いとかより黄瀬君も人を好きになるんだって安心したっていうか…、あっ、悪い意味じゃなくて、黄瀬君人と距離を置いてるように見えてたからで…、あの…っ」
わたわたと両手を動かして慌て始めた女の子に思わず破顔する。彼女は俺の外見じゃなくて、ちゃんと中身を見てくれてる。そう思うと、心が少し暖かくなった気がした。
「…はは…っ、大丈夫、分かってるから。…本当に“俺”が好きなんだ、そっか…」
女の子に告白されて、こんなに嬉しく思えたのは初めてかもしれない。少しだけ、傷ついていた心が癒された。
「…やっぱり、駄目ですよね…。黄瀬君は赤司君が好きなのに…」
…この子なら、もしかしたら本気で好きになれるかもしれない。
「…一週間、試しで付き合ってみるってのはどうかな?その間で、キミのこと好きになれそうだったら、ちゃんと付き合ってほしいんだ」
「ぜっ、全然大丈夫です…!…でも、赤司君は…?」
「…実を言うとさ、俺昨日赤司っちにフラレたばっかなんだよね」
「あ…、ごめんなさい…」
「平気だよ。だから今日と明日は部活やりに行かないんだ。それに、キミなら好きになれそうだから」
「…すごく、嬉しいです。勇気出してよかった…」
じわりと目を潤わせ、ニコリと頬を染めて笑う彼女を見て、黄瀬も自然と笑顔が溢れた。
「よかったら、今から一緒に帰らない?」
「はい…!」
「じゃ、帰ろっか」
鞄を片手に持ち、彼女と一緒に屋上を後にする。
靴に履き替えたところで戸惑いがちに手を差し出され、それを強く握って歩き出す。黄瀬のすぐ隣で顔を真っ赤にしながら笑っている彼女を、素直に可愛いと思えた。
******
「…黄瀬遅いな」
体育館で黒子たちと練習をしていた赤司は、なかなか来ない黄瀬に眉を寄せた。
「黄瀬君ならラブレターをもらっていたので、それの返事をしに行ってると思いますよ。もう少しかかるんじゃないでしょうか」
隣にいた黒子がそう教えてやると、赤司は扉に向けていた視線を黒子に向けた。
「…ラブレターの返事?」
「はい。断りに行くと言ってましたよ」
「…そうか。だが遅すぎる気がするな。ちょっと探してくるから各々練習していてくれ」
「え?あ、はい…」
持っていたボールを籠に戻して、黄瀬を探しに体育館を出る。来るまで待っていればいいのだが、何故か落ち着かない。どこで告白されているのか分からないため校内を回ろうとしたが、案外すぐに見つかった。今まさに校門を出るところの黄瀬は、隣にいる女子と手を繋いで笑い合っていた。傍から見れば、恋人同士にしか見えない。
「……どういうことだ…?」
顔を赤く染めて黄瀬を見つめている女子を、黄瀬が優しく引っ張って校門から出て行ってしまった。そんな二人が見えなくなっても、赤司は暫くその場から動けなかった。
あれが黄瀬にラブレターを渡した女子だとしたら、黄瀬は告白を受け入れたと言うことか…?
いくら考えても分かるわけもなく、そのまま踵を返して体育館に戻る。帰ってきた赤司に気づいた黒子が、ゆっくりと近づいてきた。
「あれ、一人ですか?黄瀬君は…?」
「………黄瀬は断りに行くと言っていたんだよな?」
「あ、はい。そう言ってましたけど…。どうかしたんですか?」
「……いや、なんでもない。黄瀬はもう帰ったみたいだ」
「そうですか。仕事でも入ってしまったんでしょうか」
「…そんなところだろう」
黒子に練習を再開させ、赤司もボールを取りに用具室へと走る。正直気になって仕方がなかったが、後でさり気なく本人に聞いてみればいいだろうと、今は考えないようにした。
******
次の日、登校途中に偶然黄瀬を見つけ、その後ろ姿に駆け寄り袖を軽く引っぱって話しかけた。
「黄瀬」
「…あ、赤司っち…っ」
黄瀬はビクリと大袈裟に肩を跳ねさせると、ゆっくりとした動作で赤司に振り返った。しかしすぐに目線を明後日の方向へ背けてから早口で言い放つ。
「え、えっと…っ、ごめん赤司っち…、俺今日日直だから急いでるんだ、じゃあまた!」
「は?おい!」
少しもこちらを向かずに黄瀬は走って行ってしまい、残された赤司は首を傾げることしか出来なかった。
それから、校内で会う度に黄瀬に声をかけているのだが、話すどころか、顔も合わせようとしない。明らかに嘘だと分かる言い訳を残して走って逃げていってしまう。放課後も部活に来ないで、昨日見た女子と帰って行くのを目にした。
そんなことが三日続き、テスト期間が終わり部活に来るようになってもあからさまに赤司を避ける黄瀬に、さすがの赤司も痺れを切らし昼休みに黄瀬の教室へ向かった。ここ最近ずっと一緒に帰っているらしい女子と楽しげに話している黄瀬の腕を何も言わずに引っ掴んで、無理やり教室から連れ出す。
「えっ!?ちょ、赤司っち!?」
女子が心配そうにそんな赤司たちを見ていたが、そんなことは気にせずに使われていない教室に連れ込んだ。扉を閉めて黄瀬の方を向くと、バツの悪そうな顔をした黄瀬と目が合う。
「……な、何か用っスか…?」
「何で俺を避けるんだ?」
「…なんでって…」
「テスト期間も部活に来なかったよな。最近も部活が終わったらさっさとあの女子と帰って行くのを何回か見たが」
最初は肩を小さくしていた黄瀬だったが、赤司がここまで言い終わると眉を寄せ始める。そして少しの沈黙の後、睨むかのように赤司を見た黄瀬が震える声で話し始めた。
「…避けるって…当たり前じゃないスか…っ。もう忘れたの?赤司っちが言ったんスよ?学校でもどこでも話しかけるなって」
「…は?」
「話すのも嫌なくらい俺のこと大嫌いだからって。…だから…赤司っちに不快な思いさせてたんだって気付いたから…なるべく視界に入らないように避けてたのに…」
「いつ俺がそんな事を言った?何の事を言われているのか見当もつかないんだが」
「…自分で言ったことじゃないスか。…嫌いなら、俺に話しかけないでほしいんスけど。そういうことされると辛いんスよ…っ。…もう…、期待させるようなことすんなよ!」
目尻に涙を溜めてそう叫ぶと、黄瀬は赤司を置いて教室から出て行ってしまう。すぐに追いかけようとしたが、赤司が教室を出た時にはもう黄瀬の姿はどこにもなかった。
「…嫌い…?俺がいつそんな事を言った…?」
覚えのないことを言われ、困惑するしかなかった。だが、黄瀬もあんな剣幕で冗談なんか言うわけもなく、訳が分からなくなる。
「……、…」
ふと、思いだした。今まで赤司に覚えがない時は、だいたいアイツの仕業だった。赤司と瓜二つの弟。そういえば、この前黄瀬に会ったとも言っていた。ここまで考えてハッキリした。
「……またアイツか」
怒りを込めてそう呟き、黒板を思い切り殴りつける。隣の教室まで響いてそうな音も、今の赤司の耳には入ってこなかった。これまでは何をされても無反応で通してきたが、黄瀬に関しての事だけはどうしても許せない。
溢れて収まらない怒りを隠そうともせずに、赤司は静かに教室へと足を進めた。血の滲んでいる手を、真っ赤になるほどに握りしめて。
‐END‐
5に続く