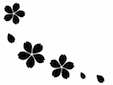二度目の
「…えっと、マジバ…行きますか?」
赤司の後ろ姿が見えなくなっても誰も口を開く気配がなかったからか、黒子が躊躇いがちに言葉を放った。
「あ、あぁ、早く行こうぜ」
「…ごめん、俺今日は帰るね」
「俺も今日は帰らせてもらう」
「赤ちんいないし俺も帰るー」
「そうですか…」
「ごめんね黒子っち。じゃ、また明日」
「…はい」
無理して笑う黄瀬に続いて、緑間と紫原もその場を後にした。残された黒子と青峰は無言で顔を見合わせてから行きつけのマジバへと足を進めた。
「…ビックリしました」
「は?何がだよ」
「黄瀬君と赤司君ですよ。黄瀬君の泣いてるところ、初めて見ました。赤司君のあんなに怒っているところも…。2人ともあまり感情を表に出さないじゃないですか」
「そうかあ?赤司はともかく、黄瀬はコロコロ表情変わってるだろ」
「そうなんですけど、そうではなくて。黄瀬君って笑顔とか泣き真似とかいじけた振りとか、そういう冗談半分の感情ばかりしか見せないじゃないですか。本心からの素顔とか、たまに見せるバスケの時くらいで。それ以外は表情がいつも嘘っぽいっていうか」
「あー…?黄瀬の違いなんてわっかんねーわ」
「まぁ僕も断言は出来ないんですけど…。兎に角いつも作った様な表情ばかりな気がするんですよ」
手を顎に当ててそう言うと、青峰は少し間をおいてから言いにくそうに口を開いた。
「……なぁテツ」
「何ですか」
「…さっきの告白大会、ドッキリとかコントとかじゃねーよな?」
「そんなわけないじゃないですかアホ峰君」
「アホ…!?」
「黄瀬君だけならまだしも、赤司君までそんな暇なことはしないと思いますよ。それに、あんな後味の悪いドッキリがありますか?」
「そりゃそーだけどよ…、男同士だぞ?あいつら」
「恋愛に男も女も関係ないですよ。好きになったのがたまたま同性だった、それだけのことです。当人同士の問題なんですから他人が口出しすることじゃないですよ。結果がどうなったとしてもせめて二人が今までと変わらず笑い合えるように、遠くから応援していましょう」
「おぉ…(何言ってんのかよく分かんねーけど)」
「…て、どこかの本に書いてありました」
「本かよ!」
*****
「黄瀬」
何も考えず、ただボーっと帰路を歩いていると、唐突に名を呼ばれた。振り返るとすぐ後ろに緑間がいつもの難しい顔で立っていた。こんなに近くまで迫っていた緑間の気配を、名前を呼ばれるまで微塵も感じなかったなんてどれだけ呆けていたのだろうか。
「…緑間っち、どうしたんスか?わざわざ」
「わざわざではない。帰り道が一緒なのだからついでに決まっているだろ」
「あ、そういえばそうだったっスね」
咄嗟にいつものおちゃらけた笑顔を作ろうとして失敗した。今の自分の顔は何とも形容し難いものになっている事だろう。苦笑いに近いそれをどう受けとったのか、緑間が眉間のシワを増やしながら重々しく口を開く。
「…お節介だとは思うが、赤司の言っていたことは本当だぞ」
「赤司っちの言ってたこと?…あぁ、俺のこと好きってやつ?」
「そうだ」
「…分かってるっスよ。赤司っちがあんな冗談言う訳ないし」
そうだ、赤司の言葉は本心に間違いない。だからこそ、あの最後の台詞はいくら考えても意味が分からなかった。納得出来なかった。
―――好きだから、友達でいたい。
「…ていうか、なんで赤司っちが本気だって分かるんスか?」
赤司のことだからないとは思うが、『相談でもされた?』と付け足す。
「…いや、相談などはされていない。たまに赤司と打つ将棋の最中に、よくお前の話題が出てくるのだよ。話している間の赤司の顔は緩みきっているしな。多分、本人は自覚していないと思うが」
「…赤司っちが、俺のことを…?」
「お前が階段で転んで頭打っただの、黒子を昼飯に誘っても嫌だと断られていじけていただの、服を前後ろ逆に着ていただの、あいつには珍しく爆笑していたぞ」
「は!?なんかいいの一つもない気がするんスけど!?」
「…まぁ、あいつにも何か思うところがあるんだろう」
顔はいつもと変わらずの仏頂面だが、励ましてくれているのだと分かる。緑間のらしくない行動に頬が緩む。
「…ありがとう、緑間っち」
「…ふん」
「でも俺、緑間っちは青峰っちと同じで『男同士なんてありえない』って言うタイプだと思ってた。まさか励まされるなんて夢にも思わなかったっス。明日雨降るかも。台風並みの」
「…そうか、殴られたいのだな」
「嘘っス!冗談っスよ!!」
緑間のお陰で、少しずついつもの調子がでてきた。明日、赤司に理由を聞きに行こう。心の内でそう決め、少ないながらも緑間との他愛のない会話を楽しみながら家路を歩いた。
*****
いつもならまだ寝ている時間に黄瀬は家を出た。早朝で、しかも土曜日だからか、通学路には黄瀬以外の人影はない。
一軍は今日、スキルアップのために一日部活が入っていた。練習の最中に部活に関係すること以外で赤司に話しかければ間違いなく怒られるだろう。だから部活が始まる前に話を済ませておこうと早めに学校へと向かっていた。赤司のことだ、多分もう部室にいることだろう。少し前に、寝ぼけて時計を見間違えていつもより一時間も早く家を出た時も、部室にはもう赤司がいた。黄瀬を見て、『早いな』と驚かれた。理由を話せば『黄瀬らしいね』と笑われてしまったが、お腹を押さえて笑う赤司はその時初めて見て、思わず携帯を取り出して写真を撮ったのを思い出す。すぐに消せと怒られたので消去してしまったが。あれは勿体なかった。
案の定、部室にはすでに赤司がいた。日誌をつけていたらしく、真剣な面持ちでペンを走らせている。扉の横から中を伺っていた黄瀬に気付くと、少し微笑んでペンを座っていた長椅子の上に日誌とともに置いた。
「おはよう、黄瀬。珍しく早いじゃないか」
「おはよう赤司っち。赤司っちも相変わらず早いっスね」
「まあね。黄瀬はまた寝ぼけて時計でも見間違えたのか?」
クスクスと笑いながら言ういつもの調子の赤司に、昨日のことで緊張していた心が解れた。ゆっくりと赤司に近づき、手を伸ばせば触れられる距離で足を止める。
「違うっスよ。…昨日のこと、聞こうと思って」
「昨日のこと?」
「…なんで、友達以上にはなりたくないんスか?」
「…ああ、そのことか」
赤司がそう呟いたと同時に、周りの空気が一気に重たくなる。先程まで柔らかく微笑んでいた赤司の顔も、真剣なものへと変わった。
「なりたくない、じゃなくて、なれないんだ」
「え?どういうこと…?」
「なりたくてもなれないんだよ」
「……えっと…?」
恋人になるならないは、本人たちの意思で決めるはずだ。なりたくてもなれない、なんて言い方だと、誰かに反対でもされているのかとしか考えられない。親にでも話したのだろうか。
「…誰かに反対でもされたんスか?」
「いや、そういうことじゃない。俺に問題があるんだ」
「問題?」
「……高校から俺は…」
そこで言葉を切ると、悲しそうな、辛そうな、感情を押し殺してる表情で唇を噛み締めた。最近は見ることがなかった、初めて赤司を見た時に感じた、悲哀に満ちたあの表情だ。
「…赤司っち?」
「………中学卒業と同時に、引っ越すんだ。京都に」
「京、都?え、なんでっ!?」
「家の都合でな。だから、もし黄瀬と付き合うとしたら、卒業までに別れないといけないんだよ」
「遠距離恋愛だってあるじゃないスか!海外って訳じゃないんだし、俺月1くらいなら会いに行けるし、それにメールとか電話だって…!」
繋ぎ止めようと必死な黄瀬の台詞に、赤司はただただ苦笑いを浮かべるだけだった。それが無理だという拒絶の意味を持っていることはすぐに理解した。
「…なんで…」
「すまない黄瀬。…そろそろ皆も来る時間だ。この話は終わりにしよう」
俯いたまま呆然と立ち尽くしている黄瀬を残して、赤司は静かに部室を出る。音を立てずに後ろ手に扉を閉めて、深いため息を一つ。そんな赤司に遠慮なく無言の視線を横から送ってくる人物に、ゆっくりと顔を向ける。
「そんなところで立ってないで、中に入ってきても良かったんだけどね、緑間」
扉のすぐ横で、猫だか兎だかよく分からない奇妙な人形を抱えて立っている緑間に声を掛けると元々寄っていた眉に更に深くシワが寄せられた。仏頂面の大男が巨大でファンシーな可愛いぬいぐるみを抱き抱える様は何とも珍妙だ。
「あんな空気の中をズカズカと入っていくほどアホではないのだよ。…それより、本当の理由を黄瀬に言ってやらないのか?」
「言う訳ないだろ。言いたくない。それに、この事は他言してはいけない決まりなんだよ」
「俺はいいのか?」
「緑間は信用できるからね。黄瀬たちが信用できないって訳じゃないんだけど」
意味有り気に緑間を見つめた後、赤司は緑間の横を通り過ぎていく。用具室の扉の前で足を止めると、何か思い出したように再度顔だけ緑間へと向けた。
「ああ、あと俺たちはどうやら好みが似ているようだから、何かあった時はお前に任せられるから、かな」
「…どういう意味だ」
「それはお前が一番分かってるだろ?」
不敵な笑みでそう言葉を残して、赤司は用具室の中に入っていった。暫く用具室の扉を見つめていた緑間は視線を目の前の部室に戻し、ドアノブに手を添えた。
「……黄瀬絡みになると、お前は馬鹿になるのだよ」
*****
次の日。黄瀬はモデルの仕事のため京都に来ていた。京都の美しい街並みを背景に何枚も撮影し、仕事が終わった頃には空はもう綺麗なオレンジ色に染まっていた。メイクさんがくれた撮影用の衣装のまま、せっかく来たんだからとあちこち見ながら散歩することにした。ファンの子たちに見つかると色々と面倒なので、なるべく人通りの少ない道を選んで歩く。
「…ん?あれって…」
小さな橋を渡ろうとした時、橋の隣にあった公園のベンチに見慣れた赤い髪の後ろ姿が見えた。
「もしかして、赤司っち?何で京都に…?」
恐る恐る近づいて、横顔がはっきりと見える位置まで移動する。目が隠れるくらいまで伸びた前髪に、黄瀬より少し短い後ろ髪、伏せていても分かる吊り上った切れ長の燃えるように赤い瞳。
「やっぱり赤司っちだ…!」
「…ん?」
「あっ」
黄瀬の声に反応して、本を読んでいたらしい赤司が顔を上げる。黄瀬を視界に入れると少し驚いたように目が見開かれた。何も考えずに声をかけてしまったが、まだ昨日の整理を自分の中で出来ていないことを思い出す。
「…涼太?何でここにいるんだ?」
「…ん!?え、ど、どうしたんスか赤司っち…?」
急な名前呼びに思わず声が裏返る。確か赤司の二人称は苗字だったはずだ。今まで誰かの事を下の名前で呼んでいるところなんて、黄瀬が知っている中では1度もなかった。
「何がだ?」
「なんかいつもとちょっと違うっスよね…?」
「そうか?僕はいつも通りだが?」
「僕!?やっぱりいつもと違うっスよ!!」
見た目や声などは確かに見慣れた赤司だったが、所々違うところがある。一人称と二人称、そして赤色ではない左目。纏っている雰囲気もなんだがピリピリしていて近づきがたい感じだ。
「頭でも…打ったんスか?」
「僕がそんなヘマをすると思うのか?」
「…思わないっス」
「そういうことだよ」
「え?」
「本当に涼太は馬鹿だなぁ。今日はこういう気分なんだよ。気にするな」
棘の入った言い方に、やはり違和感を覚える。
(でも、赤司っちは一人しかいないし…。機嫌でも悪いのかも…)
無理やり自分を納得させ、そろそろと赤司の隣に腰を下ろす。
「で、なんで涼太はここにいるんだ?」
「仕事の撮影場所がここの近くだったんスよ。赤司っちは?」
「僕はただの散歩だよ。やっぱり外は気持ちがいいね」
「散歩のためにここまで?家の周りとかじゃ駄目なんスか?」
「知り合いに会いたくなかったんだよ。家の周りだとばったり会うかもしれないだろ?それに、もう少しでここに住むことになるからちょっと下見にね。ん、引っ越すことはもう言っていたかな?」
「…あ、うん。…昨日、教えてくれたじゃないスか」
「そうだったね」
ニコリと笑うと再び本に目を戻し、ページをパラパラと捲り始める。捲る速さにちゃんと内容が頭に入ってくるのかと疑ってしまうスピードだ。話しかけていいものか迷って、少しの間を置いてからおずおずと疑問に思っていることを聞くことにした。自分で考えたところで何時までもウジウジと解決しないなら、いっそ本人に直接でも聞いた方がいい。
「…昨日、帰ってからよく考えたんだけど、でも納得出来なかったっス。付き合えない理由、引っ越すだけじゃないよね?…まだ何かある気がする」
「…へぇ、お前にしては鋭いね」
「やっぱり、まだ何かあるんスか?」
「ああ。聞きたいのか?」
「…うん」
黄瀬の返事に赤司は本を閉じ、口角を上げて妖艶な笑みを向ける。けれどその赤と黄の瞳は少しも笑ってはいなかった。獲物を仕留めようとするかのような鋭い色を纏っている視線に、ギクリと肩が跳ねる。聞いてはいけない。その今まで見たことのない尖った雰囲気に黄瀬は恐怖の二文字が頭に浮かびあがった。
「お前のこと、好きでもなんでもないからだよ」
「………え…?」
目を見開く黄瀬を横目に、赤司は優雅に立ち上がる。
「寧ろ、僕は涼太が嫌いだ。こうして話をするのも虫唾が走る。それぐらいに大嫌いだ」
見下ろすように、見下すように言い放つ。黄瀬は何も言えなかった。口が動いてくれなかった。
「だから、これからは学校でもどこでも、僕に話しかけないでくれると助かる」
顔こそ笑顔だが、その口から告げられた言葉は何とも酷なものだった。
「…暗くなってきたから、僕はそろそろ帰るよ。涼太もなるべく早く帰るんだぞ。じゃあ、また明日学校で」
黄瀬が何も言えないと知っていてか、赤司は返事を待たずにブラウンのジャケットを翻して公園から出て行ってしまった。その遠ざかっていく後ろ姿を見つめながら、先程の赤司の言葉を頭の中で繰り返しループさせる。
「…………き…ら、い…?」
やっと口から出てきた言葉は、自分でも分かるくらいに震えていた。昨日、一昨日と言ってることが真逆な気がする。俺を好きと言ってくれていたのは幻聴だったのか。それとも、皆の前だったから、俺が惨めな思いをしないように気を使ってあんな嘘をついてくれたのか。
(……分からない…)
三日連続で色々あったせいで、もう頭がパンク寸前だった。元々そこまで考えることが得意じゃない所為もあるが、整理が追いつかない。けれど二つだけ確実なのは、フラれたということと、赤司に嫌われていたということだ。
(…俺、赤司っちに嫌われてたんだ…。…だから……そっか…)
その後、どうやって家に帰ったのかはあまり覚えていない。気付いたら自室のベッドに座っていた。
「…明日から部活なくてよかった…」
帝光は明日から2日間、期末テストの為部活動がない。しかし、個々の練習は自由なので本当は行きたかったし、行くつもりだった。赤司や黒子たち五人も行くと言っていた。
「赤司っちの前で普段通りでいられる自信ないし、また勝手に涙出てきたら嫌だし…」
テスト期間中は部活に行くのは止めよう。早く吹っ切れなければ。
「…暇になった時間、何しようかな…」
*****
「只今帰りました」
返事を返してくれるのは使用人だけだと分かっているが、丁寧な挨拶で玄関の扉を開く。
「おかえり」
「…ただいま。玄関に座って何で本読んでるんだ?僕に何か用?」
予想とは違い、玄関の傍らには自分の部屋から持ってきたのだろう椅子に座って本を読んでいる兄がいた。靴を脱ぎながら言う弟の隣に立ち、兄はいつもの表情のない顔で話し始める。
「携帯を返してくれないか。明日の自主練のことで緑間に伝えたいことがあるんだ」
「ふーん。…はい、携帯」
ポケットに入れていた携帯を取り出して兄に渡す。二人で一つの携帯は、今は兄の物だ。だから弟がこの携帯を持つ日など、今日のように外に出る時しかないので、持っていてもあまり意味はない。携帯を受け取って用事が済んだらしい兄は、さっさと自室に戻ろうと歩き出す。
「今日、面白いことがあったよ」
「そうか」
弟の話に振り返りもせずに答える。興味がないということだろう。
「僕が京都に行ってたのは知ってるよね?そこで涼太と会ったんだ」
「!!」
黄瀬の名前を出した途端、ピタリと足を止め焦りを隠しきれていない表情で振り向く。兄にニコリと微笑むと、早く続きを話せと視線が訴えてきた。
「モデルの仕事で京都に来ていたらしいよ。面白い偶然だろ?」
「…気づかれなかったのか」
「僕たちの違うところは左目の色だけなんだ。気付かれる訳がない。最初は少し不信がっていたみたいだけどね」
「……黄瀬に何もしてないよな?」
「僕が涼太のこと嫌いなのは知ってるよね?」
「…知ってるから聞いたんだ。してないならいい」
兄は小さく息をついてから弟を一睨みし、奥の部屋へと消えて行った。その様子を見ていた弟は片手で口を、もう片手で腹部を押さえ、しゃがみこむ。
「…く…はは…っ」
響かないようなるべく声を噛み殺し、肩を震わせて笑い出す。
「…ははは…ふ…っ…」
こんなに笑ったのはいつ振りだろうか。笑いすぎて涙が出てきて、お腹も痛い。
兄はあんな駄犬のどこがいいのだろうか。いくら恐ろしいくらいに似ているといっても、好きな相手を見分けられないなんて。兄の趣味はさっぱり分からない。
「…はー……。どうなるか、明日から楽しみだ…」
口元に残る笑みはそのままに、弟は消えるように自室へと戻っていった。
‐END‐
4に続く