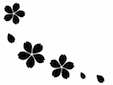始まりの関係
その人の第一印象を大体の人は口を揃えて『近寄りがたい』とか『怖い』など言うけど、俺は全然違っていた。
―――悲哀に満ちている。
何でそう思ったのかは自分でもよく分からない。
ただ、真っ赤な射るような瞳はとても悲しくて、全てを諦めているような、そんな色が見え隠れしているように見えた。
*****
黄瀬が一軍に昇格してスタメン入りしてから早いもので約ニヶ月。
「あーかしっちっ!!」
一際賑やかな声が仲間に加わった日常に皆が慣れてきた中、部活が終わるのと同時に黄瀬は赤司に後ろから抱きついた。その様子にキセキの面々はまたか、という眼差しを向け、2人を置いてさっさと部室に戻っていく。
「こら黄瀬。部活終わりは汗をかいているんだから、抱きつくのは止めろといつも言っているだろう」
「別にいいじゃないスかー。赤司っちに抱きつくの俺好きなんスもん」
困ったように笑う赤司の肩口にぐりぐりと額を押し付けながら口を尖らせ甘える様に言えば、くしゃ、と優しく頭を撫でられた。丁寧に、そして優しく髪を梳くように撫でられ、気持ちよさに目を細める。
「まったく…、困ったやつだな」
赤司に撫でられるのは何よりも好きで、そのために抱きついていると言ってもいいほどだ。一日一回は必ず強請って、撫でてもらっていた。
「ほら、着替えに行くぞ」
「はーい」
最初は悲しそうな瞳の理由が知りたくて赤司に近づいていた黄瀬だったが、いつからか自分をもっと見てほしくて、褒めてほしくて、求めてほしくて傍にいるようになっていた。この感情がなんなのか、もちろん黄瀬自身も分かっている。彼の素顔を知る度に胸が高鳴り、彼の行動一つ一つから目が離せない。赤司を見ている内に、ほんの興味本位の感情がいつの間にか恋愛感情にすり替わっていた。だからと言って別にどうするという訳でもなく、今までと変わらず接しているのは今の関係を壊したくないというエゴからだろう。告白をして断られた時に、友達という今の心地の良い立ち位置まで失うのは辛すぎる。だから例え赤司が誰かと付き合ったとしても応援するし、もしそのことで赤司が相談してきたとしても笑顔で話を聞くと思う。自分の気持ちは一生胸にしまって置こうと思った。
いや、思っていた。
「あの、赤司君…、少しいいかな…?」
制服に着替え、マジバに寄っていこうという話になったスタメンの面々が部室を出ると、見覚えのない女子生徒がほんのりと頬を染めながら近づいてきた。どこかもじもじとしながら、上目遣いで赤司の事を伺っている。
「何かな」
「話があるの…出来たら二人きりで…」
女子生徒の様子からして告白をしようとしてることが一目瞭然だが、当の赤司は分かっているのかいないのか、呼ばれるまま一緒に体育館裏に行ってしまった。そんな赤司の後ろ姿を見送りながら、青峰は大きく欠伸を漏らす。
「ありゃ告白だな」
「え、そうなんですか?」
「黒ちん鈍ーい。どう見ても告白でしょ」
「そんなことはどうでもいいのだよ。赤司を待つのか?」
「もちろん待ちますよ」
「てか、待ってねーと後がこえーしな」
顔を見合せ話し始めた皆の声がどこか遠くに聞こえて、全く頭に入ってこない。体育館の影に消えていった赤司と女子生徒の姿が頭を占領して嫌な汗が流れてくる。
「明日の練習量三倍とかにされそうだよね。ねー、黄瀬ちん」
「………」
「黄瀬ちん?」
「ご、ごめん、教室に忘れ物してきちゃったみたいだから俺取ってくるっス!」
「そうなの?行ってらっしゃーい」
「ここで待ってますね」
胸がざわついて、思わず嘘をついて駆け出した。忘れ物なんかしていない。というより、教科書は置き弁しているし、家で勉強なんてしようという発想が出てくることもないからノートなど忘れてもどうでもよかった。ただ赤司を追いかけるための口実でしかない。
体育館裏に着いて辺りを見回すと、少し先に向かい合うようにして話をしている二人を見つけ、咄嗟に物陰に隠れた。いい感じに離れているために、会話が全然聞こえない。
「…な、何してるんだよ俺。別に、赤司っちがあの子と付き合おうが、関係ないじゃん」
赤司を応援すると決めたのも、好きと伝えないと決めたのも自分なのだ。みんなと一緒に赤司が帰ってくるのを待ってればいい。そう思う反面、断って、首を横に振ってほしいと願っている自分がいた。
「―――っ」
けれど黄瀬のその願いとは違い、赤司は女子生徒に向けて、首を縦に振った。それを見て女子生徒は目尻に大粒の涙を溜めて笑った。
「…そ、んな…」
足に力が入らなくなり、黄瀬はその場に座り込んだ。
―――赤司に恋人が出来た。
その事実が黄瀬の胸を大きく抉る。じわじわと広がる胸の痛みに比例するように、瞳からボロボロと大粒の涙が流れ出る。いくら拭っても溢れて止まらず、その涙が点々と地面に染みを作る。
これは後悔だ。心ではあんなに平気ぶっていても、いざとなると気持ちを伝えておけば良かったという今更な後悔。どこかの誰かが、『本当に大事なことは叶わなくなってから気付く』と言っていたのを思い出した。本当にその通りだ。せめて気持ちを伝えて、赤司の口から『ごめん』と、『無理』と断ってほしかった。そうすれば諦めもついて、心から応援出来ただろう。
けど、もう遅い。
「…ふ…、ひっ…く…」
赤司にはもうこの想いを伝えることは出来なくなってしまった。
「……ほんと、俺…バカすぎ……ぅ…」
「…黄瀬?」
「っ!?」
いきなり声を掛けられ、ビクリと肩を震わせて顔を上げると、赤司が目の前に立っていた。あまりのショックに、赤司が近づいていたことに気が付かなかったようだ。
「…あ、か…」
「なっ、どうしてこんなところで泣いているんだ!?」
黄瀬の顔を見た瞬間、赤司はぎょっと目を見開いてすぐにポケットから皺一つない綺麗なハンカチを取り出した。そのハンカチで涙を拭いてくれようと手をこちらに伸ばす様子がスローモーションの様に目に入ったが、その手が黄瀬の頬に触れる直前に勢いよく立ち上がり、全力疾走でその場を離れた。
「黄瀬!?おい!」
「何でもないっスから!」
「何でもなくないだろう!待つんだ!」
「嫌っス!」
逃げる黄瀬を赤司が追いかけてくるので、さらに足を速める。今はまだ、赤司の顔は見たくなかった。それにこれ以上自分の泣いているところも見せたくない。
しかしその足は何かに思い切りぶつかり、走ってきた勢いを殺せず押し倒す様に倒れこんだ。
「うわあ!?」
「なっ!?」
派手に転んだ割にどこにも痛みはなく、自分の下敷きになっている柔らかい何かにこれは何だろうかと不思議に思う。
「いて、て」
そろそろと目を開けると、すぐ間近に眼鏡のずり落ちた緑間の呆けた顔があった。緑間がクッションになってくれたおかげで怪我をしないで済んだようだ。その緑間の後ろに驚いた顔をした皆もいる。どうやらがむしゃらに走っている内に元の場所に戻ってきてしまったようだ。
「なんなのだよ一体」
「ご、ごめん緑間っちっ!大丈夫?」
「ああ、お互い怪我はないようだな。一体何事なのだよ」
慌てて上から退いて、下敷きにしてしまった緑間の腕を引っ張って2人で立ち上がる。砂だらけになっている緑間の背中を謝りながら叩いていると、その様子を見ていた黒子が少し驚いたように声を上げた。
「…黄瀬君?何で泣いてるんですか?」
「えっ」
「うぉ、マジだ。目ぇ真っ赤だぞお前」
「あ、えっと、これは…」
「黄瀬!!」
追いついたらしい赤司の怒鳴り声に、再度ビクリと肩を震わせる。赤司から逃げていた事をすっかり忘れてしまっていた。反射的にまた逃げようとしたのだが、腕を強く掴まれてしまいそれは阻まれた。
「待てと言っているのが聞こえないのか…っ」
今まで聞いたことがないほど低い赤司の声音に、黄瀬はもちろん、隣にいた黒子たちも背筋を伸ばした。
「…ど、どうしたんですか?赤司君」
「…何があったの?」
「何で黄瀬泣いてんだ?」
「…それは俺も聞きたい。黄瀬、何で泣いてるんだ」
「………」
「黄瀬」
促すような赤司の言葉に、黄瀬は静かに振り返る。
「どうしたんだ」
強く、けれど優しく問われ、先ほど以上に涙が溢れ出る。
何でこの人はこんなに優しいのだろう。
何で俺を心配して追いかけてくれるのだろう。
何で…。
泣き止まない黄瀬にどうしたらいいのか分からずオロオロする黒子たち。だが赤司はふっと優しく微笑み、いつもの様に黄瀬の頭を撫でた。
「!」
「落ち着いたか?」
微笑みながらそう言われ、きゅぅ、と胸が痛む。まるで愛しいものでも見るかのような柔らかな笑みに勘違いしてしまいそうになる。もう全てが遅いのは分かっているけれど、告げてしまいたくなる。
どうせ叶わないのなら。
してもしなくても同じなら。
「…お…俺」
「うん」
「…赤司っち、の、ことが」
伝えて断られた方がずっとマシだ。
「…好き、です。俺と付き合ってください」
「………うん?」
「友情とかじゃなくて、恋愛感情の方っスから」
真っ直ぐ赤司の目を見て言い、分かりきっている答えを待つ。見開いた赤司の瞳はため息が出そうになるほどに綺麗な真紅で、優しく細まったこの瞳に見つめられる事が大好きだった。けれど、それも今日で見れなくなるだろう。
「え、き、黄瀬君…?」
「急に何言ってんだお前!?」
「告白ー?」
黒子たちは口々に驚き、黄瀬を見た。何故か緑間だけは驚きもせず、小さなため息を吐いてメガネのブリッジを上げていた。
「……それは、本気で言っているのか?」
「もちろん本気っスよ。冗談なんかじゃないっス」
静寂が辺りを包み、我慢して止めている涙が流れそうになる。心配そうに黄瀬と赤司の顔を交互に伺っている皆は居心地の悪そうに黙って成り行きを見守っていた。
すぅ…、と赤司の息を吸う音が聞こえ、思わず身構える。
「……俺もだ」
「……え」
「俺も、黄瀬が好きだ」
「…う、うそ…」
全く思ってもみなかった返事に、素直に信じられなかった。これは夢ではないかと。
「嘘なんてついてどうする」
「だ…だって、さっき女の子に告白されてOKしてて…」
「なんだ、見てたのか。それで泣いてたのか?」
こくりと頷くと、また柔らかい笑みを向けられる。その笑顔に胸が微かに高鳴った。
「確かに告白はされたが、好きな相手がいる、と断った。その後、せめて友達になってくれと言われたからそれは了承したんだ」
「…その好きな相手って…」
「黄瀬に決まってるだろ?」
「っ!」
そこまで言われて、やっと赤司の言葉が本当であると思えた。
「赤司っち…」
「……でも、」
黄瀬の頭を撫でていた手が離れていき、優しく微笑んでいた顔が真剣な表情へと変わった。
「付き合うとか、そういうのは無理だ」
「……え…?」
「俺は今のまま、黄瀬とは友達でいたい」
「…は…?」
何を言っているのか、理解できなかった。好きだけど、付き合うのは無理。好きだけど、友達以上にはなれない。お互いに好き合っているのに、恋人同士にはなれない。一体どういうことなのだろう。
黄瀬の頭では黒い靄が渦巻いているだけで、答えは出てこなかった。
「…すまない。それと、用事が出来たから今日は先に帰ることにするよ。また明日」
「は、はい…」
「ばいばーい」
「…おう」
「気を付けて帰るのだよ」
少しずつ小さくなっていく赤司の背中を、誰一人口を開かずに見つめていた。
‐END‐
2に続く