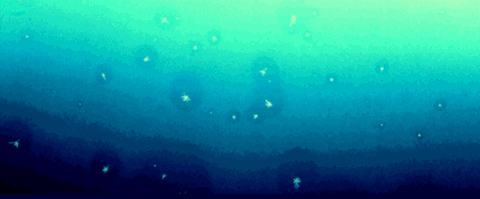ピアス
ある日の午後、アイリスとザックスはザックスの家のテーブルで向かい合わせに座りながら話していた。
特にこれ、といった話はないが、幼馴染だけあって、ウマがあうらしい。少し離れた歳の差から、兄妹にみられることもしばしばあるくらいだ。もちろんそれは、ミッドガルや地方からやってきた商人たちくらいだけれど。
「ねえ、ザックス」
アイリスがザックスに声をかける。今までの世間話とは違う、明らかに意図のある呼びかけだった。
「んー?」
「そのピアス、どこで手に入れた、んだ?」
砕けそうになる言葉を取り繕うアイリスに、ザックスは怪訝そうにする、いつまでも幼く見られたくないと背伸びするアイリスの心中には気付かない。
アイリスが気になっていた、ザックスのピアス。彼がここ何日か前からつけていて、綺麗な色をしているものだ。小さくころんと丸い形が可愛らしい。見たことがない海のように深く、窓から切り取られた空のように淡く、どこか艶めいた蒼いピアスだ。真っ黒な髪をもつザックスによく馴染んでいる。
「どこ……だったかなあ」
「覚えてないの、か?」
「うーん……?」
「…はあ」
アイリスは、呆れたようにため息をついた。
まあ、こういう人だから仕方がないかと諦める。おそらく外へ出かけた時か、商人が来たときに買ったのだろう。彼らは珍しいものをたくさん持ってきてくれる。物々交換でもよしとしてくれるのは、アイリスやザックスたちの村にとってはありがたいことだった。
「アイリス、気になるのか?」
「ん? んー、まあシンプルだし、色も綺麗だから」
アイリスの言葉にザックスは、「ふーん」というと、右耳のピアスをはずした。一体何をするのかとアイリスがじっと見つめていると、
「じゃあ、やるよ」
と、アイリスの手のひらそれを落として、にかっと笑った。
「お揃いって久しぶりだなー」
子供のような笑顔に、アイリスは何だか照れくさくなって顔を背けた。いくら兄妹のようで、実際に兄のように慕っていたとしても、こういった時にザックスは幼なじみだと感じる。
「アイリス、目とか髪とか綺麗だから、よく似合うぜ」
そう言われて、自身の髪を指先でいじる。雪のように真っ白く、軟らかな指通りのそれは、遺伝子の突然変異というやつだ。ひどく目立つし、見知らぬ人には当然奇異の目で見られる。
髪と同様に色素のないダークレッドの瞳も、魔物のようで嫌いだった。
「あー、嫌か。お下がりは」
「そんなこと、!」
その目を隠すために伸ばしていた嫌いな髪も、その目も、ザックスは綺麗だと笑って受け入れてくれた。もうずっと昔のことだ。
「……ありがとう」
「どーいたしまして」
アイリスは、照れくさそうに笑いながらピアスを握りしめ、右耳につけた。まだ、じんわりと熱を持っているそれは、アイリスにどこか安心感を与えてくれる。いつまでも心地よい熱が消えないようにと願った。
今も、アイリスの右耳には蒼いピアスがある。
誰かがそのピアスはなぜ片方だけしかないのかと尋ねれば、いつも「半身だから、かな。アイツと、最後のお揃いなんだ」と言った。
綺麗なピアスだねと誉められれば、照れくさそうに、けれど嬉しそうに笑うのだった。
硬く、冷たい石のピアス。時折思い出したように触れると、それはどこか懐かしい温もりを伝えてくれた。
△Fragmentary Stories TOP