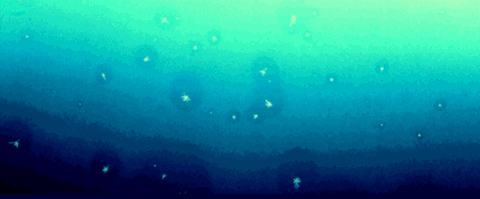花を売る女性
いつか、誰かが言っていた。
「ミッドガルに、空はない」
と―――。
「たしかに、な」
灰色のピザを下から見上げて、クラウドはひとつため息をついた。
神羅カンパニーによって建設されたここ、ミッドガルは便利には便利だが、日光が拝めないためどうにも陰鬱になりがちだ。ここに長年すんでいる人々はそれが顕著で、いつも生気のない顔をしている。かくいう自分も、端から見ればそうなのだろうか……と、クラウドは苦笑した。
こんな世界で満足に生きている人はそうそういないだろう。
クラウド自身、それが嫌で神羅を抜けたのだから。
そしてはた、と思い出す。
いったい、ミッドガルに空がないと言ったのは誰だったかと。ぼんやりと輪郭がぼけて、声もくぐもって聞こえる。知っている。クラウドは、この人間をたしかに知っているけれども、どうしてか思い出せない。考えれば考えるほど、耳鳴りが響く。
「…なんなんだ」
眉を寄せて、手が届きそうで届かない不愉快な感情に、クラウドは思い出すのをやめた。
それよりも、今は大事なことがある。
何でも屋と称して引き受けた仕事で、先ほど八番街の魔洸炉を爆破してきた。反神羅勢力・アバランチに協力したためだ。
クラウド自身は大して何もしてないが、見つかるのは時間の問題で、今はバラバラに逃げて、一度汽車で合流し、アジトへ帰宅ということになっていた。
路線橋を走り抜け、クラウドは眼下を走る列車に飛び降りた。ガン、と背負った大剣が音を立てる。クラウドは顔をしかめると、すぐに中に入れるところを探した。
貨物車両で、荷物の搬入口が空いている車両を発見し、クラウドはそこから身を滑り込ませた。
「……花、みんな見向きもしないな」
「うん。でも、きっと、来てくれる」
「ああ」
誰が、と女性は訊ねなかった。訊ねなくても、知っていたからだ。
せわしなく、顔を伏せて歩きさるミッドガルの人々を見て、白髪の女性は花売りワゴンに目を落とした。
――綺麗なのに。
荒んだ人々の心には届かないのだろうかと肩を落とし、女性はもう一人の茶髪の女性に声をかけた。
「エアリス、今日はもう遅い。帰ろう」
「……うん」
エアリスは悲しそうに目を伏せた。
と、そのとき。
「待てー!」
「!? エアリス、離れてて」
「う、うん」
ワゴンが塞いでいた路地から、一人の青年が出てきた。金髪碧眼で紺のソルジャー服を着て、背中に大きな刀を背負っている。
「ソル、ジャー…?」
女性はクラウドをみてぽつりと呟くと、すぐにクラウドの腕をつかんで引き寄せ、ワゴンの影に隠した。
「何を…っ?!」
「静かに」
そして何事もなかったように振る舞っていると、神羅兵が数名かけよってきた。
「今、誰かここを通らなかったか?」
「あちらへ行った」
「そうか。よし、あっちだ!」
バタバタと、いくつもの足音がせわしなく消えていった。
すっかり足音がきこえなくなると、女性はクラウドを引っ張り出した。
「何やったんだ。その格好、ソルジャーだろう?」
「……色々と訳があってな」
「…そうか」
「すまない。助かった」
クラウドは女性とエアリスに向き直って言った。
「大したことじゃない。神羅は私たちも好きじゃないからな」
「そうか…礼と言っては何だが、その花をくれないか」
クラウドがワゴンに目をやると、エアリスはにっこりと笑って、花を一輪、クラウドに手渡した。
クラウドは小銭をエアリスの手に落とすと、すぐにきびすを返して歩き出した。何やら、悠長にしてはいられないようだ。
「…そうだ、名前」
クラウドは思い出したように足を止め、振り返った。
「あんたたちの名前は?」
「わたしは、エアリス」
「私はアイリスだ」
ぴり、とクラウドの頭に電撃のようなものが流れる。どこかで、聞いたことのある名前だ。しかし思い出せないので、クラウドはそうか、と言い残して闇に走り去っていった。
「クラウド、か…」
「アイリス、知ってるの?」
「…わからない。あいつが言っていたのとは、様子が違う」
「そっか」
アイリスは、プレートが覆う空を見上げて呟いた。
「どこにいるんだ……、ザックス」
△Fragmentary Stories TOP