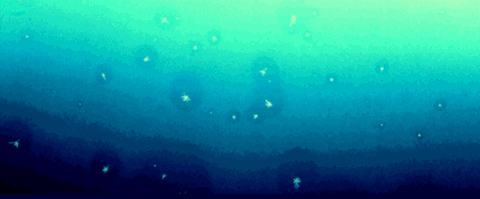木曜日には花束を持って
「………」
「……?」
「……………」
「ふう」
私は、クラウドのバイクを横目に、自分のバイクにもたれかかって溜め息をついた。
ちらりとクラウドの歩いていった方向を見やると、クラウドと、客が話しているのが見える。
けれど会話は聞き取ることができない。
受取人の女性をしばらく見つめていたが、やがて飽きて視線を逸らす。
――あの、大きな戦から2年たった今。クラウドと私は、いまだモンスターが蔓延っていて遠くまで荷物を運べない人たちに代わって、その荷物を届けるという仕事をしている。
これが中々良い商売で、依頼はあちこちからある。依頼人の中には、タークスのレノや、仲間のバレットなどもいる。
いまはその荷物を届け終わったところだ。今回の依頼人は若い女性で、一人暮らしをしている姉に届けてほしいものがある、ということだった。
「アイリス」
考えことをしていたら、クラウドが近寄ってきたのに気がつかなかった。
「ん? ああ、終わったか。次は?」
「ジュノンの方…だな」
「よし」
クラウドは手元のメモを見てからバイクにまたがる。
私も、今しがた寄りかかっていたバイクを立てて、乗り込む。
クラウドのバイク、フェンリルはクラウドの刀が収納でき、頑丈でスピードもある優れものだ。私のバイクは、多くの荷物がつめるスペースがあり、深く背もたれることができる座席がついている。
ちなみに、フェンリルには二人乗ることができるが、私のは一人乗りだ。
バイクに乗ったクラウドがこちらを見る。
「アイリス、顔色が悪い。先に戻っているか?」
「? いや、あと少しだろ、大丈夫だよ」
「…そうか」
そしてエンジンをかけて走り出す。
風が髪をさらっていき、とても気持ちがいい。しかし、ときたまモンスターが姿を現し襲い掛かってくる。
私たちは荷物に傷がつかないように気をつけながら、手早く片付ける。
そしてまた、走り出す。
風を感じたくてやたらとスピードを出すときもあるし、逆にゆっくりなときもある。
クラウドには、いつもそれで小言を言われる。
「またのご利用を」
私がそういうと、受け取った人は小さく頭を下げて扉を閉めた。
これで、今日の仕事は終わりだった。
空はうっすらと赤みがかかっていた。今日は比較的少なかったが、遠くまで荷物を運びに来るので、移動に時間がかかりいつもミッドガルに帰るころには空が暗くなっている。
「よし。アイリス、帰ろう」
「ああ」
クラウドが私に声をかけてバイクに乗る。
私も乗り込んだが、ちょうどその時、クラウドの携帯電話が鳴った。
クラウドは怪訝な顔をして、一度バイクを降りると少し離れて電話を取った。
よく聞き取れないが、おそらく仕事ではないだろうか。一段落しても、頃合を見計らったように仕事が入る場合も稀ではない。
案の定、クラウドは電話を切ってこちらへ戻ってくると、
「すまない、アイリス。先に戻っていてくれ」
と言われた。
本当は一緒にいってもいいのだが、いかんせん、ミッドガルまでは距離があるから、暗くなる前に先に帰れということなのだ。
拒むと、しばらくクラウドの小言をきくことになるから、大人しくしたがって、ティファとマリンに知られるが吉だろう。
私は頷くと、クラウドの後姿を見送ってから、反対側へ走り出した。
カラン
店のドアを押したのは、時刻も6時にかかる頃だった。ミッドガルの空は薄暗く、クラウドが帰ってくるころには真っ暗になっているだろうと思った。
「おかえり、アイリス。クラウドは?」
「ん。クラウドは、まだ仕事」
「そっか」
出迎えてくれたのはティファだった。カウンターでグラスを拭きながら、私の言葉に頷いた。
彼女はいつも忙しそうに働いている。手伝う、といっても昼間はあまり店にいないので、マリンやデンゼルの世話くらいしかできない。
私はジャケットを脱いで手に持ち、ゴーグルを頭から首元まで引き下げて2階へと上がる。
キィ
とドアをきしませ、部屋へ入る。
部屋の中は薄暗く、窓からミッドガルの灯が少しだけ入ってきていた。
そしてそのまま、その場に座り込み膝を抱えて丸くなる。ジャケットとゴーグルはベッドに放り投げた。
「はぁ……」
こてん、と頭を傾ける。
最近、クラウドは帰りが遅い。今日みたいに電話がかかってくることもあれば、用事があるといって私を先に帰らせることもある。
尾行してもいいのだが、どうせすぐに気づかれるし、そうする必要性が見当たらないからだ。
私は最近、クラウドがお客などと話しているときに垣間見る笑顔を、他人に見せたくないと思ってしまう。
嫌だ、と思うときもある。
そう思っていることに気づくと、すぐに頭を振る。
こんなことを思っているなんて知られたくはないし、そんなことを考えている自分が嫌だったからだ。
けれど客の中にはもちろんそういう意識を持っている人たちも居る。
そういう人たちはみな、クラウドの前には笑顔を見せるが、私は嫌悪の対象でしかない。
だからそういう客は基本的にクラウドに任せている。
だけどやっぱり、知らぬ人に笑顔を見せないでほしいと願うのは我が侭なのだろう。
仕事なのだから、といつも割り切ってきた。
毎日、そんな思いに耐えながら生きてきた。
だけど今日でクラウドと帰らないのは1ヶ月を越える。いつも一緒にいたい、とかいつも一緒に帰りたい、とは思わないけれど。
実際、私はクラウドといる時間が長いのだから。
だけどクラウドは私に今までどおりに接してくる。
もはや、限界だった。
一度そう思ってしまうと、後はどんどん止まらなくなった。
やっぱり、一分一秒でも側にいたい。子供みたいだし、情けない。そう思うと、私はやっぱりクラウドが好きなんだと思う。
泪が頬を伝って流れる。
顔を伏せて、服の袖で拭うけれど、泪はどんどん流れ出てくる。
コンコン
「アイリス?」
ドアをノックする音がして、次に控えめなティファの声が聞こえた。
「ティファ……?」
流石にバレただろうか。
普段あまり部屋を訪ねに来ることはないのだが……とにかく、不自然にならないように対応しなければと思い、嗚咽が漏れないように声を殺す。
「…アイリス、どうかした? クラウドとなにかあった?」
「………」
「ねえ」
「………なんでわかっちゃうんだろうな」
しばらくは黙していたが、ティファが立ち去る気配を見せないので、重い口を開く。
ティファはぽつりぽつりと話す私の声に静かに耳を傾けていた。
「私はっ…、そんな風に思ってしまう自分が嫌いなんだ…っ」
背中越しに、ティファが扉にもたれたのがわかった。
もう、自分でも何を思っているのかわからなくなっていた。
「……アイリス。クラウドに、話してみたら?」
「っ!?」
「アイリスは嫌かもしれないけど、クラウドだって、後からそれを知ったらどうして俺に話さなかったって言うと思う」
「………」
「…下、戻るね」
そう言って、ティファは下へ降りていった。
私はひどく赤面してからベッドに突っ伏した。泪は止まっていた。跡は、あったけれど。
「ん……」
どうやらあれから眠ってしまったようで、窓の外にはすっかり月が浮かんでいた。
一度眠ってすっきりした。頭も冷めた。
明日の朝、ティファに謝って、クラウドと話して、花束を持ってエアリスのところへ行こう。
そして布団にもぐりこんで眠ろうとしたとき、ノックの音がした。
「ティファ…?」
がちゃりとノブをひねってあけると、クラウドが立っていた。
吃驚して身を引くと、ノブを握っていた腕をぐいと引っ張られて、気がつけばすっぽりとクラウドに抱きしめられていた。
「クラウド……?」
「…ティファから、聞いた」
「!」
何を、と問う必要はなかった。
「すまない。気づいてやれなくて」
「…クラウドの、せいじゃない」
「それでも、アイリスに嫌な思いをさせた」
「…もう、いいんだ。さっぱり忘れることにしたんだ」
「?」
クラウドが不思議な顔になる。
「その話は、もういいんだ」
もう一度、今度はまっすぐにクラウドの顔を見据えて言う。
「…そうか」
「ああ。…クラウド、明日、花束を持ってエアリスのところへ行かないか?」
「! い、いや…木曜日じゃ駄目か?」
「いや、かまわないけど…」
「それじゃあ、木曜日に、花束を持って」
「でも、なぜ木曜日なんだ?」
「…木曜日になれば、分かる」
意味ありげに言葉を残してクラウドは、「おやすみ」といって自室へ戻った。
木曜日の朝。
その日に限って仕事は入っていなかった。
珍しいこともあるものだ。
ともあれ、私たちはエアリスの好きな花束を持って、バイクに乗り込んだ。
目指すのは、忘らるる都。
忘らるる都につき、バイクを降りる。
花束を持って中へ入っていく。
下へ降りると、そこにはぎっしりと蓮の花を浮かべたあの池があった。
「これ…!」
「アイリス、忘れていただろうが、今日はアイリスの誕生日だ」
「え? そうだったのか」
クラウドはやや呆れ顔で、もっていた花束を池の中へ投げ込む。
私も同じようにする。
「おはよう、エアリス。今日は私の誕生日だったらしい」
「過去形じゃなくて、誕生日、だ」
「はは、どっちでも同じさ」
自分が可笑しくて笑っているのか嬉しくて笑っているのか。
蓮の花は、1ヶ月前に私が好きだとクラウドに伝えたものだった。
△Fragmentary Stories TOP