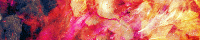
(少し先の未来であり、ifの世界です)
夜の7時を過ぎた頃。いつもであれば辺りは暗く、それはガキの頃にはむしろビビって通れなかったくらい。
しかし今日は違った。8月19日。今日は俺の家の近くの神社で、祭りが開かれるのだ。
「ブン太は何食べる?フランクフルト?」
「うん」
俺が祭りで一番最初に食べるもの。それはフランクフルトだった。何故ならフランクフルトなら歩きながら食べれる。食べながら、他の食べ物も買って回れるから。
「手前の方にあるといいねえ」
俺の手を引いて階段を上がっていく幼馴染が着ているのは、濃紺に赤の金魚が泳いでいる柄の浴衣。今年の夏前に俺と一緒に選んだものだ。既に見るのは三回目になる。
「ま、無かったらビッグ焼き鳥でもいいけど」
階段の上に少し古ぼけた鳥居が見えてきた。家から近いという理由で、俺達はいつも正式な入り口では無い裏の入り口から中に入っていた。
ふと、父親の顔が浮かぶ。『ブン太、いいか?』。確かあれは、六歳の時だったか。『祭りの日の十九時十九分十九秒に鳥居を潜るんじゃないぞ』。あれ、今って何時だった?えーっと、確か……。
「あ、フランクフルトありそう!ブン太ラッキー!」
振り返って前方を指差すひなこが、鳥居を潜りながらこちらへと振り返る。
「お、マジ?」
ラッキー。そんな彼女を見ながら言おうとしたその言葉が、俺の口から出る事は無かった。
振り返って俺の事を見ていたはずのひなこが、突然、目の前から消えた。
それはあまりにいきなりの出来事で、俺は思わず息を呑む。そして次の瞬間、俺は信じられない物を目にした。
「え?」
……誰だ、この子。
たった数秒前まで俺の右手を引いていたひなこの場所にいるのは、ひなこでは無かったのだ。背は濃紺の浴衣を着ていたはずの彼女とは違い、大体俺の腰くらい。今まで繋いでいたはずの手は何故だかとても小さく柔らかくなっている。
しかし何処か見覚えのある黄色い浴衣を身に付けた少女は、勢い良く振り返った。
「……えっ?」
まさに時が止まった様に俺の顔を見て固まる少女の顔を、俺は知っている。
ばっと手を引いて俺を見上げる彼女は、怯えた目をしていた。なんだ。どうなってんだよ。全然意味が分かんねえ。でもたぶん、いや、この子は絶対……。
「ひなこ?」
俺は恐る恐る、幼馴染の彼女の名前を呼んだ。目を丸くして俺の事を見上げていた少女は、ビクリと肩を揺らす。そして俺の顔と髪を見て。
「ぶ、ぶんた……?」
少し離れた祭りの喧騒に掻き消されそうなその声は、俺の耳までしっかり届いた。
「そう、ブン太!」
しゃがんで、彼女の両手を自分の両手で包む。流石にしゃがんだら俺の方が小さい。見上げて、もう一度名前を呼ぶ。
「本当にブン太なんだ…」
信じられないとでも言うような表情で俺の名前を呟き、俺の手の中から右手を取り出した彼女は、ペタリと俺の頬に手を当てた。
「うん、そう。ちょっとでかいけど、お前がよーく知ってる、丸井ブン太」
頬に当てられている小さな手に自分の手を重ねる。俺の言葉を聞いて嬉しそうにふにゃりと笑った彼女の笑顔は、ついさっきまで見ていた笑顔と全く同じで。
……ああ、本当にアイツなんだ。そう思ったら急に愛おしさが込み上げて、小さな身体をギュッと抱き締めた。
「……っと、そうじゃなくて」
身体を離して周りを見渡す。景色は何一つ変わってない。携帯を見ると映し出された時間は七時二十三分。……待てよ?さっきこの鳥居を潜ったのって。
* * *
「焼きそばおいしい!」
「屋台の焼きそばって美味いよな」
「うん!」
とりあえず腹が減った俺達は、祭りを見て回るよりも先に焼きそばと焼き鳥を買った。どうやら彼女もまだ食べていなかったらしい。そして今は境内の石段に腰掛け、二人で焼きそばを食べている。彼女が紅しょうがは要らないと言うから、今日の俺の焼きそばの紅しょうがは大盛りだ。
あの後、まさかとは思ったけど鳥居の傍に見た時のないじいさんが立っていた。声を掛けられて話をしたら、驚く事にこの神社の鳥居の事について教えてくれた。
色々と生まれや理由やらはあるらしい。でもとりあえずは、二十時二十分。この時間にもう一度鳥居を通れば、元に戻れるとの事だった。ちなみにそのじいさんは、瞬きをした瞬間に消えていた。
「ねーね、ブン太」
「ん?」
「はたちのブン太にはかのじょいる?」
「ぶっ」
予想外の質問に、思わず焼きそばが鼻から吹き出そうになった。
「だ、だいじょうぶ!?」
そう言ってトントンと俺の背中を叩く小さな手。俺は横に置いていたお茶を掴んで、一気に焼きそばと一緒に流し込む。
「あーサンキュ、もう大丈夫」
「うん」
俺の言葉に頷いて、彼女は再び焼きそばを口にする。
「それで、かのじょいるの?」
「……」
もぐもぐと口を動かしながら首を傾げる彼女。
「いると思う?」
「……わかんない」
「わかんないって何だよ」
「じゃあ、いそう」
「じゃあかよ……」
あーあ。コイツ、マジでこの時は俺の事は眼中にねえんだな。
焼きそばを頬張り続ける彼女を見て、当時の自分へ思いを馳せる。小三だろ?……いやいや俺、百パーセントお前の事好きだったんだけど。
「いるかもな」
「え、かもなの?」
「うん」
「じゃあ、フタマタかけてるの?」
「ちげーよ!」
「だって付き合ってるかも、なんでしょ」
「……はぁ。何処でそんな言葉覚えんだ」
俺はそう呟いて、焼きそばの最後の一口を口に入れる。
今現在、鳥居のせいで十一年前に行ってしまった彼女と俺は付き合っている。小さい頃からの俺の思いは高校二年の夏に漸く届き、そして今も変わらずに続いていた。
でも、今の関係を、この時の彼女に伝えようとは思わなかった。何がとかじゃない、何となく。でも、伝えちゃいけない気がした。
「つーか焼きそば食い終わるじゃん。かき氷は?」
「あ、食べたい!」
「じゃあそれ食い終わったら二回戦目行こうな」
「うん!」
それから焼きそばの空を捨てた俺達は、かき氷を求めて人混みの中へと入った。
「ブン太は今日、かき氷何味食べるの?」
いつもよりも随分と小さな手。いつもよりも少し高い声。でも、俺を見上げるこの顔は全く変わらない。
「俺?いちごミルク」
「え!じゃあ私と同じだ!」
「……ああ」
彼女の言葉に、蘇ってくる記憶。
小さい頃、いつも最後に食べていたかき氷。俺は余裕で一個食べれるけど、彼女はどうしても一個を食べ切る事が出来なくて。それでもかき氷を食べたいという彼女からいちごミルク味のかき氷は貰えるから、俺はいつも他の味にしていた事を思い出した。
「いや、やっぱメロンにするわ」
「メロン?」
「うん」
「でもメロンもおいしいよねぇ」
「一口ちょうだいね!」。そう言って笑顔になる彼女の頭を撫でる。……ちっせーなぁ。彼女の頭も、俺の手一つで覆われてしまうくらいに小さくて。
この子は、アイツであってアイツではない。
この子と居れば居る程、アイツに会いたくなるからだ。
力いっぱい抱き締めたい。息付く暇もないくらいにキスをしたい。大好きだって、今すぐに伝えたい。
でも、今目の前にいる彼女に出来る事は、一つも無かった。そんな事が許されるのは、一緒に選んだ金魚柄の浴衣を着た彼女だけだ。
ああ、早く会いてえ。
* * *
かき氷を買い、やはり途中で食べられなくなった彼女の分も俺はペロリと平らげた。「ブン太って、はたちになってもブン太なんだねぇ」。瞬く間に無くなっていくかき氷を見ながら、彼女は嬉しそうに笑った。
「そうだよ、当たり前だろい」
「……わたしもわたしのまま?」
「はっ、そうそう。そのまんまでっかくなってる」
「えー!」
そう叫ぶと、一気に頬を膨らませる。
「わたしのままなわけないでしょ!」
「びっくりするかもしんねーけどマジでそのまんまだから」
「う、うそだ!」
「本当、見せてやりたいくらい」
俺の言葉に、目に見えてガックリと項垂れてしまった。
「どんだけ落ち込んでんだよ。何、変わってないと嫌なの?」
「……いやじゃないけど」
「けど?」
「だって周りのお姉ちゃんたちはみんな『綺麗になったねぇ』って言ってもらってるもん」
「わたしもきれいになったねって言われたいのにな」。しょんぼりと小さくなってしまった彼女の声は、暗闇に消えていく。
「……そういう事なら、大丈夫だ」
そう言って、さっきまで一緒にいたアイツを思い出す。笑った顔、マジで変わんねえななんて思って、でも今笑っていい所じゃないのはわかってるから。
彼女の頭に手を乗せて、顔を覗き込む。俺が視界に入ったのか、俯いていた顔を少し上げた彼女と目が合った。
ドクン。その瞬間、俺の心臓が大きく脈を打った。
掛けようとしていた言葉は、どこかへ消え去った。違うとか駄目だとか、そんな事を考える間も無かった。そのまま無意識に、俺は彼女の唇に吸い寄せられるように顔を近づける。
ブー、ブー。その時突然、ポケットに入れていた携帯が震えた。その振動に、俺は触れる寸前で我に返る。何が起きたのか理解出来ないのか、キョトンとして俺を見ている彼女。その目から逃れる様に俺は離れた。
ポケットから取り出した携帯を見ると、二十時二十分まで、残り五分を知らせるアラームだった。
食べ終わった空やペットボトルを捨てて、鳥居に向かう。歩きながらふと、ギュッと少し強く手を握ってみた。チラリと見るけど、彼女は気付いていないのか前を向いたままだ。……ま、気付かねえよなぁ。
それなら、と今度は指を絡めてみる。流石にそれに気づいたらしく、不思議そうに俺を見上げてきた。俺と目が合った彼女は、すぐに笑顔になる。そして今度は、ギュッと手を握り返してきた。
「……」
直後、一気に自分の心の中で、一つの感情が大きく膨らんだのがわかった。見た目がどうとかそんなのは、どうやら俺には関係無いらしい。
この子はアイツであって、アイツじゃない。
でもこの子は、小三の俺が好きだったアイツだ。
そんな当たり前の事を思って、思わず笑いそうになる。さっき散々この子に二十歳になっても変わってないって言ったけど、俺だって全然変わってねえじゃん。
何歳になっても俺は、コイツの事が好きなままだ。
ゴミ捨て場からはすぐに鳥居の前に着いた。時計の表示は、二十時十七分。
「まだ?」
「ん、あと三分くらい」
「そっか」
そう呟いた彼女が、俺の顔をじっと見つめてきた。
「どうした?」
「……ううん。メロンミルク、おいしかったね」
「だろい?ま、練乳は間違いねーからな」
「うん!来年はメロンミルクにしてみようかな」
えへへと笑いを零す彼女だけど、どうやらこの記憶は一日寝れば消えてしまうらしい。道理で俺の中でこの日の記憶が無い訳だ。
だからきっと彼女は、来年もいちごミルクを食べるだろう。
「そうだな。それでガキの俺にも教えてやってくれ」
「……うん!」
時計を確認する。後、二分。
「ねー、ブン太」
「ん?」
「あのね、ブン太は優しいからね、絶対かわいいかのじょが出来ると思うよ!」
「……」
「だから、フタマタはだめだよ」
そう言って少しだけ目尻を下げた彼女を、俺は、力いっぱい抱き締めた。
「ばーか、俺が二股なんかする訳ねえだろ」
身体を離し、初めて会った時の様にしゃがんで手を取って彼女と向かい合う。
「お前は本当に鈍過ぎるから全っ然気づかないけどな、俺は昔から、お前に心底惚れてる。もうすぐ会えるブン太も、それはおんなじだ」
何も言わないでいる彼女が、俺の言葉を聞いて目を見開いた。
「さっきはお前に聞かれてそのまま大きくなったって言ったけど、そのまま大きくなったお前の事が、俺はずっと好きで……」
好きと想いを言葉にすると、思ったよりも俺の中で反動が強い。グッと奥歯を噛み締めて、溢れそうになる思いに耐える。
「だから、変わる必要なんかないからな。安心して、そのまま大きくなれ」
好きだ。俺が何歳になっても、お前が何歳なっても、俺はお前の事が大好きだ。
手を伸ばして頭を撫でると、彼女は弾けたように一気に顔が赤く染った。
「なんだよ、照れてんのか」
「……わ、わかんない」
困ったように眉を八の字にする彼女が可愛くて、思わず頬が緩む。
ブー、ブー。手の中の携帯が震えた。確認したら、既に二十分になっていた。
「よし、それじゃあ九歳の俺と仲良くしろよ」
立ち上がり、手を離して彼女の背中を押す。
「ブン太、ありがとう!」
振り返った笑顔が、まるで吸い込まれる様にして消えていく。
そして、あたかも今鳥居を歩いて潜ったのだと思わせる様な浴衣姿が、現れた。
振り返った状態で固まったまま、俺を見つめる彼女。そんな彼女の腕を掴んで引き寄せて、俺は自分の腕の中に閉じ込める。
「良かった、ちゃんと帰ってきて」
心臓が激しく脈を打つ。俺の腕の中、ゆっくりと顔を上げた彼女が顔を綻ばせた。
「ただいま」、そう最後まで言いきるのを待たずして口付ける。
たったの一時間。一時間しか離れていなかったはずなのに、こんなにも焦がれるものかと思う程に愛おしくて仕方ない。
「顔、ちゃんと見せて」
口を離して彼女の頬に手を当てる。……ああ、やっと戻った。安心して、そのままもう一度唇に触れるだけのキスをする。
「私って、すぐわかった?」
「当たり前だろい」
「本当に?じゃあどう、九歳と比べて変わった?」
「うーん……」
変わってない、訳じゃない。
「変わってない」
そう言って今度は、彼女の瞼にキスを落とす。
「ええ、そんな訳無いでしょ!」
いやだから、その反応がもう同じだわ。
「本当」
「嘘!」
「お前が変わんないお陰で、自分がロリコンなんじゃねえかって結構マジでビビったもん」
「……」
俺がそう言うと、彼女は目を大きく見開いた。
「あー待て待て。俺の名誉の為に言うけど、断じて手は出してない」
「……」
「……いや、正直未遂まで行ったけど」
「ちょ!」
「仕方ねーだろ!」
「仕方ないの!?」
はぁ。本気でビックリされて、大きくため息をつく。
「昔っからずっと好きだったって、何回も言ってんだろい」
一瞬彼女は驚いたような表情をしたけど、すぐに嬉しそうに目を細めた。そして、「だからきっと、向こうのブン太もあんなに優しかったんだね」。そう呟いて、声を漏らして笑う。
「俺、そんな優しかった?」
「うん!だってね、今よりも綺麗になったって言ってくれたの!」
「……は」
「もう凄いキュンキュンしちゃったもん」
いつ言われた事かわからないけど、思い出して心底嬉しそうにする彼女に、俺は初めて手を離してデコピンをお見舞した。
「いたっ」
「お前はガキに口説かれてんじゃねーよ」
「や、ガキだけどブン太だから別にいいでしょ?」
「……」
なんかモヤモヤする。俺だけど、確かに俺なんだけど、でも今のコイツと付き合ってるのは俺な訳で。
「……ダメだ」
「えっ」
「いい訳ねえだろ、お前は俺のだ」
あの子はコイツで、コイツはあの子。同じようで、だけど全く同じじゃない。
でも、同じじゃないけど、俺の心を掴んで離さねえのはいつまでもお前だけ。それはこれからも、ずっとだ。
これは夏のある日に起きた、たった一時間の夢のような出来事。