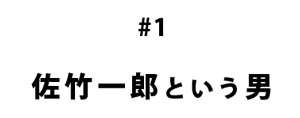
園内の広さは、想像を遥かに超えていた。人の賑やかさも手伝い、乗り物の待ち時間の辛さもあってなのか、一郎の疲労感に拍車をかけた。どこへ向かっても人はじりじりとしか進まず、やっとの思いでその群れを抜けても窮屈さはあまり変わらなかった。
泉水は他愛なく喜んでいるようだったが、櫻子は相変わらず楽しんでいるのかそうでないのか、一見するとよく分からない。何気なく時刻を見れば、もう昼の十二時を回っていた。どうりで腹も減って、力も出ないわけである。
「時間も時間だし、そろそろ飯にしないか?」
「何言ってるのよ。今こそみんなご飯に出ているんだから、乗り物に回るチャンスじゃない」
一郎の提案はあっさり郁美によって却下され、それもそうかと思いつつ見渡せばやはり人がひしめき合っていて、ここまで来るともはやそんな問題ではない気がしてならない。汽車型のアトラクションまでは何とか粘ったが、次にティーカップに並ぼうとした際に一郎は休ませてくれと申し出ていた。ほとんどその場から逃れるようにして、郁美に二人を任せてしまうのであった。
おろおろと老人のように歩き、それからベンチに腰かけるその姿はさぞかし哀愁たっぷりだったに違いない。
一郎はなけなしの小遣いから買ったフライドチキンを齧りながら、行列に並ぶ家族らの姿を少し離れた場所から見つめていた。見れば自分とそう変わらない年頃ではないだろうか――四十代にさしかかるかそうでないかくらいの、日に焼けた肌をした男性が、息子と思しき少年を肩に乗せている。軽々と、大した事がないような様子だ。あんな事を自分がすれば、たちまち一年分の肩こりがずっしりと襲い掛かってくるに違いない。
何気なく自分の腹に目を落とすと、中学・高校とサッカー部で鍛え上げていた筈の身体に贅肉がこびりついているのに気が付いた。日頃の運動不足と、暴飲暴食による報いだった。自業自得でしかないのだが、恨みがましくそんな自分のだらしなくなった身体と、目の前ではしゃぐ男性をつい見比べてしまう。
「それ、いくらしました?」
一瞬、自分に話しかけられているのかどうかと、一郎は考え込んだ。ゆっくりと視線を横へと流すと、一人の青年がこちらへ向かって足を進めている。一歩、また一歩――と、青年は隣のベンチに極々自然の流れで腰かけた――年齢は――、二十代後半くらい……だろうか。
何といえばいいのか独特な雰囲気を持った青年だった。半袖のカッターシャツにネクタイ、サスペンダーという装いをしていたが、良く言えば英国紳士風で、意地悪に言えば西洋かぶれといった具合だった。けれど、それも計算ずくなのだろう。着る人が着れば完全にダサくなってしまいかねないファッションも、彼が身に着けると垢抜けて見えた。一目見た瞬間に『怪しい』と思い、次に見た瞬間には『かっこいい』と思ってしまっていた。
青年が軽やかに笑いつつこちらを一瞥したので、それで改めて「自分が話しかけられていた」という事を思い出したのだった。青年の視線が、一郎が片手に持っていたほとんど齧りつくされたチキンに向けられているのを知り、一郎は慌てて口元を拭った。
「……五百円。コンビニで買えば、この半額で済むのになあ」
消費税は省いておいた。ハハハ、と間を埋めるように笑って一郎は背筋を伸ばした。青年は、こちらに合わせるように薄めの唇を僅かに持ち上げて微笑む。
「なるほど。こっちにまでガーリックのいい匂いがしまして」
それは一瞬、遠回しに警告されたのかと思い一郎は肉身のなくなった骨を少し慌てた様子で下げた。が、青年の表情にそんな気配はなく、心の底から本当にそう思ったから口に出しただけのようだった。
大人らしく利口な喋り方で、決して他者を舐めてかかったり威圧するようなものではない。――多分。只、彼の目的は読めないままなのは変わらない。
「……いやー、どこも混雑していて困りますよ。これ一本買うのに恐らく十分はかかった」
気付くとこちらからどうでもいい事を話し始め、それも内容が愚痴という始末で、それでも青年は気を悪くするでもなく一笑を浮かべて応じたのだった。
「さっきまでこの暑さにやられて食欲もなかったんです。それで何食べようかちょっと悩んでて」
とりとめのない会話を漏らす青年の、この上なく自然体な立ち振る舞いは却って不気味な程だった。細かく年齢にしてみれば、二十半ばくらい……二十五、六歳程だろうか。もう少し若くても頷けるし、逆に上だと言われても納得ができた。不思議だったのは、その年頃の青年が、何故こんな場所に一人でいるのかという点だ。もしかしたら自分と同じように、家族――或いは恋人や友人がいて、離れているだけなのかもしれない。
「連れもいないんで楽なんですけどね、合わせる必要がないですから」
彼はまるで一郎の心を読んだように、その今しがた感じた疑問を何の自意識も感じさせずにさらりと口にした。次の疑問はすぐさまやってきた。じゃあ、一人で遊びに来たとでも言うのだろうか? 遊園地に?
……いや。
今時は、さほど珍しくもない話なのだろうか。適齢期くらいの男が一人でどこへでも出歩くというのは。考え直しておいて、一郎は間を持たせる為(無意識のうちではあるが)ベンチに座り直した。
「いやあ、年寄りには向きませんな。こんな場所は。……忙しなくてどうも合わない」
自虐を込めて思わずミゾオチの辺りに溜まっていた澱のようなものを吐き出せば、青年はやはり屈託なく笑うばかりであった。嫌味なものは、一切感じさせない。それから青年はゆったりとした口調と共に、行列を差した。その列の中には、家族も待機している。
「――あれは、お子さんですか?」
青年の問いかけに、一郎は視線を持ち上げた――「あの、セーラー襟のワンピースをした髪の長い子と、オーバーオールの少年」。見るのも億劫だった行列はいつの間にやらそれなりに進んでいて、郁美と櫻子と泉水の三人は、あともう少しかというところにまで来ているようだった。
「ええ、その通りです。……何故分かったのですか?」
「いえ、大した理由なんて別にないんですけど。そのスマホカバー、あの女性が持ってるのと対になってるデザインだったので。女性との年齢的にもそうかな、って勝手に推測しただけなんです。……て、何か失礼ですね。すみません、勝手にごちゃごちゃと」
この距離でそれが確認できた事に驚きつつ、「目がいいんですね」なんて素直に答えるべきなのか迷い、やめておく。言葉にすると嘘くさくなりそうに感じられて、一郎は感嘆したような声を漏らすだけに留めておいた。
それから、横手に置いたままにしていたスマホカバーに改めて目を落とす。ちょうど二年前に購入したものだった。数少ない記憶を掘り起こす。いや、なんて事はない、子どもに人気のキャラクターをあしらったケースだった。一郎の方は、緑色をした出っ歯の恐竜で、郁美は赤色の雪男。子どもにせがまれて(主に言うのは泉水なのだが)、揃いで買ったものだ。
その時の記憶を思い起こしながら、一郎はあの時はまだ家族みんなが仲良くしていたな……と、感慨深くなった。櫻子だってもっと笑っていたような気がするし、今となっては考えられない。出来るなら、あるべき家族の姿に戻りたかった。子の誕生に素直に喜び、慈しみあっていたあの頃のように。
淡い思い出に浸りつつ、一郎はふっとため息を吐き出した。
「遊びたい盛りなんですかね。今日もこんな暑い中遊園地なんかやめて、涼しい場所に行かないかって提案したんですけど、全く受け入れてもらえなくて。只でさえこの人口密度ですからね、嫌になりますよ、ほんと」
またもや愚痴っぽくなってしまうが、青年の醸す雰囲気に乗せられたように一郎はつい口を滑らせてしまう。
「実は今日も、ここに来た時すぐに案内図の事で家内と口論になりましてね。俺なんかアナログ人間だから、昔のガイドブックを持ってきたまではいいんですけどそれが何と数年前のものでして。見れば所々改装中だという話じゃない……で、まぁ、そんなものはアテになんないでしょって」
溜めていた不安を吐き出すように話せば、青年は嫌な顔一つせずにそれも黙って聞いているようだった。全く黙ってというわけではなく、時折相槌のようなものを打った。その間、彼はとても穏やかな目をしている。
「いやぁ、まあ、俺がその辺はしっかりとしとくべきだったんですよ……でもね、俺にも言い分はあったんです、そのう……日頃から妻にもちゃんと色々とやってほしいというか、えぇと……どうなんだろう?」
「ここは広さを売りにした遊園地ですからね、一年ごとにどんどん巨大化していくんですよ。創立してから約二十年もの間、絶えず建設工事が続けられているんです」
自身の生活への不平不満に話が逸れそうになり、軌道修正を図ろうと言い淀む。青年はそれも汲んだのか朗らかに微笑みつつ話しただけだった。一郎が肩を竦めつつ、背もたれにその背を預けながら青年を見つめ返す。
「成程。どうしてそんなややこしい事をするんでしょうね、却って客足が遠のきそうだ。みんなどうしてそんなにあっさり受け入れられるんでしょうか」
それはこの遊園地だけではなく、全ての事象において言える事柄なのかもしれないけど。青年はしばし考え込むように、口元に指を添え、どこか遠い目をさせた。心ここにあらずといった表情に見えたけれど、青年はまた口を開いた。
「決まったルートさえ守っていれば、外れる事はないのです。ただ……そうですね、これはもしかすると全世界において言える話ではありますが――社会心理学でいうところの“制度的行動”。ここから外れた行動を取ったが最後、広い土地は入り組んだ迷宮そのものとなりえるのです」
青年の口から語られた言葉は、どこか道筋をなさないもののように聞こえた。適当というわけではない。彼自身が答えを見つけようと、あれこれ模索しているような口調だった。
「……しかし広すぎるのも考え物というか――でかければいいというものでもないだろうに」
対する自分の返答が、少々薄味すぎるような気がした。しかし青年は馬鹿にしたりはせずに、それも真剣に考え込んで、ややあってから膝を組み換えた。言った。
「これは飽くまで俺の考えなんですが……、まあ、仕組みはアリ地獄のようなものですよ。えぇと……、あ、ここの話に絞るんですけどね。この遊園地、色んな企業とタイアップして、たくさんブランド店が入ってきているでしょう? 少々広くして店を並べても、工事費はそう変わりませんからね――競い合って有名店同士があちこちこの遊園地で繋がれば、そりゃあ規模も大きくなりますよ」
今度は、何となく分かった。彼の言わんとする意味が。
「じゃあ、つまり……出入り口が分かりにくくなっているのも、えぇと、その……わざとという事かな」
「っていうのが、まぁ俺の仮説みたいなものです。この箱の中でいかにお金を落とさせるか――簡単にみんなが帰ってしまうようでは、何も売れませんし。それでは流石に投資した側も困りますからね」
青年の雰囲気にすっかりのめり込んでしまったかのように、一郎は感心したかのようなため息をまた漏らした。一緒に声も出ていたかもしれない。
「あ……、っと。ついついまた話しすぎたな、悪い癖が出ちゃったよ」
独り言のように漏らした後に、彼は反省するかのような表情を浮かべた。
「すみませんね。こんなつまんない話、長々としちゃって」
「いやいや、そんな発想はなかったから。俺も、へぇーとなったよ」
素直にそう述べると、青年はまた少しだけ笑った。今度は無邪気さを感じさせる笑い顔だった。それから青年は用事でも思い出したのか、機敏な動作でベンチから立ち上がり、衣服の乱れを片手で整えた。
「お嬢さんと坊ちゃんから、目を離さないようにしてくださいね。迷子にならないように」
「ん? あぁ、それは勿論――」
それから、青年は一郎に向かってどこからともなく取り出した名刺を差し出した。一郎がそれを受け取って、目をやった。そこに並んでいたのは見事に英文字だったので、面食らってしまった。
「……アーノルド=ロマノフ、です。ま、調査でちょっとここに」
アーノルドと名乗った青年は、話している限りでは自分と同じ人種にしか見えなかったのだが。日系何世……という事なのだろうか? 名刺には、『The New World 記者』とあった。……なるほど。ジャーナリストなのか。それで、すとんと腑に落ちた。頭にあった疑問が一つ消えた。そうか。仕事でここに来た、というわけか。
「それでは、職務に戻ります。すみませんね、せっかくの休日を邪魔する形になってしまって」
「あ、い、いや……」
踵を返したアーノルドは、やはりそつのない仕草で人ごみの中へと消える。人の中に溶け込むその動きは実に違和感のないもので、人目を惹く存在であるのにも関わらずすぐにどこにいるか分からなくなってしまった。
←前 次→
top▼
覚えてる人いたらめっちゃ嬉しいです。
こんな明るい性格じゃなかったよね〜彼。
名前洋風なんですが東洋人の設定なので
見た目は完全日本人なんですよ。
日系なんちゃら人的な。
昔の連載ではイギリス人と日本系の血が
混ざってるみたいな感じでしたね。