むかしむかし、怖い未来がそこにはありました
部屋に戻るなり、冷房を全開にした。うんざりするような夏の暑さに、只でさえ疲弊していた精神が更にすり減るような思いがした。窓ガラス越しの紫外線にじりじりと肌を焼かれる思いがして、すぐさまカーテンを閉めた。
遠く聞こえるヒグラシの儚げな鳴き声に、風流なんてまるで感じなかった。
柏木はベッドの上に腰かけて、灰皿に積もった吸殻の山を見て捨てるのも億劫だと思いつつ新たな煙草を吸い始めた。このところ前と比べ吸う量が格段に増え、あまり口にする事もなかったアルコールを流し込み意識がとろけるまで煽る日も少なくはなかった。
一か月が経過しても、あの時の事を思い出さない夜はない。
動物的な匂いに混ざった排泄物の汚臭、人々の悲鳴、全てが頭からこびりついて離れない。眠ろうとすると、あの少女のクスクスと笑う声が耳の奥で響くような気がして、寝付けなくなった。それに耐えてようやく眠りにつけたかと思えば、何度も何度も繰り返しあの時の夢を見るようになる。
飛び散った脳漿が壁にこびりつく様子や、引きずり出された大腸や肝臓、飛び出した眼球、それらを何度も何度も見る羽目になる。打ち消すには、大量の睡眠薬が必要になった。また、眠っていない日常生活でもそれらは不意に割り込んでくる。
本当にふとした瞬間、人々の群れの中に首を深紅に染めた男子学生がぼーっと突っ立ているのを目撃する。交差点の向こう側に、異常に顔色の悪いサラリーマンがこちらを睨んでいるのに気付く。スーパーで買い出しをしている時も、食肉コーナーに小太りのおばさんが生肉を齧っている妄想に囚われる。
「……くそっ……」
当然、そんな精神状態でフェリーの運転なんぞ出来る筈もなく、今は内勤の方に回された。周りからは哀れみの目で見られた。心療内科で処方された抗不安剤の力に頼り、何とか他者との会話に問題はなかったが、突然のように姿を見せる狂気じみた悪夢を押しやる事は出来なかった。
「木崎……」
彼がいなくなる前、脱ぎ捨てられたままのシャツを手繰り寄せた。あるわけがないのにまだその温度が失われていないんじゃないかと期待して、抱きしめた。
あれから木崎の姿を求めて、彼の実家にまで足を運んだ事があった。もっと早くにそうすればよかったのだが、木崎は中学時代の事もあるのかあまり自分の家族の話をしたがらなかった。そのせいもあって、柏木も深く掘り起こすような事は控えていた。こうなってしまえばもはや関係のない事だった。
が、いざ家の前にまで来ると――あれが彼の妹だろう、自分の覚えている限りでは歩き出したばかりの小さな女の子だったけど――友人と談笑する女子高生に出くわしてしまい、流石に不審者になりかねないと思いそそくさと引き返してしまった。
また日を改めよう、と思った。
(どこにいるんだよお前、本当に……)
ひどく泣きたい気持ちになりながら俯いていた。吸い忘れていた煙草の灰が音もなくベッドの上に落ちる。――この失踪は木崎の意思だったんだろうか? 何となく、そうではないような気もした。何の感情も、介入しない事のような気がした。もっと即物的な事があって、それが彼をかき消してしまったような気さえした。やがて彼に巡り合えたとしても、きちんとその身体に魂は残っているんだろうか。
しばらくそうしているうちに、うとうととしている事に気が付いた。久しぶりに、薬に頼らない自然な眠気が訪れようとしていた。そのまま夢も見ない眠りに三、四時間程落ちたが、朝までは眠れなかったのかすぐにまた目が覚めた。いっそこのまま一生目覚めない方が、自分にとっては幸せだったかもしれなかった。
再び目覚めた部屋はやはり自分の部屋のままだった。何の変化もない。只――、
柏木は強烈な違和感に苛まれるように身を起こした。どんどん、どんどん、とどこからともなく何かをぶつけるような音が聞こえて完全に目を覚ました。
部屋の中は暗い、スマホを見ると時刻は二十二時……それから室内を見渡すと、スーパーから帰ってきた時のまま放置されている中身の入った袋が一つまず目に入り、柏木はベッドから立ち上がる。
今の音は何だったのか、と視界を前後させるのだが音は既に止んでいた。
「……」
何だろう。何が――よろよろとその足取りを進めた。玄関のドアに、自分の名を呼ばれているような気がしたからだ。そしてその予想は辺り、ドアをノックされていると気付いた。成程。異音はノックだったのか。誰だ? こんな非常識な時間にノックなんて。周りに響くんだよ。そもそも家に来る事自体どうかしているし、こんな真似ができる奴ときたら一人しか思い浮かばない。
「柏木くん」
待ち望んでいた筈の声だったのに、どういうわけなのか嬉しくなれなかった。ドアに近づける足を止めてしまった。
「木崎?」
「開けてよ、ここ。合鍵なくしちゃったんだ」
――木崎は……
いつでも帰ってきた。仕事で帰りが遅くなろうとも寄り道せずにまっすぐにこの部屋に帰ってきた。死体になっても帰ってきそうだな、と笑った事を思い出す。木崎は……柏木は何故かその扉を開けるのを酷く悩んでいた。この扉の向こうにいるのが本当に木崎なのか、よく分からない思いに囚われていた。何言ってるんだ? 木崎は木崎だろ? それ以外何があるんだよ。木崎の顔をした別の誰かっていうのか、馬鹿らしいよオカルトだろそんなの……
「柏木くん、どうしたの? 開けてくれよ」
インターホンが鳴っている。
木崎はもういない。
インターホンが鳴っている。
木崎はもういない。
インターホンが鳴っている。
木崎はもう――……
俺はおかしい。あの時からおかしくなっている。見えない筈のものを見る。自分の記憶や視覚さえも信じられない。俺は……その扉を、ずっと開けないでいる。
『……那岐さんは、他の世界も見ているの?』
揺れる電車の中、那岐は鞄の中からその文庫本を取り出していた。ややボロボロの装丁と日焼けしたせいで黄ばんだページが年季を感じさせるが、読むのに別段支障はなかった。
(本当に難解な本なのね、これ)
那岐は、一つに結ったその髪を靡かせながら手元の本を必死に読み続けていた。那岐――いや、この世界ではまたその名を変えて。後に出会う仲間達からは『エル』という名で呼ばれるその少女は、どの世界であっても人ごみというものが苦手だ。
(乗り物の中で本を読むと、気分が悪くなるのね)
これも、実を言うと最近知った事だった。この世界にはまだまだ知らない事がたくさんあるのだけど、自分はキルビリー達とは違い観光気分でここにいるわけではない。彼らを呼んできて共闘してもらうのも手かと思ったが、ロッキンロビンが重傷なのもあり今回は単身で向かう事に決めた。
(……と、言っても彼らは勝手についてくる可能性もあるけれど……)
そんな事を考えていると、乗客達が騒々しくなりたちどころに悲鳴が上がった。本を閉じ、エルは持っていた日本刀へと手を伸ばす。人々を掻き分け、『あの子』の姿を探した。――見つけた。
「ど、どうしよう……!」
「ねぇ、あれってゾンビなの!? 何でここに!……けど武器なんか持ってないわ!」
怯える女性二人組を避け、エルは刀の柄へとぐっと手を伸ばした。討つべき敵の数は……一体。転化したのは着崩したブレザーを纏った女子高生のようだ。もはや見慣れたものであったが、果たしてそれに慣れていくべきものなのかは複雑だった。
少し前の自分ではこんな事考えもしなかった。
少しずつ変わり始める自分に戸惑いもするが、後悔はなかった。迷いも躊躇もなかった。
「助けて!」
やがて、そのか弱い少女の、救いを求める声が響いた。猶予などあるわけもない。
――林檎……、
そうだ。もう、迷ったりなんかしない。
私はどこにいようとも、私よ。
姿や形や名前が違っても、私は私。
そして、必ず生き残る。
(何度でもあなたを見つけ出して見せる)
そして――……
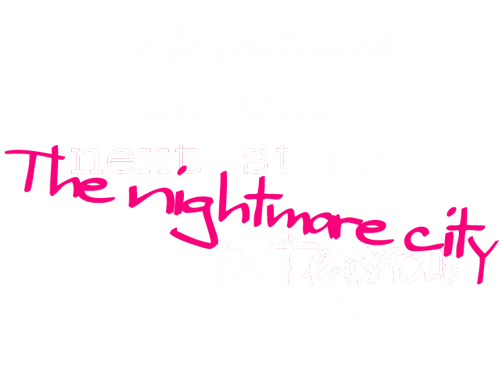
“きっと何度でも、あなたを救い出してみせる。”

キートン山田「インテグラルに続く」