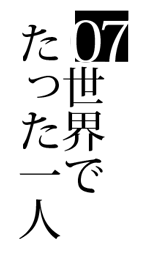
その壮絶な姿に一瞬面食らったものの――木崎はすぐさま視線を動かすと、次の一秒のうちにショットガンを拾い上げていた。足先で蹴り上げて手繰り寄せ、それを掴みざま腰だめに構えていた。
「アンタの言う通り。……トドメはしっかりと刺すべきだったようだ」
言い終えないうちにその銃口から火花が散った。マザー・ファイアフライの顔に当たる部分が半分、消え失せていた。憚りもせずに血を吹き出しながら、辺りを一層焦げ臭い匂いが包み込んだ。木崎はポンプを動かすと、勢いよく吐き出されたシェルが宙を舞い駐車場のアスファルトにカランと転がった。
隣では、膝から倒れ込む運び屋の背後に駆け込み、ベイビードールが慌ててその身体を支えた。
「い、意識はまだある、けど」
弱弱しいベイビードールの声に、木崎は屈みこみ両耳を押さえて震えるミミに話しかけた。
「ねえ、君……」
「イケメンでもサイコパスは無理ッッ!」
その動きは、ミミの小ささも相まってかバネ仕掛けのぬいぐるみか何かを思わせた。ミミが叫びざまに飛びあがり、逃げ出そうとするのを慌てて木崎が背後から腕を掴み、引き戻した。
「ひぃいっ……あ、あたし何も見てませんし何も話しません! だだだ・だから拷問してバラバラにしたりドラム缶に詰めて沈めるのとかはやめてくださぁい!!」
「落ち着いてくれ、俺は警察だよ。ホラ」
「なになになになに、あ、あたし別に捕まるような事してないわよ〜っ!?」
もはやパニック状態にあるミミに、木崎は肩を竦め困り果てたようなため息を吐いた。
「……だから女の子は苦手なんだよ、俺」
「あー。お姉さん、これっ!」
そんな木崎に代わり、ベイビードールが出したのはストラップの付いた名札ホルダーである。それはミミが院内を出歩く時に用いる、スタッフ証明書であった。これを使えば病院内の緊急通路などを動き回れるという社員カードなのだが、財布と一緒にいつも持ち歩く癖でつい所持していた。
「!……あ、あれっ、いつの間に……」
「言っとくけど盗んだわけじゃないよ。さっきおねーさんが落としたもの、だからね」
言われてみて慌ててリュックを見ると、ミミはそこでようやくのよう、ジッパーが開けっ放しになってるのに初めて気付いた。財布とスマホはベイビードールが回収してくれたのか、一緒に手渡してくれた。
「……あ・あ・ありが……と……」
まだ事態を飲み込み切れず(いやはや当然だ)、ぽかんと口を半開きにするミミに、続けざま木崎が木製の四角い箱を手渡した。大きさは、十九センチ程のミミの両手に収まるくらいのもの。持ち手のついたそれは、多分救急箱だろう。薄茶色のケースには、緑色の十字マークが刻まれている。
「縫合用の糸と針、さっきの事務室から調達してきた。麻酔はないけど何とかできない?」
木崎の言葉に、ミミは思わず耳を疑った。ついでに、彼を二度見した。……あ、超かっこういい。何て整ったお顔だろう、超好みかもしれない。出来ればこんな状況で出会いたくなかった――まあイケメンだから良しとされる問題ではなくて、ミミは半笑いで木崎を見つめ返していた。
「へ? あ、あの、えっと……はい??」
「まあ立ち話もアレだからね。そこに俺達の車があるから、どうか一緒に来て欲しい。彼の手当てを頼む」
「え……ええっ!?!?」
独身アラサー女子、イケメンからのお誘いはそりゃ願ったり叶ったりで嬉しいけれど――いやいやそんな事考えている場合じゃないってば! ミミは口をぱくぱくとさせながら鉄骨に胴体を抉られた男を改めて見てぞっとし、事態を一気に思い出した。
「――手当てって、いったい何!? どういう事よ、こんな明らかに重傷な人をどうしろってわけ!?」
「医者なんだろう、だって」
「い、医者よ! 確かに医者よ、けど獣医なの!! 動物の傷くらいしか縫い合わせた事なんかないわよ、こんな明らかに胴体千切れかかってる人なんか治せるわけないでしょう!?」
あまりにも簡単そうに言ってのける木崎に、ミミは我を忘れて全力で抵抗した。こんなに必死になったのはよもやいつ以来だろう、と感慨深くなるほどに。
「大丈夫、そんなに動物と変わらない人だよ。……多分」
ベイビードールの全く大丈夫じゃない補足事項に、益々ミミは関わらない方が良かったのではないか……と助けてもらっておいて何だが激しく後悔していた。
「俺と君で運ぶから、えぇと……君ばかりで何だか紛らわしいな……みみみさん?」
「区切るところ違います、なるかみ、みみです」
木崎の問いかけにミミはすかさず答えたが、彼はあまり頓着しておらずあっさり流してしまった。その呼び方にかつて好きだった男の事を思い出し、何だか複雑な思いに囚われた。こんな時だっていうのに、彼の事を思い出すとちょっと胸が落ち着く辺り、まだ未練がましく好きだと気付きもやもやした。
「みみみさんは先に行って車の扉を頼むよ、これが鍵。――で、あれが俺の車。よろしく頼んだよ」
「えっ、ちょっ……」
ふと、静けさを取り戻しつつ周囲――ここから見て、燃え爆ぜるマザー・ファイアフライの遺体の背後辺り。奇妙な唸り声がたちまち聞こえてきたのに臆し、ミミは振り切るようにその場から駆け出した。……もうヤダ、これから絶対一人旅はしない、知らない土地なんか行かない、絶対に!――男の治療が終わったらさっさと抜け出してやる!
木崎がネームレスの上半身を抱え、ベイビードールが見た目にはそぐわぬその腕力を発揮し彼の脚を支えた。
「……あぁ、そうだ。君も、名前は何? あと今この死にかけてる人も。――俺は木崎だ、って、何か今更な感じするけどね」
「――。アーノル……じゃない。ベイビードール、だよ。こっちのオッサンは“名前がないのが名前”」
「何それ? 難しい事言うなあ」
「運び屋ネームレス。名無しの権兵衛なんだってさ、俺もこの人の本名は知らない。聞いても教えてくれなかった」
「え。……じゃあ君達、そんなに仲良くないの?」
「何で? 別にそんな事ないよ」
「だったら何でお互いの名前を知らないのさ。今時はそういうのが当たり前なのかい」
妙に古風な事を述べる木崎に、ベイビードールが苦笑交じりに言葉を紡いだ。ずぼらそうに見えてそういうところは気にするのか。
「仲がいいというか、その……友達同士って関係でもないからさー、ほら? うん? 何だろ、仕事上の相棒……的な……?」
「……仕事上――、そもそも運び屋って職業は何だい? 運送業者の事?」
「う、運送業者……間違っちゃいないけど多分アンタの解釈とは違う気が……って。ああ、もうホラ! ちゃんと前見て歩かなきゃ!」
こんな気が抜けるようなやり取りを続けている間にも、ネームレスの身体からは依然としてドバドバと鮮やかな血が流れ続けていた。鉄骨が遮っているものの、問題はこれをどうすべきなのか、だが。
先回りしたミミが扉を開け、三人を乗せる態勢を整えていた。何でこんな目に、と思いつつもここは大人しく乗せてもらった方が身の安全が保障されそうだ。木崎が運転席に乗り込み、助手席にはベイビードールが飛び乗った。
「手元が暗いわ、灯りが欲しい」
「これくらいでいい?」
手術台さながら、ベイビードールは座席からマグライトを掲げながらミミに問いかけた。ミミが頷くと、上に羽織っていたスカジャンを脱ぎ傍らに置いた。
「み、見たら分かるけど想像以上に出血量が酷いわね……火で焼きながら止血を繰り返した方がいいかも、原始的だけど」
「火?……あ! 俺、煙草吸うからライターならあるけど」
ベイビードールが取り出したのはリボンやラインストーンでデコられた恐ろしく使いにくそうなピンクのジッポライターであった。
「煙草……?」
ミミがまじまじとベイビードールの顔を眺めたが、もはや真面目に構っている場合ではないのかもしれない。常識的に、とか何とか考えるのはナンセンスだろう。もはや。
ベイビードールがその姿勢のまま、運転座席の木崎に問いかけた。
「行き先はもう決まってるんでしょう?」
分かり切ったように尋ねたけれど、彼はハンドルを握り締めたまま反応をしなかった。言葉はなかったが、視線は気持ちおずおずと下がったようであった。
「……電話するなら一回車停めなきゃダメよ〜、お巡りさん」
ベイビードールがどこか茶化すように言ったが、木崎はそれも深刻に受け止めていた。しばし置いて、彼はブレーキを踏んだ。それから「すぐ終わるから」と告げて、ポケットを漁り始めた。
スタンドリング付のカバーが装着されたスマートフォンを取り出すと、片手で操作している。……電話番号は頭に入っていた、これでもし、彼が電話に出てくれなければ――このまま諦めるつもりですらあった。だけど、それでいいのかと自問する声はあった。
一秒。二秒。三秒。――出来れば……いや。無事でいて欲しかった。四秒。五秒――六秒目で、急速に迷いが生じてしまいどうしようかと思い、いっそ切ってしまうべきか悩んだ。
『もしもし?』
知らない番号(悔しいけれど)からの着信なだけあって、一瞬彼の声は不思議そうであった。――良かった、ともかく思った。間に合った。
「も……もしもし、柏木く――、柏木さんの携帯ですか?」
『え、ええ……そうですが? どなたですか?』
その声は明らかに不信感を纏わせていた。けど、怪しがられても、引き下がる事は出来なかった。小さく深呼吸してから、木崎は呼吸と共に声を吐き出した。
「その、き、木崎です……隣の……」
『え、き、木崎さん!? ど――どうかされましたか? あの、どうして俺の番号が……』
正体が分かり彼はほんの一瞬安堵したみたいだが――いや、どうなのだろう。余計に不気味さが増しただけだったか。けど、もう一秒の時間さえ惜しかった。回り道している暇なんかないのだ。
木崎は無意識的に目を瞑り、首を横に振ってから振り絞るように声を漏らした。
「ごめん」
それは、以前まで、木崎が当たり前のように柏木に言っていた言葉だった。今は少し意味合いやニュアンスやらが、変わってくるのかもしれないけど。
「回りくどい事は思いつかないや。……柏木君、その、よく――よく、聞いて欲しいんだけど」
『……、はい? な、何、でしょうか』
柏木は、当然だろうけれども他人行儀な敬語を止めなかった。その丁寧な言い回しに無闇に傷ついたが、ともかく。木崎は一呼吸置いてから、込み上げてくる叙情めいた言いようのない感情を押し込めて、そして幾分か迷いながらも続けた。
「今、家にいるのならすぐに……すぐに家族、を連れてその部屋を、離れて欲しい」
『…………』
こんな事を言って、もしかしたらその場で電話を切られる事も覚悟した。でも、柏木はそうしなかった。――ああ、と木崎は思った。やっぱり君は優しい人なんだね、いや、もしかしたら怪しすぎて切るのを躊躇っているだけなのかもしれないけど。……でも、いい風に解釈してあげるよ。
「必ず……必ずその人の手を離しちゃダメだよ。途中で誰かに話しかけられたりしても、相手にしないで、出来る限り人目につきそうな場所を歩いてくれ。……真っ直ぐ外を出て、バス停前の交番に向かって欲しいんだ。分かるでしょ?」
呼吸の為の、しばしの静寂。依然として通話は続いていた。途切れる事はなかった。……安心した。
「――今の時間帯からいって、そこにいる巡査は島田っていう俺の同期だ。若い人と年配の人がいるかもしれないけど、若い方がそう。まあどちらにせよ信用できる人だから安心して……そして交番に入ったら俺の名前を出してくれ。木崎から、遊園地の方で問題が起きた。自分をここで匿うように彼から電話があったって。多分、それだけで伝わる」
『いや、あの。その、一体……何の話なのか……』
当然、彼は困惑しきったような声を漏らしていた。どこからどう問いただすべきなのか迷っている風な声質だった。
「お願いだ。どうか今は俺を信じて欲しい」
無理な難題なのは百も承知の上だけれども、懇願するように言ってから木崎はため息を吐いた。本日何度目になるやら分からない、ため息だった。彼がこんな説明で信じてくれたのかどうかは分からない。だけど、木崎は無性に嬉しかった。――いやはや、幸福でもあった。見捨てるという選択肢だって、あった筈だった。
だけど、それなのに彼の為に動けた事がどうしようもなく誇らしかった。自分にこんな事が出来るなんて、信じられなかった。きっとこの気持ちを味わうために俺は生まれてきて、そして彼に出会ったのかもしれない。
「柏木くん」
電話の向こうで彼は今頃、眉を潜めているに違いない。大いに想像がついたのだけど、あと、あとどうか一言だけ許してほしかった。そう、これだけは言えるだろう。
「――愛してる」
あの時、中学という空間で出会ってから俺達はずっと一緒だった。学校へ通っていた意味なんて今となってはよく分からないけど、もし、あの場所が自分に何かを与えてくれたのだとしたらそれはきっと柏木君の存在だ。……通話を切ると、木崎はスマホを傍らに置いた。ハンドルをきつく握ると、正面を改めて見据えた。
後ろの座席ではミミが焼いたピンセットを押し当てながら傷口を確認しているようだった。
「ね、ねえ、先に病院に行くんでしょう!? 緊急手当てなら一応やるけど、流石にこれを治せってなったら無理だからね」
「もうあと三十分程、耐えられるように治療を施す事は無理?」
「さ・さ・さ・さっきから無茶振りばかりホントにやめてくださいよおっ! 一刻も早く病院に連れて行かないとぉおおーッッ!!」
ミミの魂の叫びが、車内にキンキンとした調子で響き渡った。木崎はその間にも、細野のあのニヤついた笑い顔を思い浮かべながら、奴がどういうつもりでいるのか探るように眉間に皺を寄せた。
――俺をすぐに殺さなかった事を、絶対に後悔させてやるからな
←前
TOP▼
って感じなんだろうけどなぁw
いきなり隣人からこんな電話来たら怖すぎるが
木崎君の心情考えたらいたたまれんな。
ミミちゃんもとんだ巻き込まれですな。