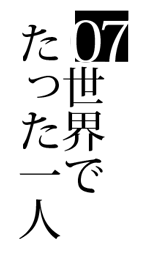
画面の中、極々ちいさなそのウインドウの中。木崎は「あれ?」とか「こうだっけ」とか時々妙な独り言を混ぜながらキーボードを打ち込んでいた。……本当に大丈夫か、それで、と声掛けしそうになった所で、どうやら作業は完了したらしい。
「終わったのか、それで?」
尋ねかけてみると、木崎は「うん」と頷いてから、幾分か真剣なまなざしでこちらを見つめた。
「……、十五分。あと十五分後に、ここは消し飛ぶ」
「一応聞くけどさ、それって間に合うんだよね。さっきの女の子と一緒に俺達も地下に潜ってた方がいいって事はないの?」
「――目先の命を考えるとしたら勿論それが一番安全だろうね、けど……本部や国の役人達にとって君らの存在は恐らくあの化け物達とほぼ同等と考えた方がいいと思う。俺の立場では君達の安全を保障できない、上手く立ち回って庇う事も擁護する事もちょっと難しい」
「むしろお前はそれでいいのか?」
ネームレスの問いかけに木崎は歩きながら、ちょっと小首を傾げて不思議そうな顔をさせた。疑問符を浮かべたその視線を受けながら、ネームレスが言葉を紡ぐ。
「逆に言えばお前は残っても問題ないって事だろう、つまり。大人しく助けを待つのがいい筈じゃないか」
「……ああ、そういう意味か」
なるほど、と木崎が納得したように正面を向いた。
「俺は結局、この事件についてあれこれ問われる立場になるだろうし。細野……、えーと、ここを襲撃した奴の出方によっては事件を計画した張本人として扱われる事になるかもしれないから。面倒くさいでしょ……」
「とか、何とか言って。――ほんとはさっき言われた人の事、助けに行きたいんでしょ、貴方?」
言葉の終わりに被せるように、ベイビードールが問いかけた。それで木崎は一旦移動を止め、正面を向いたままの姿勢でしばし黙り込んでいた。あまり悠長にしていられる場合でもないのに、とネームレスは思ったがベイビードールは喋りを止めなかった。
「行っちゃえば? そんなに気になるんならさ。俺達も付き合おっかー、何なら」
「おい、勝手に決めるな。俺は……」
「何かそういうのイラっとすんだよね、嫌いな相手の思い通りになるのって。で、そいつは俺の方が優位に立ったって思いこんだまま終了すんの? 無理、絶対ヤダ。ドヤ顔で威張ってるそいつの顔に一発ブチ込んでやりたい気分だわ〜」
木崎はややあってから、少しだけこちらに視線を傾けつつ吐き捨てるように呟いた。
「……事情が複雑なんだよ」
「いーや、単純だね。実際にややこしくしてんのはアンタ自身だと思うよ」
「…………」
思い当たる部分があるのか何なのか、木崎は伏し目がちになったかと思うとため息交じりにまた正面へと戻った。ベイビードールの言葉が何らかの形で彼の心を突いたのは違いないだろうが、結局彼がどういう結論に至ったのかは分からなかった。
「とにかく時間がないんだ。先を急いだほうがいい、今は」
まあ、それは正論であり、今一番に考えるべき事であった。足を止めてまで論じている時間んも惜しかった事を思い出し、ベイビードールはそれ以上何か言う事もなかった。建物の外に――エレベーターを使い上へと昇ったかと思うと、また階段を使い上へ。正確には地上へと戻ったようである――最後の扉を開いて出ると、血の跡が規則正しく道筋に続いているのが分かった。まるで道しるべのように、それは点々と続いていた。
先程の件と言い、もはやその細野という男がこちら(と、いうか木崎一人なのだろうけど)を挑発しているのは明らかだった。逆に言えば分かりきった罠なのかもしれないが、木崎はその可能性については指摘しなかった。
「この施設、どこかの地下に作られてたんだねぇ。それも結構深い、外との気温差があるし」
「聞いて驚くなよ。改装の決まっていた巨大テーマパークの地下四百メートルに、この場所は建設されていたのさ」
それを聞いた途端、ベイビードールはやや目を細めて木崎を見つめ返した。
「……それ本当?」
「何だい、思い当たる節があるような顔をしているね」
「やっぱりそうだったんだ!……んああーあああっ、俺の調査もいいところまで行ってたってのにちきしょうっ! もぉおおおお少しで尻尾掴めるところだったってぇのになぁ!……ちぇっ、めんどくせぇや。……あーゴメン、詳しい話は後でするよ……はあ……」
「――ああ、そうしてくれ」
地団太を踏み悔しがるベイビードールを尻目に、ネームレスが一歩前へと出た。
「しかし……何でまたわざわざそんな目立つ場所にしたんだ?」
「さぁね。色々と説はあるみたいだけど……。単純に土地が余っていたからっていうのと、音がうるさいからかき消してくれるっていうのと――、う〜ん、あとは気候だとか、人の出入りが多い分誤魔化す時の言い訳がしやすいとか、条件も良かったんじゃないかな」
とどのつまり、彼は真相については知らないようである。ネームレスはそれ以上追及する事はせずに、曖昧なため息で返したのだった。
「ここまで来ればもう大丈夫かな。……で、あそこに停めてある白のセダンが見える? とりあえずアレに乗ってくれるかな」
「お前の車か?」
「そう。別に盗むわけじゃないから安心して」
「わぁーお! あれアメ車じゃない? 旧車とはまた渋いねえ、やっぱしかっこいい男が乗る車はかっこいいねえ〜ぇ」
「……冷やかさないでくれよ」
この木崎も、ベイビードールが相手だとたまに調子を狂わされるのか何なのか……時々対応に困るような素振りを見せるのが、妙に可笑しく、また不思議であった。――その気持ちは何となく分からないでもないが。
外は闇が濃く、その底では何かの虫の声が響いていた。命を切らす前の蛍光灯のようなジィイイ、という声を上げながら、三人は闇の中を走った。――と、その途中で地響きがしたかと思うと幾分か足元が膨れ上がるような感覚が走った。
それは思わず足を止める程の、地響きだった。
一瞬地震かと勘違いしたが、轟音が鼓膜に乱暴に体当たりしたのを機に爆発が起きたんだと理解した。名前も知らない野鳥達が夜の空に鳴き声を上げながら四方に飛び立ってくのを見送り、ネームレスがゆるゆると顔を持ち上げた。
「っ……、モタモタしてたら巻き込まれるところだったな。確かにこれは地震で片付けられるくらいの自然さだ」
「ね、ねえ。何か聞こえない?」
一息吐く、なんていう間さえ入れずにベイビードールが不穏な事を言い出した。ネームレスと木崎が顔を見合わせてから、息を潜めて周囲へと視線を動かした。続けざま、再び轟音に鼓膜を揺るがされた。
「あ」
再び姿を見せたのは、忘れようにも忘れられない、あの不気味なフォルム。ただしその巨躯にはもれなく火炎が付着しており、濃紺の闇に支配され尽くした辺りを明々と照らしつけていた。……爆発でも死にきれなかったらしいマザー・ファイアフライが、けたたましい悲鳴と共にこちらへ向かってくる……。
「何て生命力だ。ゴキブリ並かよ」
感嘆とも畏怖とも取れる声で、ベイビードールが囁くように言った。ふとその燃え盛る物体に目を奪われていたが、ネームレスはもう一つの異変に気付いた。マザー・ファイアフライはこちらへ焦点を絞り向かってきているのだろうとばかり考え込んでいたが、よくよく見ればどうもそうではないらしい。
「きゃー、きゃぁあーっ! いや、いやっ!! 何なのよぉおおお!!」
小柄な女性が、必死で斜面を駆け抜けていた。いや、身を低くしている為なのかもうほとんど這っているといった方が正しいのかもしれない。彼女自身の的が小さい為か、マザー・ファイアフライもその攻撃を上手く当てられずにいるようであるが、足の長さ的にほぼ追いつかれているといっても過言ではなかった。
「誰だろ、あれ?」
「……さあ。いずれにせよ、仲良く遊んでいるようには見えないな」
ベイビードールとネームレスがそれぞれ顔を見合わせてから再び視線を持ち挙げた。Sサイズ程の洋服を真っ白に汚しながら、彼女――ミミはこちらにも気付く事なくひたすら逃げ続けていた。
「っあ、あたしがっ! あたしが一体!! 何したっていうのよ、ばかぁああっ!!!」
口を伝って出るのは訳も分からぬ罵り言葉で、ミミは頭を伏せながら運良くその一撃をかわしているようであった。ベイビードールがハンドガンを抜き出して、両手で構えた。
「……伏せてっ!」
「!!」
一瞬ばかり、ミミの「えっ」といった具合の目つきとぶつかるも、彼女は言われるままにまるまるヘッドスライディングの要領でしゃがみこんだ。そのはずみで、リュックが前のめりにずるっと飛び出してから、中身が勢い良く散らばるのが見えた。
ベイビードールがそれを見計らって引き金を引く。銃口が発光し、それは相手に被弾したようなのだが――マザー・ファイアフライは動きを一瞬止めただけで虫が止まった程度にしか捉えていないようであった。あまり、効果的な一撃には見えなかった。
見兼ねたようにネームレスが自身も持っていたショットガンで応戦する。もはや隠しようのないボリュームの咆哮と共に、マザー・ファイアフライが前脚を動かし、手近にあった物置を破壊した。砕片が吹っ飛んできたが、ネームレスはクレー射撃宜しくその勢いを伴って飛んでくる鉄くずを撃ち落としていた。
ほんの一瞬ベイビードールが怯んだようだが、すぐに「ありがとっ」とお礼を告げてスカートを翻した。
――そうだ。撃つ、とは、こういう……
何故か撃った瞬間の衝撃や反動や、耳を塞ぎたくなるような発砲音は、すぐに受け入れられなかった。神経が昂っているからだったのか、それとも自分がまだ自分をよく分かっていないだけなのか、いや単純に受け入れたくないだけなのか分からない。
けれどもそれらの衝動は、一緒くたになって扉を開けてネームレスの脳内に沁み込んできた。再び引き金を引き、マザー・ファイアフライの巨躯目掛けて撃つと、9ミリパラベラム弾よりは明らかに威力のあるのであろうスラッグ弾は、化け物の身体を幾分かそげ落とした。
マザー・ファイアフライはその身体を支える筈の前脚を断たれ、バランスを崩し倒れ込んだ。尻餅をついた状態のまま、ミミが「きゃあっ」と悲鳴を上げた。
「もう撃たなくても、あのまま焼け死ぬんじゃないか」
背後から木崎の声がしたが、何故か今の自分の中にはあまり意味のある言葉として入ってこなかった。何の戒めにも、ならなかった。
「駄目だ。完全にトドメを刺す、背後から狙われたんじゃ溜まったもんじゃない」
「今の一発でも、俺達の居場所をばらしたようなものだよ。この親玉以外にも生き残っている化け物がいたら銃声を聞きつけて、」
木崎がそれを止めようとしたが、ネームレスの様子がどこかおかしい事に気付いて一度言葉を切った。
「……?」
ネームレスはその熱を持ったままの銃身を下げたものの、何かに視線を奪われたかのように静止したまま動こうとしない。――ネームレスは……魅せられたように死にゆく怪物を見つめていた。いや、正確にはその前に佇む、存在している筈のない『幻影』に。
『だめ』
幻影が口を動かして、声を出した。勿論、ネームレスの耳にしか届いていない声だった。その幻は、少女の姿をしていた。途端、切迫した義務感に苛まれた。理性と破壊、の言葉が、それぞれ頭蓋を焼き尽くす。
少女の幻が、両手を広げて立っていた。死にかけるマザー・ファイアフライを庇うようにして。
『だめ、撃たないで。撃っちゃダメ』
うなじが熱を持ち、強烈な眩暈と共に頭痛を呼び出した。――何だ? 俺はいったい今、何を見ている。
解答のない問いに煩悶し、先程前の昂揚感が嘘のように消えていく……。
『……そよ達、一緒にいられなくなっちゃうよ……』
神経と思考が引きちぎられて、分離しそうな程の感覚を覚えた。全身の毛穴という毛穴からひんやりとした汗が吹き出すのを我慢できなかった。ネームレスはその場にショットガンを落とし、耐え難い嘔吐感に襲われた。……駄目だ。ダメだダメだダメだ!
「おい、どうしたんだい?」
「ふ・二人共!」
木崎がネームレスの肩を揺さぶった時、覆い被さるようにベイビードールが叫んだ。
「避けてっ!!!」
ベイビードールが踏み込んだのも遅く、次の瞬間だった。あっという間のうちに、時は進んでいた。息をする間さえこちらに与えず――“ろうそくは消える瞬間にこそ一際大きな炎を発する”、という、法則がある――マザー・ファイアフライが残る力を総動員させ、千切れていない方の前脚を使い横手に見える鉄鋼を殴り飛ばしていた。甲高い金属音が一つ響いていた。
大柄な見た目にそぐわずバネのようにその腕は動き、平べったい金属の塊はスピードを伴って凶器と化していた。
「うっわぁあああ!? ま、ま、マジかよ、運び屋さんッ!?」
彼の胴体に、その『凶器』が深々と突き刺さっていた。――これは引き抜くと恐らく上半身と下半身が千切れる、不用意に動かすのは……。
←前 次→
TOP▼
クラシックタイプ乗りって超絶オサレ番長やね。
シボレーのマリブね、わいもこれ乗りたかった。
操縦じゃなくて助手席がええな、
超燃費悪そうだしむっちゃ故障多そうだが
カッシは逆に堅実な国産車だろうね。
軽四ではないと思いたい私がいるけど、
それはそれで倹約家なのかな? って好感度増すね。
彼なりにきっとプライドがあって
30も近い男が貯金がないと嫌だろっていう感じ
木崎君は貯金少なそうだねぇ、
彼の辞書に節制の二文字はない。何の話だこれ。