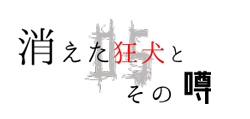
櫻子は学食で頼んだのであろうオムライスを頬張りつつ、もう片手にはカバーのかけられた文庫サイズの本を読んでいた。食事中に案外行儀が悪いと思いつつ、それさえも無邪気だと笑って許せそうなのはやはり彼女の事を悪く思っていない、動かぬ証拠なのかもしれない。
「私、窓際のこの席が好きなの。ここで本を読みながらゆっくりご飯を食べるのが楽しみなんだから」
悪びれもせずに微笑む櫻子は、他の人間のように席を立つ気配もなく、まして自分もどこか別の場所に移動するでもなく。結果、同席というか――向かい合う形で何となく腰かけた。ほとんど無意識のうちの行動だったかもしれない。何となく、うっすらとだがこの一人の女子生徒への興味が沸いていたのもあるのかもしれない。
「……その割には今までここで出会った気がしないな」
「いつも来ているわけじゃないもの。けど、貴方がいない時は毎日こうやってここにいたわ」
「――なるほど、ね」
納得したわけではないが、櫻子がそういうのならそうなんだろう――と、今は思うしかない。事実、学食へ足を運んだのは久しぶりの事で、何だか急にこのカレーうどんが無性に食べたくなったのもあった。正直特別美味しい代物ではない……とは思うが、何故か思い出したように食べたくなった。割り箸を割りつつ、湯気の立った汁の中に箸を突っ込んだ。
「お前、知らないわけじゃないんだろう。俺の事」
「何が?」
平然と聞き返す櫻子の顔からは一切悪意のようなものは感じられなかった。不思議そうにそのはっきりとした眉を上げ、構わず食事を続けていた。
「俺の噂だよ」
「?」
「俺に関わった奴は大概みんな不幸になる。見てみろよ、ここに俺が入った瞬間明らかに空気が変わったのに気付かなかったか? 見渡してみろよ、誰もいない。厨房にいる連中の顔つきも明らかに異質なものだろ、どいつもこいつも見て見ぬふりをしていやがる」
櫻子はそれを聞いても別段興味を持っている風でもなく、あっさりと「ふうん」と受け流した。自分の話をして怯えなかった女は、これが初めてだったかもしれない。何としてでも降伏させてやりたいという闘争本能のような思いが頭をもたげ、つい躍起になったように次の言葉を紡いだ。
「俺が周りから何て呼ばれているか知っているかよ」
「全然?」
呼んでいた文庫本から顔を上げ、櫻子がゆったりとした口調で返した。
「“教室の死神”だってさ」
「何、それ」
すかさず櫻子は可笑しそうに笑い、緩んだ口元を指先で押さえた。白く綺麗な指先に目が行き、透明な笑顔と嵩んで目が眩みそうになった。くすくす、と櫻子は唇を上げ、無邪気に微笑んでから再びこちらを見つめた。
「そういうの、好きなの?」
「何が?」
「人に怖がられたり、避けられたり、そんな風にあだ名をつけられたりするのが」
彼女の視線はこちらにしっかり向けられていた。
「……まさか。流石にそれはないけど」
「じゃあ、どうして何も知らない私まで追いやろうとするの?」
それは何か責めたり軽蔑したり、こちらを咎めるようなものではなく、只不思議に感じている事を口にしただけといった調子であった。
「――だって怖くないのかよ。アンタも、気付かないうちに巻き込まれてもし何か起きたらどうするんだ?」
「その時はあなたが私を守ってくれればいいじゃない」
肩を竦めながら、櫻子がスプーンを置いてゆっくりと呟いた。意味、というか意図が飲み込めずに、啜りかけのうどんもそのままにして彼女を見つめていると、その姿が可笑しかったのか櫻子はまたクスクスと笑った。
「うどん、口から出てるよ」
可笑しそうに言い、櫻子はこちらを指差してまた一笑を浮かべた。慌てて食べかけていたうどんを啜ると、そうしている間に彼女は食事を終えたトレーをまとめて立ち上がった。手元の文庫本を持つと、櫻子は通り過ぎ際にこちらに向かって微笑みかけながら言った。
「じゃあね、死神くん。またどこかで一緒になれたらいいね」
意味深な彼女の言葉に、何かを期待する程の純粋さは持ち合わせていない。けれど、その眩しい笑顔はいつまでも胸に刻まれたままで燻る事はなかった。
きっかけやなれそめなんて、第三者からすればくだらないものに過ぎないんだろう。彼女とのその些細なやりとりが自分にとってどれほど真新しく鮮明なものであるかなど、説明したところで誰かに分かる筈もないだろう。
佐竹櫻子とはそれ以来、校内で会う時も軽く挨拶をかわすような間柄になっていた。廊下ですれ違った時や、別の教室でたまたま居合わせた時など、彼女の方から何らかのコンタクトを取ってきた。
櫻子はその容姿にしたってそうだが成績優秀なことも手伝ってか他の生徒達からも男女問わずに人気があるようだった。自分とは違い、彼女の周囲には常に誰かしらが存在していた。そんな彼女の『特別』になりたいだなんておこがましい感情は決して抱かない。只、時々こうやって会話が出来たらそれでもう十分だと思った。――只、それだけで良かった。
「最近、何か楽しい事でもありましたか?」
父親が不在の夕食の時、母がそんな風に尋ねてきた事があった。顔を上げると、いつもと変わらぬ装いの母がそこにいた。何故かその存在感に威圧され、別に後ろめたい事があったわけでもないのに一瞬息を飲んでしまった。
「――変わらず楽しい学校生活を送っています」
「そう。ならば良いですわ」
しかし妙だった。
どうしてこの人は変わらずこう、気丈な態度を崩さずにいれるものか。父は外に若くて美しい愛人を何人も囲い、今日も夕食へは姿を現さない。それが日常化していて、母はそれにずっと気付いている。気付いているが、知らないふりを貫き通しているのだ。
「……母さんは良いのですか?」
「え?」
「父さんの素行に不満はないのですか」
その日、初めてであった。そんな風に母に父との関係について問いただしたのは。息子から恐らく自分にとっては最大の禁忌であろう、目を背けてきた事実を口にされ一体何を思ったのだろうか。母はすぐには何も答えなかったものの箸を持ったまま、しばらく喜怒哀楽のどれにも属さない表情でこちらをじっと見つめていた。
「あのお方は、母さんという人がありながらまた別の存在にもうつつを抜かしております。そんな事が許されていいのか自分には到底理解が――」
「お黙りなさい」
静かに威圧するような声が飛び、同時に母は箸を食卓の上に叩き付けるようにして置いた。
「あの方は今まであなたが幸せに暮らせるよう、最低限の務めは果たしてきているでしょう。貴方がここまでを無事に過ごしてきたのは誰の為だと思っているの?」
母の顔を見て、はたと気付いた。――ああ、この人は怯えている……自分が日に日に老いていく事、若い頃の美しさを失い、いつか父に捨てられるのではないかという恐怖に――紛れもなく母はそれでも父の事を愛しているのだ。いや、愛しているかどうかは分からないが、彼から興味を失われる事に怯えている。
夕食を終え、ふらふらとした足取りで父の書斎へと赴いた。普段はそこへ立ち入る事が禁じられている。鍵をかかっているのがほとんどだが、その日はまるでそうする事を仕向けられたかのように半分だけ扉が開いた状態で自分を迎えていた。
何故か櫻子の姿を求めるよう、ドアノブを開き、十数年この家にいながら初めてその部屋へと入る事が叶った。小難しい本が並ぶ棚を見送り、革製のソファー、埃一つとして乗っていないガラステーブルに、閉め切られたブラインド。どこかの社長室を思わせるような、部屋そのものが厳重な重圧感に満たされたその空間で、パソコンや作業用の資材が置かれたエグゼクティブデスクへと足を動かした。まもなく辿り着いた。引き出しを開いた。
「……これは……」
几帳面な父親からは考えられない程乱雑に突っ込まれた、中身のはみ出たファイルや茶封筒。ぐしゃぐしゃに丸められた用紙。続けて引き出しを順番に開けると、信じられないようなものが次々と姿を見せた。いわゆるSM用のグッズというのか、奴隷につけるようなトゲのついた首輪や何らかの錠剤、赤色のロープ、名称などは知らないが手枷や猿轡のような何か。それらはまだ笑って済ませられそうだが、次に開いた引き出しに詰められていたのはほとんど拷問具に等しいものたちだった。
思わず息を詰まらせた。それらには全て変色した血の跡があり、使用の痕跡が認められたからだ。注射器や浣腸器のようなものも、ごちゃごちゃと、まるで小学生がおもちゃでも片付けたかのような雑さで詰め込まれているのも気味が悪かった。
視線は最初に見たファイルや封筒へと戻っていた。震える手でそれを手にした。見てはいけない、と自らの中で警鐘が促されたが、背後で何故か櫻子の声を聞いたような気がした。理由は分からない。だが、彼女の幻が耳元で囁いた。
『見て。目を逸らさないで、ちゃーんと見て。何が真実? ちゃんとその目で見定めるの』
しばし固唾を飲んでると、僅かに開いたままの扉から声がした。同時に、扉が軋んで開く音も。
「最近、あなたに近づいて来る小便臭い小娘がいるでしょう」
分かり切っていたが、母親の声だった。
無視して、先を急ぐようにその封筒の中身を開いた。中から出てきた写真には、父の愛人と思しき若い少女らが被写体として収められていた。どれもこれも情事中のものだろう。性行為に励んでいる中年の顔と、父の普段の顔を思い浮かべてみた。思わず口元を押さえた。少女たちはどれも自分とそう変わらないくらいの年代、或いはそれよりももっと下かもしれない。下手をすると、月経もまだ訪れていないような面立ちの世代もいた。
←前 次→
TOP▼
この辺はエレウシス読者はピンとくるかもね。
でも母親も可哀想な女性だ、
この父親は多分まあ何かヤクザ屋さんとか
極道とかパイプのあるそっち系なんでしょうけど
その妻になった奥さんも、年々女としての
魅力を失くしていく自分に怯えながら
権力のある夫に捨てられたくないから必死に
黙認してたんだろうなあ。そりゃ狂うわ。