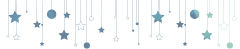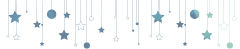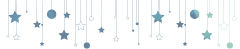
優しくなんてしないでほしい(貞)
僕とシンジ君が付き合い始めてそろそろ1ヶ月になる。とは言っても元々から僕達は友達で一緒にいることが多かったから、恋人に昇格したあとも僕達の関係性に大きな変化はない。
でも少し変わったこともある。シンジ君が毎日僕のお弁当を作ってくれるようになった。放課後も休みもシンジ君と過ごすことが当たり前になった。
人目を忍んで、キスをするようになった。
「キス」と言えば苦いエピソードがある。初めてシンジ君とキスをしたときのことだ。僕はとても緊張していて、口唇を合わせるつもりだったのに気づいたらシンジ君に盛大に頭突きをしてしまっていた。シンジ君は涙目になって、それでも許してくれて、でもシンジ君が痛いのは嫌だから、それ以来僕はキスには細心の注意を払っている。
シンジ君が好きすぎてすぐに我を忘れてしまう僕は、その余裕の無さゆえにシンジ君を大事にできない。それでも僕と付き合ってくれるシンジ君を大切にしたいんだ。
それなのに気持ちばかり空回ってて、それがとても悔しい。
昼休み、校舎の屋上でいつものようにシンジ君のお手製弁当を食べた。今日は僕が大好きなタコさんウインナーが入っていて、シンジ君の深い愛情をウインナーと一緒に噛み締めた。僕の身体はシンジ君の温かい思いやりで満たされている。
「渚…」
僕が空っぽになったお弁当箱をしまっていると、シンジ君が僕の肩にコツンともたれ掛かってきた。
いつものつっけんどんなシンジ君とは違う、甘えるような仕草。クラスメイト達の前では僕に対してとてもクールなシンジ君は、最近二人きりになるとキュートになる。
ツンとしたシンジ君と可愛いシンジ君の両方を知っているのは僕だけで、それがとても嬉しい。
「どうしたの、シンジ君?」
お弁当箱を脇に置いてシンジ君を抱き寄せると、シンジ君が甘い匂いを振り撒いて僕にすり寄ってきた。そっと目を閉じたシンジ君はどうやらキスをねだっているようだ。
初めての時の苦い失敗を繰り返さないように僕はじりじりとシンジ君との距離を詰めて彼の薄桃色の口唇に触れるだけのキスをした。そしてそのまま僕が口唇を離そうとすると、突然シンジ君の手が僕の頭の後ろに回された。
「し、シンジ君?」
驚きのあまり僕の声が上ずる。だが困惑する僕に構わずシンジ君が僕にキスを仕掛けた。何度も触れるシンジ君の口唇は火傷しそうなほど熱い。繰り返されるキスに理性が飛びそうになった僕は懸命に身体に溜まってい熱をやり過ごす努力をする。
そんな僕をじっと見つめてシンジ君は少し悲しそうな顔をした。
「…優しくなんてしないでほしいんだ、渚。」
僕の背中に回されたままのシンジ君の腕が震えている。それがなぜなのか、僕には分からない。
「でも、でもでもシンジ君。僕はシンジ君を大事にしたいよ?」
「バカ、渚…」
なかなか上手にできないけれど、シンジ君のことを誰よりも一番大切にしたいと伝えたつもりだったのにシンジ君は不機嫌そうに頬を膨らませた。
「渚となら痛いのも激しいのも、いいかなって思ったんだよ。」
そう言ってそっぽを向くシンジ君。シンジ君の言葉の真意を測りかねて、押し黙ってしまった僕の耳をシンジ君はぐいっと引っ張った。
「いつまでも触れるだけのキスじゃもどかしい…渚はそう思わないの?」
「それは…僕だってシンジ君ともっともっと色んなことしたいよ!したいけど、でも…僕、キスも満足にできなかったし…」
もにょもにょと口ごもるとシンジ君に頭をはたかれてしまった。
「キスだってなんだってひとりで頑張って上手くできるものじゃない…渚ばっかり悩むんじゃなくて僕も一緒に考えさせてよ、お互いが気持ちよくなれる方法をさ。僕達恋人なんだろ?」
晴れやかに笑うシンジ君が、そんなシンジ君がくれる優しさが、僕の気負いを押し流してくれる。
お互いに支え合って協力し合えばきっともっといい関係になれるんだ。
「シンジ君、もっとキスしてもいい?」
僕が尋ねると、シンジ君は頷く代わりにそっと瞳を閉じた。
‐おしまい‐
++++++++++++++++++++
渚って気持ちばかりが先行して不器用なんだろうなーという妄想から生まれました。でもシンジ君は渚の不器用さが嫌いではなくて、むしろ愛おしさを感じているのです。
back