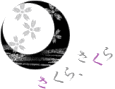また、幼馴染の夢を見た。戻って来い、と必死になって手を伸ばしてくれている蒼空の夢だ。
――蒼空…。
逢いたい。伸ばされた手を掴みたいと心の底から思う。
――でも…。
何か違う。
足りない。
隣にはもうひとり、幼馴染がいたはずだ。
なのに、
「………、」
名前が分からない。顔も声も思い出せない。存在が、思い出せない。
蒼空もそうだった。なのに、ある日突然思い出した。まるで、翔流の死と引き換えたかのように。
「だって、蒼空は…、」
――さくら、戻って来い!!
戻りたい。
でも、戻れない。
迷子になりそうな魂を、放ってはおけないよ…。
・
・
月の光だけが射しこむ塔の部屋。開かない窓辺で丸い月を見上げていたさくらは、ふと手に握りしめていた花の首飾りを月光にかざした。
キラキラと花の上で反射する月の光は、闇の中でまるで生きているかのように踊る。この桜の花は、きっと池のほとりのあの桜なのだろう。なぜか、それがさくらには分かる。
これを手にしたときに、知るはずのない楓姫の記憶が流れ込んできた。楓姫の魂はこの枯れることも朽ちることもない、時を止めた桜の花と同化てしまったのかもしれない。だから、桜の種…、さくらの手に触れて楓姫の記憶が放出したのかもしれない。
そんなことを考えていた時、部屋の扉が静かに開き、こつこつと足音を響かせた疾風がさくらの傍に来た。
「そなたに、渡さねばならないものがある」
疾風は手にしているものをさくらに差し出した。
「これ…っ!?」
「翔流の手がずっとこれを握っていたらしい」
「じゃあ、翔流はこれを小屋に取りに行ったの?」
「そうなのだろう…。なぜこんなものを、とも思うが、あれにとっては大切なものだったのだろうな」
さくらが疾風から受け取ったのは裂けた衣だ。
「これ、繕ってあげようとして失敗したの。ここの前と後ろを縫い合わせちゃって手が通らなくなって、翔流にすごく笑われた。記念に残しておきたいとまで言われたわ…」
小屋を出る前夜にどうしても直したくなった。だが、縫い合わせた糸をほどきかけのまま、結局直せずにそのまま小屋に置いてきてしまったのだ。
「翔流…。こんなものを取りに行って…っ」
衣を抱きしめると翔流の匂いがして、たちまちさくらの涙腺は崩壊してしまう。こんなもののために翔流は死んでしまったのかと思うと、やっぱりやりきれなくなる。
だが。
「なるほどな…。翔流がこれをそれほどまでに大切に想ったのが分かる気がする」
「……え?」
「そなたとの些細なことが、あれにとっては何よりもの至福だったのだろう」
この衣はその象徴。
「翔流にはそのようなものがあってよかった。これは命を懸けるに値するものだ…」
「疾風…」
翔流を羨むような疾風の言葉はさくらの胸にせつなく染み込んだ。さくらは涙を拭い、手のひらに乗せた花の首飾りを疾風の目の前にそっと差し出した。
「これを見て、疾風」
言われるままにさくらの手のひらに視線を落とした疾風は、やがて漆黒の瞳をこれ以上ないほど見開いた。
「――まさか…!?これは楓とともに海の底に沈んだはずでは…。そなた、どこでこれを…!?」
「寝台の下。奥の方に落ちていたの」
「寝台の下に…?何故…っ!」
さくらは疾風の手のひらに首飾りをそっと乗せる。
「いつか私の傷を読んだみたいにその首飾りを読んで…。きっと楓姫の記憶が見えると思うから」
「楓の記憶…?そなたは見たのか。思い出したのか…!?」
さくらはゆっくりと頷いて、そのあとに首を振った。
「でも、楓姫の記憶は楓姫のもの。私の記憶ではないわ」
「――っ!?」
「早く…、あなたの知らない楓姫を見てあげて」
疾風は首飾りを手の中に包むようにして握りしめた。
◇
床にがくりと膝をついた疾風は、長い銀色の髪を垂らして俯く。漆黒の瞳から滴る銀の雨がぽつりぽつりと床に染みを作った。
「楓は、自害したのではなかったのだな…」
「そうよ…」
「俺を、憎んではいなかったのだな…」
「愛していたのよ。ずっと、疾風だけを」
「く…っ」
想い合っていながら口にすることができなかったのは、互いに背負う“国”があったからだ。七晩の交わりがあっても尚、愛だけは言葉にできず、時を止めた花に込めた疾風の愛を守りたいがために死んだ楓の想いに触れて、疾風は堪えきれない嗚咽をもらし、肩を震わせる。枯れることも朽ちることもない永久の花が、疾風の手のひらからするりと床に落ちた。
「そなたの言うとおり、捧げなどしなければ…、いや、術など使えなければ俺は…」
「疾風…っ」
さくらはうなだれる疾風の頭を胸の中に抱きしめた。
「何かを失うたびに考えた。捧げなどしなければと…!民のため捧げている俺が、己を惜しんでそう考えてしまうことが情けなくてたまらなかった…!だから、誰に止めるよう乞われても決して止めなかった…!だが、今ほど悔いたことはない…。俺は…、俺は…!」
捧げさえしなければ、病もなく、種を失うこともなく、愛する人と共に長い人生を生きられた。そのすべてを捧げてもいいと、本当に思っていたのだろうか。領家に生まれつき、術を扱える最後の術士であったから、自分が民を守らなければと、15の幼い頃に過剰に使命感を募らせてしまったのは事実なのだ。
「捧げは偽善だったのだ…」
「疾風!そんなことは言わないで!」
「だが、事実だ!」
「違うわ!偽善で自分のすべては捧げられない!疾風は心から領民の幸せを願ったのよ!」
「………だが!」
「楓姫は思っていたわ。たとえ疾風に余命がなくても子どもが出来なくても、命ある限り疾風の傍で疾風を支えて生きていきたいって…。民のために捧げをする疾風のことを、ちゃんと分かっていたからこそ楓姫はそう思ったはずよ…!だからお願い…。後悔なんてしないで、これからのことを考えて」
「……姫」
「姫じゃないわ…。疾風も、もう分かっているでしょ?いいえ、あなたはきっと初めから分かっていた…」
捧げの術は、すべてを捧げてこその効果なのだから。
「………俺は、楓を喚ぶこともできなかったのだな…」
願うことはすべて退けられ、なにひとつ叶わない――。
「咎だけが重い…」
さくらは腕に力をこめて疾風を抱きしめる。
「楓姫の魂はきっと自分で疾風の傍に還ってくるわ。あんなに純粋に疾風のことを想っていたのだから」
「………そなたは優しいな。だが、俺は楓には逢えないだろう…」
いつか楓の魂が生まれ変わり還ったとしても、その時自分はもういない。さくらを召喚したことにより己の魂を消耗し、欠片も遺さずに滅する魂は転生も叶わないのだ。今世でも来世でも、楓の魂と再び逢うことは叶わない。
「最後の最後まで俺は咎を重ねて朽ちるだけなのだ…」
「疾風…」
さくらが何を言っても、何をしても、疾風を癒してあげることはおそらくできない。
だが、傷ついた孤独なこの人を、何もせずに見ているだけなどできないのだ。ほんの少しでもいいから疾風の心を軽くしたい。今の疾風は保護者のいない子どものように頼りなくて無力だから。
「疾風…。元気を出して…」
さくらは疾風の銀髪をいたわるように撫でた。
「今まで独りでよく頑張ってきたね…。疾風は立派な領主だって思う」
「…!?」
疾風が顔を上げてさくらを見つめる。慈愛に溢れた優しい眼差しがさくらから自分に注がれていることを知った疾風は、全身から険や力が抜けていくのを感じた。
「…姫」
髪に触れるさくらの手が優しくて心地好い。さくらの胸に顔を埋めれば、柔らかなふくらみと花のような香りが疾風を無条件に包む。
「私が楓姫の代わりに最後まで傍にいる…。疾風がこれ以上寂しくならないように傍にいる。だから…」
もう泣かないで、とさくらは疾風をぎゅっと抱きしめた。
「……ひ…めっ」
これまでさんざんに奪い尽くしてきたというのに、この姫はなんて優しい言葉を紡ぐのだろうか。
「何を言う…。そなたの心には翔流しかいないのだろう」
愛しているのは翔流ひとり。
それは変わらない。
でも――。
「……もう翔流はこの世のどこにもいないと知った時、どんな翔流でもいいからもう一度逢いたいって心の底から思ったわ」
「どんな翔流でも…」
夢でも幻でも、生まれ変わりでも――。
「楓姫を取り戻したかった疾風の気持ちがよく分かったの…。私は楓姫じゃない。でも、同じ気持ちの疾風を放っておけない。余命がない定めなら、その命尽きるまで傍にいる。あなたの癒しになりたいと思う」
「―――っ」
ずっと遠ざけてきた“甘え”が、今、赦されている。これこそがおそらく、疾風が心の底から望み求めていたことだ。無条件に甘えられる、それが許される居場所を得ること。
疾風は膝をついたまま、さくらの胸に頬を擦りよせた。
「あぁ……、姫…」
なんと優しい匂いだろうか。
なんと温かな感触だろうか。
疾風は赤子が母親の乳首を探すように衣の上から頬ずり、唇を動かした。だが、最後は手でまさぐって求める其れにたどり着いた。
衣からぽろりと零れた片方の乳房を夢中になって吸う疾風は幼子のようだ。
さくらは疾風を抱く腕に力を込めて乳房を与え、やがてもう片方の乳房にも疾風の手がたどたどしく触れてくる。
さくらは疾風の銀髪に頬を摺り寄せた。何度も、何度も。
窓の下。
月の灯りに照らされるのは、立ったまま前かがみに乳房を解放するさくらと、床に膝をつきそれにしゃぶりつく疾風。
「疾風…」
母の温もりを求める幼子と、我が子に無償の愛を注ぐ母親のように。
「そなたに触れるのは…、幾日ぶりだろうか…」
掠れた声で疾風が囁いた。
「私であなたを癒せるなら…、思うままに触れて…」
さくらは心からの言葉を囁き返す。15才の時から国と民の命運を独りで背負ってきた疾風には、弱音をさらけ出し甘えられる場所が必要だったのだ。望むものすべてを奪われてしまってからは、ますます“癒し”が必要だった。
今、自分が疾風にとってのそんな存在になれるなら。
それで疾風が、残りの命を自分も含めた松風の幸せのために使えるのなら。
「……っ、姫――っ」
これは、淫らな交わりではない。傷ついた幼子を慰めたいと願う、母性からの行為。母の乳房ほど、幼子を癒せるものはないのだから。
なのに。
「さくら…」
「――!!」
こんな時に、疾風は初めて呼ぶさくらの名を声に乗せたのだ。
「は…やて…?」
これまで一度も名を呼んだことなどなかったのに。
「さくら…、さくら……っ」
しなやかな指で、濡れた唇で、弱々しく乳房を弄りながら何度もさくらと。
やっぱり狡い男だ。
こんな時にそんなふうにせつなく、求めるように名を呼ばれたら、抱きしめるこの腕を放せなくなってしまう。母性だけの行為ではすまなくなってしまう――。
「疾風…!」
さくらの涙が乳房を弄る疾風の手の甲に落ちた時。
「さくら――っ」
心の底から手を伸ばすような声で名を呼んだ疾風が、さくらの顔を自分に引き寄せ唇を重ねた。
深く。
激しく。
――蒼空…。
逢いたい。伸ばされた手を掴みたいと心の底から思う。
――でも…。
何か違う。
足りない。
隣にはもうひとり、幼馴染がいたはずだ。
なのに、
「………、」
名前が分からない。顔も声も思い出せない。存在が、思い出せない。
蒼空もそうだった。なのに、ある日突然思い出した。まるで、翔流の死と引き換えたかのように。
「だって、蒼空は…、」
――さくら、戻って来い!!
戻りたい。
でも、戻れない。
迷子になりそうな魂を、放ってはおけないよ…。
・
・
月の光だけが射しこむ塔の部屋。開かない窓辺で丸い月を見上げていたさくらは、ふと手に握りしめていた花の首飾りを月光にかざした。
キラキラと花の上で反射する月の光は、闇の中でまるで生きているかのように踊る。この桜の花は、きっと池のほとりのあの桜なのだろう。なぜか、それがさくらには分かる。
これを手にしたときに、知るはずのない楓姫の記憶が流れ込んできた。楓姫の魂はこの枯れることも朽ちることもない、時を止めた桜の花と同化てしまったのかもしれない。だから、桜の種…、さくらの手に触れて楓姫の記憶が放出したのかもしれない。
そんなことを考えていた時、部屋の扉が静かに開き、こつこつと足音を響かせた疾風がさくらの傍に来た。
「そなたに、渡さねばならないものがある」
疾風は手にしているものをさくらに差し出した。
「これ…っ!?」
「翔流の手がずっとこれを握っていたらしい」
「じゃあ、翔流はこれを小屋に取りに行ったの?」
「そうなのだろう…。なぜこんなものを、とも思うが、あれにとっては大切なものだったのだろうな」
さくらが疾風から受け取ったのは裂けた衣だ。
「これ、繕ってあげようとして失敗したの。ここの前と後ろを縫い合わせちゃって手が通らなくなって、翔流にすごく笑われた。記念に残しておきたいとまで言われたわ…」
小屋を出る前夜にどうしても直したくなった。だが、縫い合わせた糸をほどきかけのまま、結局直せずにそのまま小屋に置いてきてしまったのだ。
「翔流…。こんなものを取りに行って…っ」
衣を抱きしめると翔流の匂いがして、たちまちさくらの涙腺は崩壊してしまう。こんなもののために翔流は死んでしまったのかと思うと、やっぱりやりきれなくなる。
だが。
「なるほどな…。翔流がこれをそれほどまでに大切に想ったのが分かる気がする」
「……え?」
「そなたとの些細なことが、あれにとっては何よりもの至福だったのだろう」
この衣はその象徴。
「翔流にはそのようなものがあってよかった。これは命を懸けるに値するものだ…」
「疾風…」
翔流を羨むような疾風の言葉はさくらの胸にせつなく染み込んだ。さくらは涙を拭い、手のひらに乗せた花の首飾りを疾風の目の前にそっと差し出した。
「これを見て、疾風」
言われるままにさくらの手のひらに視線を落とした疾風は、やがて漆黒の瞳をこれ以上ないほど見開いた。
「――まさか…!?これは楓とともに海の底に沈んだはずでは…。そなた、どこでこれを…!?」
「寝台の下。奥の方に落ちていたの」
「寝台の下に…?何故…っ!」
さくらは疾風の手のひらに首飾りをそっと乗せる。
「いつか私の傷を読んだみたいにその首飾りを読んで…。きっと楓姫の記憶が見えると思うから」
「楓の記憶…?そなたは見たのか。思い出したのか…!?」
さくらはゆっくりと頷いて、そのあとに首を振った。
「でも、楓姫の記憶は楓姫のもの。私の記憶ではないわ」
「――っ!?」
「早く…、あなたの知らない楓姫を見てあげて」
疾風は首飾りを手の中に包むようにして握りしめた。
◇
床にがくりと膝をついた疾風は、長い銀色の髪を垂らして俯く。漆黒の瞳から滴る銀の雨がぽつりぽつりと床に染みを作った。
「楓は、自害したのではなかったのだな…」
「そうよ…」
「俺を、憎んではいなかったのだな…」
「愛していたのよ。ずっと、疾風だけを」
「く…っ」
想い合っていながら口にすることができなかったのは、互いに背負う“国”があったからだ。七晩の交わりがあっても尚、愛だけは言葉にできず、時を止めた花に込めた疾風の愛を守りたいがために死んだ楓の想いに触れて、疾風は堪えきれない嗚咽をもらし、肩を震わせる。枯れることも朽ちることもない永久の花が、疾風の手のひらからするりと床に落ちた。
「そなたの言うとおり、捧げなどしなければ…、いや、術など使えなければ俺は…」
「疾風…っ」
さくらはうなだれる疾風の頭を胸の中に抱きしめた。
「何かを失うたびに考えた。捧げなどしなければと…!民のため捧げている俺が、己を惜しんでそう考えてしまうことが情けなくてたまらなかった…!だから、誰に止めるよう乞われても決して止めなかった…!だが、今ほど悔いたことはない…。俺は…、俺は…!」
捧げさえしなければ、病もなく、種を失うこともなく、愛する人と共に長い人生を生きられた。そのすべてを捧げてもいいと、本当に思っていたのだろうか。領家に生まれつき、術を扱える最後の術士であったから、自分が民を守らなければと、15の幼い頃に過剰に使命感を募らせてしまったのは事実なのだ。
「捧げは偽善だったのだ…」
「疾風!そんなことは言わないで!」
「だが、事実だ!」
「違うわ!偽善で自分のすべては捧げられない!疾風は心から領民の幸せを願ったのよ!」
「………だが!」
「楓姫は思っていたわ。たとえ疾風に余命がなくても子どもが出来なくても、命ある限り疾風の傍で疾風を支えて生きていきたいって…。民のために捧げをする疾風のことを、ちゃんと分かっていたからこそ楓姫はそう思ったはずよ…!だからお願い…。後悔なんてしないで、これからのことを考えて」
「……姫」
「姫じゃないわ…。疾風も、もう分かっているでしょ?いいえ、あなたはきっと初めから分かっていた…」
捧げの術は、すべてを捧げてこその効果なのだから。
「………俺は、楓を喚ぶこともできなかったのだな…」
願うことはすべて退けられ、なにひとつ叶わない――。
「咎だけが重い…」
さくらは腕に力をこめて疾風を抱きしめる。
「楓姫の魂はきっと自分で疾風の傍に還ってくるわ。あんなに純粋に疾風のことを想っていたのだから」
「………そなたは優しいな。だが、俺は楓には逢えないだろう…」
いつか楓の魂が生まれ変わり還ったとしても、その時自分はもういない。さくらを召喚したことにより己の魂を消耗し、欠片も遺さずに滅する魂は転生も叶わないのだ。今世でも来世でも、楓の魂と再び逢うことは叶わない。
「最後の最後まで俺は咎を重ねて朽ちるだけなのだ…」
「疾風…」
さくらが何を言っても、何をしても、疾風を癒してあげることはおそらくできない。
だが、傷ついた孤独なこの人を、何もせずに見ているだけなどできないのだ。ほんの少しでもいいから疾風の心を軽くしたい。今の疾風は保護者のいない子どものように頼りなくて無力だから。
「疾風…。元気を出して…」
さくらは疾風の銀髪をいたわるように撫でた。
「今まで独りでよく頑張ってきたね…。疾風は立派な領主だって思う」
「…!?」
疾風が顔を上げてさくらを見つめる。慈愛に溢れた優しい眼差しがさくらから自分に注がれていることを知った疾風は、全身から険や力が抜けていくのを感じた。
「…姫」
髪に触れるさくらの手が優しくて心地好い。さくらの胸に顔を埋めれば、柔らかなふくらみと花のような香りが疾風を無条件に包む。
「私が楓姫の代わりに最後まで傍にいる…。疾風がこれ以上寂しくならないように傍にいる。だから…」
もう泣かないで、とさくらは疾風をぎゅっと抱きしめた。
「……ひ…めっ」
これまでさんざんに奪い尽くしてきたというのに、この姫はなんて優しい言葉を紡ぐのだろうか。
「何を言う…。そなたの心には翔流しかいないのだろう」
愛しているのは翔流ひとり。
それは変わらない。
でも――。
「……もう翔流はこの世のどこにもいないと知った時、どんな翔流でもいいからもう一度逢いたいって心の底から思ったわ」
「どんな翔流でも…」
夢でも幻でも、生まれ変わりでも――。
「楓姫を取り戻したかった疾風の気持ちがよく分かったの…。私は楓姫じゃない。でも、同じ気持ちの疾風を放っておけない。余命がない定めなら、その命尽きるまで傍にいる。あなたの癒しになりたいと思う」
「―――っ」
ずっと遠ざけてきた“甘え”が、今、赦されている。これこそがおそらく、疾風が心の底から望み求めていたことだ。無条件に甘えられる、それが許される居場所を得ること。
疾風は膝をついたまま、さくらの胸に頬を擦りよせた。
「あぁ……、姫…」
なんと優しい匂いだろうか。
なんと温かな感触だろうか。
疾風は赤子が母親の乳首を探すように衣の上から頬ずり、唇を動かした。だが、最後は手でまさぐって求める其れにたどり着いた。
衣からぽろりと零れた片方の乳房を夢中になって吸う疾風は幼子のようだ。
さくらは疾風を抱く腕に力を込めて乳房を与え、やがてもう片方の乳房にも疾風の手がたどたどしく触れてくる。
さくらは疾風の銀髪に頬を摺り寄せた。何度も、何度も。
窓の下。
月の灯りに照らされるのは、立ったまま前かがみに乳房を解放するさくらと、床に膝をつきそれにしゃぶりつく疾風。
「疾風…」
母の温もりを求める幼子と、我が子に無償の愛を注ぐ母親のように。
「そなたに触れるのは…、幾日ぶりだろうか…」
掠れた声で疾風が囁いた。
「私であなたを癒せるなら…、思うままに触れて…」
さくらは心からの言葉を囁き返す。15才の時から国と民の命運を独りで背負ってきた疾風には、弱音をさらけ出し甘えられる場所が必要だったのだ。望むものすべてを奪われてしまってからは、ますます“癒し”が必要だった。
今、自分が疾風にとってのそんな存在になれるなら。
それで疾風が、残りの命を自分も含めた松風の幸せのために使えるのなら。
「……っ、姫――っ」
これは、淫らな交わりではない。傷ついた幼子を慰めたいと願う、母性からの行為。母の乳房ほど、幼子を癒せるものはないのだから。
なのに。
「さくら…」
「――!!」
こんな時に、疾風は初めて呼ぶさくらの名を声に乗せたのだ。
「は…やて…?」
これまで一度も名を呼んだことなどなかったのに。
「さくら…、さくら……っ」
しなやかな指で、濡れた唇で、弱々しく乳房を弄りながら何度もさくらと。
やっぱり狡い男だ。
こんな時にそんなふうにせつなく、求めるように名を呼ばれたら、抱きしめるこの腕を放せなくなってしまう。母性だけの行為ではすまなくなってしまう――。
「疾風…!」
さくらの涙が乳房を弄る疾風の手の甲に落ちた時。
「さくら――っ」
心の底から手を伸ばすような声で名を呼んだ疾風が、さくらの顔を自分に引き寄せ唇を重ねた。
深く。
激しく。