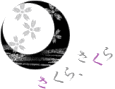りんご飴に金魚すくい。
とうもろこしに射的の屋台。
太鼓と笛の祭囃子が響く人ごみの中で。
『黒じゃなくてピンクのがよかったのに……』
『ピンクでも黒でもたいして変わらないだろ』
『ちがうよ。ピンクと黒はぜっんぜんちがう』
『水風船には変わらないだろ』
『変わるもん…。黒いのは可愛くないもん』
『可愛くないの釣って、悪かったな』
『わざと黒いの釣ったくせに…。隣にピンクのあったのに…』
『わ、わざとじゃないって…。間違えただけだよ』
『うそだもん…。意地悪したんだもん…。わたしのことキライだから、わざと意地悪したんだもん…っ』
『ま、待てよ!キライなんて言ってないだろ!』
『………』
『おい!さくら!戻って来い!』
(追いかけてくれて、しっかりと捕まえてくれた手――)
なのに、
――さくら、戻って来い…!
(あの時は、どうして手が届かなかったの――?)
――戻って来い…!
(あんなに必死になって手を伸ばしてくれたのに…!)
――さくら、戻って来い!!!
・
・
はっと目を開けたさくらの頭は混乱していた。今見た夢はさくらがいた元の世界の夢だ。そして、祭りに一緒にいった男の子は幼馴染の――、
「蒼空…」
この時代に来てから今まで一度も思い出さなかった幼馴染。
「違う…。思い出せなかったんだ…」
名前も顔も存在すらも。
大学の友達のことは思い出せても、いつも一緒にいた幼馴染の顔はぼやけてしまって、それがだんだん薄れて行って、いつの間にか存在を見失っていた。
「どうして急に夢なんて…。それに…、」
戻って来い、と必死になって手を伸ばしていた蒼空は――。
思い出せなかった幼馴染の夢を見て、懐かしいのに胸が騒ぐ。
「だって、蒼空は…!」
鼓動が激しい。
焦燥感が募ってくる。
だが、唐突に扉を叩く音に続いて姫様失礼しますの声に、さくらはこの時代の現実へと引き戻された。入ってきたのは世話係の朔夜だった。
◇
「……疾風は、どうしたの?」
血を吐いた夜から一週間が経ち、あれから疾風がこの塔の部屋に姿を見せないことが気になって、さくらはためらいがちに朔夜に尋ねた。
べつに疾風が来ないことを憂いているわけじゃない。病にかかっているらしい体のことを慮っているだけだ、と何故か自分に言い訳をしながら。
「……っ」
一瞬、朔夜は言葉につまり、だがすぐにいつもの冷静さを取り戻して答えた。
「今、少し多忙になっておいでです」
「なにか、あったの?」
「………いえ」
「病気がひどくなっていたりしてるの?」
「――いえ…、そうではなく…」
朔夜の返答は歯切れが悪い。
今朝、幼馴染の夢を見てから色々なことで胸が騒いで仕方がない。
この塔の部屋からは西側の海しか見渡せない。部屋を出ることができないさくらには外の様子がまったく分からない。戦がどうなっているのかも、翔流が無事でいるのかも、この部屋に来る時以外の疾風が何をしているのかも、何も知らないのだ。
「翔流が戦に出てからもうずいぶん経つけど、軍はまだ帰ってこられないの?」
「………そのことについては、姫様には何も話してはいけないと疾風様に言われています」
「どうして…!?戦が気になるのは当たり前よ!翔流が心配なの…!」
朔夜は苦しそうに顔を曇らせる。そんな朔夜の様子は、さくらにますます焦燥感を募らせた。
「お願い。私にちゃんと教えて。戦のことも、それから疾風の病気のことも…!」
「……申し訳ありません」
朔夜は悲しそうに首を振った。
「疾風様の言いつけに背くことはできません。ですが、姫様が心配なされるようなことは何もありません。疾風様は松風の領主ですから、時にはこのように多忙に見舞われることもあるのです」
それだけです、と朔夜は微笑むがさくらには納得できない。
心がざわざわするのだ。
だが朔夜はそれ以上何を訊いても答えてはくれなかった。
そして。
さくらの不安は翌日になってさらに大きなものに膨らんだ。いつもなら日が昇るとやってくる朔夜までが、今日は午後になっても来ないからだ。
絶対に何かあったのだ。朔夜が来られないくらいに大変なことが。
だが、こんな塔の上にいては城の様子など何も届かない。
せめて城の中がどのようになっているのかだけでも知りたいと、いても立ってもいられなくなったさくらは、ひとりで寝台から出ることにした。
疾風が苦しんでいた時は、卓上の水差しを取りに行けたのだ。扉のところまで行くことが出来たら、何か聞こえてくるかもしれない。
だが。
「痛っい…っ」
気が焦っているからか、今日は寝台から豪快に転げ落ちてしまった。床の上にうつ伏せに倒れたさくらは、打ち付けた腰をさすりながら寝台の縁に掴まろうと手を伸ばした。
その時、寝台の下にキラリと光るものを見た気がしてさくらはもう一度うつ伏せになって下を覗いた。
「なに…?」
確かに、寝台の下で何かがキラキラしている。潜れるほどの隙間はないからめい一杯手を伸ばしてそれを取ろうとする。
「あと、少し…っ、届いた…!」
鎖のようなものに手が届いて引っ張って引き寄せると。
「綺麗…。ペンダント?」
それは白の中に薄紅色が滲んだ花の形をした首飾りだった。
「この花…、」
よく見ると、花は造花ではなく生花だ。
「桜の花…?」
だがまるで時を止めたように鮮やかなまま触っても握っても崩れたりしないほど固まっている。不思議で思わずじっと見入っていると、ふいに胸がどくんと跳ねた。
「痛い…っ」
どくんどくん、とまるで激しい動悸に襲われたかのように心臓が跳ねる。
いつかの疾風のように胸を押さえてうずくまった時、胸の奥の奥、一番深いところから切ない想いが吹き出し高波のようにさくらに押し寄せたのだ。