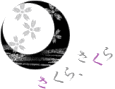『かけるは面白いことを考えるのね。あきづきに水を入れるなんて誰も思いつかないわ』
『そうだろう?こんなことはオレしか思いつかない』
『翔流はそなたを喜ばそうと、いつも変なことばかり考えているんだ』
『変なことって、ひどいや兄上!』
『でも、それなら私はとても喜んでるわ!だって、すごくきれいだもの!』
『だけど姫…。これにはちょっと欠点があって…』
姫が死んでから今まで振り返ることが出来なかった子どもの頃の思い出。
あまりにも無邪気すぎたあの頃が胸に痛くて。
「………」
思い出に浸る翔流を、さくらは何も言わずに見つめていた。夕焼けはだんだんと薄れていき、茜色は藍色に覆われようとしている。辺りが暗くなってきたことに気が付いた翔流がやっと我に返って、黙って自分を見つめていたさくらに目を向けた。
「すまない。ぼんやりしてしまった」
さくらは首を横に振って微笑んだ。
「幼馴染の人のことを思い出していたの?」
「ああ……」
「その人のこと好きだったの…?」
「……ああ」
物心がついた時にはもう姫のことを好いていた。幼い頃は姫をめぐって兄と張り合い、どうにかして姫の気を自分に向かせようともした。兄は花など綺麗なもので姫の気を引いたが、翔流はどちらかといえば体を使うことを得意とした。だが姫は女の子だ。翔流のやんちゃにそうそう付き合えはしない。だから良かれと思ってしたことが裏目に出ることが多かった。
そんな翔流が唯一、姫に綺麗だと喜んでもらえたのが水を入れたあきづきだった。
「…今もその人が好き?」
翔流はゆっくりと首を振って笑った。
「もういない」
「……え?」
「遠くに行ってしまったからな」
何かが狂い始めたのは、姫との政略結婚が決まってからだった。
なぜなら、
――姫が本当に愛していたのは俺ではない…。
それを知っていながら婚約をしてしまったのは、幼いころから好きだった人を妻にできるという、思いがけず自分に巡ったその好機に手を伸ばしてしまったからだ。
『翔流に嫁ぐように言われたの…。翔流は私で、いい――?』
あの問いの中には、姫の助けを求める心が投入されていたというのに。
『俺は、そなたを妻にできることを幸せに思う』
そう答えたときの絶望した姫の顔が、それからずっと翔流の迷いになった。
大切に想う人だからこそ、自分ではなく姫が真に愛する人と結ばれるべきではないのかと、婚礼の日取りが決まってからも迷い続けていた。
政略結婚とはそういうもの。思い通りの相手と思い通りの結婚はできないもの。
おそらく姫はそう覚悟をしていたのだろうが、思い通りの相手と結ばれる道が、姫にまったくなかったわけではないから。
だから、婚約を白紙に戻す決意をした。もう婚礼の日は迫っていたが、それでも手遅れになる前に姫に告げようと決意していた。
――なのに…。
まさに、告げようとしたその日に姫は死んでしまった。
絶望を抱いて、自害してしまったのだ。
『翔流に嫁ぐように言われたの…。翔流は私で、いい――?』
あの時に、否と答えていたらそれほどまでに姫を苦しめることはなかった。心のない相手と結婚するということは、姫にとって死に値するほどに辛いことだったのだろう。
姫の死そのものも、姫が死に至った因にも打ちひしがれた。二度と立ち直れないと思うほど、翔流の心は折れてしまったのだ。
思い出は綺麗なことばかりじゃない。綺麗だったものまでも呵責に潰され、思い出すことも赦されない疵になっていた。
だが――。
「翔流…」
翔流の好きな人は、もういない――。
遠い場所へ行ってしまったのか、それとも亡くなってしまったのかは分からないけれど、それが死にたいと思うほどの疵だったのだろうか。
今思えば、出逢ったころの翔流は時々心が痛がっているような悲しげな顔をしていた。
――なんて、つらそう…。
翔流の恋は、きっと悲しいものだったのだ。今、憂う翔流の顔を見ればそれが分かる。
さくらの胸が息苦しさで押しつぶされそうになる。翔流の痛みも、それが好きな人を想っての疵であることもさくらにとってはつらい。つらいことが痛みと感じるほどに、さくらは翔流を……。
ふいに、翔流の手にあるあきづきの水風船がぱちんと割れた。
「………」
「割れちゃったね…」
翔流の衣にこぼれた水をさくらは手で払う。そして、破れたあきづきを手に取って残念そうに見つめた。
「これには、もろい、という欠点があるんだ。薄い袋が長く水に耐えられない」
「でも、見せくれてありがとう」
「さくら…」
あの時、同じことを姫も言った。微笑みながら、見せてくれてありがとう、と。
「ずっと割れずに手元における水秋満月を見せてやれればよかったのだけどな…」
翔流は肩を下げてため息を吐く。
「そんなことない。翔流がそんなふうにがっかりするのがせつないよ。綺麗なあきづきを私に見せてやりたいって思ってくれた翔流の気持ちが一番嬉しいから。翔流が好きだった人も、きっとそう思ったと思う」
「……っ」
「だから、上手く言えないけど…、翔流…」
そんなに心を痛めないで、と胸の中で叫びながら、さくらは一生懸命に笑顔を作る。
何かの想いを必死に届けようとしてくれるさくらがいじらしくて、翔流の胸は熱くなった。
姫が自分に微笑んでいるあの思い出は綺麗なままだ。いや、たった今、苦しいものから綺麗なものになったのかもしれない。姫に関わる過去のこと全てが少しずつ穏やかなものに変わっているのは、さくらと出逢ってからだ。
「木登りをさせたことがあった…」
唐突に語りたくなって翔流は沈みかけた陽を見つめながら言った。
「好きだった、その人を…?」
「ああ。怖がってたが俺が付いているから大丈夫だからと半ば強引に木に登らせて、一緒にこんな夕焼けを見た。見せたかったんだ、木の上から見る夕焼けを」
「その人、夕焼けを見て綺麗だって喜んだでしょ?怖がっていたことなんて忘れて」
「そうだが…。どうして分かった?」
「私だったら、きっとそうだって思ったから」
そうか…、と翔流は微笑んだ。
「だがそのあと、俺はいろんな大人たちにさんざん叱られた」
姫に木登りをさせるなどなんたることと父、兄、そして姫の父にもさんざん絞られた。
「そういえば…、」
あの時も叱られていじけて桜の木の元に行った。ちょうど花が咲き始めた頃だったが、ちらりちらりと咲く桜に向かい叱られた恨み言を呟いた。その後、頭と心を冷やして皆のところに戻ると、
『また一緒に木登りしようね』
と、姫は笑ってくれたが、父や兄はいつまでも怒っていた。
「そして、それ以来木登り禁止になった」
「ふふ。ありがちなオチだね」
「はは。そうだな」
今、こうして思い出として振り返り、さくらに話して懐かしむことができているのが不思議にも思うし、当然とも思う。
姫を失ってからさくらに出逢うまでは確かに死に囚われていた心が、生に向かって解放されていくことに少しの罪悪感はあるとしても、今、自分の心は――。
「翔流…」
さくらは翔流の両頬を両手で包むようにそっと触れた。
「さくら…?何故こんなこと…?」
「さっきから翔流が痛そうだから…。つらいの、我慢しないでね」
「……ッ」
「私にできること、ないのかな…?翔流がそんな顔しなくてもいいように…、私に、なにかできること…」
「さくら……」
胸に熱い塊がこみ上げてきた翔流は、十分だ、とさくらの両手に自分の手を重ねた。十分すぎるぐらいに、さくらの存在が翔流の疵を癒しているのだから。
「……だが、ひとつだけ希うことを許されるなら、今少し、このままでいてくれないか」
完全な甘えだ。
だが、今しばらく、このままさくらの温もりに触れることを赦されたい。
日を重ねるごとに水が流れるようにさくらに惹かれていく、歯止めのきかないこの心は罪なのかもしれないが、それでも今は。
「うん…、分かった」
素直に頷いて笑うさくらの額に翔流は自分の額をこつん、とぶつけた。
「翔流…っ?」
翔流の顔が近くに来て、さくらの顔に熱が集まっていく。
だが、翔流の顔も赤くなっている。
目と目を合わせてしばらくしてから、翔流は視線を横に外して言った。
「さくらには、いないのか…?」
「え?」
「想い出の中の、好いた男…」
「………たぶん…」
「たぶんとは?」
「翔流に逢うまでのこと…、あまりよく覚えていないの…」
というか、記憶に穴が空いている気がする。大切だと思っていたもの、それだけが抜け落ちているような気がするのは思い違いなのだろうか。
「そうか…。なら、俺がさくらの想い出になれればいい…」
「……かけ…る…」
すっかり日が沈んでしまってからも、ふたりは額をくっつけあい、互いの温もりを希うのだった。
『そうだろう?こんなことはオレしか思いつかない』
『翔流はそなたを喜ばそうと、いつも変なことばかり考えているんだ』
『変なことって、ひどいや兄上!』
『でも、それなら私はとても喜んでるわ!だって、すごくきれいだもの!』
『だけど姫…。これにはちょっと欠点があって…』
姫が死んでから今まで振り返ることが出来なかった子どもの頃の思い出。
あまりにも無邪気すぎたあの頃が胸に痛くて。
「………」
思い出に浸る翔流を、さくらは何も言わずに見つめていた。夕焼けはだんだんと薄れていき、茜色は藍色に覆われようとしている。辺りが暗くなってきたことに気が付いた翔流がやっと我に返って、黙って自分を見つめていたさくらに目を向けた。
「すまない。ぼんやりしてしまった」
さくらは首を横に振って微笑んだ。
「幼馴染の人のことを思い出していたの?」
「ああ……」
「その人のこと好きだったの…?」
「……ああ」
物心がついた時にはもう姫のことを好いていた。幼い頃は姫をめぐって兄と張り合い、どうにかして姫の気を自分に向かせようともした。兄は花など綺麗なもので姫の気を引いたが、翔流はどちらかといえば体を使うことを得意とした。だが姫は女の子だ。翔流のやんちゃにそうそう付き合えはしない。だから良かれと思ってしたことが裏目に出ることが多かった。
そんな翔流が唯一、姫に綺麗だと喜んでもらえたのが水を入れたあきづきだった。
「…今もその人が好き?」
翔流はゆっくりと首を振って笑った。
「もういない」
「……え?」
「遠くに行ってしまったからな」
何かが狂い始めたのは、姫との政略結婚が決まってからだった。
なぜなら、
――姫が本当に愛していたのは俺ではない…。
それを知っていながら婚約をしてしまったのは、幼いころから好きだった人を妻にできるという、思いがけず自分に巡ったその好機に手を伸ばしてしまったからだ。
『翔流に嫁ぐように言われたの…。翔流は私で、いい――?』
あの問いの中には、姫の助けを求める心が投入されていたというのに。
『俺は、そなたを妻にできることを幸せに思う』
そう答えたときの絶望した姫の顔が、それからずっと翔流の迷いになった。
大切に想う人だからこそ、自分ではなく姫が真に愛する人と結ばれるべきではないのかと、婚礼の日取りが決まってからも迷い続けていた。
政略結婚とはそういうもの。思い通りの相手と思い通りの結婚はできないもの。
おそらく姫はそう覚悟をしていたのだろうが、思い通りの相手と結ばれる道が、姫にまったくなかったわけではないから。
だから、婚約を白紙に戻す決意をした。もう婚礼の日は迫っていたが、それでも手遅れになる前に姫に告げようと決意していた。
――なのに…。
まさに、告げようとしたその日に姫は死んでしまった。
絶望を抱いて、自害してしまったのだ。
『翔流に嫁ぐように言われたの…。翔流は私で、いい――?』
あの時に、否と答えていたらそれほどまでに姫を苦しめることはなかった。心のない相手と結婚するということは、姫にとって死に値するほどに辛いことだったのだろう。
姫の死そのものも、姫が死に至った因にも打ちひしがれた。二度と立ち直れないと思うほど、翔流の心は折れてしまったのだ。
思い出は綺麗なことばかりじゃない。綺麗だったものまでも呵責に潰され、思い出すことも赦されない疵になっていた。
だが――。
「翔流…」
翔流の好きな人は、もういない――。
遠い場所へ行ってしまったのか、それとも亡くなってしまったのかは分からないけれど、それが死にたいと思うほどの疵だったのだろうか。
今思えば、出逢ったころの翔流は時々心が痛がっているような悲しげな顔をしていた。
――なんて、つらそう…。
翔流の恋は、きっと悲しいものだったのだ。今、憂う翔流の顔を見ればそれが分かる。
さくらの胸が息苦しさで押しつぶされそうになる。翔流の痛みも、それが好きな人を想っての疵であることもさくらにとってはつらい。つらいことが痛みと感じるほどに、さくらは翔流を……。
ふいに、翔流の手にあるあきづきの水風船がぱちんと割れた。
「………」
「割れちゃったね…」
翔流の衣にこぼれた水をさくらは手で払う。そして、破れたあきづきを手に取って残念そうに見つめた。
「これには、もろい、という欠点があるんだ。薄い袋が長く水に耐えられない」
「でも、見せくれてありがとう」
「さくら…」
あの時、同じことを姫も言った。微笑みながら、見せてくれてありがとう、と。
「ずっと割れずに手元における水秋満月を見せてやれればよかったのだけどな…」
翔流は肩を下げてため息を吐く。
「そんなことない。翔流がそんなふうにがっかりするのがせつないよ。綺麗なあきづきを私に見せてやりたいって思ってくれた翔流の気持ちが一番嬉しいから。翔流が好きだった人も、きっとそう思ったと思う」
「……っ」
「だから、上手く言えないけど…、翔流…」
そんなに心を痛めないで、と胸の中で叫びながら、さくらは一生懸命に笑顔を作る。
何かの想いを必死に届けようとしてくれるさくらがいじらしくて、翔流の胸は熱くなった。
姫が自分に微笑んでいるあの思い出は綺麗なままだ。いや、たった今、苦しいものから綺麗なものになったのかもしれない。姫に関わる過去のこと全てが少しずつ穏やかなものに変わっているのは、さくらと出逢ってからだ。
「木登りをさせたことがあった…」
唐突に語りたくなって翔流は沈みかけた陽を見つめながら言った。
「好きだった、その人を…?」
「ああ。怖がってたが俺が付いているから大丈夫だからと半ば強引に木に登らせて、一緒にこんな夕焼けを見た。見せたかったんだ、木の上から見る夕焼けを」
「その人、夕焼けを見て綺麗だって喜んだでしょ?怖がっていたことなんて忘れて」
「そうだが…。どうして分かった?」
「私だったら、きっとそうだって思ったから」
そうか…、と翔流は微笑んだ。
「だがそのあと、俺はいろんな大人たちにさんざん叱られた」
姫に木登りをさせるなどなんたることと父、兄、そして姫の父にもさんざん絞られた。
「そういえば…、」
あの時も叱られていじけて桜の木の元に行った。ちょうど花が咲き始めた頃だったが、ちらりちらりと咲く桜に向かい叱られた恨み言を呟いた。その後、頭と心を冷やして皆のところに戻ると、
『また一緒に木登りしようね』
と、姫は笑ってくれたが、父や兄はいつまでも怒っていた。
「そして、それ以来木登り禁止になった」
「ふふ。ありがちなオチだね」
「はは。そうだな」
今、こうして思い出として振り返り、さくらに話して懐かしむことができているのが不思議にも思うし、当然とも思う。
姫を失ってからさくらに出逢うまでは確かに死に囚われていた心が、生に向かって解放されていくことに少しの罪悪感はあるとしても、今、自分の心は――。
「翔流…」
さくらは翔流の両頬を両手で包むようにそっと触れた。
「さくら…?何故こんなこと…?」
「さっきから翔流が痛そうだから…。つらいの、我慢しないでね」
「……ッ」
「私にできること、ないのかな…?翔流がそんな顔しなくてもいいように…、私に、なにかできること…」
「さくら……」
胸に熱い塊がこみ上げてきた翔流は、十分だ、とさくらの両手に自分の手を重ねた。十分すぎるぐらいに、さくらの存在が翔流の疵を癒しているのだから。
「……だが、ひとつだけ希うことを許されるなら、今少し、このままでいてくれないか」
完全な甘えだ。
だが、今しばらく、このままさくらの温もりに触れることを赦されたい。
日を重ねるごとに水が流れるようにさくらに惹かれていく、歯止めのきかないこの心は罪なのかもしれないが、それでも今は。
「うん…、分かった」
素直に頷いて笑うさくらの額に翔流は自分の額をこつん、とぶつけた。
「翔流…っ?」
翔流の顔が近くに来て、さくらの顔に熱が集まっていく。
だが、翔流の顔も赤くなっている。
目と目を合わせてしばらくしてから、翔流は視線を横に外して言った。
「さくらには、いないのか…?」
「え?」
「想い出の中の、好いた男…」
「………たぶん…」
「たぶんとは?」
「翔流に逢うまでのこと…、あまりよく覚えていないの…」
というか、記憶に穴が空いている気がする。大切だと思っていたもの、それだけが抜け落ちているような気がするのは思い違いなのだろうか。
「そうか…。なら、俺がさくらの想い出になれればいい…」
「……かけ…る…」
すっかり日が沈んでしまってからも、ふたりは額をくっつけあい、互いの温もりを希うのだった。