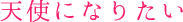
「ご所望のコーヒーです」
「遅い」
「ハイ、すみませんデシタ……」
立ちすくむこちらへ向けられるのは威圧的な瞳、一度捉えられれば並のベータやオメガなら、それに気圧され呼吸すらままならなくなるだろうそれに、彼はすぃっと視線だけを逸らし、口を開いた。
「謝るしか能がない出来損ないが」
「そうでゴザイマスネー」
彼の反応に瞳の圧は数段ましたが、それを気に止めることはせず言葉を続ける。
「蘇芳(スオウ)さん、これ以上言ったら怒りますよ」
柔らかな声が二人の間に割入り、ふとその場の空気を変えた。
「あぁ、悪いね七葉(ナノハ)、君の愚兄とはどうにも馬が合わなくて」
「……それならいちいち俺をパシんのやめてくれますかね」
ボソリと呟けば、またも場の空気は変わる。本当に自分勝手なやつだと呆れにも似た感情を覚えながらも、本音が漏れでないようにキュッと唇を引き結ぶ。
「七葉がお前以外を傍に置くのは嫌だというんだ、仕方ないだろ?」
「いつの話をしているんですか!僕は兄ちゃんに迷惑かけるぐらいなら他の人でいいって言ってるのに……!」
目の前で繰り広げられるどうでもいい会話を聞きながら、彼は購買のパンをひと口齧った。
ただでさえ短くなった大切な昼休みをこれ以上無駄にはしたくないからだ。
本音を言えば今すぐに自分の教室に戻りたいものだが、下手に男の機嫌を損ねる方が面倒なことになると分かっている。
「……い、おい、知種(チグサ)!」
「んぁ?」
知種と呼ばれた彼は最後のひと口を頬張りながら声の主へと視線を移す。
眉間に寄った皺から察するに、まだそこまで苛立っているわけではないらしい。
「マヌケ面め……まぁいい、今日の放課後、七葉を俺の部屋に招く、荷物持ちをしろ」
「俺学校終わったら用事あんだけど」
「それは今後お前の生活を天秤にかけても大事なものか?」
「あーはいはい、仰せのままにー。けど荷物持ちしたら帰るからな、」
「ごめん……兄ちゃん」
「べつにー?もう慣れたわ」
茅原知種と茅原七葉は兄弟である。しかし義理で同級生の、ではあるのだが。
知種の母はオメガだった、実の父はベータだったそうなのだが、物心つく前に死別しているせいで、顔すら写真でしか見たことがない。
けれど写真で見る限り、狐のようなつり目は父親似のようだった。
その割に、目の大きさが母親に似たおかげで、所謂三白眼に近い目をしているのだが、知種は別段それを気に止める様子も見せなかった。
というのも、弟の七葉が影響しているだろうか、彼はアルファの父と母の元に舞い降りた天使だ。産みの母であるアルファの女性は、オメガの女性と駆け落ちして姿を消した。
曰く政略結婚であったそうなのだが、結婚以前より、相手のオメガとは番であったらしい。
それはさておき、七葉はそれはもう誰が見ても天使だった。ふわふわの色素の薄い細い髪に、くりくりとした瞳、白磁のように透き通った肌に、小鳥のさえずりのような美しい声、その上性格までも純粋で、正にどこをとっても完璧な、神が創りたもうた芸術作品。
卑屈になるまでもなく、一つとして彼に勝る部分が無いせいで、全てがどうでもよくなってしまったのだ。
しかもたった数ヶ月しか違わないのに、七葉は知種を兄として酷く慕っていた。二人の出会いは幼稚園の年長だったか、とにかく長い間、兄弟として過ごしている。
もちろん何度も喧嘩だってした、しかしいつの間にか仲直りして、また遊ぶ。もしかしたら本物の兄弟以上に兄弟らしかったかもしれない。
だからこそ知種自身も七葉を可愛がったし、大好きだった。
しかし、運命というのはさも残酷で、情け容赦なく二人に溝を作ろうとするのだ。
中学に上がった頃のことだ、義務として行われるバース検診で、二人どちらもオメガであると診断された。
正反対のオメガ、かたや愛されるために生まれたオメガ、そして知種はといえば、蔑まれる事が約束されたオメガである。
両親はその結果を聞いても落胆することはなかった。昔に比べ、オメガの人権が確立していた事もあったのだろうし、父にして見れば、愛し合っている母同様、オメガは守るべき対象であった、その上実の息子は愛される運命にあるのだ、何を悲しむことがあるだろうか。
母はといえば、七葉についてはその器量や外見から一切の心配をしておらず、知種については私の息子が気合でも運でもなんとかしないわけがないと、謎の自身を抱いていた。
それもあって、家庭内は至って円満……だったのだが、安泰と思われた生活は突如変貌を遂げることとなった。
七葉に魂の番が現れたのだ。それが野坂蘇芳、その人である。
彼は父が務める会社の会長の孫、とどのつまりは逆らえない相手である。
受験生同士勉強会でも開いたらいいとかいう大人達の提案にのってしまったせいで、三人は出会い、志望校や住居さえも援助するからと変えられて、もう二年ほど二人暮らしの上、蘇芳ともそれなりの付き合いになってしまった。
知種と違い、七葉は蘇芳を嫌っているわけではない、蘇芳だってアルファであるし、何様俺様な態度を引き合いに出したとしても勝るほど、家柄に加え顔までいい。
母親が北欧の方出身らしく、目鼻立ちらもちろん、七葉以上に色素が薄く、瞳の色も青みがかったグレーである。
涼やかな目元に美しい色の瞳とは、もう向かう所敵無しではないだろうか。
とはいえ、知種に関してはタイプに該当しないせいで、キュンともスンとも言わないのだが。
本来ならば、蘇芳と七葉で勝手によろしくやっていればいいものを、七葉は他人に対し酷く気を使うのである。
それを理由に、仰々しい使用人連中に世話を焼かれるのは困ると蘇芳に申し立てたのだ。
そのせいで、兄ならば文句はないだろうと知種は勝手に召使いどころか、給料もでないので奴隷に仕立てあげられた。
親も逆らえなければ下手なこと言って怒らせるとあとが面倒で、あえて逆らうことはしていない。
おかげさまで、最悪の高校生活である。
「それにしても、友人もいないくせに用事か?」
「誰のせいだと思ってんだよ、それに数人はいるしな。ご期待に添えなくてスミマセンネー」
そんな知種でも全く自由がないわけではない。
例えば、二人のデートがない休日や放課後は蘇芳には縛られない。
しかしなんの因果か、それともどちらかに誘発されているせいか、発情期間が被るせいで、自由な時間など、驚く程に少なくはあるのだが。
「兄ちゃん、出かけるのはいいけど早く帰ってきてね、発情期ももうすぐなんだし」
「わぁってるよ、でもな、俺は抑制剤ちゃんと効くから、一週間家にいっぱなしってのも暇なんだよ……その前くらい遊びたくなんの」
くしゃりと七葉の頭を撫でながら言って見せれば、案の定と言うべきか、蘇芳は眉根を寄せた。
「知種……」
「あーはいはい、弟に触れるのさえ許可制とは恐れ入る」
独占欲の強さは人一倍である蘇芳、彼の全てを甘んじて受け入れる七葉、二人の行動に呆れつつ従う知種。そんな三人には知種のみぞ知る秘密があった。
それは蘇芳の魂の番が、七葉ではなく知種だという事実である。
野坂蘇芳と茅原七葉の傍には必ず茅原知種がいた。
それは三人が出会った当初より続いていることであり、七葉の発情期を除き、知種が彼の隣にいないことなど無い。
だから蘇芳は気付かなかった、それとも認めようとしなかったのか、出会って二年以上が経過した今でさえ、知種が魂の番であるという事実を認知していないのだ。
片や知種はといえば、最初こそ、本当に最初だけ、蘇芳に気付いて欲しがっていた。
しかしそんな見込みは微塵も感じられず、諦めるのも一ヶ月くらいだっただろうか、とても早かったのだ。
とはいえ、知種がオメガである事に変わりはなく、自分の発情期と七葉の発情期が被るせいで、持て余した熱は留まる所を知らず、家に一人残されるまま、一週間もの地獄に興じるという道を選ばざるを得なくなったのは、納得の出来ないところだった。
だから、知種は嘘をついた。
二人から見た彼は、抑制剤がうまく効き目を表して、大人しく家にこもっているだけのオメガだろう。
事実は違う。知種は発情が近づく度、街に出ては己の匂いを振りかざし、男を探した。発情期の間、自分を抱いてくれる人間を。
運が良ければ今後番にでも棒にでもすればいい、なんて考えながら、もはや両手では数え切れない人数を相手にしている。
時にはベータ、時にはアルファ、趣味の悪い人間に至っては、輪姦の真似事だってした。
一人に愛され幸せに生きる美しい弟とは違い、地を這い泥水を啜ってでも生きながらえようとする知種……オメガ同士の二人は既に、真逆の人生を歩んでいる。
「ちーぐさ!」
二人を送り終え、今度は自分の番だとばかりに燻る熱で身を焦がし街に繰り出せば、すぐに相手は見つかったらしい。
「……なんだ、てめぇか翠(アサギ)」
裏路地に入った途端ドンと勢い良く、大きな体がフェロモンを発し始めた千種の身を包んだ。
「水臭いよね、言ってくれればいつでも相手してやんのにさ。あーあ、こんなにフェロモンぷんぷんさせちゃって、手加減出来なくなるって」
彼は白昼堂々あからさまに千種の胎を撫でると、あえて耳に息がかかるよう囁く。
ゾクリと背筋に不快なものが這う感覚を抱き、押し退けるように彼から離れ向き直る。
「誰がてめぇとヤるって言ったよ、しつけぇからヤダ。この前も輪姦プレイなんかさせやがってクソが」
視線の先に彼の姿を捉えた瞬間、目を閉じたくなった。
それもそうだろう、その男、野坂翠はといえば誰もが目を奪われるほどに美しいのだ。
艶やかな黒髪、涼やかな目元、通った鼻筋にスラッとした足、唇はしっとりと濡れ、その声は蕩けるように甘い。
きっと誰しもが彼に目を奪われ心を奪われる。
だからこそ、千種は彼を直視などしたくない。
「なぁに千種、照れてる?」
「照れてねぇわ!」
加えて、彼は野坂蘇芳のお従兄弟様だ。正直なところあまり関わりあいたくなかった。
「千種が発情期ってことはあの可愛い子も?羨ましいねぇ蘇芳は、今頃発情期に任せて腰振りまくってんだろ」
爽やかな雰囲気からは想像もできないほど品のない言葉の数々。
きっと顔で近づいた女性陣やオメガたちは卒倒する程だろう。
「てめぇが言うかよ万年発情期ヤロー」
「そうそ、俺万年発情期だから一発ヤッてくんない?」
そもそも何故野坂蘇芳の従兄弟とこんな関係になっているかといえば始まりは半年前のことだ。
←back