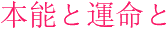
「お疲れさん、俺は会ったことないけどやっぱいるんだな」
「政次には金吾がついてるからね。でも、金吾も金吾だよ、俺には銀くんがいるってわかってんのに……そりゃ、発情期は鬱陶しいけど」
時刻は七時、普段は既に金吾が帰宅しているはずの時間だ。
丙と政次は、久方ぶりに二人で夕食を共にした。と言っても、夫婦の寝室を間借りして、ではあるのだが。
「そういえばお前、最近発情期以外は家に帰ってねぇだろ」
「何かあったとき楽だから、こっち。そもそも部屋もらってんのに、わざわざすぐそこの家に戻らなくてもって感じだし」
丙には三つの場所が与えられている。一つは使用人全員が等しく使える談話室、もう一つは丙の仕事場兼寝室、そして最後は庭に建てられた実家だ。
彼は高校卒業前までは、実家の方で寝泊まりする事も少なくなかった。けれど、高校卒業後すぐに使用人頭になった手前、仕事を早く覚えるためにも屋敷で寝泊まりする回数がグッと増えた。
政次の妊娠がわかってからは前回の発情期まで一度も帰っていなかったせいで、多少掃除が大変だったと記憶している。
「たまには発情期じゃなくてもそっちで寝てみたらどうだ?こういう時は一人になって考える時間だって必要だろ、丙の場合は特に」
「でもまだやることあるし、金吾の夕飯出したり食器洗ったり……」
「俺らはガキか、それくらい出来るわ。それに、今日はうちの旦那が勝手にしでかした事だからなぁ……ま、妻に任せとけよ」
ニッといたずらっぽい表情で笑った政次の考えている事が、丙にはなんとなくわかる。
それに加え、政次が自分で妻だとか嫁だとか言う時は悪巧みしていることが殆どだ。
「お手柔らかにな、悪気ないだろうし俺のためにやってくれたんだろうから」
「金吾次第だな。とにかく、今日はもう休め、これお願いじゃなくて指示だからな」
政次との関係性は今や友人ではなく主人と従者だ。と言っても、政次は命令だなんだと主従関係を連想させるものはしない、もしするとしたら今のように丙が弱っている時の休暇指示くらいだ。
「そう言われたら今日は金吾に仕事に戻れって言われるまで戻れないからなぁ、有難く休ませてもらうか……それにしても、そんなに酷い顔してたか?」
屋敷に帰ってきて開口一番、政次の事を任せてあった加藤さんの口からでたのは、何かあったの?だった。他の使用人にも次々と心配の言葉を投げ掛けられたかと思えば、最後には政次に困惑の表情を向けられた。
「鏡見ろって言っても気付かないよな……あん時ほどじゃねぇにしろ、そのレベルだ」
「あん時って……あー……思い出すだけで自己嫌悪でおかしくなりそうだ」
今回は自己嫌悪なんてしないだろうが、一瞬頭を過ぎった記憶に、丙は顔を顰める。思い出す度に苛まれる嫌悪感はきっとこれから先、和解が無い限りずっとこのままなのだろう。
丙は二人が食べた分の食器を片付けると、政次に言われた通り家に戻った。
夜の冷えた空気が部屋中に充満し、息を深く吸い込むとむせてしまいそうな程だ。
彼はエアコンヒーターの電源を入れると、早々に着替えベッドに入る。
時刻はまだ八時過ぎ、いつもなら考えられない時間なせいか、目を瞑っても眠れそうもなかった。
「……魂の番か」
ポツリと小さく呟いてため息を吐く、誰よりも銀司の運命でありたいと願ったが、そうでない事は元より気が付いていた。
それならばいっそ出会わなければいいと、出会わず一生を終える方が多いのだから大丈夫だろうと、そう高を括っていたのに、運命とは残酷なものだ。
「……っ、くそ」
匂いが脳裏に焼き付いて離れない、丙は耐えきれず拳をベッドに振り下ろせば、勢いをそのままに跳ね返った。
もしもあの男が出会ったままの性格であれば、番になっていたのだろうかと、そんな考えが浮かんで首を振る。
「俺は銀くんの番にしかならない……」
言い聞かせる様に口に出し、ぐるぐる巡る思考にそっぽを向く。
顔を両の手で覆い、ぐっと下唇を噛めば、ほんのりと血の味が口の中に広がり始めて、ため息を吐きながらギュッと目を閉じる。
どれくらいそうしていただろうか、ふと玄関の方からカタリと小さな物音がしたような気がして、丙は一気に起き上がった。
「金吾か……?」
まさか、屋敷で政次に何かあったのだろうかとの想像が頭を過ぎり、寝巻きのまま階段を駆け降りる。
玄関に着いたところで、小窓から見える景色に映ったのは、確かに人影だった。
「え……」
が、丙は月に照らされぼんやりとだけ映る姿を見た瞬間、ドキリと胸が高鳴った、と、同時に、夢でも見ているのではないかと頬を抓る。
痛みを実感し、急く動作で鍵を開けのうとするも驚き過ぎてうまく開けられない。十秒以上経過してやっと、彼は勢いよく玄関のドアを開けたのだ。
「銀くんおかえりなさい!」
そこには確かに、焦がれにこがれた銀司がいた。
「どうしたの?帰ってくるなら言ってくれれば、俺銀くんの好きなものいっぱい作って待ってたよ?でも帰ってきてくれるだけで嬉しい、上がってよ銀くん、ミルクココアなら直ぐにいれられるから」
興奮状態のまま、畳み掛けるように語りかける。中に入ってもらおうと掴んだ手も、離すことをしなかったせいで、さっき痛みを実感したはずなのに、現実味を全く帯びてはくれない。
「なんで会社に来ていた」
唸るような低い声だ、銀司はまるで丙の言葉など聞こえなかったようにそう問うた。
月明かりの逆光で表情まではうまく見えないが、機嫌が良いとはお世辞にも言えない時の声。
「あー……ただの手伝い」
「丙」
怒気を孕んだ声で名前を呼ばれる。けれど、銀司は恐らく何も知りはしないだろう、そもそも金吾が言うはずもない。
となれば、これは彼の直感だ。ただそれだけなのに彼は帰ってきた、発情期以外で銀司が夜に屋敷へ帰ってきたのなんて半年以上ぶりだというのに。
「…………はぁ、わかった、話すから上がって。リビングは寒いからエアコン点けて待っててよ」
ともすれば、これ以上誤魔化したところで彼は納得しないだろう。
「いい、部屋に行ってる」
「それはそれで俺が銀くんを襲ってしまいそうになるんだけど」
冗談めかして言うけれど、半分冗談ではない。
そもそも、銀司はタイミングが良すぎるのだ、毎回毎回計ったように、丙が何かあった時には必ず彼の姿がある、まるで、守っているかのように。
だからこそ、縋りたくなってしまう。
「はい、ココア。マシュマロも浮かべてみたよ」
コトリと彼の前にマグを置く、カーペットに座り込み、あぐらをかいたままの彼は、チラリとそれを見たが、手をつけることはせずに、目の前に座るよう顎を動かした。
「改めて、おかえり銀くん、今日はどうしたの?」
「どうしたはこっちのセリフだ、なんでお前の車があそこにあったんだよ」
聞けばどうやら、社に帰ってきた時丙の車が止めてあったのを見たらしく、手伝いに呼ばれたのかと思ったが、執務室に姿が見えなかったのを不審に思った銀司が金吾に丙の所在を尋ねたのが始まりらしい。
結局秘書が乗ってくるはずだった丙の車で、銀司は今日ここに帰ってきた。
「金吾に呼ばれて会社に行ったからだよ、仕事かと思ったけど、その実お見合いみたいなものだった。金吾はまだ銀くんには言う時じゃないって言ってたけど、何考えてるかはわからない」
丙は銀司に嘘を付くことはしない、というよりも、付けない。どんな些細な事だとしても見抜いてしまうからだ。
「……それで、どうするんだ?」
どうするもなにも、答えは一つしかない。もしここで考えているなどと言ったものなら、機嫌は地まで落ちることだろう。
「いつも言ってるけど、俺は銀くん以外いらないし断ったよ……でもさ、銀くん、金吾がそういう事したのは咎めないんだね?」
「大方いつもの突然の思いつきだろうからな……それに、破談ならいい」
実のところ、嘘を見抜けるのは銀司だけではない。丙もまた、銀司の嘘ならば見抜くことが出来る。
ずっと一緒にいたせいか、自分のことより何よりお互いのことの方が詳しいのだ。
恐らく彼は、金吾の本当の意図をわかっている。
「それならそれでいいけどさ」
丙はゆっくりと立ち上がると、今度は銀司の後ろに周り、座り込んだ。
「……俺のことはもういいよ銀くん、守られなくても、ちゃんと一人で立っていられるよ。これ以上、銀くんに傷ついて欲しくない……見てる俺も辛い」
そして、決して顔を見られないように銀司の事を抱き締めて、小さくそう溢す。
その声は悲痛に満ち溢れ、少し震えているようにも聞こえた。
「…………まだだ」
銀司は静かにそう答えると、丙は諦めたように笑った。
「そっか……あーあ、こんな事ならあの時噛まれておくんだった」
答えを聞くやいなや、笑ったままふっ切れたかのように立ち上がると、そのままベッドに倒れ込んだ。
「冗談じゃねぇ、流されてたまるかよ」
「銀くんは本当に優しいよ……ねぇ銀くん、今日は出ていかないで、俺と一緒にいて……隣で寝てくれない?」
どんどんと切実さを帯びる声、続く沈黙は丙の心臓をザクザクと刺し、一秒が一時間にも思えるほどに長く感じた。
「お前、本当に断ったのか……?」
「断ったよ、けど、胸がざわついて気持ち悪い」
だって、銀司を目の前にしているというのに、あの匂いが思い出されてしょうがないのだ。
思い出したくもないのに、銀司一色で染められたいのに、嫌でも思い出してしまう。
「……今日だけだ」
「うん、ごめんね銀くん、わがまま言って……ありがとう」
その日は二人で抱き合って眠りについた。発情期以外でとなると、何年もしていなかった行為に、胸は高鳴ったが、銀司の匂いに酷く安心して、銀司の色に染められている気がして、ぐるぐると思考が駆け巡っていた先ほどとは打って変わって、すぐに睡魔が丙の意識を攫っていった。
翌朝、会社に見送りして以降はまた同じ毎日の繰り返しが始まるのだろう。けれどそれでも、丙はこの一時の幸せだけで充分だったのだ。
が、丙と銀司が穏やかな時間を過ごす一方、屋敷の夫婦は一触即発だったと、後に政次の口から語られた。
「ふーんふふーん」
そんな夜から五日ほど経った日の事だ、丙はあれから日常が戻ったというのに驚く程に上機嫌で、鼻歌を歌いながら仕事をする程だった。
屋敷の窓は一点の曇りもなく磨きあげられ、床も鏡のように己の姿が反射する。
いつも綺麗にしていたとはいえ、もはや綺麗すぎて落ち着かなくなる程だ。
そのせいか、政次に掃除は止めて買い物に行ってこいと屋敷を出されたのは今から一時間位前のこと。
「あとは……あの飴か」
つわりがなくなった分舐める頻度はグッと減ったものの、政次は今でも食欲がない時はそれを口に放っている。
早速探さなくてはとフロアを移動している時の事だ、丙の携帯に着信が入ったのは。
「誰だ、これ……」
見知らぬ番号に首を傾げながら、もし知っている人だといけないからと、通話ボタンを押した。
『……さつきか……?』
が、それが間違いだった。丙はビクリと体を震わせて、携帯を落としそうになる。
『俺だけど、薬持ってきてくれないかな?熱で頭ボーッとしててさ、いつものマンションにいるから、じゃあ後で……』
「は!?ちょ、おい待て切るなよ!」
一方的にそれだけ言うと電話は切れたが、名乗らなくても相手が誰かなど一瞬でわかった。
「なんで、俺に……」
皐月かと彼は問うた、皐月の姓は確か上杉だったはずだ、ともすれば、上杉と卯月、番号同士が隣にでも並んでいたのだろう。
が、問題はそこじゃない。
彼はきっと皐月に電話したと思っているはずだ、このままなら待てど暮らせど皐月は来ない。
もし電話を切ると同時に倒れていたら?意識を失っていたら?そんな状態なら、再度電話する事も出来ないだろう。
手助けする謂れは無いが、これで死なれては後味が悪い。
今ならまだ間に合うかもしれない、そう思えば丙は、反射的に、彼に電話を掛けていた。
赤柳光雅に。
6話→
←back