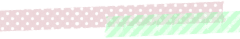
一年後、それでもきみがすき
不安があるわけでもない、不満が募るはずもない、いまのわたしは多分驚くほど幸せで、これ以上望んだらそれこそ罰があたりそうなのだ。それなのに、このすっきりすることのない、まるで満たされていないかのような気分と言ったらなんなんだろうか。
「準備はもういいのか?」
「うん。荷物は送ってあるし、手続きは済んでるし、後は身一つで行くだけ。」
「そっか。」
エスカレーター式に進める大学を蹴り、学外を受験することを決意したのはつい半年前。暖かく見守られ(三郎以外)、ときに応援という名の邪魔をされ(主に三郎)、気分転換だと行っては外に連れ回され(特に三郎)、ストレスフルな受験生活を送るつもり満々で臨んだ毎日がいつもと何も変わらない賑やかな日々で、時間はすっと通り去っていった。
わたしたちは受験生であると同時に高校三年生でもあり、つまりそれは当り前のことなのだけれど、入試が近付くということは同じようにこの生活ともお別れすることを示していた。内部入試の友人たちがわたしに遠慮しつつも、最後の高校生活を貪欲に楽しんでいる姿を見ると、気持ちがぶれるというか傾きかけそうになったこともあった。けれど、毎日閉館まで学校の図書館に粘り続けるわたしを、気を使って暖房も切られた放課後の教室で待ってくれている兵助の存在や、予備校で開かれる模試の後に、ごはんに誘ってくれる雷蔵や三郎、ハチの存在は大きかった。“気づかい”と“さりげなさ”の中間とでも言えばいいのだろうか、彼らのサポートがなかったら、いくら陸上で慣れている「ひとりの戦い」であったとしても折れていたかもしれない。かも、ではなく間違いなく折れていた。
そしてわたしは、第一志望の大学に受かったのだった。
「ご両親は?」
「仕事が立て込んでて忙しいみたい。手続きが終わってからとんぼ帰り。でも兵助に会いたかったみたいだよ。」
「え。それ本当か?春樹のご両親海外だもんな、なかなか機会がないから会えたらよかった。」
「夏にまとめて休みが取れそうって言ってたから、その時にでも会ってあげてよ。」
「よし、今から鍛えておくか。」
「なんで?」
「一発殴られたときのために腹をもっと引き締めておこうかと。」
「顔かも。」
「…打つ手がない。」
「そこまで絶望的な顔をしなくても。家の両親というか父親はそんなことしないって。」
「娘に関しては理性を失うのが父親だ。」
「それってもしかして将来の自分のこと、兵助…」
諸々の雑多な手続き類を済ませるために、海外から一時帰国していた両親を空港まで見送ってきたのは午前中のこと。さすがに受験中も放任していたことを申し訳なく思っていたらしく、終始娘である私に甘かった。そこで珍しく寛容な、というか財布の紐が緩めの両親を最大限有効的に利用させていただいた。
「大学生の一人暮らしで二部屋台所別っていうのは贅沢じゃないのか?」
「そこは日頃いかに私が寂しくて心細く暮らしていたかを切々と訴えたから大丈夫。」
「あっそ。現金な娘は俺のタイプじゃないなー。」
「奥さんは多少狡賢くなくちゃだめでしょ。夫のサポート役ですから。」
「…」
「顔緩んでるよ。」
「ぶほっ。」
「…」
引越しを明日に控えたわたしは、バイト帰りに空港まで迎えに来てくれた兵助といつものように町を歩きまわっていた。夜には雷蔵、三郎、ハチと五人でごはんを食べる約束をしている。今からどこかに遠出するには時間がなく、かといってどちらかの家で落ち着いてしまうことも躊躇われたのだ。
「バイトどうだった?あと、自車校は大変?」
「バイトは順調。短時間にしては割がいいし。運転はだいぶ慣れたよ。」
「バイクとは全然違う?」
「自分より断然でかいしな。守られてる感じはするけど。夏には春樹のこと買った車に乗せられるくらいに自信つけておかないと。」
「うん。怖いけど隣に乗ってあげようじゃないか。」
「人間ナビでよろしくー。」
わたしたちは、先の約束をあまりしない。いつなにが起こるかわからないから。どんなタイミングでさよならすることになるかもわからないから。自分たちが悲しくなるような要因を、わざとできるだけ遠ざけてきた。けれど今になって未来の約束をするのは、離れることが原因だからじゃない。寂しいからでもない。我儘になったからだ。相手のこれからを拘束したいだなんて、とんだ傲慢なことを大真面目に考えるようになったから。
「大学。楽しみだけど、億劫だなぁ。」
「春樹は、実は人見知りするしな。新しい環境が好きってわけでもないみたいだし。」
「嫌いではないけどね。頑張ってみるよ。」
「今みたいに、すぐに会いに行ったりはできないんだからさ、あんま無理すんなよ。」
「うん。力抜く。」
「なんかあったら電話しろよ。ベッドに直行してふて寝の前に。」
「そこは保障できないかも。」
「いうと思ったよ。」
「よくおわかりで。」
いつもと同じ会話と共に、三年間隣で見てきた風景が、今日に限って違うものに変わることはない。高台にある学校、長く続く遊歩道、隣を流れる緩い川の流れ。すれ違う見慣れた制服。いつもよりわざとゆっくりと歩く斜め上の兵助の横顔。なぜだろう、景色がいつもと違って見える。輪郭がぼやけて端々から色が滲んでいく。綺麗だけど物悲しいのは、ああそうか、自分が泣きそうだからなのか。
「自分のことなのに、春樹は泣くのに気づくのが一呼吸遅いなぁ。」
「泣こうと思って泣いたわけじゃ、ないから、だよ。」
困ったように笑う兵助が、立ち止まって涙を拭ってくれた。普段はハンカチを渡してくれるだけなのに。普段と違うことはしないでほしいのに。今日を特別になんてしないでほしいのに。そんなの兵助だって十分わかってるはずなのに、それでもいつもよりずっとやさしく抱きしめてくれる兵助に甘えている私が一番、いつもとおなじように振る舞えていなかった。
「自然と涙が出るほど俺と離れるのが悲しいか、そうかそうか。殊勝な心がけだ。」
「ちっがうよ、悲しいとかじゃないよ。さびしいんだよ。」
「そっかそっか。」
「不安はないよ?わたしたちなら遠恋もなんとかなると思う。根拠なんて、ないけど、ね。」
「確信なんかできなくてもわかるよ。」
「でも、不安がなくても。さびしいとかは思うの。それってどうしようもないよね。」
「それってどうしようもない。だから大人しく抱きしめられてればさ、緩和されるかも知れない。」
「やだ。」
「なんで。」
今みたいに兵助がいないときはそれなら、わたしはどうすればいい?どうやってさびしさを紛らわせればいい?さびしさと上手く折り合いをつけられる?そんなこと、無理に決まっているから抱き癖なんて、つけちゃいけないのに。
「考えてること、わかるよ。でもいわせてもらう、そこまでさびしい思いをさせるつもりはないからな。」
「っく、うー…」
「ますます泣かれるなんて、信用ないな俺。」
「ちっがうってば、弱ってる時にそのせりふはずるいって意味!!」
「なんだ、感動してたのか。」
「もう黙れへーすけー。」
「はいはい、黙って抱き締めさせてもらいますよ。」
わたしたちは、やっぱり我儘だ。好きだからずっと一緒にいられるようになんて、一番の我儘を押し通そうとあがき続けてる。兵助にとってわたしが、わたしにとって兵助が一番の相手かどうかなんてわからないのに、好きだからのそのたったひとつの理由に縋りついて縛られてでも、一緒にいたいと。
「あんまり泣くなよ。」
「そうだね、三人にこれから会うんだし、さすがに心配されそう。」
「や、俺が離したくなくなるだけ。」
「そっちか、えろくくち。」
「おっとフラグが立ちましたね。」
「引っぺがすよ…」
*お別れ話(距離的な)でも、やっぱり最後は明るくしめたいドラマチックレコードです。