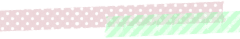
五ヶ月後、わがまますぎるふたり
「それは若干犯罪だと思う。」
「それは私が?それともこの恰好をさせた三郎が?」
「…両成敗?」
「疑問に疑問で答えないでよ…」
高校生活最後の文化祭、三年生は部活での出し物もほぼオブザーバー、有志が集って屋台を何店か持つぐらいが毎年の恒例だった。けれど、私たちのクラスは三年間持ち上がりだったこともあってか仲が良く、最後ということもあってクラスで喫茶店を開くことになった。もちろん、当然のごとく三郎やハチがしゃしゃり出たため、平穏無事に事が進むわけがなかったのだけど。
「その格好じゃ、歩けないか?」
「え、兵助一緒に回ってくれるつもりだったの?」
「最後だし、毎年主催者側だったからろくに楽しんだこともないしな。」
「行く!!もちろん、兵助が隣を歩かれて嫌じゃなければだけどね。」
「気にしないよ。」
「あははうふふってお前ら店の邪魔だ!!そういうことは向こうでやれ、向こうで!!」
ひょこっと顔を出したのは、白雪姫の魔女の格好をした三郎だった。鷲鼻が精巧に再現されていて、正直気味が悪い。魔女の腕には籠、籠の中には毒りんご、毒りんごの代わりにはお店のメニュー票が入っていた。廊下から見るとかなり凝った装飾で覆われた教室の中、もといお店の中では忙しそうに七人の小人や、シンデレラやアラジンのジャスミン、美女と野獣のベルなどが働いていた。私たちのクラスは仮装喫茶を敢行していたのだ。しかも、某夢の王国のキャラクターたちで。もう隠しても意味がないけど。
「三郎は、まだいいよな。お前、絶対ブーイング受けただろ。」
「ふん、計画者が得をするのは道理なんだよ。」
「じゃあ、なんでハチがアリスなんだ?」
「…こんなでっかい鷲鼻つけるよりはましだ。」
元・男子校で女子がどうしても少ないため、お姫様などが多いこのネタは却下されかかっていた。それを、三郎が勝手に「よしわかった、ハチがアリスをやる、雷蔵は白雪姫をやる、俺はなんと鷲鼻つけて魔女をやってやる!!だからお前ら女装しろ!!」と男子みんなを無理矢理引きずり込んだのだった。おかげで数少ない女子生徒は大迷惑というか大混乱というか「またか、」という諦念をいつものごとく漂わせた。三郎が無茶をいって、ハチがそれに便乗して煮詰めて、細かいところをカバーするのは大抵雷蔵や私だった。諦めて女装用のコスチュームを大慌てで人数分構想し、型紙に起こし、布を用意してから「お母様に作ってもらえ。」と男子生徒全員に渡して放り投げた。
四人しかいない女子は、裏方に徹する気満々でいた。飲み物を準備したり、焼き菓子を焼いたり。その方が「女装喫茶」として盛り上がるだろうとも踏んでいたからだ。もちろん接客なんて面倒だから逃げたかったというのが本音。そしたら意外な落とし穴が待っていた。
「それで女子が男装なわけか。」
「いやー、春樹似合うな!!」
「ネバーランドに置き去りにしてあげようか。」
日頃のお礼、とかなんとか言って丁寧に作られた衣装が手渡されたのは当日。周りの痛すぎる雰囲気に負けて、私は即席ピーターパンに扮していた。緑タイツにミニスカート並みの緑のぺらいワンピース。部活のセパレートよりよっぽど恥ずかしい。対して兵助はクラスで出し物をするわけでもないので一日中オフ。見なれた制服が今はただ羨ましい。今日も午前中は暇だったからと、出席だけ取って映画を見に行ってきたらしい。
「ピーターパンは休憩中なんだろ?」
「あぁ。春樹はずっと働きっぱなしだったから、後はもうあがり。」
「じゃあもう残り時間あまりないけど、見て回ってくるね。」
「おー、その格好で歩く広告やってこい。」
「…着替えようかな。」
「はいはい、着替えてる時間がもったいなから行くぞ、春樹。」
本当は、最後の文化祭も一緒に回ったりは出来ないと思ってた。事前に私がお店に出ることは言っていたし、そもそもこんな恰好をしたら歩いてくれないと朝から少し落ち込んでいた。だから、兵助から誘ってくれたのは意外だった。ほいっと差し出された手を握り、私たちは初めて学校内で手をつないだ。周囲の視線が私の仮装に対するものなのか、それとも手を握っていることに対することなのか、曖昧になるところは、この仮装のおかげかもしれない。
「春樹はどこか行きたいとことかあるか?」
「私?そうだな、何か食べ物買って、どこかでゆっくりしてたいな。」
「俺も昼食べてないから腹減ったな…」
結局屋台でたこ焼きやら飲み物やらを手に入れた私たちは、いつものように屋上へ向かった。こんなときでも二人で落ち着いていられる場所というと一番に思い浮かぶのが屋上なのだ。
「こんな日でも屋上は静かだね。」
「屋上が解放されてるって知らないんじゃないか?」
「それもそうか。」
今はもう、隣に座るようになったけれど、最初は距離を取って、しかも対角線上に座っていた。お互いが誰なのかもわからずに、目だけで挨拶をしていたあの頃。でも私の隣にいる兵助は、あの頃とは違う存在だ。もう私の中の外側には置いちゃいけない相手だ。
高校三年の秋、世間で言う受験生、私たちが逃れられない道。内部試験でエスカレーター式に上がることが可能だった大学を、私は志望していなかった。でも、その事実を兵助に伝えることが出来ないでいた。伝えるなら、今が最後で最高の機会だと思った。出会った屋上で伝えることができたなら。
「学外受けることにしたの。」
「うん。」
「やっぱり知ってた?」
「いつ言ってくるかと思った。隠してるみたいだったから知らないふりしてたけど。気づかないわけがないだろ。」
兵助の笑い方は少し困ったように眉が下がる。とても優しい笑い方だと思う。相手を困らせない、自分だけが悲しむための笑い方。それをさせている私の成長のなさにはつくづく呆れるところだけれど。
「うん、ごめんね。時間かかって。」
「ちゃんと言ってくれたから、いいんだ。」
思わず兵助のシャツを掴んでしまう。彼ならわかってくれるとどこかで甘えていた私。わかってくれるどころか私の将来を考えて応援してくれるに違いないと、確信までしていたとことん卑怯な私。そう、私は不安で仕方がなかったのだ。いつも一緒にいたのに、兵助を知らなかった頃に、また戻ることができるんだろうか。屋上に行っても兵助に会えない毎日を過ごせるのだろうかと。いつから私はこんなに、他人に、兵助に依存するようになってしまったのだろうか。
「離れて俺は、大丈夫かな。」
「それは、私でしょ。兵助は、大丈夫なんだよ。」
「…そうか?俺ってそんなに強かったか?」
ははっと笑う兵助は、強くなんかない。強いと、思っていたいのは私の勝手な都合だ。振りまわしてばかりの私が無理矢理兵助へ押し付ける、本当はいらない強さ。それでも、兵助を悲しませることが目に見えるとしても、私は自分の目標を諦められない。そして兵助にもそうであって欲しい。私のために自分のことを犠牲にしてほしくはなかった。何より私は犠牲にしてもらえるほどできた相手ではなく、重荷にもなりたくなかった。最後まで我儘なのは私なのだ。
「俺も相当だけど、春樹もかなり我儘だよな。一緒にいたいって思ってるのにどっちも自分が大事だ。」
「謝っておくけど、別れる気もないよ。だって兵助のこと好きだし。」
「なんだそれ。俺だって春樹のことよっぽど好きだし。」
「うん、いろいろ申し訳ないなって思う。依存してるし、遠恋なんて辛いのに別れないとか言うし。挙句の果てに好きとかなんだそれ、だよね。」
「ほんとだよ、春樹より俺のこと大事にしてくれる女の子なんてたっくさんいそうなのに、大事にしたいとか思える相手を見つけんのがもうめんどくさい。というか見つける気がない。」
「あー、はいはい同感です。」
「あー、よかったよかった。」
言ってることはあっけらかんとしているのに、どうしてこんなに泣きそうなんだろう。まだまだ受験なんて先のはずなのに、受かるかどうかもわからないのに。どうしてもう、離れることが前提になっているんだろう。そして不安を削るように言葉を並べているんだろう。
「大丈夫にすればいいんだ。」
そういって兵助は、私が泣くといつもしてくれるように、抱きしめながら優しく背中を叩いてくれた。そうか、いつのまにか私は泣いていたのか。
「春樹に付き合える男なんて、俺ぐらいだから他探す必要なんてないだろ。」
「自分だってそうでしょうが。」
「そうだよ、ちゃんと認めるよ。」
私だって認めてるよ。ただ、失いたくないから。そのための努力なら惜しまずにいたい。兵助を大事にしていたいという我儘だけは、どこにいてもきちんと守っていたい。
今日も兵助の腕の中は優しかった。