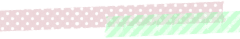
二年前、きみとわらう
人は、自分が発している空気が周囲にどんな影響を与えるかということを、もう少し考えてから落ち込んだり笑ったりした方がいいと思う。上手い言葉が出てきてくれないけど、自分の外見に責任を持つということは割と重要なことだ。
新しい環境に慣れるのが得意かまたは早いか、と聞かれれば、苦手だが順応性は優れていると答えるのが一番正確だ、そういう風に自分を理解している。
父親の海外赴任に母親がついて行ってしまったのは、驚きだった。それによって自分が一人暮らしをしなければならなくなったことは、予想外すぎてさほど驚きもしなかった。人間あまりに突拍子もないことが起こると、難しく考えなくなってしまうらしい。それでも、何でも自分でしなければ解決されない毎日は、16歳の私には新鮮だけど少し重い。高校は緩い上り坂を越えると見えてくる。新しく買った、ペンキで塗ったくったような子供っぽい真っ赤な自転車が、私の足だ。通い始めて二週間、部活も決まり先生にも恵まれ、高校生活の幕開けは順調だと言える。只一つ、不満ではないものの、いつまでも慣れないことがあった。
県下有数の進学校だが、共学になったのは今から三年前、よって絶対数女子が少ない。文系理系関係なく、クラス比はほぼ男クラ状態。それがこの高校の特徴だった。だからというわけではないものの、教室自体にはなるべく遅くつくようにしていた。予鈴がなるまで後七分。この程度が先生が現れるまでのちょうどいい時間だった。引き戸型の扉を、控え目に開けて入る瞬間がいまだに一番緊張する。まっ黒な学ランだらけの教室に、紺色の長めのカーディガン、黒地に寒色系と金色のチェック柄のプリーツスカートは、さすがに目立つのだ。みんな普通に接してくれるけれど、まだまだ入学したてということもあってか女の子である私には親切だし、とても敬われている気がする。
「佐山さーん、おはよ。」
窓際の後ろから二番目、そこが私の席だった。挨拶されたことに少しだけ戸惑うが、おはよう、と周囲に笑顔で手を振るのが日課となりつつある。男の子ばかりだけれど、クラスメートとは上手くいっているつもりだ。席が隣の鉢屋くんは、人をからかって遊ぶところがあるけれど、基本的には明るく、自称お祭り男の竹谷くんとともにクラスのムードメーカー的な存在である。
「今日も朝練?」
「うん。テニス部はないの?」
「月曜と金曜はないんだ。」
「陸上部もほぼ自主練みたいだけどね。」
中学から中距離専門で陸上を続けている。高校では体力のきつくない文化系の部活を選ぶつもりだったのだけど、見学に行ったら走りたくてしょうがない自分がいたため、当初の考えをあっさり捨てることにした。
「そうだ、今日の分の古典、現代訳してきた?」
「してきたよ、見る?」
「え、いいのか?」
「この間筆箱を忘れた私に一日貸してくれたお返し、には安いけど。」
「助かる!!俺当たるんだよー。」
「佐山さん、三郎甘やかさなくていいんだよ?」
「おはよ、不破くん。別に甘やかしてるわけじゃないよ。お礼?」
「そう?でも次頼られた時はピシッと掌たたいてやって。」
「はーい。」
私の前の席に座る不破くんは、鉢屋くんと中学からの同級生らしい。穏やかなしゃべり方や物腰からは想像がつかないけど、とっても剣道が上手いらしい。鉢屋くん曰く、面を着けると人格がかわるとかなんとか。
お昼休み、私は屋上でのんびりごはんを食べたり、本を読んだり、音楽を聴いたりして過ごしている。数少ない女の子のクラスメートたちは吹奏楽部に所属していて、お昼休みもそっちのけで練習に勤しんでいる。仲もいいし、部活が休みの放課後は遊びに行ったりもするけど過剰な慣れ合いはない。だからいいんだとは思うけど。屋上は学校が坂道の上にあるせいか眺めがとってもいいのだ。
この時間の屋上を私と二分するのがもうひとり。先輩なのか同い年なのかもわからないけれど、端正な顔立ちの男の子。彼もここが気に入っているらしく、お昼休み中ひとりで過ごしている。少しだけ離れた位置に陣取って、なんとなくお互いがそろってからお弁当に手をつけるのが暗黙のルールになっていた。そのせいか毎日顔を合わせるので、頭を下げるだけだけど、挨拶をするようになった。
私は彼の雰囲気が好きだった。憂鬱そうな顔も、辛そうな表情もしない。もちろんものすごく幸せそうな顔もしないけれど。彼が自分の感情を流しっぱなしにしないところに、とても好感を抱いたのだ。誰かに甘えようという形に入らないところが、独りではないけれど、ひとりでも全然かまわないように見えた。実際、他の場所で見かける彼は友達に囲まれていて今とは違う、年相応の男の子のように豪快に笑いもする。名前も学年も知らないけれど、一緒にいて落ち着く彼のことを、私は静かに好きになっていた。
その日は、屋上に行こうとしていたところを、社会科の先生に捕まって、重たい地図やらプリントやらを何度も往復して運ぶ羽目になった。だから屋上についたのは、いつもより30分近く遅かったのではないだろうか。お弁当を食べる時間も削られたため、急いでカンカンカンカン、と階段を駆け上り、勢いよく扉を開けようとしたら、拍子抜けするように勝手に扉が開いた。開かれた先、明るい空、その下にいつもの笑顔。
「今日は、休みかと思った。」
少し困ったように笑っていたのは、屋上のもうひとりの住人だった。彼が座るいつもの場所には手のつけられていないパンが二個、無造作に置かれていた。見つめられて固まった私は、咄嗟に言い訳のように話してしまった。
「え、っと先生に捕まってしまって、」
「それは大変だったな。」
「うん。あの、食べてなかったの?」
「なんとなく習慣づいていたから癖、で。」
「そっか…じゃあ食べようか?」
「ああ。」
今日、初めて声を聞いた。落ち着いた低い声、そしてなんとなく私も習慣にしていたので、同じことを考えていたことがただ嬉しかった。
「「いただきます。」」
その日以来、必然的に二言、三言、と会話が増えるようになり、私は屋上に行くことを違った意味で意識し始めていた。
これが兵助と私の出会いだった。