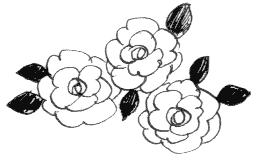一:四月二十八日 日中
ジャーっと洗面所の蛇口から出ている流水を両手で掬い、バシャバシャと顔を洗う。タオルで顔を拭き、目の前の鏡に映る自分の顔を見た。
(……陰気臭い顔)
相変わらず、愛想もへったくれも無い顔だと思った。でも、肌艶は良くて髪もツルツル。唇も荒れていない。手先だってほら、手荒れしないように毎日念入りにハンドクリームを塗って。人工的な着色なんて施していない自爪は、飲食店の店員らしく短く整えて。頭のてっぺんから指先まで抜かりなく身嗜みは整えている。こんな陰気臭い顔の上に見窄らしさまで重なってしまえば、いよいよ周囲に不快感を与えてしまいそうだから。
本来ならば、気に病んでいてもおかしくないこの状況。何故こんなにも身なりに気を使う精神的余裕があるのか。それはこの世界に来てからの私が、夜の9時には就寝して朝の5時に起床する健康優良児だからだ。しかし、それだけではない。明らかに私の精神を支えている要因は他にある。
(両親と似てるんだよな、人柄というか何というか……)
本当に偶然見つけたバイト先。そこの店主夫妻の明るい人柄。それが両親に似ている気がする。
家を留守にしてばかりの両親。私を置いて長期間仕事に行ってしまう両親を、私がどんな気持ちで送り出し、帰りを待っていたか。
『ナマエ、寂しい思いさせちゃってごめんね』
『何言ってんのお母さん、私一人でも大丈夫だよ』
『はは!ナマエは母さんよりしっかりしてるからなぁ!』
申し訳なさそうな笑顔で『ごめんね』と言ってくるくせに、次の瞬間にはもう何事もなかったかのように陽気に笑い飛ばす両親。そんな両親だったから、私を信頼した上での事だとわかってたから、寂しいなんて思わなかった。こちらの心も晴れやかになるような、表裏のないカラッとしたあの笑顔が好きだった。そんな両親だったから、私も笑顔で送り出し、帰って来たら笑顔で出迎えなければ。そう思っていた。
『ナマエ、お土産買ってくるからな!』
『うん、楽しみにしてるね』
『次は何が良いかしら、ふふっ!』
『お母さん楽しそうだね』
『女の子にお土産選ぶのって楽しいのよね、こっちまで乙女に戻った気分で』
『父さんも楽しいよ、娘の顔を思い浮かべながら似合うものを選ぶのは』
下心なんて無い、親子の会話。同情なんかではない、はっきりと私に向けられた、見返りなんて求めない親としての愛情。
私は両親が好きだった、周りが育児放棄だの何だの罵って来ようとも。私は、いつだって二人の帰りを待っていた。なのに……、なのに突然、帰って来なくなってしまった。笑顔で「おかえり」って、いつでも言う準備はできていたのに。
(まだ、おかえりって言えてない)
せめて遺骨だけでも、家に帰って来てくれていたら良かったのに。どうして、どうして「おかえり」って、言わせてくれなかったの。「いってらっしゃい」って送り出したんだから、「おかえり」って言わないと、締まらないじゃないか。
(考えないようにしてたのに、)
今さら考えても仕方がないことだとわかっている。だから考えないようにしていた。この世界に来る前から、ずっと。それなのに、何でまた急にこんなこと。それもよりによって今日だなんて。
(……準備、しなきゃ)
家から徒歩10分前後の場所にあるバイト先の茶房。仕込みに携わっていないとは言え、7時から営業が始まるから6時半には店に着いてないと。
洗面台の鏡、そこを開いて歯ブラシを取り出す。開きっぱなしのまま歯を磨き始めたのは、その方が鏡に映る自分の顔を見なくて済むからだ。
---
………………もうすぐ閉店の15時55分。まだチラホラとお客さんの残っているこの店内。16時閉店と言っても、時間を過ぎたところで別に追い出しはしない。閉店作業をしつつ、その間に帰って貰えば構わない。そんな見慣れてきた光景の中に、今日はいつもと違うことがあった。
「何と言いますか、圧巻ですね」
厨房の作業台に乗った大量のあんみつ。アイスクリームを乗せていないそれらは、全て持ち帰り用。その数は二十を超える。それを大きな発泡スチロールの箱の中に綺麗に詰めていき、保冷剤も仕込む。
「まぁね。毎月、月末週に予約が入るんだ」
この店には暗黙の了解が幾つか存在する。これはその内の一つだ。店のどこにもテイクアウトが出来るなんて書いてない。勿論、予約を受け付けているなんてことも。なんというか、“一見さんお断り”のような雰囲気がある店なのだ、ここは。だからこそ顔馴染みの優しい常連さんばかり、働く側としてはかなり気が楽だ。
16時頃に取りに来るというお客さんに合わせてあんみつ達を詰め終えると、大きな発泡スチロールの箱の蓋を閉めた。それを一人で持ち上げようとしたら、「重いから」と止められた。
「すみません、スナックすまいるです。例の物を取りに伺いました」
厨房の外から声を掛けて来た男性。このバイト先は偶然見つけたはずなのに、どうしてこうも世間は狭いのか。その言葉は聞き覚えのある店の名前だった。
「おや、来たね」
「お待ちしておりました」
お時さんの背中について行って厨房から出て行くと、髷を結わえた細身の男性がいた。
「こんにちは、……おや」
「この子はバイトのナマエちゃん。今月頭から働いてくれてるんだ」
「そうでしたか、はじめまして。毎月末にお世話になっておりますので、今後もよろしくお願いしますね」
ぱっと見の年齢は、30代くらいだろうか。丁寧で物腰柔らかな口調の男性。でもハキハキと聞き取りやすいし、少しダンディーな感じ。あのキャバクラのボーイさんなのだろうか。よそ行きの取り繕った口調かもしれないが、何となく接客している姿が思い浮かぶ話し方だと思った。
「こちらこそ、どうぞよろしくお願い致します」
「こちら、お代です」
「はい、お預かり致します」
お時さんから事前に聞いていた話だと、いつもピッタリの金額を持って来てくれるのだという。その人から封筒を受け取り、中身を確認すると言われた通りだった。
「こちら、領収書です」
「ありがとうございます」
そしてこれも言われていた通り、事前に用意していた領収書を手渡す。そこに手書きで書かれた“スナックすまいる”の文字は私が書いた。それを懐にしまった男性は、いつも通り、という顔でスッと厨房に入ると発泡スチロールの箱を軽々と持ち上げた。先回りするように出口の方へ向かった私は、ガラガラと引き戸を開けた。するとペコッと軽く頭を傾けて会釈をする男性。
「ではまた、来月」
「はい、ありがとうごさいます。お待ちしております」
彼を完全に見送ってから、私は店の扉を閉めた。
(とても感じの良い人だったな)
店で働いている時、私は意識的に少しだけ話し方を変えている。と言っても、せいぜい滑舌を良くする程度のものだが。金銭のやり取りが発生する場面では特に。聴き取りづらくてトラブルが起きたりしたら大変だから。それは忙しい朝の時間が一番顕著かもしれない……気を抜くと陰気臭い顔になるし、冷たくて愛想が悪いと捉えられかねない話し方になってしまうから。この世界だから云々ということではなく、そんな店員がいたら自分が客の立場でも嫌だから。こちらが愛想良くしていれば、相手もそれなりに優しく振る舞ってくれるし、接客においては必要な事だと思ってる。
(本当に、みんな優しい)
そう、みんな本当に優しくしてくれる。常連の皆さんは勿論、初めてくるお客さんだって。「いらっしゃいませ」と笑顔で出迎えて。レジで二、三言葉を交わして、「美味しかった」「また来るね」なんて社交辞令に私も笑顔で「ありがとうございます」と返す。使い古された形式的な物ではあるが、誰も不愉快にならない平和で円滑なコミュニケーション。店員側としても気分が良く働けるし、それでお客さんが本当にまた来たいと思ってくれるなら万々歳だろう。
常連のお客さん達は、よく話しかけてくれる。まるでそれが当たり前とでもいうように。
『ナマエちゃんに一緒に出歩く友達がいたとはこいつぁ驚きだ。いつ来ても店に居るから友達いねぇんだと思ってやした』
まぁ内容は一先ず置いておいて、自然に名前も呼んでくれる。
『アンタは気をつけた方がいいですぜ』
“アンタは”と、店内で唯一若い女の私に向けられた言葉。わざわざ言葉にするということは、警察として市民である私を心配している気持ちが少なからず入っているということだと思ってる。あれだけ物語の中で性悪のように描かれているけれど、関わりの薄いモブ市民には普通に優しいお巡りさんなんじゃないだろうか。
そしてあの人、前に購入しに来た以来会っていない坂田さんも。
『マジでなんかあったらいつでも依頼しに来いよ』
『随分と熱心な営業活動ですね』
『ちげーって。この街に住む先輩として言ってんの。ここは良い街だが、治安の悪りぃところもあるからな。無償の善意よりも金発生した方が頼みやすいんだろ?』
『坂田さん』
『ん?』
『私、万事屋さんの場所知りません』
『……今度連れてってやるよ。じゃあな』
彼も例に漏れる事なく優しかった。レジ前で繰り広げられる会話なんて、大体は社交辞令。思わず鳥肌が立ってしまった、あの社交辞令。その場のコミュニケーションを円滑にする上辺だけの店員と客の会話は、誰も不幸になることがない。
暗黙の了解を知っている彼は、紛うことなき常連客。もしかしたらスクーターで来てたのかもしれないけど、あんみつに乗せたアイスクリームが溶けきってしまわないくらいの近隣に住んでいる彼。最近会っていないが、しばらく会うことはないだろう。そう思うと何だかホッとする。何となく前回の鳥肌が立った感覚を思い出してしまい、気分が落ち着かないから。
『いつ店に来ても居る』なんて言う人達には、まるで私が馬車馬のように働いてるかのように見えているかもしれない。しかし、それは違う。この店にだってちゃんと休業日がある。ただし定休日ではなく、不定休日なのだ。月末近くになると店内の壁に来月の休業日を書いた紙を掲示する。これも暗黙の了解の一つだ。普段は最低でも週一回は必ず休みがあるらしいのだが、今月は少し異例だったという。
「明日からついに連休ですね」
時刻は17時前。パラパラと残っていたお客さんを全員見送って、三人しかいない店内。テーブルを念入りに拭いたり、床を掃除したり。片付けをしながら、店主夫妻に向かってにそう話しかけた。
そう、明日から大型連休。元の世界と同じくここにも存在しているらしい。大型連休と言っても人によっては普通に平日を挟むし、はたまた有給を取れば超大型の連休にもなる。
四月二十九日から五月八日の十日間、店を休業するのだと言う。これは店で働き始めた時から予め聞いていた話だから、別に驚きはしない。そのため今月の休業日は少なくて、四月の半ばにあった二日間のみ。
店主夫妻はもともと動いている方が性に合うらしく、中途半端に休むより毎日働いている方が体調がいいと言う。私もそれに便乗したかったのだが、さすがにバイトの私は『休みなさい』と言い渡されて、初めて休んだのが眼鏡の彼に出会った四月十日。その後に二度、休業日があった。そこから休みはなくて今日が四月二十八日。でも明日からは休みなので、合計日数だけで言えば週休一日はある計算になる。正直、体感としては十分休んでるし、私も働いている方が……この店にいる方が体調が良い。
「お孫さんと会えるの楽しみですね」
「そうだなぁ、いやぁ、早く会いてえなぁ!」
「この人ったら、浮かれちゃってんだよ」
「おめえだってあんなにたくさん着物繕ってたじゃねえか」
「一人目は男の子だったからさぁ、やっぱ女の子の方がちょっとばかし張り切っちまって」
三月末に生まれたばかりだと言う二人のお孫さん。なんでも息子さん夫婦は江戸ではなく京に住んでいるらしく、まだ会えていないのだと言う。この大型連休の休業日は、お孫さん達に会うために前々から予定していたもの。それならもう少し休めば良いのに、とも思うのだが『待ってくれてるお客さんがいるから』と以前聞いた時に言っていた。仕事とお客さんが好きなんだろうな、というのが伝わってくる。不定休にしているのも『定休日にしてしまうと、その日だけが休みって人が来れなくなるかもしれないから』だって。
「でもナマエちゃんには寂しい思いさせちまうねぇ」
お時さんが眉尻を下げた、少し申し訳なさそうな笑顔でそう言った。その表情が母親と重なる。
『寂しいんだろう』
私は本来、この言葉をかけられるのが大嫌いだ。でもそれは上から目線の同情の場合。人の足元を見るような下心のある、そんな同情が嫌い。
この世界に来てからこの言葉を掛けられるのは二度目。しかし一度目も、今回も、お時さんだから別に構わない。きっと善意100%だという確信があるから。
「そんなことありません。この機会にやりたい事もありますから」
「まぁそうよね。女の子だもんねぇ、色々やることあるわね」
化粧品やら服の買い物ひとつ取ったって、女は色々と時間がかかるものなのだ。都会に出て来た女がやりたいと思いそうな事なんていくらでもあるだろうし、きっと言い訳の材料は簡単に見つかる。
「京で何かお土産買ってくるからね。息子の家の近所に可愛い和小物屋が多いんだよ」
「そんな、お気遣いなく」
「いやいや、若い女の子に買ってくるお土産選ぶのって楽しいんだから!」
「そうだよ、年寄りの楽しみ奪わないでおくれ」
さっきまでの申し訳なさそうな笑顔が嘘みたいに、店中に響き渡るような元気な声で笑い飛ばすお時さん。それに便乗するように目尻に濃い笑い皺を作っている平五郎さん。
あぁ、本当に善意の塊みたいな人達だ。私だっていつまでも“人の善意を信用できない”なんていう程病んでいない。……いや、違う。病まずにいられているのは確実にこの店主夫妻のおかげなのだ。ここまでわかりやすい善意を向けてくれる人の気持ちを無碍にするほど薄情じゃない。結局そういう優しい人間に懐く単純な奴だ、私は。……と言うよりも、この夫妻を前にすれば誰だってそうなるだろう。だからこそあんなにも沢山の常連さんがいるんだから。
「ふふっ、ありがとうございます。では、お言葉に甘えて。楽しみにしてます」
「ははは!ナマエちゃんはそうやって笑ってる方が年相応で可愛いよ」
私のことを“子供扱い”してくる人達。可愛いなんて、元の世界で最後に言われたのはいつか全く思い出せない。でも悪い気はしない。だって実際親子ほど歳の差があるし、本心だってわかるもの。その裏表のないカラッとした笑顔に、こちらの心も救われるのだ。
(それに、“登場人物”じゃないから)
そもそも、裏なんて詮索する必要がないのだ。登場人物でないのであらば、普通の人。前の世界でも今の世界でも違わない、ただ普通に新しく出会った人。
まだ今月に出会ったばかりとは言え、たった三人の従業員で一日の大半を過ごしているのだ。割と濃い二十数日間だった気がする。彼らと過ごすこの店での日常は、あまりにも平和、平穏、平凡。こちらもつられて自然と笑顔が出てしまい、なんとも緊張感が湧かない。二人のその雰囲気に、気が緩んでしまうんだ。
「いってらっしゃい、お二人とも」
私が前回このセリフを言ったのは、もう一年以上前のことだ。