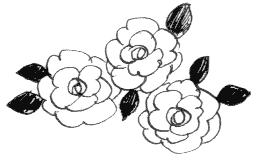四月二十四日 日曜日
日曜日の朝は全体を通してお客さんは少ないが、遅い時間までまばらに席に座る人が残ることが多いらしい。時刻は9時前、総悟くんを含めて三人お客さんが座っていた。カウンターについさっき来たばかりの総悟くんと、小綺麗なおじさま。残りの一人は平日にも来る事がある大工のおじさんで、テーブル席で新聞を広げて読んでいた。総悟くん以外はもう食べ終わっていて、食後のお茶を飲んでいるところ。
カウンター席のお客さん達と話すお時さんの陽気な笑い声を聞きながら、私は空いているテーブルを念入りに拭いたり、消耗品の補充をしていた。残るは新聞を読んでいるおじさんが座るテーブルのみ。拭くのは後にして、一声掛けてから割り箸と爪楊枝の補充をする。
「ナマエちゃん、なんか物騒な事件あったみたいだよ」
目線は新聞の一面に向いたまま、指を差して「これ」と言われた。座っている彼の横から紙面を覗き見ると、そこには大きな文字で『婦女暴行事件』と書かれている。
「今朝のニュースでやってましたね」
「あ、知ってた?」
世間話をするためには、この世界の社会情勢やゴシップの情報を仕入れる必要がある。初めこそ「この世界のテレビを見ていたら気が滅入る」なんて思っていたのだがそんなことを言っている場合では無い。この世界の細かい歴史やら常識やらがわからない私にとって無知は罪、言葉は最大の防御。付け焼き刃でも口先だけでも、何食わぬ顔で堂々と話せば私の拙い知識でも武器となる。そのため家ではテレビをつけっぱなしにしているし、もう一視聴者としてテレビを観る事にも慣れた。この事件も早朝のニュースで見たのだ。
「刀で斬られたってよぉ。本当に物騒な世の中だな、しかも犯人捕まってないって」
元の世界でも似たような事件はあっただろう。異なる点といえば凶器が刀ではないということと、事件の頻度。この世界は廃刀令が出ているとはいえ刀を持つことを許されている人もいるし、無許可で帯刀している者も居る。おそらくニュースにすら取り上げられていない刃傷沙汰がごまんとあるはずだ。前の世界よりも確実に死の危険が身近なのだが、まだその実感は湧いていない。
「まぁこの辺りで起きた事件じゃねえが、他人事じゃねえよ。被害者若い女の子みてぇだし、ナマエちゃんも気ぃつけろよ?」
この事件はかぶき町周辺ではなく、私の生活圏からかなり離れた場所で起きたもの。それに私には「モブキャラの私が新聞の一面に載るような大きな事件に巻き込まれるはずがない」などという、根拠のない自信があった。そのせいかあまり気にも留めていなかった。
とはいえ、それでも気をつけるに越したことは無い。この辺りはお世辞にも治安がいいと言える地域ではないのだ。
「お気遣いありがとうございます」
私の言葉を聞くと新聞を畳んで「お勘定頼むよ」と言って席を立つ。彼に付いてレジへ向かい、会計を済ませて店から出ていく背中を見送った。
そして続き様に、カウンターで食べていたお客さんもレジに向かって来た。この人は土日にたまに来る品の良いおじさま。お釣りの小銭を渡すと、そのお客さんが口を開く。
「先程の話、聞いてましたけど本当に物騒ですね。特に夜は一人で歩かない方が良いですよ」
「そうですね。しばらくは一人で出歩かないようにします」
「それが良いですよ。お気をつけて」
「はい、ありがとうございます」
そのお客さんが店から出ていく背中も見送って、テーブル席を片付けに行く。先にお膳は下げていたので空いた湯呑みと、水の入っていたコップを両手に持って厨房の流しに持っていく。
その途中で総悟くんの手元をチラリと見ると、既に定食を三分の一程度食べ進めている。今帰ったお客さんの食器はお時さんが下げてくれたらしいのでテーブルだけ拭こう。そう思って食器を置くのと入れ替わりに洗った布巾を持って厨房から出てくると、こちらを見ている総悟くんと目があった。
「ナマエちゃんに一緒に出歩く友達がいたとはこいつぁ驚きだ。いつ来ても店に居るから友達いねぇんだと思ってやした」
驚いた顔なんてこれっぽっちもしていない上に、何とも棒読みでそんなことを言う。真顔なのに心なしか目はイキイキしているように見えるのは気のせいだろうか。
彼にそのような話は一度もした事が無いのだが、上京したてで働いてばかりの私に友達がいないとわかっていて言っているのだろうか。
「…嘘も方便ですよ。変に心配かけられませんから」
先程のおじさまとの会話を聞いてた上での彼の発言にそう答える。
あの場ではあの回答以外出来ないだろう、と。帰る直前の客に変なことを言って、困らせるわけにも足止めするわけにもいかない。そもそもレジ前で繰り広げられる会話なんて大体は社交辞令なのだ。それをこちらも社交辞令で返したに過ぎない。
「するってーと、友達いねぇのは図星かぃ」
「間違いないですね」
彼とは目線を合わせずに、先程までお客さんがいたカウンターテーブルを布巾で拭きながら言った。
「ふーん。ま、さっきのおっさん達の言う通りアンタは気をつけた方がいいですぜ」
さほど興味もなかったのか、すぐに別の話題に切り替えた。アンタは、とはどう言う意味だろうか。それが気になって、テーブルを拭く手を止めて彼の方を見る。
「ぱっと見ぃじゃ良家の娘に見えねぇ事もないからな」
「どう言うことですか?」
いよいよ話が見えない。警察だから表に出ていない情報も知っているのだろうか、と思いながら聞き返した。
「とにかく、精々巻き込まれねぇよう休みの日は家で大人しくテレビでも見ときなせぇ」
それ以上は教えてくれないらしく、話に区切りをつけるようにピーマンの肉詰めを一口で詰め込んでもぐもぐし始めた。これ以上話す気はないと悟り、テーブルを全て拭き上げてもう一度厨房に戻った。
「ナマエちゃん、賄い食べるだろう?ちょうど準備出来たから持って行きな」
「ありがとうございます」
先程のお客さんが帰るタイミングで私の賄いを準備していてくれたらしく、平五郎さんが声をかけてくれる。お時さんがセットしてくれたであろうお膳から、臥せてあるお茶碗とお椀をひっくり返してご飯と味噌汁を装う。それをお膳に乗せて厨房を出て、総悟くんの横の席に置いた。
「お隣よろしいですか?」
「かまいやせんよ」
無言で座るほどの仲でもないし、かと言って無言で離れて座るほど険悪でもない。何やかんや毎回横の席に座っているのだが、今回は声を掛けてからそこに座った。
「ナマエちゃんマジでいつ来ても居やすけど、出稼ぎか何かですかぃ?」
先程の会話に戻るのか、そう聞いて来た。この人に一人暮らしだとかいう話は、たしか一度もしたことが無い。初めこそ質問攻めにされた記憶があるが、それ以降は内容も大して思い出せないような会話しかしていない。上京してあくせく働いているのは、故郷への仕送りに必死だからだと思われているのだろうか。
「あ、言ってませんでした?家族いないんです」
「あー、」
次に出す言葉を迷うように、覇気のない間延びした声を出す。彼が言葉を紡がぬように、私は引き続き言った。
「家族も友達もいないからこそ、身軽に一人で江戸に来れたんです。せっかく心機一転、再出発した女の過去を聞くなんて野暮ですよ?」
先程の彼の「友達がいない」というのは、「江戸には」という意味で言ったのだと思う。しかし、それも含めてもう何も聞かれないように。これ以上踏み込むな、と先手を打って制する意味でそう言った。
聞かないで欲しい。私の故郷のこと、知己のこと。だってそこには誰もいない、知ってる人なんて、この世界のどこにもいるはずない。仮に聞かれても「友達も家族もいない女が田舎から出てきた」、そう言えば言葉足らずな説明にも関わらず訳ありだと察してくれるのか、今のところ深く追求されたことは無い。
私の部屋から、本棚の漫画の他にも消えたものがある。それはクローゼットの上段に仕舞っていた物の一つ、写真だ。まだスマホが普及していなかった頃からの名残で、写真は現像されたものをアルバムに収納することが多かった。幼稚園、小学校、中学高校の学校行事の写真。それには当然、卒業アルバムも含まれる。それら全ての写真が無くなったのだ。私の幼少期のピン写真や、両親と田舎に行った数少ない写真だけを残して。友人との写真は跡形もなく消えたというのに、実に気味が悪い。
もともと家を空けることの多かった両親と一緒に撮った写真など数える程しか無く、数冊あったアルバムには一冊で足りるほどの写真しか残っていない。スカスカになったそのアルバムに、入れ替わりで増えている写真があった。まだ幼い頃の私と、同い年くらいの知らない男の子が二人で映っている写真が二枚。それぞれ違う男の子で、歳も違う。一枚は3歳くらいだろうか。もう一枚はもう少し成長していて、そもそも撮った記憶がないので確実な年齢がわからないがおそらく小学校高学年くらい。どちらにも共通して言えるのは背景が田園風景である事と、色褪せたのかセピア色で日付の印字もない事、今まで見た記憶も撮った記憶もない写真だという事。
どうやら私の過去もこの世界に順応したのか、知らない思い出に塗り替えられてしまったらしい。しかし記憶はそのままのせいで、自分の写っている写真なのに何も語ることができない。どうせやるならそこまでしっかり書き換えてくれないと不便で仕方がない。いっそ前の記憶が、思い出が消えてしまった方が気が楽なのに。
私の過去は一体どこへ行ってしまったのだろう。今まで生きた軌跡はどこへ行ったのだろう。それとも初めからなかったのだろうか。私が思い出だと思っているのが虚構で、この記憶がおかしいのかもしれない。
心の中でぐしゃりと何かを握りしめる音がした。握られているのは写真。それは部屋から消えてしまっても、私の記憶の中にある光景の写真。ぐしゃぐしゃに丸めたそれは、誰にも話すことのできない私の思い出。私はそれを思い出せなくなるその時まで、心の中の誰にも見られない部分に仕舞っておく事しか出来ない。
「そうだよ総悟くん。女ってなぁちっとくらい秘密があった方が魅力的なもんよ。俺なんかかーちゃんのこと産まれた時から知ってるからよぉ」
「何言ってんだい、アタシだってあんたに一つや二つ、一人や二人隠し事くらいあるよ」
「おい一人や二人って何でぃお時」
私の言葉のあとにすぐ続くように、平五郎さんとお時さんの痴話喧嘩が始まった。それは私への、いや。私と総悟くんへの助け舟。これ以上この会話は広げるべきではないと察したのだろう、さすがは年の功だ。
私も彼も、その痴話喧嘩にクスクスと小さく笑いながら目の前の食事を食べ進める。横にいるのは先程ほんの一瞬だけ気不味そうにしていた彼ではない、至って普通。私は心の底から夫妻に感謝しながらピーマンの肉詰めを一口齧り、美味しい、と頬を緩める。大丈夫、今日の私もちゃんと"普通"だ。
(2022/05/01)
カウンター席のお客さん達と話すお時さんの陽気な笑い声を聞きながら、私は空いているテーブルを念入りに拭いたり、消耗品の補充をしていた。残るは新聞を読んでいるおじさんが座るテーブルのみ。拭くのは後にして、一声掛けてから割り箸と爪楊枝の補充をする。
「ナマエちゃん、なんか物騒な事件あったみたいだよ」
目線は新聞の一面に向いたまま、指を差して「これ」と言われた。座っている彼の横から紙面を覗き見ると、そこには大きな文字で『婦女暴行事件』と書かれている。
「今朝のニュースでやってましたね」
「あ、知ってた?」
世間話をするためには、この世界の社会情勢やゴシップの情報を仕入れる必要がある。初めこそ「この世界のテレビを見ていたら気が滅入る」なんて思っていたのだがそんなことを言っている場合では無い。この世界の細かい歴史やら常識やらがわからない私にとって無知は罪、言葉は最大の防御。付け焼き刃でも口先だけでも、何食わぬ顔で堂々と話せば私の拙い知識でも武器となる。そのため家ではテレビをつけっぱなしにしているし、もう一視聴者としてテレビを観る事にも慣れた。この事件も早朝のニュースで見たのだ。
「刀で斬られたってよぉ。本当に物騒な世の中だな、しかも犯人捕まってないって」
元の世界でも似たような事件はあっただろう。異なる点といえば凶器が刀ではないということと、事件の頻度。この世界は廃刀令が出ているとはいえ刀を持つことを許されている人もいるし、無許可で帯刀している者も居る。おそらくニュースにすら取り上げられていない刃傷沙汰がごまんとあるはずだ。前の世界よりも確実に死の危険が身近なのだが、まだその実感は湧いていない。
「まぁこの辺りで起きた事件じゃねえが、他人事じゃねえよ。被害者若い女の子みてぇだし、ナマエちゃんも気ぃつけろよ?」
この事件はかぶき町周辺ではなく、私の生活圏からかなり離れた場所で起きたもの。それに私には「モブキャラの私が新聞の一面に載るような大きな事件に巻き込まれるはずがない」などという、根拠のない自信があった。そのせいかあまり気にも留めていなかった。
とはいえ、それでも気をつけるに越したことは無い。この辺りはお世辞にも治安がいいと言える地域ではないのだ。
「お気遣いありがとうございます」
私の言葉を聞くと新聞を畳んで「お勘定頼むよ」と言って席を立つ。彼に付いてレジへ向かい、会計を済ませて店から出ていく背中を見送った。
そして続き様に、カウンターで食べていたお客さんもレジに向かって来た。この人は土日にたまに来る品の良いおじさま。お釣りの小銭を渡すと、そのお客さんが口を開く。
「先程の話、聞いてましたけど本当に物騒ですね。特に夜は一人で歩かない方が良いですよ」
「そうですね。しばらくは一人で出歩かないようにします」
「それが良いですよ。お気をつけて」
「はい、ありがとうございます」
そのお客さんが店から出ていく背中も見送って、テーブル席を片付けに行く。先にお膳は下げていたので空いた湯呑みと、水の入っていたコップを両手に持って厨房の流しに持っていく。
その途中で総悟くんの手元をチラリと見ると、既に定食を三分の一程度食べ進めている。今帰ったお客さんの食器はお時さんが下げてくれたらしいのでテーブルだけ拭こう。そう思って食器を置くのと入れ替わりに洗った布巾を持って厨房から出てくると、こちらを見ている総悟くんと目があった。
「ナマエちゃんに一緒に出歩く友達がいたとはこいつぁ驚きだ。いつ来ても店に居るから友達いねぇんだと思ってやした」
驚いた顔なんてこれっぽっちもしていない上に、何とも棒読みでそんなことを言う。真顔なのに心なしか目はイキイキしているように見えるのは気のせいだろうか。
彼にそのような話は一度もした事が無いのだが、上京したてで働いてばかりの私に友達がいないとわかっていて言っているのだろうか。
「…嘘も方便ですよ。変に心配かけられませんから」
先程のおじさまとの会話を聞いてた上での彼の発言にそう答える。
あの場ではあの回答以外出来ないだろう、と。帰る直前の客に変なことを言って、困らせるわけにも足止めするわけにもいかない。そもそもレジ前で繰り広げられる会話なんて大体は社交辞令なのだ。それをこちらも社交辞令で返したに過ぎない。
「するってーと、友達いねぇのは図星かぃ」
「間違いないですね」
彼とは目線を合わせずに、先程までお客さんがいたカウンターテーブルを布巾で拭きながら言った。
「ふーん。ま、さっきのおっさん達の言う通りアンタは気をつけた方がいいですぜ」
さほど興味もなかったのか、すぐに別の話題に切り替えた。アンタは、とはどう言う意味だろうか。それが気になって、テーブルを拭く手を止めて彼の方を見る。
「ぱっと見ぃじゃ良家の娘に見えねぇ事もないからな」
「どう言うことですか?」
いよいよ話が見えない。警察だから表に出ていない情報も知っているのだろうか、と思いながら聞き返した。
「とにかく、精々巻き込まれねぇよう休みの日は家で大人しくテレビでも見ときなせぇ」
それ以上は教えてくれないらしく、話に区切りをつけるようにピーマンの肉詰めを一口で詰め込んでもぐもぐし始めた。これ以上話す気はないと悟り、テーブルを全て拭き上げてもう一度厨房に戻った。
「ナマエちゃん、賄い食べるだろう?ちょうど準備出来たから持って行きな」
「ありがとうございます」
先程のお客さんが帰るタイミングで私の賄いを準備していてくれたらしく、平五郎さんが声をかけてくれる。お時さんがセットしてくれたであろうお膳から、臥せてあるお茶碗とお椀をひっくり返してご飯と味噌汁を装う。それをお膳に乗せて厨房を出て、総悟くんの横の席に置いた。
「お隣よろしいですか?」
「かまいやせんよ」
無言で座るほどの仲でもないし、かと言って無言で離れて座るほど険悪でもない。何やかんや毎回横の席に座っているのだが、今回は声を掛けてからそこに座った。
「ナマエちゃんマジでいつ来ても居やすけど、出稼ぎか何かですかぃ?」
先程の会話に戻るのか、そう聞いて来た。この人に一人暮らしだとかいう話は、たしか一度もしたことが無い。初めこそ質問攻めにされた記憶があるが、それ以降は内容も大して思い出せないような会話しかしていない。上京してあくせく働いているのは、故郷への仕送りに必死だからだと思われているのだろうか。
「あ、言ってませんでした?家族いないんです」
「あー、」
次に出す言葉を迷うように、覇気のない間延びした声を出す。彼が言葉を紡がぬように、私は引き続き言った。
「家族も友達もいないからこそ、身軽に一人で江戸に来れたんです。せっかく心機一転、再出発した女の過去を聞くなんて野暮ですよ?」
先程の彼の「友達がいない」というのは、「江戸には」という意味で言ったのだと思う。しかし、それも含めてもう何も聞かれないように。これ以上踏み込むな、と先手を打って制する意味でそう言った。
聞かないで欲しい。私の故郷のこと、知己のこと。だってそこには誰もいない、知ってる人なんて、この世界のどこにもいるはずない。仮に聞かれても「友達も家族もいない女が田舎から出てきた」、そう言えば言葉足らずな説明にも関わらず訳ありだと察してくれるのか、今のところ深く追求されたことは無い。
私の部屋から、本棚の漫画の他にも消えたものがある。それはクローゼットの上段に仕舞っていた物の一つ、写真だ。まだスマホが普及していなかった頃からの名残で、写真は現像されたものをアルバムに収納することが多かった。幼稚園、小学校、中学高校の学校行事の写真。それには当然、卒業アルバムも含まれる。それら全ての写真が無くなったのだ。私の幼少期のピン写真や、両親と田舎に行った数少ない写真だけを残して。友人との写真は跡形もなく消えたというのに、実に気味が悪い。
もともと家を空けることの多かった両親と一緒に撮った写真など数える程しか無く、数冊あったアルバムには一冊で足りるほどの写真しか残っていない。スカスカになったそのアルバムに、入れ替わりで増えている写真があった。まだ幼い頃の私と、同い年くらいの知らない男の子が二人で映っている写真が二枚。それぞれ違う男の子で、歳も違う。一枚は3歳くらいだろうか。もう一枚はもう少し成長していて、そもそも撮った記憶がないので確実な年齢がわからないがおそらく小学校高学年くらい。どちらにも共通して言えるのは背景が田園風景である事と、色褪せたのかセピア色で日付の印字もない事、今まで見た記憶も撮った記憶もない写真だという事。
どうやら私の過去もこの世界に順応したのか、知らない思い出に塗り替えられてしまったらしい。しかし記憶はそのままのせいで、自分の写っている写真なのに何も語ることができない。どうせやるならそこまでしっかり書き換えてくれないと不便で仕方がない。いっそ前の記憶が、思い出が消えてしまった方が気が楽なのに。
私の過去は一体どこへ行ってしまったのだろう。今まで生きた軌跡はどこへ行ったのだろう。それとも初めからなかったのだろうか。私が思い出だと思っているのが虚構で、この記憶がおかしいのかもしれない。
心の中でぐしゃりと何かを握りしめる音がした。握られているのは写真。それは部屋から消えてしまっても、私の記憶の中にある光景の写真。ぐしゃぐしゃに丸めたそれは、誰にも話すことのできない私の思い出。私はそれを思い出せなくなるその時まで、心の中の誰にも見られない部分に仕舞っておく事しか出来ない。
「そうだよ総悟くん。女ってなぁちっとくらい秘密があった方が魅力的なもんよ。俺なんかかーちゃんのこと産まれた時から知ってるからよぉ」
「何言ってんだい、アタシだってあんたに一つや二つ、一人や二人隠し事くらいあるよ」
「おい一人や二人って何でぃお時」
私の言葉のあとにすぐ続くように、平五郎さんとお時さんの痴話喧嘩が始まった。それは私への、いや。私と総悟くんへの助け舟。これ以上この会話は広げるべきではないと察したのだろう、さすがは年の功だ。
私も彼も、その痴話喧嘩にクスクスと小さく笑いながら目の前の食事を食べ進める。横にいるのは先程ほんの一瞬だけ気不味そうにしていた彼ではない、至って普通。私は心の底から夫妻に感謝しながらピーマンの肉詰めを一口齧り、美味しい、と頬を緩める。大丈夫、今日の私もちゃんと"普通"だ。
(2022/05/01)