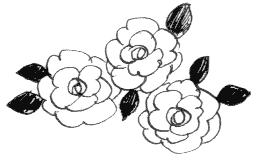一:5月6日
鼠色の無機質なロッカーと、鏡が張り巡らされた横長の化粧台に丸椅子がずらりと並ぶ。なんとなく粉っぽくて、くらくらする甘い香りが立ち込める空間に少し酔いそうになる。
「鏡花さん、そろそろ準備お願いします」
「はい」
私は、控室に呼びに来たボーイさんの声に返事をした。
“鏡花”
それはここ、“スナックすまいる”でバイトしている間の私の偽名……つまり源氏名だ。本名で働くのは少し気が引けた。『源氏名でも構わない』と店長に言われ、咄嗟につけた名前だ。朝のニュース番組で見た『今日の四字熟語は、鏡花水月ですぅ〜』と気の抜けたナレーションが耳に残っていてそこから付けただけ。何の由来も思い入れもない。
「あ、先に店長の部屋に寄って行って下さい」
「わかりました」
今日の日付は5月6日、この世界に来てからついに一ヶ月が経った。何故私が今、ここにいるのか。それを説明するにはあの日、坂田さんに連れられて初めてこの店に来たあの時まで遡る必要がある………………。
▼
『ついて来い』
路地裏でそう言って来た彼の背中を追っている内に、本来の目的地だったスーパーはもうとっくに通り過ぎてしまっていた。前に坂田さんに街案内してもらった時とは異なり、“夜の店”に活気が出てくる時間帯。隣を歩く勇気がなくて彼の一歩後ろで左右に視線を散らしていると、視界に入る看板を見たことがあるような、ないような。この辺りは以前彼に連れてきてもらったような、もらわなかったような……と、その程度の曖昧な記憶。たった一度歩いただけじゃ完璧に覚えられないし、昼と夜で風景が異なる。そもそも似たような看板ばっかりなのだから……いや、そんなものは言い訳だ。これが現代っ子の宿命、今までスマホに頼り過ぎていた罰かもしれない。
(さっき、坂田さんがいなかったら、どうなってたんだろう)
あのまま路地裏に引きずり込まれて、良いとこで体を触られる程度。最悪の場合は嬲り殺されていたかもしれない。呼んでもいない坂田さんの登場により私は助かった。
そんな私を助けた張本人の彼は、先程から引っ切り無しに声を掛けられている。周囲の喧騒も理由ではあるのだが、彼と私の間に会話がないのはそのせいだと思う。ティッシュを配るキャバ嬢、居酒屋の客引き、店の前で大きな看板を持った人、千鳥足の酔っ払いなど。多種多様な人物に声を掛けられるがその中に誰一人、私の“知っている”人物はいなかった。
(……みんな私と同じ、モブ)
かぶき町で顔の広い彼の事だ。声を掛けて来る人物の中には、ただの店員と客という顔見知り程度の知り合いの者もいるだろう。私もその人たちと同じだ。もう道でぶつかった“あの日”とは違う。私はもう、ただの知り合いなのだ。偶然町で会って話すことも、一緒に歩くことも何も不自然なことではないのだから堂々としていれば良い。そう言い聞かせ、丸まっていた背筋が伸びてきたところで“知っている”店の前にたどり着いた。
“スナックすまいる”の扉を潜ると慣れた様子でボーイさんと話す坂田さん。それを横目に店内を見渡すと、目下に下り階段。奥まで通路が続き、その左右にボックス席がズラッと設置されている。
(……本物だ)
何とも既視感のある光景が広がっていた。決して遠くない距離に住んではいるが、実際足を踏み入れることになるとは思わなかった。そこは間違いなく、あの“将軍様ゲーム”が繰り広げられていた場所で、実際にこの目で見ると少し胸が躍る。
――――――しかし、席に着いてから数刻で私は厠へ逃げ込むことになった。
この場所で会う可能性の高い二人、お妙さんと近藤さん。二人との同席に関しては何ら問題も心配もなかった。予想の範囲内に過ぎなかったから。問題は、坂田さんの発言だった。
「少し、席を外しても良いですか?」
「何、厠?」
「はい」
私は会話の切りの良い所で席を外し、厠……お手洗いへ向かった。個室に入り、鍵を閉め、深いため息をつきながら便器に腰かけた。そして、先程坂田さんに言われた言葉を思い出す。
『騒がしい所の方が良いと思って。ナマエちゃんが寂しそう〜にしてたから』
『明日から休みなんだろ?どうせやることなくて暇なんだろ?寂しいでちゅね〜?ぷぷぷっ』
(何で……あんなこと言うかなぁ)
わざとらしい笑い方だった。そしてピンと不自然に伸ばした指先で口を覆って。太くゴツゴツした男らしい指、手首から肘にかけて浮き上がった筋。そんな逞しい体の男が無意識にやるはずのないポーズは、確実に私を馬鹿にしていた。
(あぁでも……やっぱ、“銀さん”って感じしたなぁ)
下ネタもセクハラも、下品なものだと捉えられない事がある。そのためには、時と場合を見極める観察力や空気を読む力が必須。相当高等なトークスキルだと思ってる。“今この場で下ネタを言ったらどうなるか”を判断した上で言うものは、相手に精神的苦痛を与える穢らわしいものとは限らない。あの人はもともと口が達者で、空気が読める。そして、自然な気配りができる人だと思うから。
『女には陰で色々やる事がありますから、それなりに忙しいんですよ』
『あれか、髪の毛とか眉毛とかケツ毛とかの処理?』
『何で全部毛の話なんですか』
『女の陰の努力つったら全身の毛に纏わる話だろ』
(……あぁやって、話を逸らしていく人なんだろうな)
馴れ馴れしくスルッと人の懐に入り込んでくるくせに、肝心なところではきちんと一線引いて距離を取るのが上手。それは同時に、相手にも踏み込ませない壁があるとも言える。その縮まらない距離に安堵する。あなたの軽口に、こちらものらりくらり。核心に触れなくても許される気がしてしまう。
(でも……人の気も、知らないでさぁ)
『寂しそう〜にしてたから』
『寂しいでちゅね〜?』
春、出会いと別れの季節。何もかも全てと別れを告げた私が、どんな思いであなた達と“出会っている”と思ってるんだ。胸にどろっと黒いものが流れて、心の中にぐしゃぐしゃに丸めて隠し持っている写真を汚していく。それはまるでマグマの様に熱を持っていて、全部跡形もなく溶かしてしまう。冷え固まったころには、それはもう別物。あぁ、やっぱり私の“思い出”なんて初めから存在してない虚構なのかもしれない、って。
(余計な事考えちゃうから、要らないなぁ……休み)
平五郎さんとお時さんと一緒に過ごすあの店での日常は、あまりにも平和、平穏、平凡。店では店主夫妻だけでなくお客さんも『ナマエちゃん、ナマエちゃん』って、たくさん名前を呼んでくれる。
『ナマエちゃん、明日から二日休みね』
『え、……さらに突然ですね』
『もう仕事、慣れただろう?いい加減休まないと』
『せめて一日に……』
以前、お時さんに言われた言葉を思い出す。私への気遣いだったことは理解している。しかし、私は休みなんて本当に欲しくなかったのだ。
『おやおや、寂しいのかい?ふふ、じゃあ一日ね』
私はまた深いため息をついて、便座から立ち上がった。トイレの個室から出た私は、ジャーっと水道水で手を洗う。顔を上げると、大きな鏡に自分の姿が映っている。その顔を見ると無意識に顔を俯き、一番深いため息を吐いた。
「ナマエさん」
「……お妙さん」
背後から聞こえた声に思わず顔を上げると、鏡に自分以外の女性の姿が映っていた。その女性はこちらにゆっくり歩み寄って来て私の横で足を止める。
「ご気分でも悪いですか?」
「いえ、……初めて来る場所で、少し緊張してしまって」
きっとため息を聞かれてしまったのだろうと思い咄嗟に出た言い訳ではあるが、嘘じゃない。キャバクラに来るのは当然初めてなのだ。実際、緊張はしている。
「あら、とっても馴染んでますよ?」
「お妙さんが盛り上げ上手だからですよ」
「ふふっ、ありがとうございます。……ナマエさん」
落ち着いた口調の、ソプラノボイスが私の名前を呼ぶ。
「実は、折り合ってお願いがあるんです」
「……何でしょうか?」
「明日からお休みって、仰ってましたよね?よかったら、うちでバイトしませんか?」
「バイト、ですか?」
「えぇ、実は今、人手不足が深刻でして。急繕でも人が欲しいんですけど、誰でも良いというわけにもいきません。ナマエさんなら、接客業もされてますし即戦力になってくださるんじゃないかと思うんです」
「私は、場を盛り上げたりするのは苦手で」
本当に。先ほどまでのお妙さんのように場の沈黙を作らないような気遣いができる女ではない。
「それは大丈夫ですよ。お願いしたいのは私のヘルプですから。安心して下さい」
正直、目の前に垂らされているその糸はとても魅力的だった。
(私、働いている方が…………体調が良いんだよなぁ)
そう思うと、無意識に手を伸ばして掴んでしまう。
「わかりました。やらせて下さい」
「ありがとうございます。本当に助かります。ふふっ、セクハラはぶっ潰しますからその辺も安心して下さいね」
鈴が鳴るような綺麗な笑い声、可憐な笑顔。それに似つかわしくない、力拳をアピールする様なポーズ。彼女が強いことをよく知っているので、その発言は何と頼りがいのある事か。
「あー、ほんと良かった!銀さんのことだからきっとまた会わせてくれると思ってたんです。男の人って単純ねぇ」
「??」
「初めて会ったあの時から目を付けてたんですよ」
「……あぁ、」
なるほど。初めからバイトに勧誘するつもりだったと。正直、初対面の時からあまり良い印象を持たれていないのだと思っていたのだが、あれはここに至るまでの布石だった、ということらしい。
(……やっぱり敵に回したくないタイプの女の子、だ)
「あ、そういえばお幾つか伺っても良いかしら?」
酒を扱う職種だ。年齢確認が必要なのだろう。そう思い年齢を告げると、「あら、私と同じですね」という。
(……あぁ、そうか。私、彼女と同い年なのか。なんて、大人っぽいんだろう)
自分なんかと比べ物にならないくらい。前の世界で『大人っぽいね』なんて言われていた私から見ても、彼女は本当に大人びている。
ここでは私のいた世界よりも“大人扱い”される年齢が早い。私の世界では見た目だけ重厚な学生鞄を持って漠然と生きている年齢の子たちが、ここではその鞄と比べ物にならないような重たい物を背負って生きている気がする。彼女もその一人だ。幼い頃から親に代わって弟を、道場を守ってきた。そんな強く逞しい女性。
「同じくらいかなぁとは思っていたんです。あ、連絡先交換しません?携帯電話、お持ちですか?」
「はい」
一応厠に来る時に持って来ていた手提げ鞄。そこから“ガラケー”を取り出し、パカっと画面を開く。
「赤外線、私から送信しますね」
(一体、今って“いつ頃”なんだろう)
……何故、自分がいる世界よりも文明が遡ってしまったのだろうか。
ガラケー世代はこうやって連絡先交換してたのか、なんてすっかりスマホに慣れている自分は、他人事のように思ってしまう。
今、この瞬間は、漫画の“何巻”にあたるのか。
そんなことを考えている間に、人生で初めての赤外線通信を無事終えた。
▲
………………あれから話は早かった。あの後、厠を出るなり通路で会ったボーイさんに私のバイトの件を店長さんに通しておくように話をつけていた彼女。そのボーイさんは、茶房にあんみつを取りに来た人で、『一緒にお仕事できるの楽しみにしてますね』と言ってくれた。社交辞令とはいえとても安心したのを覚えている。そして翌日さっそく店長と面談をし、今現在に至るというわけだ。
「いやぁ〜、ほんとお妙ちゃんには感謝しなきゃ。こんな大物ルーキー連れてきてくれて」
ボーイさんに言われた通り控室から出てきた私は今、店長の部屋にいる。
「私も、楽しく働かせてもらいました。お妙にはもちろん、店長にも感謝してます」
彼女に誘われた際の言葉通り、私は指名客の多い彼女にヘルプとしてずっと同じテーブルに引っ付いていた。女の園、というくらいだからギスギスしたものを想像する人もいるかもしれないが、私は初めから彼女のヘルプ要員でバイトに誘われたので競う必要が無い。その立ち位置のおかげもあるが、運良く彼女とは気が合うタイプだったようで、名前を呼び捨てしあう程度には打ち解けた。
「でも今日で本当に最終日かぁ……ね、ホントにうちで働く気ない?」
「すみません。お気持ちはうれしいんですが……」
「いやいや、冗談冗談!山本さんたちにも悪いからねぇ!」
茶房のあんみつを贔屓にしてくれている店長は、店主である山本夫妻とも古い付き合いなのだという。
「それに、本当は昨日で最終日だったところを今日も来てもらっちゃって。それだけでもう本当十分助かるから。ありがとうねぇ」
店長の言葉通り、本来であれば昨日がバイト最終日だった。しかし私は今日も引き続き出勤している。これには訳がある。
「お妙ちゃんにはだいぶ無理してもらっちゃってたからなぁ……。インフル流行中でも一人生き延びてたのにまさか風邪拗らしちゃうとはねぇ」
昨日までずっと出勤日はお妙と同じ日。実は家の方面も同じで、帰りは毎日一緒に帰っていた。だからこそ、彼女の変化には気付いていた。
「一昨日から少し空咳してましたからね。過労と重なってしまったのかと」
「そうだねぇ。人手不足とは言え申し訳ないことしちゃったなぁ。でも、ほんとナマエちゃんが来てくれて助かるよ」
昨日、店を閉めた後に咳が酷くなっていく彼女に休むように言ったのは私だ。しかし『主戦力が休むとなると人手が足りない』という話になり私が微力ながらバイトを延長して出勤する運びとなった。
「私でお役に立ててるかはわかりませんが……」
「いやいや!言ったでしょ?大物ルーキーだって!ナマエちゃんなら一人でも卓に着けると思うのよ!」
キャバ嬢のヘルプには二種類ある。一つは、指名キャバ嬢と一緒に席についた時の盛り上げ役としての接客。私が昨日まで頼まれていたのはこれだ。
そしてもう一つは、指名のない客の相手や、指名キャバ嬢が他の指名客の所に居る間の繋ぎとしての接客。今日頼まれているのはこっち。正直、不安しかない。なんせ、お妙は私を席に一人にするなんてこと一切無くて、本当にずっと一緒に接客してくれていたのだ。『セクハラは(物理的に)ぶっ潰すから安心して』と言っていたことばの通り非常に頼もしくて、……勇ましい姿だった。
「お酒はこれまで通り、無理して飲まなくて良いからね」
「すみません」
「いいのいいの。むしろ飲めないならハッキリ言ってもらえたほうが助かるからね」
働き始める前の面談で『お酒は飲めるか』という質問をされた。もちろん、飲んだことなんて無い。しかし、その答えが“普通”なのか分からなかった。私と同い年のはずのお妙はガバガバ飲んでるわけだから。それに、同い年の総悟くんも飲んでいる“描写”がある。
……ここは、東京ではない。江戸なのだ。飲酒や喫煙を取り締まる概念が生まれたのは、江戸時代よりも後の話。もし“元服”という概念が生きているのであれば、この世界の人たちは私より若い人間がとっくに酒の味を知っている。そうなると“飲んだことがない”と答えるのは少しリスクが高い気がした。
「それにちょっと弱いくらいの方が可愛げもあるよ。ここで働いている子たちほんとバケモンみたいにアルコール強いから」
私は店長の質問に対して『酒が苦手』と答えたのだ。それが一番手っ取り早いと思ったから。あくまで、飲める立場であるけど手をつけてこなかった。そんな人間を装わなければいけないのだ。郷に入っては郷に従う、というわけだ。
「今日もね、無理して飲まなくて良いから。黒服が持ってくるやつはノンアルにするし、お客さんから貰ったやつはテキトーに口付けるフリしといてね」
飲めない女が酒で粗相を起こすのは問題。だからこうして飲まなくて良い選択肢を与えてくれる。とても働きやすい職場だと思う。
「はい。ありがとうございます」
しかし、いくら働きやすいと言っても私は数日ヘルプを経験しただけ。一人で席に着くなんて、引き受けてしまったのは少し浅はかだったかもしれない。
「鏡花さん、そろそろ準備お願いします」
「はい」
私は、控室に呼びに来たボーイさんの声に返事をした。
“鏡花”
それはここ、“スナックすまいる”でバイトしている間の私の偽名……つまり源氏名だ。本名で働くのは少し気が引けた。『源氏名でも構わない』と店長に言われ、咄嗟につけた名前だ。朝のニュース番組で見た『今日の四字熟語は、鏡花水月ですぅ〜』と気の抜けたナレーションが耳に残っていてそこから付けただけ。何の由来も思い入れもない。
「あ、先に店長の部屋に寄って行って下さい」
「わかりました」
今日の日付は5月6日、この世界に来てからついに一ヶ月が経った。何故私が今、ここにいるのか。それを説明するにはあの日、坂田さんに連れられて初めてこの店に来たあの時まで遡る必要がある………………。
▼
『ついて来い』
路地裏でそう言って来た彼の背中を追っている内に、本来の目的地だったスーパーはもうとっくに通り過ぎてしまっていた。前に坂田さんに街案内してもらった時とは異なり、“夜の店”に活気が出てくる時間帯。隣を歩く勇気がなくて彼の一歩後ろで左右に視線を散らしていると、視界に入る看板を見たことがあるような、ないような。この辺りは以前彼に連れてきてもらったような、もらわなかったような……と、その程度の曖昧な記憶。たった一度歩いただけじゃ完璧に覚えられないし、昼と夜で風景が異なる。そもそも似たような看板ばっかりなのだから……いや、そんなものは言い訳だ。これが現代っ子の宿命、今までスマホに頼り過ぎていた罰かもしれない。
(さっき、坂田さんがいなかったら、どうなってたんだろう)
あのまま路地裏に引きずり込まれて、良いとこで体を触られる程度。最悪の場合は嬲り殺されていたかもしれない。呼んでもいない坂田さんの登場により私は助かった。
そんな私を助けた張本人の彼は、先程から引っ切り無しに声を掛けられている。周囲の喧騒も理由ではあるのだが、彼と私の間に会話がないのはそのせいだと思う。ティッシュを配るキャバ嬢、居酒屋の客引き、店の前で大きな看板を持った人、千鳥足の酔っ払いなど。多種多様な人物に声を掛けられるがその中に誰一人、私の“知っている”人物はいなかった。
(……みんな私と同じ、モブ)
かぶき町で顔の広い彼の事だ。声を掛けて来る人物の中には、ただの店員と客という顔見知り程度の知り合いの者もいるだろう。私もその人たちと同じだ。もう道でぶつかった“あの日”とは違う。私はもう、ただの知り合いなのだ。偶然町で会って話すことも、一緒に歩くことも何も不自然なことではないのだから堂々としていれば良い。そう言い聞かせ、丸まっていた背筋が伸びてきたところで“知っている”店の前にたどり着いた。
“スナックすまいる”の扉を潜ると慣れた様子でボーイさんと話す坂田さん。それを横目に店内を見渡すと、目下に下り階段。奥まで通路が続き、その左右にボックス席がズラッと設置されている。
(……本物だ)
何とも既視感のある光景が広がっていた。決して遠くない距離に住んではいるが、実際足を踏み入れることになるとは思わなかった。そこは間違いなく、あの“将軍様ゲーム”が繰り広げられていた場所で、実際にこの目で見ると少し胸が躍る。
――――――しかし、席に着いてから数刻で私は厠へ逃げ込むことになった。
この場所で会う可能性の高い二人、お妙さんと近藤さん。二人との同席に関しては何ら問題も心配もなかった。予想の範囲内に過ぎなかったから。問題は、坂田さんの発言だった。
「少し、席を外しても良いですか?」
「何、厠?」
「はい」
私は会話の切りの良い所で席を外し、厠……お手洗いへ向かった。個室に入り、鍵を閉め、深いため息をつきながら便器に腰かけた。そして、先程坂田さんに言われた言葉を思い出す。
『騒がしい所の方が良いと思って。ナマエちゃんが寂しそう〜にしてたから』
『明日から休みなんだろ?どうせやることなくて暇なんだろ?寂しいでちゅね〜?ぷぷぷっ』
(何で……あんなこと言うかなぁ)
わざとらしい笑い方だった。そしてピンと不自然に伸ばした指先で口を覆って。太くゴツゴツした男らしい指、手首から肘にかけて浮き上がった筋。そんな逞しい体の男が無意識にやるはずのないポーズは、確実に私を馬鹿にしていた。
(あぁでも……やっぱ、“銀さん”って感じしたなぁ)
下ネタもセクハラも、下品なものだと捉えられない事がある。そのためには、時と場合を見極める観察力や空気を読む力が必須。相当高等なトークスキルだと思ってる。“今この場で下ネタを言ったらどうなるか”を判断した上で言うものは、相手に精神的苦痛を与える穢らわしいものとは限らない。あの人はもともと口が達者で、空気が読める。そして、自然な気配りができる人だと思うから。
『女には陰で色々やる事がありますから、それなりに忙しいんですよ』
『あれか、髪の毛とか眉毛とかケツ毛とかの処理?』
『何で全部毛の話なんですか』
『女の陰の努力つったら全身の毛に纏わる話だろ』
(……あぁやって、話を逸らしていく人なんだろうな)
馴れ馴れしくスルッと人の懐に入り込んでくるくせに、肝心なところではきちんと一線引いて距離を取るのが上手。それは同時に、相手にも踏み込ませない壁があるとも言える。その縮まらない距離に安堵する。あなたの軽口に、こちらものらりくらり。核心に触れなくても許される気がしてしまう。
(でも……人の気も、知らないでさぁ)
『寂しそう〜にしてたから』
『寂しいでちゅね〜?』
春、出会いと別れの季節。何もかも全てと別れを告げた私が、どんな思いであなた達と“出会っている”と思ってるんだ。胸にどろっと黒いものが流れて、心の中にぐしゃぐしゃに丸めて隠し持っている写真を汚していく。それはまるでマグマの様に熱を持っていて、全部跡形もなく溶かしてしまう。冷え固まったころには、それはもう別物。あぁ、やっぱり私の“思い出”なんて初めから存在してない虚構なのかもしれない、って。
(余計な事考えちゃうから、要らないなぁ……休み)
平五郎さんとお時さんと一緒に過ごすあの店での日常は、あまりにも平和、平穏、平凡。店では店主夫妻だけでなくお客さんも『ナマエちゃん、ナマエちゃん』って、たくさん名前を呼んでくれる。
『ナマエちゃん、明日から二日休みね』
『え、……さらに突然ですね』
『もう仕事、慣れただろう?いい加減休まないと』
『せめて一日に……』
以前、お時さんに言われた言葉を思い出す。私への気遣いだったことは理解している。しかし、私は休みなんて本当に欲しくなかったのだ。
『おやおや、寂しいのかい?ふふ、じゃあ一日ね』
私はまた深いため息をついて、便座から立ち上がった。トイレの個室から出た私は、ジャーっと水道水で手を洗う。顔を上げると、大きな鏡に自分の姿が映っている。その顔を見ると無意識に顔を俯き、一番深いため息を吐いた。
「ナマエさん」
「……お妙さん」
背後から聞こえた声に思わず顔を上げると、鏡に自分以外の女性の姿が映っていた。その女性はこちらにゆっくり歩み寄って来て私の横で足を止める。
「ご気分でも悪いですか?」
「いえ、……初めて来る場所で、少し緊張してしまって」
きっとため息を聞かれてしまったのだろうと思い咄嗟に出た言い訳ではあるが、嘘じゃない。キャバクラに来るのは当然初めてなのだ。実際、緊張はしている。
「あら、とっても馴染んでますよ?」
「お妙さんが盛り上げ上手だからですよ」
「ふふっ、ありがとうございます。……ナマエさん」
落ち着いた口調の、ソプラノボイスが私の名前を呼ぶ。
「実は、折り合ってお願いがあるんです」
「……何でしょうか?」
「明日からお休みって、仰ってましたよね?よかったら、うちでバイトしませんか?」
「バイト、ですか?」
「えぇ、実は今、人手不足が深刻でして。急繕でも人が欲しいんですけど、誰でも良いというわけにもいきません。ナマエさんなら、接客業もされてますし即戦力になってくださるんじゃないかと思うんです」
「私は、場を盛り上げたりするのは苦手で」
本当に。先ほどまでのお妙さんのように場の沈黙を作らないような気遣いができる女ではない。
「それは大丈夫ですよ。お願いしたいのは私のヘルプですから。安心して下さい」
正直、目の前に垂らされているその糸はとても魅力的だった。
(私、働いている方が…………体調が良いんだよなぁ)
そう思うと、無意識に手を伸ばして掴んでしまう。
「わかりました。やらせて下さい」
「ありがとうございます。本当に助かります。ふふっ、セクハラはぶっ潰しますからその辺も安心して下さいね」
鈴が鳴るような綺麗な笑い声、可憐な笑顔。それに似つかわしくない、力拳をアピールする様なポーズ。彼女が強いことをよく知っているので、その発言は何と頼りがいのある事か。
「あー、ほんと良かった!銀さんのことだからきっとまた会わせてくれると思ってたんです。男の人って単純ねぇ」
「??」
「初めて会ったあの時から目を付けてたんですよ」
「……あぁ、」
なるほど。初めからバイトに勧誘するつもりだったと。正直、初対面の時からあまり良い印象を持たれていないのだと思っていたのだが、あれはここに至るまでの布石だった、ということらしい。
(……やっぱり敵に回したくないタイプの女の子、だ)
「あ、そういえばお幾つか伺っても良いかしら?」
酒を扱う職種だ。年齢確認が必要なのだろう。そう思い年齢を告げると、「あら、私と同じですね」という。
(……あぁ、そうか。私、彼女と同い年なのか。なんて、大人っぽいんだろう)
自分なんかと比べ物にならないくらい。前の世界で『大人っぽいね』なんて言われていた私から見ても、彼女は本当に大人びている。
ここでは私のいた世界よりも“大人扱い”される年齢が早い。私の世界では見た目だけ重厚な学生鞄を持って漠然と生きている年齢の子たちが、ここではその鞄と比べ物にならないような重たい物を背負って生きている気がする。彼女もその一人だ。幼い頃から親に代わって弟を、道場を守ってきた。そんな強く逞しい女性。
「同じくらいかなぁとは思っていたんです。あ、連絡先交換しません?携帯電話、お持ちですか?」
「はい」
一応厠に来る時に持って来ていた手提げ鞄。そこから“ガラケー”を取り出し、パカっと画面を開く。
「赤外線、私から送信しますね」
(一体、今って“いつ頃”なんだろう)
……何故、自分がいる世界よりも文明が遡ってしまったのだろうか。
ガラケー世代はこうやって連絡先交換してたのか、なんてすっかりスマホに慣れている自分は、他人事のように思ってしまう。
今、この瞬間は、漫画の“何巻”にあたるのか。
そんなことを考えている間に、人生で初めての赤外線通信を無事終えた。
▲
………………あれから話は早かった。あの後、厠を出るなり通路で会ったボーイさんに私のバイトの件を店長さんに通しておくように話をつけていた彼女。そのボーイさんは、茶房にあんみつを取りに来た人で、『一緒にお仕事できるの楽しみにしてますね』と言ってくれた。社交辞令とはいえとても安心したのを覚えている。そして翌日さっそく店長と面談をし、今現在に至るというわけだ。
「いやぁ〜、ほんとお妙ちゃんには感謝しなきゃ。こんな大物ルーキー連れてきてくれて」
ボーイさんに言われた通り控室から出てきた私は今、店長の部屋にいる。
「私も、楽しく働かせてもらいました。お妙にはもちろん、店長にも感謝してます」
彼女に誘われた際の言葉通り、私は指名客の多い彼女にヘルプとしてずっと同じテーブルに引っ付いていた。女の園、というくらいだからギスギスしたものを想像する人もいるかもしれないが、私は初めから彼女のヘルプ要員でバイトに誘われたので競う必要が無い。その立ち位置のおかげもあるが、運良く彼女とは気が合うタイプだったようで、名前を呼び捨てしあう程度には打ち解けた。
「でも今日で本当に最終日かぁ……ね、ホントにうちで働く気ない?」
「すみません。お気持ちはうれしいんですが……」
「いやいや、冗談冗談!山本さんたちにも悪いからねぇ!」
茶房のあんみつを贔屓にしてくれている店長は、店主である山本夫妻とも古い付き合いなのだという。
「それに、本当は昨日で最終日だったところを今日も来てもらっちゃって。それだけでもう本当十分助かるから。ありがとうねぇ」
店長の言葉通り、本来であれば昨日がバイト最終日だった。しかし私は今日も引き続き出勤している。これには訳がある。
「お妙ちゃんにはだいぶ無理してもらっちゃってたからなぁ……。インフル流行中でも一人生き延びてたのにまさか風邪拗らしちゃうとはねぇ」
昨日までずっと出勤日はお妙と同じ日。実は家の方面も同じで、帰りは毎日一緒に帰っていた。だからこそ、彼女の変化には気付いていた。
「一昨日から少し空咳してましたからね。過労と重なってしまったのかと」
「そうだねぇ。人手不足とは言え申し訳ないことしちゃったなぁ。でも、ほんとナマエちゃんが来てくれて助かるよ」
昨日、店を閉めた後に咳が酷くなっていく彼女に休むように言ったのは私だ。しかし『主戦力が休むとなると人手が足りない』という話になり私が微力ながらバイトを延長して出勤する運びとなった。
「私でお役に立ててるかはわかりませんが……」
「いやいや!言ったでしょ?大物ルーキーだって!ナマエちゃんなら一人でも卓に着けると思うのよ!」
キャバ嬢のヘルプには二種類ある。一つは、指名キャバ嬢と一緒に席についた時の盛り上げ役としての接客。私が昨日まで頼まれていたのはこれだ。
そしてもう一つは、指名のない客の相手や、指名キャバ嬢が他の指名客の所に居る間の繋ぎとしての接客。今日頼まれているのはこっち。正直、不安しかない。なんせ、お妙は私を席に一人にするなんてこと一切無くて、本当にずっと一緒に接客してくれていたのだ。『セクハラは(物理的に)ぶっ潰すから安心して』と言っていたことばの通り非常に頼もしくて、……勇ましい姿だった。
「お酒はこれまで通り、無理して飲まなくて良いからね」
「すみません」
「いいのいいの。むしろ飲めないならハッキリ言ってもらえたほうが助かるからね」
働き始める前の面談で『お酒は飲めるか』という質問をされた。もちろん、飲んだことなんて無い。しかし、その答えが“普通”なのか分からなかった。私と同い年のはずのお妙はガバガバ飲んでるわけだから。それに、同い年の総悟くんも飲んでいる“描写”がある。
……ここは、東京ではない。江戸なのだ。飲酒や喫煙を取り締まる概念が生まれたのは、江戸時代よりも後の話。もし“元服”という概念が生きているのであれば、この世界の人たちは私より若い人間がとっくに酒の味を知っている。そうなると“飲んだことがない”と答えるのは少しリスクが高い気がした。
「それにちょっと弱いくらいの方が可愛げもあるよ。ここで働いている子たちほんとバケモンみたいにアルコール強いから」
私は店長の質問に対して『酒が苦手』と答えたのだ。それが一番手っ取り早いと思ったから。あくまで、飲める立場であるけど手をつけてこなかった。そんな人間を装わなければいけないのだ。郷に入っては郷に従う、というわけだ。
「今日もね、無理して飲まなくて良いから。黒服が持ってくるやつはノンアルにするし、お客さんから貰ったやつはテキトーに口付けるフリしといてね」
飲めない女が酒で粗相を起こすのは問題。だからこうして飲まなくて良い選択肢を与えてくれる。とても働きやすい職場だと思う。
「はい。ありがとうございます」
しかし、いくら働きやすいと言っても私は数日ヘルプを経験しただけ。一人で席に着くなんて、引き受けてしまったのは少し浅はかだったかもしれない。