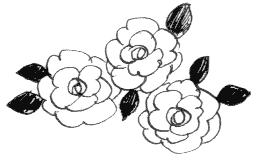二:四月二十四日 日曜日
…………そんな彼女との出会いを思い出しながら、イケオジと同じくナマエちゃんをチラリと目の端に捉える。
「まぁ夜はしばらく出歩かん方がいいでしょうねィ」
ただでさえ、日中の公園で絡まれた前例があるのだから。そもそも今日俺は、彼女に忠告しに店に来たんだ。
「あら、やっぱり心配してくれてるんだねぇ」
「……仕事増やさねえで欲しいだけでさァ」
「あっはっは!素直じゃないねぇ!まぁでもさぁ、もし街で見かけたりしたら気いかけてやってくんないかい?」
やたらと彼女と俺を絡めたがるおばちゃん。でもその言葉から“俺に心配させたい”というよりは、おばちゃん自身が彼女のことを心配していると言うことが伝わってくる。
「今んところ店以外で一回も見た事無えんですが」
「まぁ、あの子全然休まないからね」
「確かにいつ来ても居やすねぃ」
「江戸に誰も知り合い居ないって言ってたからねぇ。寂しいんだろうねぇ、なかなか休みたがらないんだよ」
そんなタイプなのか?てっきり、一人で過ごすのが好きそうな冷めたタイプの女に見えてたけど。少なくとも、同い年の俺にはそう映っていた。最初に年齢を聞いた時にはこのひどく落ち着いた女が俺と同い年か、と驚いた。しかし女の年齢なんてぱっと見じゃあわからない。姉御だってあぁ見えて同い年なんだから、そう考えると妥当だとも思った。女ってのは何でも笑顔で隠しちまう。
「しっかりしたお嬢さんですがね」
「だからこそだよ。頼り方のわからない不器用な子なんだ」
「まぁ確かに心配ではありますね。気丈に振る舞っているようにも見えて」
一回り以上歳の離れた二人には、そのように映っているらしい。俺としては憂いを帯びた微笑を張り付けてる彼女は、何考えてんのかよくわかんねえけど余裕があって達観してるような態度に見える。それに端正な顔立ちのせいか、一歩間違えばとっつき難く冷たい印象にも見えかねない女だとも思ってる。……年の功あってこそ見えるものもあるのかねぇ。
「私も街で見かけたら声をかけるようにしましょう」
「そうしてやっておくれ」
「そろそろお暇しますね。ご馳走様でした、沖田さんもまた」
「ありがとうよ」
「…………」
おばちゃんだけではなく俺にも律儀に声をかけるイケオジに、俺はもぐもぐと咀嚼しながら無言で手をひらりと振った。そして引き続き目の前の定食に箸を伸ばす。
おばちゃんは今イケオジが飲んでいた空の湯飲みを持つと「あたしゃ片付けてナマエちゃんの分の定食準備してくるから」と言って厨房の中に入って行った。どうやら今日も横で食うのは確定らしい。
「先程の話、聞いてましたけど本当に物騒ですね。特に夜は一人で歩かない方が良いですよ」
前の客がちょうど店から出て行ったタイミングで、背後のレジに向かったイケオジ。その彼の声が背中側から聞こえた。
「そうですね。しばらくは一人で出歩かないようにします」
レジ前でナマエちゃんと会話しているらしい。“じゃあ誰と歩くのか”、そう聞いたら答えるのだろうか。おばちゃんの言い方だと、まだ上京して日の浅い彼女は江戸に友人の類なんていないんだろう。イケオジもそれをわかった上で「それが良いですよ。お気をつけて」なんて何も知らないフリをして答える。これが大人の対応で、気遣いなんだろうか。何とも回りくどい。
「はい、ありがとうございます」
“いつも”より少し滑舌が良くて聞き取りやすい、ハキハキとした声。それは接客仕様の彼女の声だった。
会話が止んで引き戸を開け閉めする音を背中で聞いた後、両手にコップを持って厨房に入っていくナマエちゃんの姿が見えた。常にローテンションで、心底俺に興味のないこの冷め気味の女と話すのは気を遣わないので楽だ。それは確かなのだが、淡々としたリアクションとは別の顔が見てみたい。そう思うのは年相応の男としては100点満点の行動心理じゃないだろうか。例えば、不快に顔を歪めたブッサイクの顔だとか。そしてすぐに厨房から出てきたその女に、俺は声をかけた。
「ナマエちゃんに一緒に出歩く友達がいたとはこいつぁ驚きだ。いつ来ても店に居るから友達いねぇんだと思ってやした」
友達がいないのはおばちゃんの『江戸に知り合いがいない』という発言で気付いているのに、我ながら白々しい顔でそんなことを言った。おばちゃんに『気にかけやってくれ』なんて言われたが、あいにく俺はこんな言い方しか知らない。イケオジと違って、この女に気を遣って回りくどい言い回しをするなんて優しさも持ち合わせちゃあいない。
それに、どんな顔をするだろう、と。顔を歪めたり苛立ったりするのを期待して、嫌味っぽく言ってみた。しかしその表情は僅かに眉尻を下げた、困ったような笑顔。この顔はよく見る。
「……嘘も方便ですよ。変に心配かけられませんから」
その困り顔は、イケオジに対する罪悪感が何かだろうか。
聞けば答える女だとは思っていたのだが、この手の話題は振ったことがなかった。初めこそ質問攻めにした記憶はあるが、人間関係などを突っ込むのは避けていた。そこを掘ると自然と家族の話も突くことになる。俺自身もう誰も肉親はいないし、何となくハードルが高かったのだ。それに何かしらの地雷がある奴だろうと思っていた。朝っぱらからそれを踏んで変に気まずい雰囲気になるのは御免だし、頭を使わない薄い内容の話しかしていない。
しかし自ら話してくる事は無いが、やっぱり聞けば答える。友達がいないと言う事を隠すつもりはないらしく、素直に認めるかのように『嘘』と言った。
「するってーと、友達いねぇのは図星かぃ」
「間違いないですね」
俺に目を合わせずに俯いて机を拭いている彼女の顔は見えないが、いつもより気怠げに間延びした声に聞こえた。鬱陶しいと顔を顰めているなら物珍しい。しかし、今見えてない顔はきっといつも通り。あの代わり映えのしない、余裕そうな微笑を張り付けてるんだろう。そう思うとすぐつまらない気持ちになる。
「ふーん。ま、さっきのおっさんの言う通り、アンタは気をつけた方がいいですぜ」
俺の言葉に、机を拭く手を止めて顔を上げる。こちらを見るその表情はキョトンとしていた。
「田舎もんのお上りだなんて思わねぇし、ぱっと見ぃじゃ良家の娘に見えねぇ事もないからな」
「どう言うことですか?」
生憎これ以上は話すことができないのだが、せめてもの忠告のつもりでそう言った。一応こんな可愛げのない女だが、今日は警察という立場としての彼女へ注意喚起をしに来た。
……件の連続婦女暴行事件の被害者の特徴に、目の前の女が一致している。暗い髪色、まとめ髪、細身で大人びた風貌の若い女。そしてぱっと見育ちの良い令嬢のように見えなくもない、品も顔も良い女。見た目の特徴が全て一致しているのだ。
この事件が本当に無差別犯ならそこまで問題じゃない。狙われる母数が増えて彼女が被害者になる確率は劇的に下がるから。しかし、四人目の被害者が幕府関係者と繋がりがあったとしたら。例えば……職場の常連客だとか。これはまだ捜査中の段階であり、断言はできない。単に見た目の特徴だけを狙ったものかもしれないし、そうじゃないかもしれない。こんな曖昧なことしか言えないのは全て担当管轄がぽかやらかしたせいだ。それを聞いて『お妙さんが危ない!』なんて言っている近藤さんに土方さんがストーキングを許可するなんていう天変地異が起きたのが、つい数刻前の話。
一瞬俺も彼女の顔が浮かんだ。普段は制服で来るのを避けたり、店に入る時は常に視線に気を配っているつもりだ。しかし久々に制服で店に来てしまったのが、つい先日の話……事件が起き始めてからのことだ。私服ならまだしも、やはりあの黒い制服は目を引く。たまたまその一回を見られていたとしたら。そして彼女が店から出てくるのを見られていたとしたら。はたまた既に客の中に……。おばちゃんに『今月変な客がいないか』と聞いたのはそのためだ。とは言っても、それだけでは何の手がかりにもならないのが正直なところ。
犯人は暗闇で顔を隠すだけではなく、刀で脅して女を手籠にするような奴だ。たいした野郎じゃないし、かなりの臆病者。白昼堂々何か事を起こすとも思えない。見回りもかなり強化されるからすぐ捕まるだろうし、そうであってもらわないと困る。
友人が居ないなら用もなく夜一人で出かけることはないだろうし、そこまで心配はしていない。しかし俺のせいで何かあれば、さすがに寝覚が悪すぎる。だからわざわざ朝の緊急会議の後に店に顔を出したのだ。でも前三件に緘口令が敷かれているせいで、これ以上は何も言うことができない。
「とにかく、精々巻き込まれねぇよう休みの日は家で大人しくテレビでも見ときなせぇ」
これで話は終わり、という意味を込めて俺は今日の主菜のピーマンの肉詰めを噛み切らずに一口で放り込んだ。口いっぱいに頬張り咀嚼する俺を見て察したのか、彼女はそれ以上何も聞いて来ずテーブルを拭き終えて厨房に入っていく。
「ナマエちゃん、賄い食べるだろう?ちょうど準備出来たから持って行きな」
「ありがとうございます」
中からそんな会話が聞こえて、ものの数分でお盆を持ったナマエちゃんが厨房を出てきた。そして俺の横の席に静かにお盆を置く。
「お隣よろしいですか?」
「かまいやせんよ」
毎回なんやかんやで横に座っているのだが、律儀に声をかけて来た。この期に及んで離れて座られる方がむしろ居心地悪いし、店員として愛想悪すぎるだろうと思う。
「ナマエちゃんマジでいつ来ても居やすけど、出稼ぎか何かですかぃ?」
座って食べ始めた彼女にそう言った。婦女暴行の事件を掘り返されないように、単純にそう思ってのことだった。
「あ、言ってませんでした?家族いないんです」
別に隠していた訳ではないとでもいうように即答する彼女。そのあっけらかんとした態度に何だか拍子抜けしてしまい、次の言葉に詰まって「あー、」と間延びした声が出た。
「家族も友達もいないからこそ、身軽に一人で江戸に来れたんです。せっかく心機一転、再出発した女の過去を聞くなんて野暮ですよ?」
あぁ、“ハードルが高い”と思ってこの質問を避けていたのは、本能的に何か悟っていたのかもしれない。正しかったのだ、その勘は。彼女が初めて自ら身の上を語ってきたその内容は、とてもハッキリとした牽制の言葉だった。人差し指を口の前で立てるなんて普段やらなさそうな茶目っ気のある仕草も、可愛いなんてものではない。まるで“黙れ”と言っているようにしか見えない。
…………そういえば、こいつは俺のことモブ扱いしてるんだった。それを最初に思ったのは前回、制服で来た平日の朝。本当につい先日の、四月二十日のことだ。
「まぁ夜はしばらく出歩かん方がいいでしょうねィ」
ただでさえ、日中の公園で絡まれた前例があるのだから。そもそも今日俺は、彼女に忠告しに店に来たんだ。
「あら、やっぱり心配してくれてるんだねぇ」
「……仕事増やさねえで欲しいだけでさァ」
「あっはっは!素直じゃないねぇ!まぁでもさぁ、もし街で見かけたりしたら気いかけてやってくんないかい?」
やたらと彼女と俺を絡めたがるおばちゃん。でもその言葉から“俺に心配させたい”というよりは、おばちゃん自身が彼女のことを心配していると言うことが伝わってくる。
「今んところ店以外で一回も見た事無えんですが」
「まぁ、あの子全然休まないからね」
「確かにいつ来ても居やすねぃ」
「江戸に誰も知り合い居ないって言ってたからねぇ。寂しいんだろうねぇ、なかなか休みたがらないんだよ」
そんなタイプなのか?てっきり、一人で過ごすのが好きそうな冷めたタイプの女に見えてたけど。少なくとも、同い年の俺にはそう映っていた。最初に年齢を聞いた時にはこのひどく落ち着いた女が俺と同い年か、と驚いた。しかし女の年齢なんてぱっと見じゃあわからない。姉御だってあぁ見えて同い年なんだから、そう考えると妥当だとも思った。女ってのは何でも笑顔で隠しちまう。
「しっかりしたお嬢さんですがね」
「だからこそだよ。頼り方のわからない不器用な子なんだ」
「まぁ確かに心配ではありますね。気丈に振る舞っているようにも見えて」
一回り以上歳の離れた二人には、そのように映っているらしい。俺としては憂いを帯びた微笑を張り付けてる彼女は、何考えてんのかよくわかんねえけど余裕があって達観してるような態度に見える。それに端正な顔立ちのせいか、一歩間違えばとっつき難く冷たい印象にも見えかねない女だとも思ってる。……年の功あってこそ見えるものもあるのかねぇ。
「私も街で見かけたら声をかけるようにしましょう」
「そうしてやっておくれ」
「そろそろお暇しますね。ご馳走様でした、沖田さんもまた」
「ありがとうよ」
「…………」
おばちゃんだけではなく俺にも律儀に声をかけるイケオジに、俺はもぐもぐと咀嚼しながら無言で手をひらりと振った。そして引き続き目の前の定食に箸を伸ばす。
おばちゃんは今イケオジが飲んでいた空の湯飲みを持つと「あたしゃ片付けてナマエちゃんの分の定食準備してくるから」と言って厨房の中に入って行った。どうやら今日も横で食うのは確定らしい。
「先程の話、聞いてましたけど本当に物騒ですね。特に夜は一人で歩かない方が良いですよ」
前の客がちょうど店から出て行ったタイミングで、背後のレジに向かったイケオジ。その彼の声が背中側から聞こえた。
「そうですね。しばらくは一人で出歩かないようにします」
レジ前でナマエちゃんと会話しているらしい。“じゃあ誰と歩くのか”、そう聞いたら答えるのだろうか。おばちゃんの言い方だと、まだ上京して日の浅い彼女は江戸に友人の類なんていないんだろう。イケオジもそれをわかった上で「それが良いですよ。お気をつけて」なんて何も知らないフリをして答える。これが大人の対応で、気遣いなんだろうか。何とも回りくどい。
「はい、ありがとうございます」
“いつも”より少し滑舌が良くて聞き取りやすい、ハキハキとした声。それは接客仕様の彼女の声だった。
会話が止んで引き戸を開け閉めする音を背中で聞いた後、両手にコップを持って厨房に入っていくナマエちゃんの姿が見えた。常にローテンションで、心底俺に興味のないこの冷め気味の女と話すのは気を遣わないので楽だ。それは確かなのだが、淡々としたリアクションとは別の顔が見てみたい。そう思うのは年相応の男としては100点満点の行動心理じゃないだろうか。例えば、不快に顔を歪めたブッサイクの顔だとか。そしてすぐに厨房から出てきたその女に、俺は声をかけた。
「ナマエちゃんに一緒に出歩く友達がいたとはこいつぁ驚きだ。いつ来ても店に居るから友達いねぇんだと思ってやした」
友達がいないのはおばちゃんの『江戸に知り合いがいない』という発言で気付いているのに、我ながら白々しい顔でそんなことを言った。おばちゃんに『気にかけやってくれ』なんて言われたが、あいにく俺はこんな言い方しか知らない。イケオジと違って、この女に気を遣って回りくどい言い回しをするなんて優しさも持ち合わせちゃあいない。
それに、どんな顔をするだろう、と。顔を歪めたり苛立ったりするのを期待して、嫌味っぽく言ってみた。しかしその表情は僅かに眉尻を下げた、困ったような笑顔。この顔はよく見る。
「……嘘も方便ですよ。変に心配かけられませんから」
その困り顔は、イケオジに対する罪悪感が何かだろうか。
聞けば答える女だとは思っていたのだが、この手の話題は振ったことがなかった。初めこそ質問攻めにした記憶はあるが、人間関係などを突っ込むのは避けていた。そこを掘ると自然と家族の話も突くことになる。俺自身もう誰も肉親はいないし、何となくハードルが高かったのだ。それに何かしらの地雷がある奴だろうと思っていた。朝っぱらからそれを踏んで変に気まずい雰囲気になるのは御免だし、頭を使わない薄い内容の話しかしていない。
しかし自ら話してくる事は無いが、やっぱり聞けば答える。友達がいないと言う事を隠すつもりはないらしく、素直に認めるかのように『嘘』と言った。
「するってーと、友達いねぇのは図星かぃ」
「間違いないですね」
俺に目を合わせずに俯いて机を拭いている彼女の顔は見えないが、いつもより気怠げに間延びした声に聞こえた。鬱陶しいと顔を顰めているなら物珍しい。しかし、今見えてない顔はきっといつも通り。あの代わり映えのしない、余裕そうな微笑を張り付けてるんだろう。そう思うとすぐつまらない気持ちになる。
「ふーん。ま、さっきのおっさんの言う通り、アンタは気をつけた方がいいですぜ」
俺の言葉に、机を拭く手を止めて顔を上げる。こちらを見るその表情はキョトンとしていた。
「田舎もんのお上りだなんて思わねぇし、ぱっと見ぃじゃ良家の娘に見えねぇ事もないからな」
「どう言うことですか?」
生憎これ以上は話すことができないのだが、せめてもの忠告のつもりでそう言った。一応こんな可愛げのない女だが、今日は警察という立場としての彼女へ注意喚起をしに来た。
……件の連続婦女暴行事件の被害者の特徴に、目の前の女が一致している。暗い髪色、まとめ髪、細身で大人びた風貌の若い女。そしてぱっと見育ちの良い令嬢のように見えなくもない、品も顔も良い女。見た目の特徴が全て一致しているのだ。
この事件が本当に無差別犯ならそこまで問題じゃない。狙われる母数が増えて彼女が被害者になる確率は劇的に下がるから。しかし、四人目の被害者が幕府関係者と繋がりがあったとしたら。例えば……職場の常連客だとか。これはまだ捜査中の段階であり、断言はできない。単に見た目の特徴だけを狙ったものかもしれないし、そうじゃないかもしれない。こんな曖昧なことしか言えないのは全て担当管轄がぽかやらかしたせいだ。それを聞いて『お妙さんが危ない!』なんて言っている近藤さんに土方さんがストーキングを許可するなんていう天変地異が起きたのが、つい数刻前の話。
一瞬俺も彼女の顔が浮かんだ。普段は制服で来るのを避けたり、店に入る時は常に視線に気を配っているつもりだ。しかし久々に制服で店に来てしまったのが、つい先日の話……事件が起き始めてからのことだ。私服ならまだしも、やはりあの黒い制服は目を引く。たまたまその一回を見られていたとしたら。そして彼女が店から出てくるのを見られていたとしたら。はたまた既に客の中に……。おばちゃんに『今月変な客がいないか』と聞いたのはそのためだ。とは言っても、それだけでは何の手がかりにもならないのが正直なところ。
犯人は暗闇で顔を隠すだけではなく、刀で脅して女を手籠にするような奴だ。たいした野郎じゃないし、かなりの臆病者。白昼堂々何か事を起こすとも思えない。見回りもかなり強化されるからすぐ捕まるだろうし、そうであってもらわないと困る。
友人が居ないなら用もなく夜一人で出かけることはないだろうし、そこまで心配はしていない。しかし俺のせいで何かあれば、さすがに寝覚が悪すぎる。だからわざわざ朝の緊急会議の後に店に顔を出したのだ。でも前三件に緘口令が敷かれているせいで、これ以上は何も言うことができない。
「とにかく、精々巻き込まれねぇよう休みの日は家で大人しくテレビでも見ときなせぇ」
これで話は終わり、という意味を込めて俺は今日の主菜のピーマンの肉詰めを噛み切らずに一口で放り込んだ。口いっぱいに頬張り咀嚼する俺を見て察したのか、彼女はそれ以上何も聞いて来ずテーブルを拭き終えて厨房に入っていく。
「ナマエちゃん、賄い食べるだろう?ちょうど準備出来たから持って行きな」
「ありがとうございます」
中からそんな会話が聞こえて、ものの数分でお盆を持ったナマエちゃんが厨房を出てきた。そして俺の横の席に静かにお盆を置く。
「お隣よろしいですか?」
「かまいやせんよ」
毎回なんやかんやで横に座っているのだが、律儀に声をかけて来た。この期に及んで離れて座られる方がむしろ居心地悪いし、店員として愛想悪すぎるだろうと思う。
「ナマエちゃんマジでいつ来ても居やすけど、出稼ぎか何かですかぃ?」
座って食べ始めた彼女にそう言った。婦女暴行の事件を掘り返されないように、単純にそう思ってのことだった。
「あ、言ってませんでした?家族いないんです」
別に隠していた訳ではないとでもいうように即答する彼女。そのあっけらかんとした態度に何だか拍子抜けしてしまい、次の言葉に詰まって「あー、」と間延びした声が出た。
「家族も友達もいないからこそ、身軽に一人で江戸に来れたんです。せっかく心機一転、再出発した女の過去を聞くなんて野暮ですよ?」
あぁ、“ハードルが高い”と思ってこの質問を避けていたのは、本能的に何か悟っていたのかもしれない。正しかったのだ、その勘は。彼女が初めて自ら身の上を語ってきたその内容は、とてもハッキリとした牽制の言葉だった。人差し指を口の前で立てるなんて普段やらなさそうな茶目っ気のある仕草も、可愛いなんてものではない。まるで“黙れ”と言っているようにしか見えない。
…………そういえば、こいつは俺のことモブ扱いしてるんだった。それを最初に思ったのは前回、制服で来た平日の朝。本当につい先日の、四月二十日のことだ。