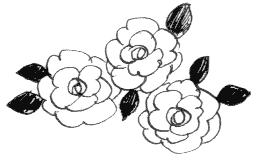二:四日九日土曜日 午前
「いらっしゃいませ」
「おはようナマエちゃん。定食一つよろしくね」
「かしこまりました」
"茶房 やまもと"
山本夫妻が営むこの店は私が一週間前、門を叩いた店だ。定食と甘味を提供している。ちなみに定食は日替わり定食のみ。
平五郎とお時、人の良さの滲み出る笑い皺が濃くなり始める中老の夫妻。今まで一度もバイトは雇わなかったそうだが『そろそろ自分達の体のことを考えて少し手を抜こう』ということで求人を出したのだと言う。扉に求人票を貼ってものの数分で私が志願して来たので驚いてはいたが、運良く即採用に至った。
今日で7日目。『慣れるまで休みはいらない』と言って連日働かせてもらっている。
家と職場の往復のみの生活をしていると"天人"や"ターミナル"と接点は無く、東京にいる時とあまり変わらないと思った。
(私、普通に生きてる)
ここが漫画の世界だなんて、まるで嘘みたいに。……それに、働いていたら時間が過ぎるのが驚く程に早い。今はあまり一人でいたくない、家にいる時間を減らしたい。休み無しでバイトしている方が気が楽だった。
……さすがに7日も連続でやっていれば慣れてきた。常連客が多いこの店では、もう名前で呼んでくれるお客さんもいる。別に自己紹介をした訳ではないのだが、山本夫妻が『ナマエちゃんナマエちゃん、』とたくさん名前を呼んでくれる。そのためか、お客さんもそれに倣ってすぐに私の名前を呼ぶ。
(“自分の存在”を、実感できるような気がする)
家に一人でいると“この世界に本来いるべき存在ではないのかも”なんて考えてしまう事もある。しかし、名前を呼んでもらうと、そう実感できる。……どうやらこの世界に来てからの私は承認欲求が満たされていないらしい。
朝7時から定食をやっているここは今から仕事に向かう会社員など、平日5日間働く勤務形態の客層が多い。私が働いた7日の内、中には5日連続で顔を合わせる人もいた。私が働き始めたのが日曜日で、今日は土曜日。平日働くサラリーマンの客層は来ないが、休みが不定期の人は来店する。まだ7日しか働いていない私にはもちろん毎日初めましてのお客さんもいるが、先程来店したお客さんのように平日に何度か顔を合わせた人もいる。
今は朝の8時20分。平日であれば一気に人が減る時間だが土曜の今日はそうでもなく、6つあるカウンター席は半分埋まっている。3つある四人がけテーブルにはそれぞれ一人ずつ。ちなみに満員の時間帯には相席してもらっている。朝ここへ来る人はみんな一人客で回転率は高い。連れ立ってきた人をまだ見たことがないのは、出勤前で時間の限られた人が多いからだろうか。みんな常識のある社会人という感じで、新参者の私にも優しく良い人ばかりだ。一発でこんな良いバイト先を見つけられたなんて、かなり引きが強いなと心から思う。
「ナマエちゃん、定食上がったよ」
「はい」
お時さんに呼ばれてお膳を受け取りに行く。ちなみに朝は甘味の提供はしておらず、日替わり定食一本集中だ。他に選択肢がないため余計な手間がかからず、かなり早く提供できる。だからこそ朝の忙しい時間帯にたくさんの常連さんが来てくれるのだろう。
「お待たせしました」
「ありがとう。いやぁ土曜の仕事憂鬱だけど、ここの飯はうまいし、ナマエちゃん眼福だし。目も口も幸せだわ」
「ちょっと鈴木さん、ナマエちゃんにセクハラしたら叩き出すよ!」
「いやいや待ってよおばちゃん!褒め言葉じゃん!ねぇ、ナマエちゃん?!」
「ごゆっくりどうぞ」
「無視ぃ!?」
その場を去り他の仕事に戻る。別に嫌な気はしていないのだ。なぜなら、社交辞令だと分かっているから。その証拠につい今しがた軽口を叩いていた彼は、もう何事も無かったかのように朝ごはんに集中している。
帰る客の会計や、食器を下げたりテーブルを拭いたり。そういう作業を繰り返しているうちに、鈴木さんも食べ終わったのか席を立ち会計をする。
「ごちそうさん、また来るよ」
現在の時刻は8時50分。彼が帰ったことで店の客は誰もいなくなった。この時間になるともうお客さんは来ない。私は勝手に、暗黙の了解か何かだと思っていた。
実はこの朝の時間帯、店先に暖簾は出していない。外からぱっと見て営業しているとはわからないが、この通り営業している。そのことを知ってる客しか店に入って来れない。つまり来る人間は全員、常連さんか山本夫妻の知人だ。
平五郎さん曰く『これ以上客が増えたら回らねぇ』とのこと。7時から9時のたった2時間。席数はそこまで多く無いが回転率がかなり早いので、結構な人数捌いていると思う。確かに店が回らないかも……と言うより、よく今まで二人で回してましたね。
10時からは暖簾を出して営業を始める。そこからは甘味の提供も始まる。この9時から10時の間に夫婦は簡単な仕込みや準備を、私は賄いをいただく。ちなみに二人は営業前に朝食を済ませている。
まだ2時間しか働いてないくせに、と思うかもしれないが1日の中で一番忙しいのがこの初っ端の2時間なのだ。ここで休憩しないと身が持たない。起き抜けにあまり食べられないので家ではヨーグルトのみを食べて、店で朝ごはんとして日替わり定食を頂いている。これがかなりの量なのだが、怒涛の2時間働いた直後の私なら完食できる。このボリュームのためなのか、朝のこの時間帯にまだ一度も女性客を見たことがない。おじ様も来るのだが、20代の男性や10代の鳶職の男の子など、比較的若い男の人が多い。
一汁三菜どころではなく、いつも六菜くらいある。白ご飯と味噌汁、香の物はいつも通り。今日の小鉢は若竹煮、ひじきの煮物、ほうれん草の胡麻和え、茄子の揚げ浸し。主菜は鯖の味噌煮。それらを自分で皿に装って準備している間に、平五郎さんが玉子焼きを焼いてくれている。一人分なのに器用に厚焼きにしてくれるんだよなぁ。お客さんに出す時より少なめにおかずを盛った器を全てお膳に乗せてI字型のカウンターに座ると、ちょうど焼きあがったらしい玉子焼きをカウンター越しに渡してくれた。
「いただきます」
まずは味噌汁から。先ほど温め直してまだ少し熱を持つそれを啜る。あぁ、今日も安定の美味しさだ。美味しいものを食べてる時も、生きてる事を実感する。次にほうれん草に箸をつけ口に運んだ。
……すると、背後から引き戸がガラガラ、と開く音がした。
(あれ、お客さんこの時間にも来るの?)
まだ咀嚼している口を、箸を持っていない方の掌で覆いながら後ろを振り向いた。
「あり?珍しい。この時間に他に客がいるなんて」
「あら、総悟くん。いらっしゃい」
「……っ、!」
目に写った姿とお時さんの言葉に驚き、口の中のほうれん草が気管に入りそうになる。
「……コホッ!ゴホッ!っ、はぁ…」
「ちょ、ナマエちゃん大丈夫かい?」
噎せて咳き込むが、何とか通常通りに飲み込むことができた。お時さんが心配して声を掛けてくれるのを聞きながら、思わず水をゴクゴクと一気に流し込んだ。
「この子は客じゃねぇよ、バイトのナマエちゃんだ」
空になったコップを机に置くと、カウンターの中から平五郎さんの声が聞こえた。その目線の先は、私の座る席から一つ飛ばした椅子。いつの間にかカウンター席に腰掛けていた彼に向いている。
「ふぅん。何でまた急に?」
「俺たちも歳だからなぁ、さすがに。ちぃとくらい手ェ抜いてかねぇと」
「バイト雇う余裕が無ぇだけかと思ってやした」
「がはは!わざわざ人の少ない時間狙ってウチに顔出してるくせに、よく言うなぁオイ!」
(……なんか、めちゃくちゃ仲良さそうなんですが)
彼に水を出しに来たついでに、私の飲み干したコップに水を補充してくれるお時さんに小声で尋ねる。
「…常連さんですか?」
「そうそう、いつもこれくらいの時間に来るんだよぉ。曜日はバラバラだけど。今日は私服だし休みかねぇ?」
この時間帯に店に入ってくる時点で常連さんに決まってるのに、つい分かりきった質問をしてしまう。下の名前で呼ぶ程親しいというのに。それに"私服"ではない時を知ってると言うことは、制服姿も知ってるのだろう。
「毎日屯所でむさくて喧しい男どもと飯食ってんですぜ?たまには静かに食いたくもなるでしょうよ」
「結局ここへ来ても、むさい俺と喧しいお時しかいねぇぞ」
「ちょいとアンタ、誰が喧しいって?」
まったく、と怒るお時さん。私はいま賄いを食べていていいのか分からず箸を置いて黙って会話を聞いていた。
「あれ、ナマエちゃん食べてていいんだよ?」
「いや、でも」
「総悟くん、別に良いだろ?」
「かまいやせんよ」
「アンタら同い年くらいだろう?私は準備してくるから若いもん同士で話してな」
「え、ちょ、お時さん、……すみません、」
呼び止める私の声を聞き流し、お時さんは厨房へ入って行ってしまった。客の横で賄いを食べる事に対しての罪悪感から謝罪を述べた。
「いんや、別に」
興味なさそうに言う彼は、お時さんが置いていった水を飲んでいる。
私はどちらかというと表情が豊かな方では無いし、大声を上げたりハイテンションで話すタイプではない。別に無表情というわけでも、愛想が無い訳じゃ無いと思う。ただ、喜怒哀楽を全身で表現するような“かまってあげたくなる愛嬌のある可愛い女の子”では無いという自覚があるだけ。
そういう質だからなのか“できる事ならばもう会いたくない”と思っていた人物が真横にいる状況でも、意外に冷静に言葉を発することができたと思う。しかし理由はそれだけではなく、江戸にいる以上今後も会う可能性があると予め心の準備をしていたのだ。まさかこの店で会う事になるとは思いもしなかったが。
……とはいえ深入りする理由もないので、早く食べ終わって仕事に戻ってしまおう。準備といっても10分もしないうちに提供されるだろうし、その間に何とか。
そう思って再び箸をつけようとしたのだが、横から刺さるような視線を感じる。
カウンター席、と言ってもバーのような回る椅子ではなく普通の木製の椅子。にも関わらず、いつの間にか体ごとこちらへ向けて座り直しており、片肘を机に置いて頬杖をついている。もう片方の腕は椅子の背もたれに置き、こちらをじっと見ていた。
「あの……」
「気にしなさんな」
(いや気になるわ。ものすっごい食べづらいわ。何、食べるなってか?)
「冷めちまいやすぜ」
別に睨むでもなく、かと言って微笑むわけでもなくただただ無表情で見てくる。
(側から見たポーカーフェイスって結構厄介なのかも)
自分もどちらかといえばポーカーフェイスに分類される方だと思うが。
「……では、お言葉に甘えて」
もう気にしないで食べよう。まだ全然減っていない定食を行儀が悪くならない程度に急いで食べ進めよう、と思った。
「今日は着物なんですねィ」
小鉢に伸ばした箸が届く前に、話しかけられた。結局全然食べさせてくれないじゃないか。
……そう、今の私は着物姿。わずかに茶味を帯びた鶯色の色無地。光の加減で見え隠れする鮫唐草の地紋は落ち着きがあり、幅広い年齢の人が着ることができそうだ。仕事中は袂が邪魔なので襷掛けしている。
実は和装一式を持っており、着付けも一人でできる。昔、両親に教えこまれた。理由は聞いていないが『絶対に一人で着られるようになれ』と。その言葉とともに、母の着物を数着譲り受けた。
まさかそれが役立つ日が来るなんて、当時は思ってもみなかった。この世界にいるからには着る事になるだろうと、部屋の整理をした時に出しておいたが……。両親は、今の私の状況を予測していたとでも言うだろうか。もしそうだとすればかなり不気味な話だ。
「えぇ、まぁ。あと、遅くなってすみません。その節は本当にありがとうございました。」
“今日は着物”というのは先日会った時と比較してのこと。つまり覚えているということを遠回しに言ってきている。
正直、顔なんて覚えてないと思っていたのに。一度助けてもらったとはいえ、ほんの数分しか関わっていなのだから。まぁ、今更「初めまして」なんて言えるほど肝は据わっていない。初対面のフリをするのは、もう無理だ。
「車を運転する予定があったので、洋服だったんですよ」
「へぇー、運転するんですかぃ」
「まぁ……。最近免許を取ったばかりですが」
「人は見かけによらねぇや。全く運転してるところ想像できやせんね」
この店で働き始める時に店主らに運転免許を持っていると話した際に、少し驚かれた。女で免許を持ってるのは変に思われるのだろうか、怪しまれたらどうしよう、自分の発言のどこに地雷があるかわからないからあまり話したくない。そう思っていたのだが、一週間経った今は正直気にしていなかった。
「世間知らずのどっかの令嬢が家出でもして来たのかと思ってやした、あん時。」
向こうは会話を止める気がないらしい。その割にはあまり興味がなさそうな顔をして話している。
(それはわざと?詮索されてる?)
そんな警戒心が湧いたのは、彼が警察という職業なのを私が意識してしまっているのだろうか。
「そんなんじゃありませんよ、凡人です。」
「ふぅーん」
「なんでい。2人とも、知り合いだったのかい?」
玉子を焼き終わったらしい平五郎さんが会話に入ってきた。
「知り合いといいますか、実は先日絡まれてるところを助けていただいて」
「あら、そうなのかい?」
焼きたての玉子焼きも乗せた定食のお膳を持ってきたお時さん。そう言いながら彼の前にそれを置いた。
「ナマエちゃん綺麗だからねぇ。ここはかぶき町も近いし……。慣れるまではあんまり夜一人で出歩かない方が良いよ」
「江戸の人じゃねぇんですかぃ?」
「……まあ、田舎から、」
東京にいた時ではなく、今現在の私の"前の住所"。そこの地名を言うと「俺より田舎じゃねぇですか」と返された。そして意外にも行儀良く手を合わせて「いただきます」と言ってから定食に箸をつけ始める。
既にこの手の内容の会話は、他のお客さんや山本夫妻とも交わしている。その度に特に不審がられることも詮索されることもなく、ただの世間話として話が終わる。それは自分のプロフィールに別に不自然な点は無いということだ。しかし自分には全く聞き馴染みの無い地名なのに、何も滞りなく会話が成立することに対して毎回胸がザワザワする。
『お前はこの世界の人間じゃない』
『お前はこの世界の人間だ』
そんな両極端なことを同時に言われている気分になるのだ。
「あんま芋臭くねぇですね」
「……どーも」
向こうが箸をつけ始めたので私も食べ始めたが、合間合間に会話を挟んでくる。
「江戸へはいつ頃来たんで?」
「先月末くらいです」
「本当に来たばっかですねぃ」
先月末、というのは私が今のマンションに入居した日。これも他の人に同じように話している。
今は4月上旬。文字通り“江戸に来た”という意味で言うならば本当は4月1日、エイプリルフールだと思う。それは目の前の彼に初めて会ったあの日のことだ。
「この辺に住んでるんですかぃ?」
「徒歩圏内ですよ。近くで働きたかったので」
こちらから質問することはしなかったが、初対面の人がするであろう一般的な会話をしながらお互いに箸を進めた。
お時さんが先程『同じ歳くらいだろう』と言ったのが気になったのか「歳は?」と聞かれ、答えると「マジで同い年じゃねぇか」と少し驚いた顔をした。どう言う意味だ、見えないって言いたいのか。
そんなどうでも良い話をぽつりぽつりと交わす、ただの店員と客の会話。そう思うと僅かに抱いていた警戒心は弱まり、普通に話せるようになった気がする。
私の方が量が少なかったとはいえ、後から食べ始めたはずの彼と、私が食べ終わったのはほぼ同時だった。
平五郎さんと、いつの間にやら厨房の中に戻っていたお時さんは片付けやら仕込みやらをしていた。私も慌てて自分の食べ終えたお膳を持ち上げて流しに持っていく。
「あらぁ、もう少し話してても良いのよ?」
「え」
「あぁ見えても総悟くんは真選組の隊長さん、落とせば玉の輿よぉ~~」
「おばちゃん、聞こえてやすけど」
「聞こえるように言ってんのよぉ」
厨房、と言ってもカウンター越しのすぐそこで中も丸見えだし声も聞こえる。
(一体何を言ってるんですかお時さん……)
「おいおいやめろよ、お時よぉ……。ナマエちゃんには高嶺の花でいてもらわねぇと。あいつらがこの娘を間抜け面で見てる顔を、この厨房から眺める愉快さったらねぇんだからよぉ」
「おっちゃん結構良い性格してやすよねぃ」
(なんてことを言い出すんですか平五郎さん)
てっきり助け舟を出してくれるものだと思ったのに。……とも思ったけど、変に男とくっつけようとするなと言いたいんだろうか。彼なりの優しさ…だと思う。たぶん。きっと。知らないけど。
「そろそろ帰りやす」
そう言って席を立った。2人は水仕事やらで手が離せないので私が会計に向かう。
不本意とは言え、変な話をしてしまったので少し気まずい。そう思いながらレジを操作する。
「700円です」
価格も毎日同じなのに必要あるのだろうか、と思いつつ一応値段を言う。
彼は財布から1000円取り出してカルトンに置いた。それを受け取り、レジを操作してお釣りを取り出す。
「お釣り300円です」
カルトンに置くか、手に直接渡すかほんの一瞬迷ったが前者を選んだ。小銭を握りしめた手をカルトンの上で開こうとした瞬間、ガッと握り拳を上から包み込まれ阻止された。
「えー、っと、」
「総悟です」
「え、」
「総悟でさぁ。ナマエチャ~~ン」
「………」
わざとらしく語尾を強調したように呼んでくる。
「総悟、くん…?」
「ん」
短く返事のように言うと、握られた手の力が弱まった。離れた手を私の握り拳の下へ差し出し受け皿のように構えたので、その手の平に小銭を置いた。
「んじゃ、また」
「ありがとうございました」
小銭を財布にしまうと、手をひらひらと振りながら引き戸に手をかけて出て行った。
(……自己紹介をしていなかったのが気に障った?)
仕方ないじゃないか、今までこの店でお客さんに自己紹介をしたことなんてないんだもの。それに彼も他の客同様、例に漏れることなく下の名前で呼んできた。
私は、元から彼の名前を知っている。初めて会った時にフルネームも聞いたし、お時さんが何回も呼んでたから改めて尋ねようと言う気にならなかった。念押しするように下の名前だけ名乗られてしまうと、今さら苗字で呼ぶのは少し気が引ける。
(あぁ、自己紹介して聞いておけば良かった)
なんて、後悔してももう遅い。……常連なのだから、本当にまた来るだろう。ここで働いている以上、逃げることはできない。今日みたいに、ただの世間話だけしていれば問題ない。ただの店員と客なんだ。きっと大丈夫、大丈夫。
(大丈夫……うまくやれる)
今の時刻は9時45分。もうすぐ暖簾をかけての営業が始まる。私は彼、もとい総悟くんの食べ終えた食器を持って流し台に向かった。
「おはようナマエちゃん。定食一つよろしくね」
「かしこまりました」
"茶房 やまもと"
山本夫妻が営むこの店は私が一週間前、門を叩いた店だ。定食と甘味を提供している。ちなみに定食は日替わり定食のみ。
平五郎とお時、人の良さの滲み出る笑い皺が濃くなり始める中老の夫妻。今まで一度もバイトは雇わなかったそうだが『そろそろ自分達の体のことを考えて少し手を抜こう』ということで求人を出したのだと言う。扉に求人票を貼ってものの数分で私が志願して来たので驚いてはいたが、運良く即採用に至った。
今日で7日目。『慣れるまで休みはいらない』と言って連日働かせてもらっている。
家と職場の往復のみの生活をしていると"天人"や"ターミナル"と接点は無く、東京にいる時とあまり変わらないと思った。
(私、普通に生きてる)
ここが漫画の世界だなんて、まるで嘘みたいに。……それに、働いていたら時間が過ぎるのが驚く程に早い。今はあまり一人でいたくない、家にいる時間を減らしたい。休み無しでバイトしている方が気が楽だった。
……さすがに7日も連続でやっていれば慣れてきた。常連客が多いこの店では、もう名前で呼んでくれるお客さんもいる。別に自己紹介をした訳ではないのだが、山本夫妻が『ナマエちゃんナマエちゃん、』とたくさん名前を呼んでくれる。そのためか、お客さんもそれに倣ってすぐに私の名前を呼ぶ。
(“自分の存在”を、実感できるような気がする)
家に一人でいると“この世界に本来いるべき存在ではないのかも”なんて考えてしまう事もある。しかし、名前を呼んでもらうと、そう実感できる。……どうやらこの世界に来てからの私は承認欲求が満たされていないらしい。
朝7時から定食をやっているここは今から仕事に向かう会社員など、平日5日間働く勤務形態の客層が多い。私が働いた7日の内、中には5日連続で顔を合わせる人もいた。私が働き始めたのが日曜日で、今日は土曜日。平日働くサラリーマンの客層は来ないが、休みが不定期の人は来店する。まだ7日しか働いていない私にはもちろん毎日初めましてのお客さんもいるが、先程来店したお客さんのように平日に何度か顔を合わせた人もいる。
今は朝の8時20分。平日であれば一気に人が減る時間だが土曜の今日はそうでもなく、6つあるカウンター席は半分埋まっている。3つある四人がけテーブルにはそれぞれ一人ずつ。ちなみに満員の時間帯には相席してもらっている。朝ここへ来る人はみんな一人客で回転率は高い。連れ立ってきた人をまだ見たことがないのは、出勤前で時間の限られた人が多いからだろうか。みんな常識のある社会人という感じで、新参者の私にも優しく良い人ばかりだ。一発でこんな良いバイト先を見つけられたなんて、かなり引きが強いなと心から思う。
「ナマエちゃん、定食上がったよ」
「はい」
お時さんに呼ばれてお膳を受け取りに行く。ちなみに朝は甘味の提供はしておらず、日替わり定食一本集中だ。他に選択肢がないため余計な手間がかからず、かなり早く提供できる。だからこそ朝の忙しい時間帯にたくさんの常連さんが来てくれるのだろう。
「お待たせしました」
「ありがとう。いやぁ土曜の仕事憂鬱だけど、ここの飯はうまいし、ナマエちゃん眼福だし。目も口も幸せだわ」
「ちょっと鈴木さん、ナマエちゃんにセクハラしたら叩き出すよ!」
「いやいや待ってよおばちゃん!褒め言葉じゃん!ねぇ、ナマエちゃん?!」
「ごゆっくりどうぞ」
「無視ぃ!?」
その場を去り他の仕事に戻る。別に嫌な気はしていないのだ。なぜなら、社交辞令だと分かっているから。その証拠につい今しがた軽口を叩いていた彼は、もう何事も無かったかのように朝ごはんに集中している。
帰る客の会計や、食器を下げたりテーブルを拭いたり。そういう作業を繰り返しているうちに、鈴木さんも食べ終わったのか席を立ち会計をする。
「ごちそうさん、また来るよ」
現在の時刻は8時50分。彼が帰ったことで店の客は誰もいなくなった。この時間になるともうお客さんは来ない。私は勝手に、暗黙の了解か何かだと思っていた。
実はこの朝の時間帯、店先に暖簾は出していない。外からぱっと見て営業しているとはわからないが、この通り営業している。そのことを知ってる客しか店に入って来れない。つまり来る人間は全員、常連さんか山本夫妻の知人だ。
平五郎さん曰く『これ以上客が増えたら回らねぇ』とのこと。7時から9時のたった2時間。席数はそこまで多く無いが回転率がかなり早いので、結構な人数捌いていると思う。確かに店が回らないかも……と言うより、よく今まで二人で回してましたね。
10時からは暖簾を出して営業を始める。そこからは甘味の提供も始まる。この9時から10時の間に夫婦は簡単な仕込みや準備を、私は賄いをいただく。ちなみに二人は営業前に朝食を済ませている。
まだ2時間しか働いてないくせに、と思うかもしれないが1日の中で一番忙しいのがこの初っ端の2時間なのだ。ここで休憩しないと身が持たない。起き抜けにあまり食べられないので家ではヨーグルトのみを食べて、店で朝ごはんとして日替わり定食を頂いている。これがかなりの量なのだが、怒涛の2時間働いた直後の私なら完食できる。このボリュームのためなのか、朝のこの時間帯にまだ一度も女性客を見たことがない。おじ様も来るのだが、20代の男性や10代の鳶職の男の子など、比較的若い男の人が多い。
一汁三菜どころではなく、いつも六菜くらいある。白ご飯と味噌汁、香の物はいつも通り。今日の小鉢は若竹煮、ひじきの煮物、ほうれん草の胡麻和え、茄子の揚げ浸し。主菜は鯖の味噌煮。それらを自分で皿に装って準備している間に、平五郎さんが玉子焼きを焼いてくれている。一人分なのに器用に厚焼きにしてくれるんだよなぁ。お客さんに出す時より少なめにおかずを盛った器を全てお膳に乗せてI字型のカウンターに座ると、ちょうど焼きあがったらしい玉子焼きをカウンター越しに渡してくれた。
「いただきます」
まずは味噌汁から。先ほど温め直してまだ少し熱を持つそれを啜る。あぁ、今日も安定の美味しさだ。美味しいものを食べてる時も、生きてる事を実感する。次にほうれん草に箸をつけ口に運んだ。
……すると、背後から引き戸がガラガラ、と開く音がした。
(あれ、お客さんこの時間にも来るの?)
まだ咀嚼している口を、箸を持っていない方の掌で覆いながら後ろを振り向いた。
「あり?珍しい。この時間に他に客がいるなんて」
「あら、総悟くん。いらっしゃい」
「……っ、!」
目に写った姿とお時さんの言葉に驚き、口の中のほうれん草が気管に入りそうになる。
「……コホッ!ゴホッ!っ、はぁ…」
「ちょ、ナマエちゃん大丈夫かい?」
噎せて咳き込むが、何とか通常通りに飲み込むことができた。お時さんが心配して声を掛けてくれるのを聞きながら、思わず水をゴクゴクと一気に流し込んだ。
「この子は客じゃねぇよ、バイトのナマエちゃんだ」
空になったコップを机に置くと、カウンターの中から平五郎さんの声が聞こえた。その目線の先は、私の座る席から一つ飛ばした椅子。いつの間にかカウンター席に腰掛けていた彼に向いている。
「ふぅん。何でまた急に?」
「俺たちも歳だからなぁ、さすがに。ちぃとくらい手ェ抜いてかねぇと」
「バイト雇う余裕が無ぇだけかと思ってやした」
「がはは!わざわざ人の少ない時間狙ってウチに顔出してるくせに、よく言うなぁオイ!」
(……なんか、めちゃくちゃ仲良さそうなんですが)
彼に水を出しに来たついでに、私の飲み干したコップに水を補充してくれるお時さんに小声で尋ねる。
「…常連さんですか?」
「そうそう、いつもこれくらいの時間に来るんだよぉ。曜日はバラバラだけど。今日は私服だし休みかねぇ?」
この時間帯に店に入ってくる時点で常連さんに決まってるのに、つい分かりきった質問をしてしまう。下の名前で呼ぶ程親しいというのに。それに"私服"ではない時を知ってると言うことは、制服姿も知ってるのだろう。
「毎日屯所でむさくて喧しい男どもと飯食ってんですぜ?たまには静かに食いたくもなるでしょうよ」
「結局ここへ来ても、むさい俺と喧しいお時しかいねぇぞ」
「ちょいとアンタ、誰が喧しいって?」
まったく、と怒るお時さん。私はいま賄いを食べていていいのか分からず箸を置いて黙って会話を聞いていた。
「あれ、ナマエちゃん食べてていいんだよ?」
「いや、でも」
「総悟くん、別に良いだろ?」
「かまいやせんよ」
「アンタら同い年くらいだろう?私は準備してくるから若いもん同士で話してな」
「え、ちょ、お時さん、……すみません、」
呼び止める私の声を聞き流し、お時さんは厨房へ入って行ってしまった。客の横で賄いを食べる事に対しての罪悪感から謝罪を述べた。
「いんや、別に」
興味なさそうに言う彼は、お時さんが置いていった水を飲んでいる。
私はどちらかというと表情が豊かな方では無いし、大声を上げたりハイテンションで話すタイプではない。別に無表情というわけでも、愛想が無い訳じゃ無いと思う。ただ、喜怒哀楽を全身で表現するような“かまってあげたくなる愛嬌のある可愛い女の子”では無いという自覚があるだけ。
そういう質だからなのか“できる事ならばもう会いたくない”と思っていた人物が真横にいる状況でも、意外に冷静に言葉を発することができたと思う。しかし理由はそれだけではなく、江戸にいる以上今後も会う可能性があると予め心の準備をしていたのだ。まさかこの店で会う事になるとは思いもしなかったが。
……とはいえ深入りする理由もないので、早く食べ終わって仕事に戻ってしまおう。準備といっても10分もしないうちに提供されるだろうし、その間に何とか。
そう思って再び箸をつけようとしたのだが、横から刺さるような視線を感じる。
カウンター席、と言ってもバーのような回る椅子ではなく普通の木製の椅子。にも関わらず、いつの間にか体ごとこちらへ向けて座り直しており、片肘を机に置いて頬杖をついている。もう片方の腕は椅子の背もたれに置き、こちらをじっと見ていた。
「あの……」
「気にしなさんな」
(いや気になるわ。ものすっごい食べづらいわ。何、食べるなってか?)
「冷めちまいやすぜ」
別に睨むでもなく、かと言って微笑むわけでもなくただただ無表情で見てくる。
(側から見たポーカーフェイスって結構厄介なのかも)
自分もどちらかといえばポーカーフェイスに分類される方だと思うが。
「……では、お言葉に甘えて」
もう気にしないで食べよう。まだ全然減っていない定食を行儀が悪くならない程度に急いで食べ進めよう、と思った。
「今日は着物なんですねィ」
小鉢に伸ばした箸が届く前に、話しかけられた。結局全然食べさせてくれないじゃないか。
……そう、今の私は着物姿。わずかに茶味を帯びた鶯色の色無地。光の加減で見え隠れする鮫唐草の地紋は落ち着きがあり、幅広い年齢の人が着ることができそうだ。仕事中は袂が邪魔なので襷掛けしている。
実は和装一式を持っており、着付けも一人でできる。昔、両親に教えこまれた。理由は聞いていないが『絶対に一人で着られるようになれ』と。その言葉とともに、母の着物を数着譲り受けた。
まさかそれが役立つ日が来るなんて、当時は思ってもみなかった。この世界にいるからには着る事になるだろうと、部屋の整理をした時に出しておいたが……。両親は、今の私の状況を予測していたとでも言うだろうか。もしそうだとすればかなり不気味な話だ。
「えぇ、まぁ。あと、遅くなってすみません。その節は本当にありがとうございました。」
“今日は着物”というのは先日会った時と比較してのこと。つまり覚えているということを遠回しに言ってきている。
正直、顔なんて覚えてないと思っていたのに。一度助けてもらったとはいえ、ほんの数分しか関わっていなのだから。まぁ、今更「初めまして」なんて言えるほど肝は据わっていない。初対面のフリをするのは、もう無理だ。
「車を運転する予定があったので、洋服だったんですよ」
「へぇー、運転するんですかぃ」
「まぁ……。最近免許を取ったばかりですが」
「人は見かけによらねぇや。全く運転してるところ想像できやせんね」
この店で働き始める時に店主らに運転免許を持っていると話した際に、少し驚かれた。女で免許を持ってるのは変に思われるのだろうか、怪しまれたらどうしよう、自分の発言のどこに地雷があるかわからないからあまり話したくない。そう思っていたのだが、一週間経った今は正直気にしていなかった。
「世間知らずのどっかの令嬢が家出でもして来たのかと思ってやした、あん時。」
向こうは会話を止める気がないらしい。その割にはあまり興味がなさそうな顔をして話している。
(それはわざと?詮索されてる?)
そんな警戒心が湧いたのは、彼が警察という職業なのを私が意識してしまっているのだろうか。
「そんなんじゃありませんよ、凡人です。」
「ふぅーん」
「なんでい。2人とも、知り合いだったのかい?」
玉子を焼き終わったらしい平五郎さんが会話に入ってきた。
「知り合いといいますか、実は先日絡まれてるところを助けていただいて」
「あら、そうなのかい?」
焼きたての玉子焼きも乗せた定食のお膳を持ってきたお時さん。そう言いながら彼の前にそれを置いた。
「ナマエちゃん綺麗だからねぇ。ここはかぶき町も近いし……。慣れるまではあんまり夜一人で出歩かない方が良いよ」
「江戸の人じゃねぇんですかぃ?」
「……まあ、田舎から、」
東京にいた時ではなく、今現在の私の"前の住所"。そこの地名を言うと「俺より田舎じゃねぇですか」と返された。そして意外にも行儀良く手を合わせて「いただきます」と言ってから定食に箸をつけ始める。
既にこの手の内容の会話は、他のお客さんや山本夫妻とも交わしている。その度に特に不審がられることも詮索されることもなく、ただの世間話として話が終わる。それは自分のプロフィールに別に不自然な点は無いということだ。しかし自分には全く聞き馴染みの無い地名なのに、何も滞りなく会話が成立することに対して毎回胸がザワザワする。
『お前はこの世界の人間じゃない』
『お前はこの世界の人間だ』
そんな両極端なことを同時に言われている気分になるのだ。
「あんま芋臭くねぇですね」
「……どーも」
向こうが箸をつけ始めたので私も食べ始めたが、合間合間に会話を挟んでくる。
「江戸へはいつ頃来たんで?」
「先月末くらいです」
「本当に来たばっかですねぃ」
先月末、というのは私が今のマンションに入居した日。これも他の人に同じように話している。
今は4月上旬。文字通り“江戸に来た”という意味で言うならば本当は4月1日、エイプリルフールだと思う。それは目の前の彼に初めて会ったあの日のことだ。
「この辺に住んでるんですかぃ?」
「徒歩圏内ですよ。近くで働きたかったので」
こちらから質問することはしなかったが、初対面の人がするであろう一般的な会話をしながらお互いに箸を進めた。
お時さんが先程『同じ歳くらいだろう』と言ったのが気になったのか「歳は?」と聞かれ、答えると「マジで同い年じゃねぇか」と少し驚いた顔をした。どう言う意味だ、見えないって言いたいのか。
そんなどうでも良い話をぽつりぽつりと交わす、ただの店員と客の会話。そう思うと僅かに抱いていた警戒心は弱まり、普通に話せるようになった気がする。
私の方が量が少なかったとはいえ、後から食べ始めたはずの彼と、私が食べ終わったのはほぼ同時だった。
平五郎さんと、いつの間にやら厨房の中に戻っていたお時さんは片付けやら仕込みやらをしていた。私も慌てて自分の食べ終えたお膳を持ち上げて流しに持っていく。
「あらぁ、もう少し話してても良いのよ?」
「え」
「あぁ見えても総悟くんは真選組の隊長さん、落とせば玉の輿よぉ~~」
「おばちゃん、聞こえてやすけど」
「聞こえるように言ってんのよぉ」
厨房、と言ってもカウンター越しのすぐそこで中も丸見えだし声も聞こえる。
(一体何を言ってるんですかお時さん……)
「おいおいやめろよ、お時よぉ……。ナマエちゃんには高嶺の花でいてもらわねぇと。あいつらがこの娘を間抜け面で見てる顔を、この厨房から眺める愉快さったらねぇんだからよぉ」
「おっちゃん結構良い性格してやすよねぃ」
(なんてことを言い出すんですか平五郎さん)
てっきり助け舟を出してくれるものだと思ったのに。……とも思ったけど、変に男とくっつけようとするなと言いたいんだろうか。彼なりの優しさ…だと思う。たぶん。きっと。知らないけど。
「そろそろ帰りやす」
そう言って席を立った。2人は水仕事やらで手が離せないので私が会計に向かう。
不本意とは言え、変な話をしてしまったので少し気まずい。そう思いながらレジを操作する。
「700円です」
価格も毎日同じなのに必要あるのだろうか、と思いつつ一応値段を言う。
彼は財布から1000円取り出してカルトンに置いた。それを受け取り、レジを操作してお釣りを取り出す。
「お釣り300円です」
カルトンに置くか、手に直接渡すかほんの一瞬迷ったが前者を選んだ。小銭を握りしめた手をカルトンの上で開こうとした瞬間、ガッと握り拳を上から包み込まれ阻止された。
「えー、っと、」
「総悟です」
「え、」
「総悟でさぁ。ナマエチャ~~ン」
「………」
わざとらしく語尾を強調したように呼んでくる。
「総悟、くん…?」
「ん」
短く返事のように言うと、握られた手の力が弱まった。離れた手を私の握り拳の下へ差し出し受け皿のように構えたので、その手の平に小銭を置いた。
「んじゃ、また」
「ありがとうございました」
小銭を財布にしまうと、手をひらひらと振りながら引き戸に手をかけて出て行った。
(……自己紹介をしていなかったのが気に障った?)
仕方ないじゃないか、今までこの店でお客さんに自己紹介をしたことなんてないんだもの。それに彼も他の客同様、例に漏れることなく下の名前で呼んできた。
私は、元から彼の名前を知っている。初めて会った時にフルネームも聞いたし、お時さんが何回も呼んでたから改めて尋ねようと言う気にならなかった。念押しするように下の名前だけ名乗られてしまうと、今さら苗字で呼ぶのは少し気が引ける。
(あぁ、自己紹介して聞いておけば良かった)
なんて、後悔してももう遅い。……常連なのだから、本当にまた来るだろう。ここで働いている以上、逃げることはできない。今日みたいに、ただの世間話だけしていれば問題ない。ただの店員と客なんだ。きっと大丈夫、大丈夫。
(大丈夫……うまくやれる)
今の時刻は9時45分。もうすぐ暖簾をかけての営業が始まる。私は彼、もとい総悟くんの食べ終えた食器を持って流し台に向かった。