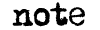お父さんがまた体調を崩した。
身体の弱いお父さんは、毎年冬から春にかけてのこの時期、一度は倒れる。
運悪く、今年は、お母さんもおばあちゃんもイレブンの仕事で出張中。年末からずっと忙しい店を閉めたままにするわけにもいかず、焔が手伝いに呼ばれた。
まだ雪深い東北の地へと旅立つ焔が、代わりにと残していったのは彼の眷属の一匹。
人語は理解するも話せず、まだ人に化けることも出来ない幼狐だ。
乙葉の家、というよりは焔の傍らに居着いており、普段からよく見かける白い子狐だった。
カーテンの隙間に垣間見える世界は、夕方から降り始めた雪に呑み込まれ、淡い光を放っている。
道ゆく人も車もなく、白い闇が音のない世界にぼくらを閉じこめる。
カーテンをきっちり閉めると、足下を幼狐が駆け抜けた。
犬用のボールで遊んでいる。
その姿はフェネックのようで、ただただ愛らしい。
「今夜はぼくたちだけだよ。寒いから一緒に寝ようか」
誰もいない夜が、ほんの少し、淋しかったのかもしれない。
いつもはあまり寄りつかないその子狐も、今日はずっとぼくのそばにいた。
抱き上げた子狐と一緒に潜り込んだ布団はすぐに暖まる。
焔と同じ日向の匂いが、僕をゆるりと弛緩させた。
まるで麻薬。
まるでパブロフの犬。
知っていてこの子を残していったのだ。
「お節介バカ」
睡りに沈みゆく僕の胸の辺りで、幼狐がキュウと不満げに鳴いた。
そして僕は翌朝、思い知ることになる。
主人を想う眷属の真っ直ぐな想い、否――意地を。
ベッドから転げ落ちた僕を、白い肌の少女が見下ろしていた。
大きな金色の瞳は、その色に似合わないほど冷たく光る。
「お、女の子だったの?! 術も使えたの?!」
「旭様のおかげですわ。はい、これ。チョコ。お世話になっているお礼なのですわ」
ぶっきらぼうに差し出された掌に、剥き出しのチョコがころんと一粒。
粘土をぎゅっと握りしめたような形は胡桃のような、松ぼっくりのような。その所々から、白い毛が飛び出していた。
「心を込めて作りましたわ。さあ召し上がれ」
にやりと笑まうその顔は、どこまでも美しく黒く。
「早く帰ってきて……焔」
ぼくの叫びは遠すぎて届かず。
嫌味たっぷりな毒の棘を刺された僕は、耳と尻尾の生えた全裸の妖少女から全力で逃げ出した。
焔の悪口は、彼女のいるところではもう二度と言うまい。
小さな妖狐の小さな恋は、何処までも深く強く、その姿を変えるほどに一途なのだ。
無理矢理、口に押し込められたバレンタインの、狐の毛入りチョコを噛み締めた。
(了)